アート・バーゼル&UBSが2025年版レポートを発表。2年連続で取引額が縮小しアート市場は変革期に突入
アート・バーゼルとUBSが最新レポート「Art Market Report 2025」を発表した。世界のアート市場規模は前年比12%減の575億ドル(約8兆3,500億円)と2年連続で縮小を見せ、高価格帯商品の取引も大幅減。他方で取引量は増加し低価格帯の市場規模が拡大するなど、アート市場は変革の時期を迎えている。
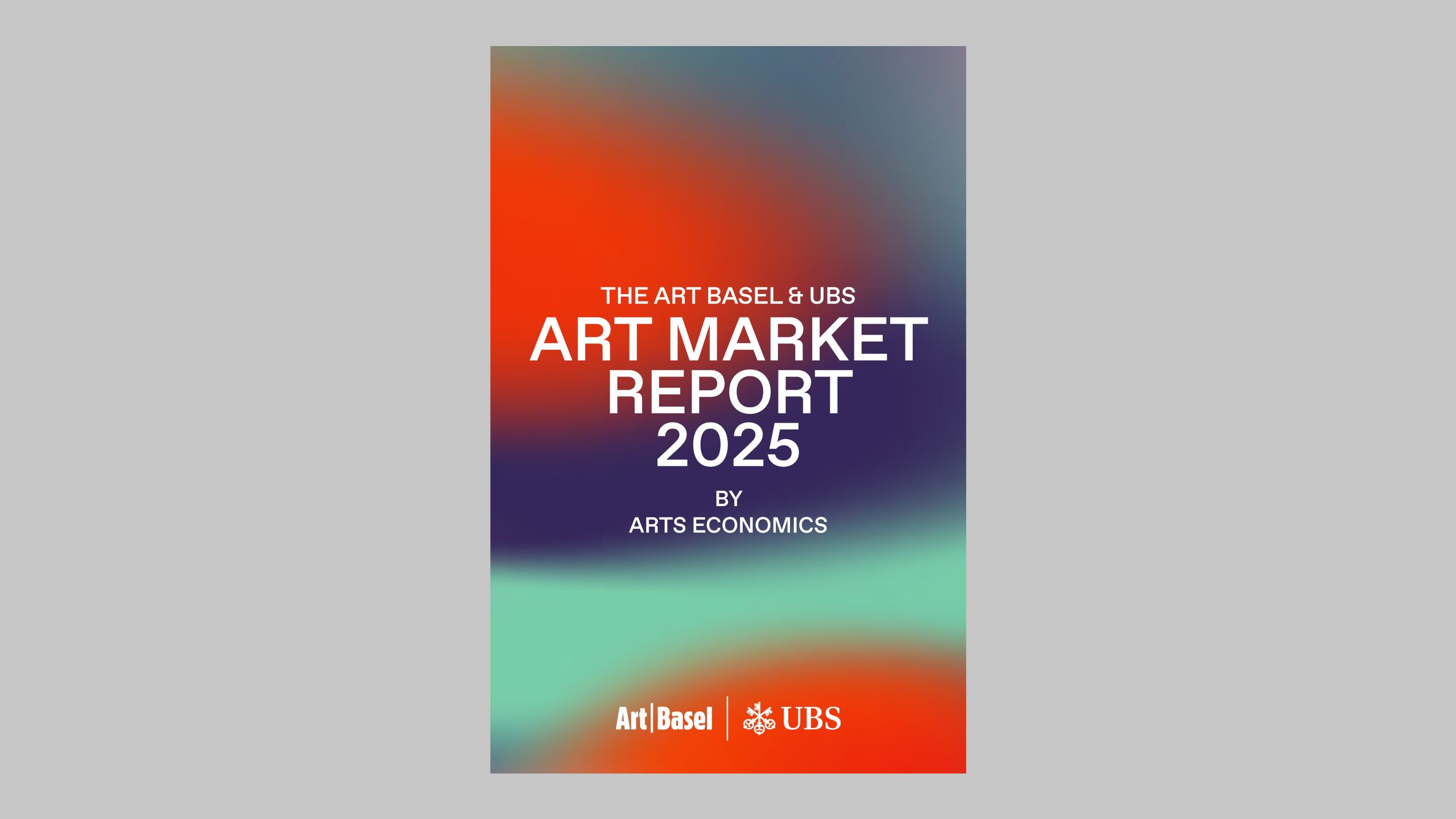
低迷する高価格帯作品と堅調な低価格帯作品
4月8日、アート・バーゼルとUBSによる「Art Market Report 2025」が発表された。世界中のディーラーやオークションハウス、コレクター、アートフェア、金融機関から収集・分析したデータに基づいてつくられた本レポートは、2024年のアート市場の状況を解説するものだ。
まずグローバルアート市場全体の規模は前年比12%減の575億ドル(約8兆3,500億円)と、2年連続で縮小を見せた。なかでも大きく変化したのは、1,000万ドル(約14億5,000万円)超の高額商品の取引だ。取引量は39%減り、金額は45%減と大幅に縮小。ルネ・マグリットの《光の帝国》(1954年)はクリスティーズ・ニューヨークで1億2,100万ドル(約176億円)で落札され、最高額の取引となったが、1億ドル(約145億円)を超える作品は本作のみ。上位10作品の総額も30%減少している。本レポートは、こうした変化の背景に米大統領選に代表される政治的不確実性があると指摘している。
他方で、5,000ドル(約72万円)未満の低価格帯作品は取引量が13%増え、金額も7%増。アート市場全体の取引量も4,050万件と前年から3%増えており、市場全体の傾向が変化していることがうかがえる。これまでアート市場が縮小する際は低価格帯が打撃を受けることが多かったが、2024年は高価格帯作品が低迷しており、市場構造が根本から変化しつつあるという。
中国市場は31%減、世界2位から転落
国ごとの市場シェアも変化を見せている。アメリカは248億ドル(約3兆6,000億円)と前年から9%減少しているものの、43%の市場シェアを誇り首位を維持。依然としてアメリカは高額作品取引の中心地であり、2024年に落札された最高額作品50点のうち、36点はニューヨークで取引されている。
最も大きな変化を見せたのが、中国市場だ。取引額は前年から31%減った84億ドル(約1兆2,200億円)に落ち着き、2009年以来の最低水準に急落。市場シェアも4%減の15%となり、第3位へと後退した。経済成長の鈍化や不動産市場の低迷が原因と指摘されており、関係者は「不動産市場の変化が富裕層の資産形成に影響を与えているほか、政府による取締強化も高額美術品市場に影響を与えている」と指摘する。なお、香港市場も低迷しており、香港における3大オークションハウスの売上は30%減少したという。
中国市場の衰退により市場シェア第2位を奪回したのが、イギリスだ。イギリスも104億ドル(約1兆5,100億円)と前年から5%下がっているものの、市場シェアは1%増の18%。オークション市場ではとくにオールド・マスターの作品取引が堅調であり、38%のシェアを占めている。ロンドンは依然としてヨーロッパの重要なオークション拠点としてみなされていると言えるだろう。
上位3カ国以外の地域でも、市場の縮小が指摘されている。売上額を見るとフランスは10%、ドイツは4%、イタリアは10%減少しており、EU全体を見ても8%減少している状況だ。アジア圏においても近年Friezeの開催やメガギャラリーの参入によって盛り上がりを見せていた韓国は15%売上が減少し、成長が鈍化している。他方で、こうしたトレンドに反し売上が増加した数少ない市場のひとつが日本だ。日本は前年から2%売上が増加しており、アート市場が成長していることがわかる。
非公開販売が好調。販売チャネルにも変化が
販売チャネルごとの変化も見ていこう。2024年はディーラー部門が6%減の341億ドル(約4兆9,600億円)、公開オークションが25%の190億ドル(約2兆7,600億円)に落ち着き、主要チャネルはともに縮小している。他方で、オークションハウスのプライベートセール(非公開販売)は14%増え、44億ドル(約6,400億円)まで伸びている。クリスティーズは非公開販売が41%増の15億ドル(約2,100億円)、サザビーズは17%増の14億ドル(約2,000億円)を記録し、市場の不確実性が高まるなかで、売り手がより慎重なアプローチをとるようになっていると指摘されている。
市場全体が縮小傾向にあるためオンライン販売も11%減の105億ドル(約1兆5,200億円)となったものの、総売上におけるシェアは変動しておらず、パンデミック以降、オンライン販売がひとつの選択肢として定着しつつあることがうかがえる。とくにディーラー部門ではオンライン販売が総売上の22%を占めており、うち46%は新規顧客による購入だ。
3,660人以上のコレクターを対象に行われたアンケート調査によれば、52%の回答者がWEBサイトやSNSを通じてアーティストやその作品を知り、直接作品を観ることなく購入していることも明らかになっている。オンライン販売は、市場の裾野を広げる役割を果たしていると言えるだろう。
ディーラーが扱う女性アーティストの割合は41%まで上昇
ディーラー市場もまた、規模ごとに異なる動きを見せている。年間売上25万ドル(約3,600万円)未満の小規模ディーラーは17%増、100〜500万ドル(約1億4,500万円〜約7億2,800万円)層は10%増と成長している一方で、500〜1,000万ドル(約7億2,800万円〜約14億5,000万円)層は3%減、1,000万ドル(約14億5,600万円)超の層は9%減と、大規模なディーラーが苦戦している。
部門別に見れば現代美術を専門とするディーラーは11%減と苦戦する一方で、モダン・アートやオールド・マスター(18世紀以前のヨーロッパで活躍した画家の作品)を扱うギャラリーは安定的な成長を見せた。市場が安定しないなかで、より安全で価値が確立されている作品への注目が高まっていると本レポートは指摘している。
本レポートが注目すべき変化としてあげたのは、女性アーティストの台頭だ。ディーラーが扱うアーティストにおける女性の割合は前年から1%増となる41%まで伸び、プライマリーマーケットでは46%に達している。地域別に見るとアメリカのギャラリーが最も高い46%、最も低い中国が25%だ。
もっとも、規模を問わずディーラーが苦境に立たされていることも事実だ。アートフェアの出展に伴う費用は上昇しており、平均するとディーラーの運営コストは10%増加しているとされる。収益性の低下を明かすディーラーは、前年の32%から43%に増加している。
オークション市場はリスクを回避する傾向
オークション市場においては、1,000万ドル(約14億5,000万円)以上の高価格帯作品の取引が大幅に減少している。その市場シェアは23%から18%まで低下し、上位50作品の合計額は2022年の半分以下まで落ち込んだ。戦後・現代アートが最大のセクターとして52%を占めているものの、売上は28%減の46億ドル。とくに1945年以降生まれの作家の作品は36%減った14億ドル(約2,000億円)に落ち着くなど、6年ぶりの低水準まで落ち込んだとされている。
とりわけ過去20年以内に制作された新しい作品の割合は、2021年の29億ドル(約4,200億円)から11億ドル(約1,600億円)まで減少しており、市場はリスクを回避し伝統的な価値へ回帰している傾向にあると言えるだろう。
地域別の動きを見ると、アート市場全体と同様、アメリカ(31%)と中国(25%)、イギリス(14%)の3カ国が70%のシェアを占めており、日本やイタリアはわずか1%に過ぎない。依然としてアメリカは世界のオークション市場の中心地であり、クリスティーズやサザビーズ、フィリップスに代表されるグローバルオークションハウスの売上の半分はアメリカで行われたオークションによるものだという。
また、とくに中国においては支払いの遅延や未払いが年々深刻化している。1,000万元(約2億円)を超える作品の販売は前年から約60%増加しているものの、うち半分はまだ支払いが行われていない。経済的に不安定な状況に置かれることで、2021年末から2024年初めまでに中国では31のオークションハウスが閉鎖してしまったという。
トランプの関税拡大がアート市場にも影響?
グローバルアート市場の縮小が見られるなかで、世界のプレイヤーは市場の動きをどう見ているのだろうか? 市場規模としては縮小傾向に置かれる一方で、慎重ながらも比較的楽観的な見方が多いという。たとえば33%のディーラーは売上増加を期待しており、47%は安定、減少を予測するのは19%にとどまった。大幅に縮小を見せた中国市場では、半数のディーラーが売上の改善を期待している。
2025年はインフレ率低下や金利の引き下げが期待される一方で、保護主義的な政策の拡大がグローバルなアート市場に影響を与える懸念は無視できない。2025年にアメリカが発表した関税拡大計画やEUの対抗措置は、国際的な取引のコストを上昇させてしまう恐れがある。
他方で、富裕層の資産状況は市場にとっての希望だと見られている。2024年末時点の世界の億万長者の総資産は前年比約20%増の15.6兆ドル(約2,200兆円)に達し、過去最高を記録。UBSの調査では、アート・アンティークへの投資を計画する富裕層の割合が前年の11%から32%へと急増している。

アート市場のエコシステムが変わろうとしている
こうした変化を受けて、本レポートはアート市場が構造的な変革を迎えていると指摘している。高価格帯作品の市場が縮小し、より手頃な価格帯の市場が活況を見せるなかで、アート市場の裾野は広がっているからだ。オンラインチャネルの安定も、市場の民主化やアクセシビリティの向上に貢献しており、新規コレクターの参入も広がっていくと見られる。
富裕層の世代を超えた富の移転も、構造変化に寄与するだろう。相続による億万長者の割合は2018年の14%から2024年には52%に増加している。次世代の富裕層はデジタル技術に精通し、社会的価値に対する意識も高いため、富裕層の変化がアート市場に異なる動きをもたらす可能性がある。
もちろん、トランプ米大統領に代表される保護主義的政策の拡大が大きなリスクとなりうることも無視できない。関税や貿易制限は美術品の国際的な移動に影響を与え、特に美術品の輸出入に依存するアメリカやイギリスといった主要市場は今後変化していくのかもしれない。
グローバルアート市場は、単に縮小しているわけではない。取引量の増加や新規バイヤーの拡大など、長期的な市場の健全性につながる要素も見られた。短期的には不確実性が続くものの、金利低下や富裕層の富の拡大、オンラインチャネルの発展など、中長期的な成長を支える要因も存在する。高価格帯作品の低迷は、むしろ多様な作品の流通につながり、さまざまなディーラーやコレクターが市場に参入する契機ともなりうるだろう。経済的・政治的に世界が大きく変動していくなかで、アート市場もまた、変革の時期を迎えようとしているのだ。


