水没したニューヨークの映像作品。ジョシュ・クラインが描いた気候変動問題
ジョシュ・クラインのロサンゼルスでの初個展が、ウエストハリウッドにある非営利アートセンター、LAXARTで始まった(会期は4月9日まで)。海面上昇で水没した不気味なニューヨークが舞台の10分間のショートフィルム作品、《Adaptation(適応)》の初上映が展示の中心だ。
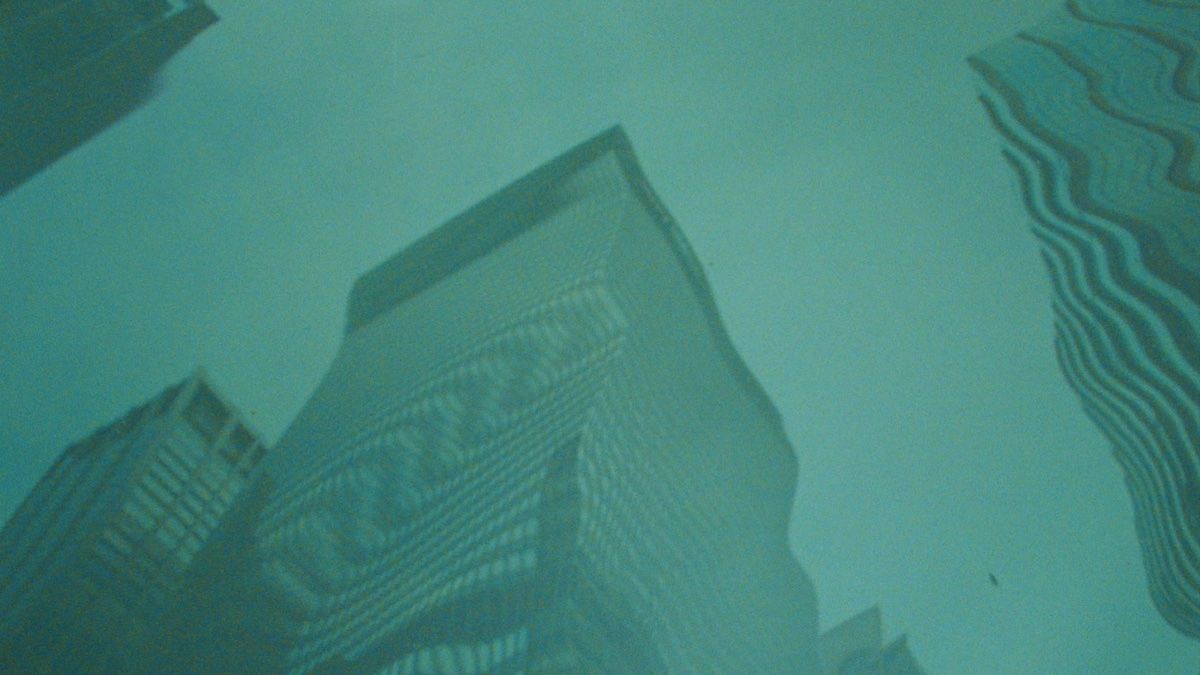
ビルや船の模型を16mmフィルムで撮影したこの作品は、エレクトロニックサウンドのミュージシャン、ガルチャー・ラストワークの物悲しくメランコリックな音楽と、絶望に沈む都市を行く俳優たちのナレーションが印象的だ。
今回の個展では、このショートフィルムとともに、関連する写真作品、彫刻、インスタレーションも展示されている。どれも進行中のプロジェクト「Climate Change(気候変動)」を構成するものだが、プロジェクト自体は2019年にニューヨークの47 Canal gallery(47カナルギャラリー)での初展示から始まっている。展覧会の解説によると、「21世紀の生活を形成する政治的、経済的、技術的、そして生物学的な変化に関する、より大きなインスタレーションサイクルの一部」だという。
ARTnewsは、《Adaption》の制作と展示に関して、ジョシュ・クラインにメールインタビューを行った。
ーーこの作品には独特の映像表現や感性がありますね。このショートフィルムを作ろうと思ったとき、何か参照したものはありますか。
クライン:2019年に制作の準備をしていた頃、「エイリアン」やオリジナル版の「ブレードランナー」のことをよく考えていました。どちらも、縮小模型やマットペイント(実写映像と背景画を合成する技術)、ブルースクリーンなどアナログの特殊効果を用いています。このやり方は、CGI(コンピューターグラフィックスで生成した画像や映像)とは違い、実際の物に本物のライトが当たっているので、いわば現実に即したものなんです。この手法なら、現在のデジタル画像処理ツールにつきまとう、ポストトゥルース(*1)を生む技術や偽情報などの問題がありません。つまり、フィクションを技術的に扱う上でより誠実な方法だと言えるでしょう。
「エイリアン」や「ブレードランナー」の衣装デザインには、宇宙で働く人を描くという点で興味深いものがあります。未来の労働を頻繁に描いたSF作家のアーシュラ・K・ル=グウィンとキム・スタンリー・ロビンソンも、私の考え方に大きな影響を与えています。大抵のSF小説では、世界を変える一人の人間だったり、何人かのグループだったり、主人公はいつもヒーローとして登場しますが、自分はこの手のヒーローから脱却したいと思っていたんです。《Adaptation》は、特別な人が世界を救う映画ではありません。自分たちが引き起こしたわけではない大災害の後始末をしなければならない、その中で生きていく普通の人々を描いています。私たちが今コロナ禍の時代を生きているように。
また、ここ数年間は、フランスの印象派とその時代背景について考えることがよくあります。19世紀後半のフランスのブルジョワたちが休日にのんびりと過ごす様子を描いた絵画のことです。《Adaptation》では、たとえディストピアの中にあっても働く人々が休息する姿を見せたかった。この世界では、厄介なことに私たちは働かなければなりません。作品の中での労働が何かは想像に任せるとして、この労働者たちのオフの時間を見せたかったんです。コロナ禍のこの2年間、私たちは色々なものを見てきました。そして今、プロテスタント的な労働倫理がペテンであり、経済という名の悪徳なマルチ商法であることは誰が見ても明らかだと思います。

ーーガルチャー・ラストワークとは、作品のサウンドトラックに関してどんな話をしましたか。何を求めているか、どう説明したのでしょうか。
クライン:私はずっとガルチャー・ラストワークの音楽のファンでした。2019年は彼のアルバム「Information」をよく聴いていました。ガルチャーは、ミニマルテクノやハウス系の音楽を作ることが多いですが、このアルバムはアンビエントだけれど感情が溢れ出すような曲で始まっています。彼のビートに乗ったシンセサイザーのサウンドとメロディーがとても好きなんです。
ガルチャーとサウンドトラックに関して話をするようになったのは2020年のことで、彼の音楽についてあれこれ話をしました。基本的にはアンビエントなサウンドトラックを作ってもらえないか頼んだわけですが、その時期に自分が気に入っている曲のことも伝えています。ア・ガイ・コールド・ジェラルドのアルバム「Black Secret Technology」やBurger/Inkの「Las Vegas」、Gas、ドレクシアやバンゲリスも話題に出ましたね。
ガルチャーがいくつか曲のアイデアを持って来たときは、かなりミニマルなものでした。デモには、この作品の持つ雰囲気だけではなくて、少なくとも私自身がコロナ禍の自己隔離中に体験した孤独や孤立感、悲しみがよく表現されていました。彼はその後、曲をもう少し仕上げてきたんですが、結局は元の感じに戻すことにしました。求めるものにぴったりだったからです。
ーー《Adaptation》というタイトルをつけた経緯について教えてください。
クライン:《Adaptation》というのは、もともと仮に使っていたタイトルでした。他にもタイトル案はあったのですが、最後まで残ったのがこれだったんです。この作品は、変わり果てて荒廃した世界で生きていくしかない人々を描いています。科学者が語る気候への適応は、すでに起きてしまったダメージを元に戻すには遅すぎるという現実を受け入れること、つまり変化の多くはもう織り込み済みであるということを意味します。
パリ協定は、世界のどの政府も達成できないのはほぼ間違いないですが、海面が劇的に上昇し、何百万、何千万という人が死に至ることがすでに想定されています。それですら、今世紀後半に私たちが直面する一番マシなシナリオなんです。気候への適応とは、防潮堤の建設や、住民の移動など、科学に基づいた現実的な計画を立てることであり、否定や希望的観測を超えていくことです。私にとっての適応とは、特にこの2年間を経た今、可能な限り多くのものを救い、苦しみを防ぐということ。ディストピアの中にあっても、尊厳、喜び、希望や基本的な人間性を主張することなんです。
ーー作品中の会話で、「水の中には酸素があるけれども、あなたのためじゃない」と言っているところがありますが、これで何を伝えようとしたのですか。
クライン:洪水は、ある種の否定としてやってくるということを言っています。人間は酸素を吸って生きていますから、酸素がないと死んでしまいます。海水の中にもたくさんの酸素が含まれていて、多くの生物の命を支えているわけです。しかし、私たち人間の命ではありません。酸素は、私や800万人の人々が住んでいるニューヨークの比喩でもあります。2メートル弱の浸水でも、道路や歩道、地下鉄など、都市として機能するために必要なインフラが消え失せます。ニューヨークは人が住める場所ではなく、海の一部になり、肺を持つ生き物ではなく、えらを持つ生き物の場所になります。未来の人々はそこを訪ねることはできますが、住むことはできません。そこに家を持つことはできないのです。コロナ禍では、マスクをつけることによって呼吸を意識するようになったんですが、昔はそんなことはありませんでした。でも、マスクは自分の安全を守るのに必要です。特に私は喘息持ちですから。
ーープレスリリースによると、「この映画は、立ち直る力や生き残る力のイメージを意図していたが、世界的にコロナ危機が続く状況で、歴史の中の今という瞬間についてより多くの意味を持つことになった」とあります。あなたの視点はどう変わったのでしょうか。制作過程で意識したことが、作品を完成させるのに影響を与えましたか。
クライン:2019年に撮影をして、2020年の初め、ロックダウンの前にラフカットを作りました。その後、ロックダウン中のブルックリンで、2020年4月から5月にかけてもう一度編集したんです。この映画の意味に対する私の思いがまったく変わってしまったので。誰もいない静かな街で、水から上がったダイバーが自分を消毒するシーンがありますが、突然、これは未来の設定だけれど、現在のことでもあると感じたんです。登場人物たちは未来の建設作業員でした。彼らは気候変動難民で、以前住んでいた家に戻り、また仕事を始めます。2020年にこの映画を制作していた時に、登場人物たちの仕事をエッセンシャルワーカーに変えました。それで、ナレーションを新しく録音し直そうと、それに沿ったテキストを書き、夏には俳優たちにマイクロフォンを送って、ズームで演出を行ったんです。

ーー自分の作品にフィルムを用いるようになったのは、どんな理由からですか。
クライン:私はフィラデルフィアのテンプル大学で映像制作を学びました。その後、ニューヨークのエレクトロニック・アーツ・インターミックス(Electronic Arts Intermix)で、ビデオアートのキュレーターとして10年間働いたので、映像はアーティストとしての自分にとってあらゆる制作の基盤でした。実は、大学の頃は映画に反感を持っていたんです。映画はビデオと比べて反民主主義だと思っていたので。学生としては、映画はとてもお金がかかるし、いろんな意味で無駄がある。でも、今は映画のことをよく知っている撮影スタッフと協力して制作するなら、映画とビデオの経済性にそれほど差はないと考えています。映画の場合はむやみにたくさん撮らないで、経済的に撮影できるように、前もってプランを立てることが大切です。
ここ10年は、洗練されたHDビデオやハイパーリアルなCGIアニメーション、商業的なイメージを批評したり(あるいは美化したり)するグラフィックスが特徴じゃないかと思います。でも、この手のビデオアートはありふれている。一方、フィルムという材料は、SFを含む映画全般で長い間使われてきたので、こうした最近の傾向とはほとんど関係がありません。今、2013年のビデオアートを見ると当時を感じさせますが、映画ならそんなことはない。時代の色に縛られないのです。それに、フィルムには深い郷愁を感じさせるところがある。自分はそれを生かして仕事をしたいと思っています。観客には今この時に対するノスタルジーを感じてもらいたいし、それを失うかもしれないということを感じてほしいのです。最近のソーシャルメディアはビデオだらけで、嘘とデマが広まるように操作されている。ビデオはフィルムほど真実じゃないし、欺瞞になるような作品をもう作りたくなかったのです。
ーー映画の中の要素は、どの程度彫刻的だと思いますか。それとも、そうは考えていないのでしょうか。
クライン:映画(またはビデオ)は、まさに私が彫刻やインスタレーションを制作するのと同じアプローチで作っています。違いは、動画の場合、観客が作品の中を歩き回ることができないという点です。カメラと編集が観客の見るものを切り取って枠の中に入れてしまう。でも撮影のセットの中では、私が作った世界の中を実際に歩き回ることができます。それは、一時的とはいえ実在する場所なんです。セットのデザイン、色、素材など全ての要素を、立体作品と同じように考えて作っています。撮影現場では、カメラが作品を見る人の目の代わりになる。つまり、撮影はアート作品を目で見るような感じだと考えています。アート作品を見る体験を記録しているのです。私にとっては、映画のスクリーンはインスタレーション空間です。逆に、インスタレーション作品では展示空間がメディアになるんです。
ーー今回、彫刻作品や写真を使った作品も同時に展示しようと思ったのはなぜですか。映画とどのくらい関係があるんでしょうか。それとも、それぞれ別個のものとして見るべきなのでしょうか。
今回、LAXARTで展示している作品は全て「Climate Change(気候変動)」という大きなインスタレーションの一部です。蝋(ろう)が溶ける彫刻《Consumer Fragility Meltdown(消費者の脆弱性のメルトダウン)》はニューヨークの47 Canalで展示したもので、額装した写真を一度水に漬けた作品はホイットニー・ビエンナーレに出品しています。どちらも2019年のことです。
彫刻作品はショートフィルムと直接関係はありません。でも、どちらも大きな全体を構成するものとして構想しています。「Climate Change」のようなプロジェクトでは、展示スペースや資金的サポートが決まったら、インスタレーションを部分的に制作していくんです。彫刻作品も映像作品も個々に独立したものとして制作していますが、一緒に構想された他の作品とともに展示すると、まったく別のアート作品になるというわけです。
ーー今回はロサンゼスで初めての個展ですが、この場所はあなたにとって特別な意味がありますか。
ロサンゼルスやカリフォルニアからは、とても影響を受けました。東海岸から初めてやってきた時は、まるで神の啓示のような驚きがありましたね。この地域には、戦後のアメリカが抱いていた夢の都市がよく体現されています。そして、私たちのカルチャーの原点でもあります。いわゆるブルーアメリカ(民主党によるアメリカ)ですね。その多くがカリフォルニアから始まっていると思います。(翻訳:平林まき)
※本記事は、米国版ARTnewsに2022年2月18日に掲載されました。元記事はこちら。
RECOMMEND
アートと環境


