「AI彼女」「ヌード化」アプリをハック! フェミニズムアートが切り込むAI時代の「ジェンダー規範」
生成AIの一般化で出現したAI彼女やヌード化アプリなどの新ビジネス。しかしそこには、古いジェンダー観を反映した集合知が詰まっている現実がある。こうした問題を孕んだAIの時代にフェミニズムアートは何ができるのか、5人の女性アーティストとその作品をもとに考察する。

AIが誰にでもアクセス可能なツールとして普及し始めた頃、理想の女性のイメージを生成できる「Gencraft」というアプリの広告が私のデバイスに頻繁に表示されるようになった。このアプリはどんな画像でも生成できるはずだが、どうやら広告やアルゴリズムは美しく若い女性たちを好むらしい。私は広告に使われていたプロンプトのスクリーンショットを撮っておいたが(そのため広告をさらに表示するアルゴリズムを働かせてしまったかもしれない)、それはこんな感じの文だった。
「赤いレオタードを着た、茶色い髪のフランス人の女の子」
「戦闘用の鎧をつけた金髪の女性」
「エルフのような細かい模様のタトゥーを背中に入れた少女が湖を眺める様子を、背後から見た画像」
プロンプトでは指定していないのに、生成された画像の女性はみな美しく、やせていて、白人だった。そして、どの女性も微笑んでいるか、穏やかで優しい表情を浮かべている。完璧でない点があるとすれば、顔の周りに乱れた髪の毛があることくらいだが、それがかえって彼女たちをリアルに見せる。フランス人女性の画像は首がありえないほど長いが、それでいてとても優雅だ。
AI生成画像にも従来のジェンダー観
こうした画像に反発を覚えるフェミニストは私だけではないだろう。ダナ・ハラウェイやアーシュラ・K・ル=グウィンなど、フェミニストの学者やSF作家たちは、AIのようなテクノロジーによって旧来のジェンダーは消滅するのではないかと想像していた。バーチャルな世界が肉体を持つアナログ世界よりも優位に立ち、人々が自分の身体を自由に再構成したりカスタマイズしたりできるようになるにつれ、性別の二元論は時代遅れになるかもしれない。彼女たちはそんな未来を思い描いていた。
しかし、AIアシスタントの媚びたような女性の声、そしてアプリが生成したフランス人女性やタトゥーの入った女の子、ブロンド娘の画像が証明する通り、旧来のジェンダー観はバーチャル空間にもしぶとく根を張っている。AIは何でも作れるはずなのに、広告に表示されるのは退屈で想像力のかけらもないイメージばかりだ。
広告に出てくる女の子たちは氷山のほんの一角で、世間には映画『Her/世界でひとつの彼女』のような男性のファンタジー──身体的・感情的欲求を持たない従属的な相手との恋愛──があふれ、アップルのApp Storeには何十種類ものAI彼女アプリがある。セクシーなアニメ風の女の子や、「いつも側にいて話を聞いてくれる」女性など、好みに合う彼女と交流できるこうしたアプリには、高価なものもあれば、ReplikaやCrushOn AIなど、1億回以上ダウンロードされているものもある。さらに、インスタグラムの中にもAI彼女がいて(もちろん、AI彼氏やAI友達もいる)、好きな時にチャットできる。
こうしたバーチャルな恋愛相手は、離婚の原因になったことすらある。その一例が既婚者向けの出会い系サイト、アシュレイ・マディソンだ。このサイトは2015年にハッキングされ、衝撃的な事実が明らかになった。配偶者や家族との関係を危険にさらし、数万円の会費を払ってまで出会いを求めた何万人の男性がオンラインで交流していたのは、ボットだったのだ。とはいえ、AIを使えば、完璧な女性と好きな方法でやり取りできる。電話を使ったアダルトサービスと違い、相手は人間ではないので何の気兼ねもいらない。他人に見られることもなければ聞かれることもなく、何も残らない。

フェミニズムのステレオタイプな女性像を打破する
こうした状況で、フェミニストには何ができるだろう? AIがなくなることはないだろうが、AIを取り巻くカルチャーを変えるための努力はできるかもしれない。アーティストのアン・ハーシュとマヤ・マンは、生成AIを使った新シリーズ「Ugly Bitches(ブサイクなビッチたち)」でそれをやろうとしている。2人は人形の画像を使ってトレーニングしたAIに、平均化された集合体を生成するよう指示を与えた。結果として現れた画像は実に奇妙で、現代の美しさの基準を揶揄しているようにも見える。この作品に表れているのは、ネット上にはびこる(マンが言うところの)「目指すべき理想の女性らしさ」に対して2人のアーティストが持つ嫌悪感なのだ。
「Ugly Bitches」プロジェクトがスタートしたのは2022年7月。きっかけは、デジタルプラットフォームのOutland向けにハーシュが動画シリーズを制作し、その中でNFTを批評したことだった。彼女はフェミニズムを謳うNFT作品の質の低さを嘆きながら、その例として、「美しく成功した女性」を漠然とイラストにしたNFTシリーズをいくつか挙げている。男性によって制作された作品も複数あり、中にはネット上で少女たちをおびき寄せて手なずけるためにNFTを利用していた小児性愛者もいた(ハーシュ自身も子どもの頃にネット上で小児性愛者と遭遇した経験があり、2010年代にそれをテーマにした作品を制作している)。
Outlandの動画中のハーシュは、明るい調子で話しながらも苛立ちを滲ませて上記のようなNFTを批判した後、「虐待されていると嘘をつき、子どもの単独親権を要求し、100万回中絶するような不器量な女性たち」を描いた作品を見たいものだと不満を露わにした。その動画を視聴したマンは、「あなたがそれを作ってみたら?」とハーシュにメッセージを送り、何度かアイデアをやりとりするうちに2人の共同制作が始まったという。2人は、成功した女性や美しい女性をもてはやす「フェミニスト」作品にうんざりしていた。そうでない女性は無価値だという考えを、より強固なものにするだけだからだ。
こうして生まれた「Ugly Bitches」(2022-)のシリーズで、マンとハーシュは敵対的生成ネットワーク(GAN)と呼ばれるAI(*1)に大量の人形の画像データを与えて訓練している。人形は、このアルゴリズムに使われるずっと前から、女性や人種の理想像を体系化し、少女たちに刷り込むために使われてきた。マンはそれを「理想的な女性らしさの極致」を表すものと考える。
*1 GAN(Generative Adversarial Network)は、正解データを与えることなく特徴を学習する「教師なし学習」の一手法。用意されたデータから特徴を学習し、擬似的なデータを生成する。
最初の作品が作られたのは2年前のことだが、GANが生成したブサイクな人形の画像はすでに時代遅れに見える。人形には不具合があるように見え、薄汚れていて、両目の位置もずれているが、そうした不恰好さは作品のコンセプトにマッチしているとマンは言う。
「不完全でどこか怪物的なのが気に入っています。私たち女性は、世にあふれる美しさの理想を真似ようとしては失敗し、自分自身をさらけ出してしまいますが、それと似ています。GANはそのプロセスを模倣しているのです」
その点でこのプロジェクトは、キュレーターのレガシー・ラッセルが2020年の著書の中で展開した「グリッチ・フェミニズム」(*2)の考え方に通じるものがあると言えるだろう。
*2 ラッセルは著書『Glitch Feminism: A Manifesto』で、白人至上主義や家父長制、異性愛的な価値観に基づく規範から外れた容姿、考え方、振る舞いを、コンピュータプログラムのグリッチ(障害・不具合)と重ね合わせている。

キャベツ畑人形、そしてブラッツやアメリカンガールといった着せ替え人形の画像で訓練されたGANが生成する「ブサイクなビッチたち」は、画像生成AIのDALL-E(ダリ)で作られた背景の中に配置されている。マンは、生成されたビッチ人形の画像を、インフルエンサーの写真にありがちな背景(海辺やダンススタジオ、高層ビル街など)と、短いテキストをランダムに組み合わせるようスクリプトを書いた。画像の下部に表示されるこのテキストは、ケンダル・ジェンナーやアディソン・レイなど、著名な女性インフルエンサーのインスタグラムポストに向けられたコメントをもとに生成されたものだ。
インフルエンサーの投稿に付いた何千ものコメントを実際に読むフォロワーはほとんどいないが、これらの文章から「人々が彼女たちをどう見ているのかを推し量ることができる」とマンとハーシュは言う。2人はコメント欄に飛び交う「きれい」「ゴージャス」「完璧」などの形容詞を「ブサイク」に置き換え、「ガール」や「ベイブ」といった言葉を「ビッチ」に置き換えた。たとえば、ある文には「あまりのブサイクさに号泣」と書かれ、その後ろに泣き顔と目がハートの絵文字が並んでいる。
2人の話では、ほとんどの人はこの作品に込められた皮肉を理解したが、「額面通りに受け取り、私たちが女性差別的だと考える人もいた」という。ハーシュによると、フェミニストのアーティストたちには、50年以上にわたって悩まされてきたジレンマがある。それは、ジェンダーについての固定観念を覆したり、批評したり、それについて何かを言おうとすると、必然的にそこに焦点を当てることになり、ある意味で固定観念が再生産されてしまうという問題だ。
では、どうすればそれを回避できるのだろうか。マンとハーシュによると、特にNFTの世界では予期せぬ反響があり、暗号資産マニアの男性たちから「ブサイクなビッチをぜひ手に入れたい」というメッセージが舞い込むようになったという。そのことに驚いたハーシュは、先行世代のフェミニスト・アーティストたちと同じ現実を突きつけられたと言う。
「何をしようと『男性の眼差し』を覆すことは不可能です。それはいつでも、あらゆるものをフェティシズムの対象とする方法を見つけます。そこから逃れようとしても無駄なのです」
ロサンゼルス現代美術館(MOCA)でこのシリーズのぬいぐるみバージョンを発表したとき、マンとハーシュはあるパフォーマンスを行った。エリザベス・ホームズ(*3)や彼女が崇拝していたスティーブ・ジョブズのような黒いタートルネックに身を包み、カリスマリーダー風のプレゼンを壇上で繰り広げたのだ。背景のスライドには「インスタグラムを5分間スクロールした後、自分が醜いと感じますか?」といった質問と、それに対する会場の人々の回答が映し出された。さらに、MOCAのギフトショップで販売されたぬいぐるみには、こんな刺激的な宣伝文句が付けられていた。
「ブサイクちゃんは、理想からあなたを解放し、ブサイクビッチ上等!と思えるようにしてくれます」
*3 医療ベンチャー企業セラノスの創業者。シリコンバレーの寵児として注目されたが、血液検査事業を裏付けるデータの出所に不正があったと判明し、詐欺罪で有罪判決を受けた。
世に溢れる女性らしさや理想的な美しさへの違和感
フェミニストのアーティストたちは、かれこれ半世紀にわたって美しさと醜さを融合させる作品を生み出してきた。そうした表現は、1970年代の強烈なパフォーマンスにまで遡れる。たとえば《Catalysis VII(触媒作用VII)》(1971)という作品で、コンセプチュアル・アーティストのエイドリアン・パイパーは、「超絶にフェミニンな」服装でニューヨークのメトロポリタン美術館の中を歩き回りながら、ほかの来館者にくっつきそうなほど大きくガムを膨らませている。
その後、私たちを取り囲むメディア空間は肥大化していき、そこに溢れる完璧な女性像が全てを覆い尽くすほど増殖するようになった。これに反応したのが、ピピロッティ・リストのようなフェミニストのビデオ・アーティストだった。2008年にリストが発表して注目を浴びた《Pour Your Body Out (7354 Cubic Meters)(体を外に排出して [7354立方メートル] )》には、銀の杯に経血を貯める女性が登場する。

アルゴリズムの時代に入ってからは、アンナ・ウッデンベルグやジーナ・ビーヴァーズがバーチャル空間での理想的な美しさを立体に落とし込んだ作品を発表している。彼女たちが浮き彫りにしているのは、大きく膨らんだ唇やバスケットボール並みに丸いお尻のように、画面の中では美しくても現実世界で再現すると不気味に感じられる美の基準の不条理さだ。
ウッデンベルグが作る等身大でリアルな女性像は、プロポーションと柔軟性がひどく誇張されていて薄気味悪いが、その1つに2018年に制作された《FOCUS #2 (pussy padding)(FOCUS No.2 [陰部ガード] )》がある。それは、青い服を着た女性が両脚の間から頭を通し、鼻がお尻にくっつきそうなほど上体を持ち上げながら、自撮り棒を使って自分の陰部を撮影する様子を表したもので、苛立たしくも不条理な理想を世間に広めるメイクのチュートリアル動画やインスタグラム広告にヒントを得て作られたように見える。こうした動画や広告は、商品を売るために不安を煽り、欲望を作り出す。ちなみに私のアカウントのアルゴリズムも、肌に十分にハリがあるかどうか、今年に入ってからしきりに心配させようとしてくる。
こうしたネット上のビューティカルチャーを題材に、彫刻的なペインティングを制作しているのがビーヴァーズだ。メイクのチュートリアルをステップごとにグリッド状のパネルに描いた作品には、スモーキーな目元の作り方や赤いリップの塗り方など、伝統的なメイクテクニックを紹介するものもあれば、メイクとアートを融合させ、(巨大な)唇にゴッホの《星月夜》を描く方法を紹介しているものもある。紙パルプの上に油絵の具で描いたレリーフ状のビーヴァーズの絵は彫刻的で、鑑賞者がいる空間に飛び出てきそうに思える。しかしマットな仕上げの少し崩れたような絵柄の作品は、美をテーマにしているものの、決して美しくはない。
ウッデンベルグやビーヴァーズのようなアーティストは、こうした「女性らしいもの」を好む女性を嘲笑しているわけではない。もしそうなら、単に形を変えた女性蔑視になってしまう。むしろ、彼女たちは自分自身のアンビバレントな感情を作品の中で探求していると言えるだろう。

ヌード化アプリを逆手に取った家父長的視線への抵抗
スウェーデンのアーティスト、アルヴィダ・バイストロムの新作は、AIとポルノによって生じ、その2つが掛け合わされたときにさらに悪化する「カジュアルな非人間化」をテーマにしている。2023年の終わり頃、彼女はundress.appに自分の写真をアップロードした。これは、ユーザーが送った画像をもとにAIがヌード画像を生成する、数あるヌード化アプリの1つだ。この手のアプリに人気があるのは、1カ月で2400万以上ものビジターを記録したことが証明している。その多くは女性の写真のみを対象とし、画像に写っている人物の同意なしに使用することができる。
バイストロムは、アプリでヌード化した自身の画像を『In the Clouds(クラウドの中)』(2024)という本にまとめている。最初の数ページに掲載されているのはごく普通のポルノ風の写真で、AIによる加工は、単に彼女の乳房を大きくするという月並みで独創性に欠けるものだ。

しかし、ページをめくっていくと、バイストロムがAIによる生成にどう介入していったかが見えてくる。生成された画像が示しているのは「AIが写真をどう見ているのか」を探る過程で、彼女がだんだんとAIを操る方法を発見していくのが分かる。たとえば、何枚かの画像では、彼女が薄いピンクなど自分の肌と同じトーンの服を着ているため、AIはどこまでが彼女の肌で、どこからが服なのかを見分けるのに苦労している。混乱したAIは、派手なピンク色の全身タイツと一体化した陰部が全身に広がっている画像や、3つの手と3つの乳首、そして切断された脚のような突起がある身体の画像を作り出している。
こうしてバイストロムがAIに課すハードルは、ページを繰るごとにますます上がっていく。たとえば丸く赤いピエロの鼻をつけた写真を与えると、AIは赤い丸とペアになるもう1つの乳首を描き、首をひねってカメラに顔と背中の両方を見せた写真では、肛門があるべきところにクリトリスを描くという具合だ。
中には、人体の構造がまったく無視され、非人間的と言っても過言ではない画像すらある。私のお気に入りの画像は、ベージュ、ラベンダー、ピンク色のサテンの下着の下に、ヘソと脚のようなものがごちゃ混ぜになった塊を描いたものだ。この肉塊は、開口部といえばヘソしかなく、腕や脚の代わりに膝のような突起しかないにもかかわらず、どこか誘惑的だ。現代思想の奇才と呼ばれる哲学者のスラヴォイ・ジジェクは、この本に寄せたエッセイの中で「誘惑するために身体が実在する必要はない」と書き、テイラー・スウィフトの性的なフェイク動画を、本人でないことは百も承知で何千万人もの人々が視聴したことに触れている。
ほとんどの画像生成AIアプリで性的な写真が禁止されているのは、どう悪用されるかが想像に難くないからだ。undress.appでさえ、バイストロムがそれを使ったプロジェクトを始めてから規約を変更している。とはいえ、ポルノコンテンツが溢れ、男性の眼差しと家父長制的なファンタジーに大きく偏向したインターネットのデータで訓練された集合知が存在することに変わりはない。バイストロムは、AIが知っていることと、それを作った人々が隠したいことを私たちに開示するよう、AIを誘導する方法を見つけたのだ。つまり、私たちがAIに見せたものを、AIがどう見ているのかを。
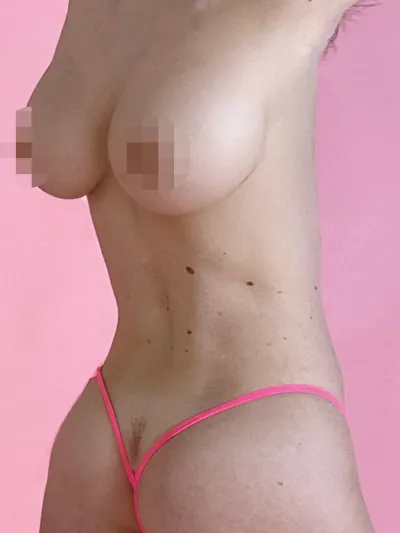
バイストロムは子どもの頃にモデルとして働いていたが、思春期を迎えた13歳の時にヒップが大きすぎると言われたという。
「すごくショックでした。でもその後、フェミニズムに傾倒し、モデルを辞め、自分の体を素晴らしいと思えるようになりました」
2010年代のポスト・インターネット・ムーブメントの中で自撮り作品が注目されて以来、彼女はモデル業界から自分自身のイメージを取り戻す方法として、また他人をモノとして扱うのを回避するために、自分自身を素材にした画像を制作している。
自分自身のイメージを取り戻すというバイストロムの意図は確かに重要だ。しかし、彼女が全ての女性の代弁者であるかのように、その作品を「フェミニスト」的だと語るときには、ある問題が生じる。アーティストであり、評論家でもあるアリア・ディーンは、2016年のエッセイの中で「自撮りフェミニズム」の制作者が白人に偏っていることを指摘。男性の眼差しの要求がいかに不均等であるかについて、黒人女性は「監視されると同時に陰に追いやられ、無遠慮に見つめられながら不可視な存在だ」と例を挙げ、バイストロムなどのフェミニズムプロジェクトが抱えるリスクについてこう論じている。
「最も牽引力のあるフェミニズム的表現が、可視性との関係において複雑さを免れている限り、それは美学化と脱政治化の中にさらに沈んでいくだけだろう」
言い換えれば、家父長制的な現状を打破するには、女性が自分の姿を自分の流儀で画像化するだけでは不十分なのだ。実際のところ、現代の美しさの基準を設定しているのは、雑誌ではなくインフルエンサーと呼ばれる人々だ。いわゆる「普通の」女性たちが自分自身をイメージ化して世に送り出しているわけだが、それでも私たちは罠から解放されたわけではない。少数の女性たちが、罠から利益を得られるようになっただけだ。
確かにアリア・ディーンの批判は正しい。だが、バイストロムがAIとのコラボレーションで生み出した最近のシリーズは、彼女が以前取り組んでいた自撮りフェミニズムの作品より直接的に、見る者と、ひいては私たちの文化と向き合い、そこに介入していると私は思う。ウッデンベルグの彫刻やパイパーのパフォーマンスと同様、バイストロムは他者の視線を呼び起こす。ただ「失せろ」と拒否するためだけに。
ただ、それが可能なのは、バイストロムがAIの訓練に使われている白人のやせ型の身体を持っているからにほかならない。彼女は、AIに退屈でありきたりの最小公倍数的ファンタジーを再生産するよう仕向けるが、それこそが肝心なところなのだ。バイストロムが言うように、「私たちは規範的な美しさに晒されすぎて、もはや興味を失っているのだろう」(翻訳:野澤朋代)
from ARTnews


