美術評論はより保守化しているのか、それとも単に燃え尽きたのか? アメリカの美術評論家が考察
「世の中の展覧会の85%はゴミ。それでも足を運ぶ価値はある」──美術評論の重鎮、ジェリー・サルツはそう喝破した。サルツは否定的な言葉の排除が批評を停止させていると言ったが、悲観ばかりの評論に異を唱えるのはルイス・ベリーだ。3人の評論家を例に挙げ、最近の傾向を分析した彼の論考を紹介する。

美術評論をやっている私には、ほかの評論家たちの気持ちがよくわかる。たしかに、ほとんどの展覧会は大したことがない。私にとって、ギャラリーめぐりは古着屋めぐりと似ている。ただし、アート作品は古着よりはるかに高価なので自分では買わないが……。ギャラリーでも古着屋でも、嬉しい出会いを期待してあちこち見て回るのが楽しい。だが、並べられたものの大半は、無難なチノパンや、ソファの上に飾っても違和感のない抽象画などの平凡な代物だ。中には、タキシードがプリントされたTシャツのように、ちょっと引いてしまう作品もあれば、気に入っても自分のサイズやスタイルに合わないものもある。
だが、ごくまれに、それも多くの場合はこれ以上探しても無駄だと感じ始めたまさにそのときに、信じられないような掘り出し物──まるで自分だけのために存在するかのようなジャケットや彫刻──に出くわすことがある。その発見は、起きそうにないことが起きたという驚きによって、さらに意味深いものになる。
ノスタルジーが蔓延する現在の美術評論
要するに、私は評論家が「最近のアート(あるいは映画や音楽)はダメだ」と言うたびに、それを疑ってかかるのだ。いつの時代も、たいていの作品は大したことがない。そして全部に目を通そうとすると、否応なしに疲れが溜まる。その疲労のせいで、芸術的興奮が滅多に得られないのは現代文化に特有の平凡さのゆえだと勘違いする批評家もいる。そしてこうした勘違いのサインは、今日の美術評論に蔓延するノスタルジーとしてあちこちに顔を出す。評論家自身が若かった頃、あるいは美術史上の黄金期など、過ぎ去った時代に対するノスタルジーだ。
このノスタルジーは、現代アートの停滞を憂える評論のあちこちに見られる。たとえば、ショーン・テートルが運営するウェブサイト、「マンハッタン・アート・レビュー」もその1つだ。彼が2023年に投稿し続けた辛口の展覧会レビューは、美術批評の存在意義に対する関心をかき立て、話題を呼んだ。
もう1つの例として、同年にニューヨーク・タイムズ紙のジェイソン・ファラーゴが書いた「Why Culture Has Come to a Standstill(なぜ文化は行き詰まったのか)」という記事がある。「最近の若者は……」という愚痴はいつの時代にもあるが、ファラーゴはこの記事で最近のカルチャー全般に対して人々が感じている不満を、過去数世紀分の文化的進歩と照らし合わせながら考察した。その論点は、アートのスタイルはもはや進歩せず、おそらく私たちが生きている21世紀は「この500年間でアートにとって最も革新的でない世紀」ということだ。
また、2024年にハーパーズ・マガジンに掲載され、賛否を呼んだ記事「The Painted Protest(絵の形をとった抗議活動)」の中でディーン・キシックは、2010年代のアイデンティティ・ポリティクスがアートのキュレーションにもたらしたパラダイムシフトへの不満を吐露し、世界がトランプ時代に移行する前、彼が20代だった頃のアート界を理想化しながら振り返っている。
良い意味でも悪い意味でも、今のアートは昔のアートとは違う。とはいえ、どの世代も歳を重ねるうちに同じようなことを感じるものだ。上で挙げた評論で何が目に付くかといえば、世界そのものがさまざまな意味でアーティストにとって生きづらいものへと変わってしまったことに対する執筆者たちの不満だろう。
現代のテクノロジーや経済的状況によって、アメリカのアート界で働く人々はいくつもの新しい要求を突きつけられている。そして、それに応えなければいけない彼らにとって、過重労働と不安定な立場は、もはや当たり前のことになってしまった。アーティストたちがこの状況に適応してきたのは不思議ではない。また、そうした事実が「アートの最盛期が過ぎたことを意味するのではないか」と考える評論家がいるのも、少々陳腐ではあるが驚くにはあたらない。

アートは停滞し、もはや進歩しないのか?
前述のニューヨーク・タイムズ紙に掲載された評論、「Why Culture Has Come to a Standstill(なぜ文化は行き詰まったのか)」でファラーゴは、西洋文化の最盛期は過ぎたと説き、一旦その事実を受け入れてしまえば、残存する文化とより充実した関係が結べるはずだと論じている。
彼は、「かつてのように、時間とともに文化が進歩しなくなったのはなぜか」という自らの問いに、スマホなどのデジタルツールが「時系列の混乱」を引き起こしたことで、芸術の進歩という概念が意味をなさなくなったと答えを出している。その代わりに出現したのが、「永遠の現在という文化」だと彼は主張する。それを代表するのがエイミー・ワインハウスの2006年のヒットアルバム『バック・トゥ・ブラック(Back to Black)』で、そのサウンドは「新しくもレトロでもなく」「ある特定の時代に作られたという感じがしない」と指摘する。
ファラーゴが議論の前提としているこの点は特に問題ないが、そこから導き出された結論は馬鹿げている。彼の主張によると、「多くの伝統的な表現分野において、可能な形式は出尽くし」、それぞれの分野の中で大きな革新が起きることはもうない。したがって、彼の考えでは、観客はモダニズム全盛期に当たり前とされていた「優れた作品はその革新性ゆえに優れている」という考え方の残滓を手放すべきだという。しかし、そう主張する彼自身も、実際には現在の文化的状況への失望を完全には乗り越えられないでいるようだ。その後に書いた他の評論でも、アートの停滞を示す事例を挙げ続け、そのたびにニューヨーク・タイムズのこの記事にリンクを貼っているのだから。
ファラーゴが憂えていることの1つは、アートがデジタル技術を介して世に広まる際、単なるコンテンツに貶められてしまうことだ。それについて彼はこう書いている。
「20世紀に私たちは『形式(スタイル)』と『内容(コンテンツ)』を分けて考えるのは誤りだと教わった。ところが21世紀になってコンテンツ(なんて言葉だ!)は、私たちが持つ機械が十分に理解し、伝達し、収益化できる文化の唯一の構成要素として、究極の復讐を果たした」
デジタル革命は、何世紀も前の印刷機と同じように文化の生産と流通に劇的な影響を与えた。だからこそ、ファラーゴがこの記事の中で「すでに4分の1が過ぎようとしている今世紀は、印刷機の発明以来、文化にとっての革新、変革、開拓が最も少ない世紀として歴史に残りそうだ」と推測しているのは奇妙だし、笑ってしまうほど時期尚早ではないかと思う。
実際に起きているのは、テクノロジーと経済が生み出す圧力によって、ファラーゴが慣れ親しんできた文化の在り方が変化しているということだろう。ここ数十年で文化的プラットフォームは、そこで発表されるコンテンツ以上に大きな変化を遂げ、コンテンツクリエイターからAIとコラボする作家まで、アーティストの活動の仕方や動機に多大な影響を及ぼしている。ニューヨーク・タイムズという高級紙の常勤ライターであるファラーゴは、自分が就いている職業が絶滅寸前の存在で、「高級紙」という言葉が時代錯誤に感じられる今、かつて当たり前とされていた枠組みが変わりつつあることを認識している。ただし、昔の常識を手放すふりをしながらも、本心ではそれを拒んでいるのだ。
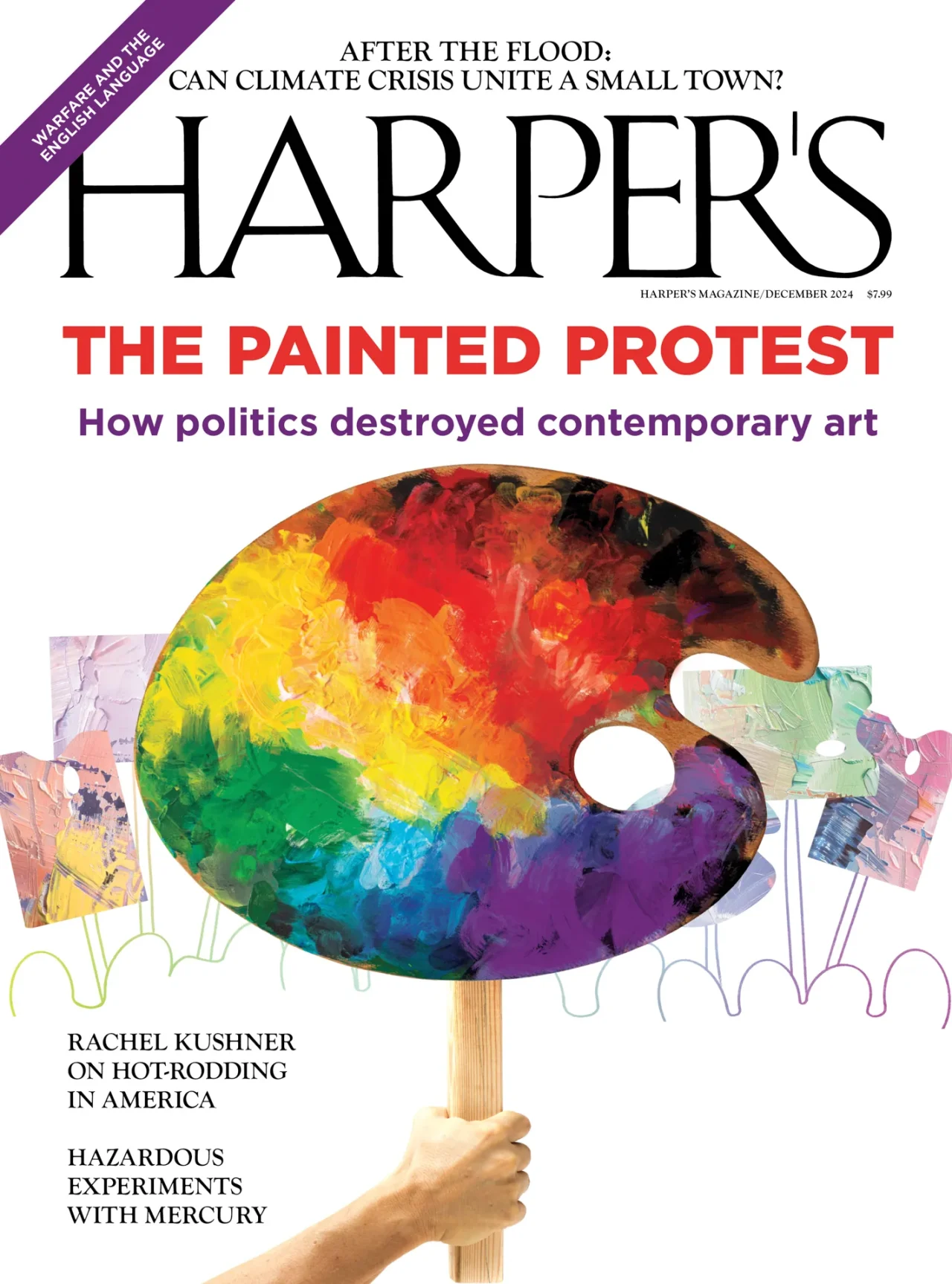
アイデンティティ・ポリティクスとアート
一方、ディーン・キシックは、若かりし日に抱いていたアートの可能性に対する楽観主義が失望に変わったと嘆いている。キシックはファラーゴと同様、現代アートが勢いを失ったのは、歴史的に周縁に置かれてきた人々や民俗の知恵といったテーマに執着しているからで、特に主要なビエンナーレでそれが顕著だと主張する。彼はまた、これもファラーゴと同様、「スピンオフ、リメイク、引用、サンプリング、リバイバル」といった、映画や音楽、ファッションの分野で幅広く採用されている手法にアートが依存していることにもうんざりしている。しかし、ファラーゴと違い、世界におけるアートの役割が小さくなってしまったことを簡単には受け入れ難いと感じているようだ。
アメリカ大統領選直後の2024年11月中旬に発表された彼の評論「The Painted Protest(絵の形をとった抗議活動)」は、誰もがそれについて意見を述べずにはいられないほど大きな反響を呼んだ。キシックは、「リベラルが作ってきた秩序への信頼が2016年(*1)ごろから崩れ始め」、アイデンティティ・ポリティクスが台頭したと書いている。文化の領域で1つの時代が終了したことを明確に示して注目された彼は、同時に、偏った見方と見当違いのロマンティシズムへの批判を浴びている。
*1 共和党のドナルド・トランプと民主党のヒラリー・クリントンが大統領選挙で戦い、トランプが勝利した年。
事実、2010年代のリベラルな文化に関するキシックの記述は、論点のすり替えや誇張に満ちている(アートは歴史的に周縁化されてきた人々の声を「増幅する」ばかりで、もはや「独創的だったり、興味深いものであったりする必要はないと考えられているようだ」という主張など)。しかし、この記事の核となっているのは、ファインアートの世界に包摂性をもたらすための取り組みが、過去10年ほどの間に制度批判から制度規範へ変化していったという主張だ。
「世界で最も影響力と資金力のある大規模展覧会が、周縁化された声を盛んに増幅している今、果たしてそれらの声はまだ周縁化されていると言えるのだろうか?」 自らが発したこの問いに対してキシックは、包摂性を目指す取り組みは「完了した」と説き、さらにそれは「型にはまり、空洞化している」と言い切った。
こうした見当違いの二項対立は、あまりに問題を単純化し過ぎている。ある人々の創作物が展示施設で大々的に紹介されながら、同じ人々が政治的あるいは経済的に疎外されたままなことは十分にあり得る。とはいえ彼の主張は、2020年代に入ってアンチ・ウォーク(*2)の言説が(つまらない不平不満に終始している場合が多いにせよ)、一部のアート好きに限らず、相当数のアメリカの有権者に主流派へのカウンターとして受け入れられた理由を的確に捉えている。
*2 社会問題に対して意識の高い「目覚めた(ウォーク)」リベラル層に対し、ウォークによってマイノリティが過度に優遇され、マジョリティの権利や価値観がないがしろにされているとする立場。
近年目立つ文化的権力をめぐる衝突は、キシックがこの記事の中で紹介している事象より前から既に起きていた。そして、こうした対立が大きな緊張をはらんでいるように感じられるのは、ソーシャルメディアがそれを煽っているからだけではない。リソースの分配が平等に行われず、ほとんどの関係者が実際には非常に小さい力しか持っていないことが、かえって対立を引き起こしているのではないだろうか。
燃え尽き症候群を乗り越える前向きな評論を
過去50年間、アメリカでは新自由主義的な緊縮財政が続いてきた。それによってアーティストやキュレーター、アートライターは苦しい立場に追い込まれ、アートの世界での成功は、以前にも増してゼロサム・ゲームのように感じられる。中産階級にとって、創造的で知的な仕事でキャリアを積みながら普通の暮らしを維持できるだけの収入と安定を確保することが難しくなっただけでなく、住居、医療、高等教育にかかるコストは賃金の伸びを上回るスピードで上昇している。
展覧会のプレスリリースに書かれた理想主義的な美辞麗句が、巨万の富を生むからくりを覆い隠すこともままあるが、アート市場は物質的な格差を誰の目にも明らかな形でさらしてしまう。こうした状況下では、経済的なセーフティネットを持たないアーティストやアート業界で働く人々は、往々にして芸術的あるいは個人的なリスクを冒すのを躊躇し、安全で確実な道を選ぶようになる。
それを踏まえると、キシックの記事の中で最も注目すべき部分は、物議を醸すために彼が確信犯的に展開した前述の主張よりも、「ハリケーンHUO」の異名を持つ著名キュレーター、ハンス・ウルリッヒ・オブリストに対する、こちらが恥ずかしくなるほどの賛美ではないかと思う。2008年にオブリストのもとでインターンとして働いていたキシックは、かつての上司の多忙ぶりを懐かしみ、こう振り返っている。
「彼は休むことなく世界を駆け巡り、会うことができるすべての人に会い、人と人とを直接、あるいは、2台のブラックベリーを駆使しながらメールで引き合わせ、彼らの間で対話が交わされることがいかに重要であるかを説いていた」
キシックはさらに、「21世紀初頭という時代を真剣に生きる模範市民として、人とつながることを極限まで追求した」オブリストは、「自滅寸前まで自分を追い込んでいた」とも書いている。しかし、アートの世界は常識に囚われず気ままに生きられる場所だと同じ記事で書いておきながら、元上司の猛烈な働き方を賛美するのには違和感がある。オブリストの病的なオーバーワークは、デジタル時代における長時間労働礼賛の原型だ。今日アート界で働く多くの人々は、経済的な必要性に迫られ、あるいは自分の役割の重要性を確認したいあまり、あるいはその両方の理由から、24時間いつでも対応できることを是とする過度なプロ意識を持っているが、その雛形を見ることができるのがオブリストの生き方だ。
私は30代になってから古着屋に行かなくなった。そして同じ頃にアートギャラリーを日常的に訪れるようになった。それはある意味、ある趣味を別の趣味に置き換えただけとも言えるだろう。双方の趣味から得られる楽しみには似たところがあり、現実的な理由もある。
プロのライターとしてアートについて書く機会が増えるにつれ、ほかのことに費やせる自由時間は減っていった。そんな生活をしながら服を揃えるために古着屋めぐりをするのはあまりに非効率的だったのだ。過密スケジュールの中でエネルギーを節約するため、私はシーズンごとに社交や仕事などそれぞれの場面に応じたコーディネートを決め、ユニフォームのように使いまわした。このHUO流ライフハックは私の毎日をより効率的にしたが、それによって、個性的なアイテムを古着屋で探す理由もなくなってしまった。
オブリストによって業界標準となった働き方からくる肉体的な疲労は、2020年代の評論家たちが嘆く美的表現の枯渇の下地を作ったと言える。文化的な仕事に就いている人々は、滅多なことでは成功できないと思い込まされ、不安に駆られて息つく間もなく動き回っている。しかも、彼らの不安には少なからず真実が含まれているのだ。
とはいえ、批評家たちがこれほど多くの作品をつまらないと言い切るのは、彼らが常に刺激にさらされ続け、燃え尽き症候群に陥っていることが関係してはいないだろうか。このことは、真面目に考えてみる価値がある。ほとんどのアート関係者は、過労と低賃金に喘いでおり、出会い系アプリのように無数の選択肢の中から見るべき展覧会や文化イベントを選ぶことを迫られる。その圧倒的な量によって、個々の選択肢の輝きは損なわれてしまう。
こうして考えていくと、民族の伝統に光を当てた展示が近年流行しているのは、これまで疎外されてきた人々の仕事を正しく評価するためだけではなく、より素朴で、今ほど人々が相互に接続されていなかった時代や場所への郷愁の反映ではないかと思えてくる。キシックのような青春時代へのノスタルジーと、ファラーゴのような美術史上の黄金時代へのノスタルジーは、内容こそ違うが形は同じだ。そのことをキシックはこう書いている。
「誰もが現在から逃れたいと思っているようだ。それぞれ異なる過去かもしれないが、私たちはただ昔に戻りたいと強く願っている」
私は今でも嬉しい驚きを与えてくれるものを求めているが、歳を重ねるにつれ、それは難しくなっている。では今、私に驚きを与えてくれるのは何だろう。思うにそれは、つまらないものや変化に対し文句を言う代わりに、自分たちがぜひ見たいと思うアート界のビジョンを明確に描いてみせる前向きな評論かもしれない。だが、そうした記事はセンセーショナルな否定よりも書くのが難しく、注目度も低い。ファラーゴとキシックも、前述の記事の中で素晴らしいと思える現代アートの作家や作品を取り挙げているし、テートルも自身のサイトで気に入った展覧会についての好意的なレビューをコンスタントに書いている(酷評レビューより数は少ないが)。
彼らの視野には、芸術的活力の枯渇という陰鬱なテーマに反する明るい点もある。今も昔も、素晴らしい作品は同じ頻度で生まれている。私たちの仕事とスマホは、それを作り、見つけるための新たな機会を生み出すと同時に、新たな障害を生み出しているのかもしれない。(翻訳:野澤朋代)
from ARTnews


