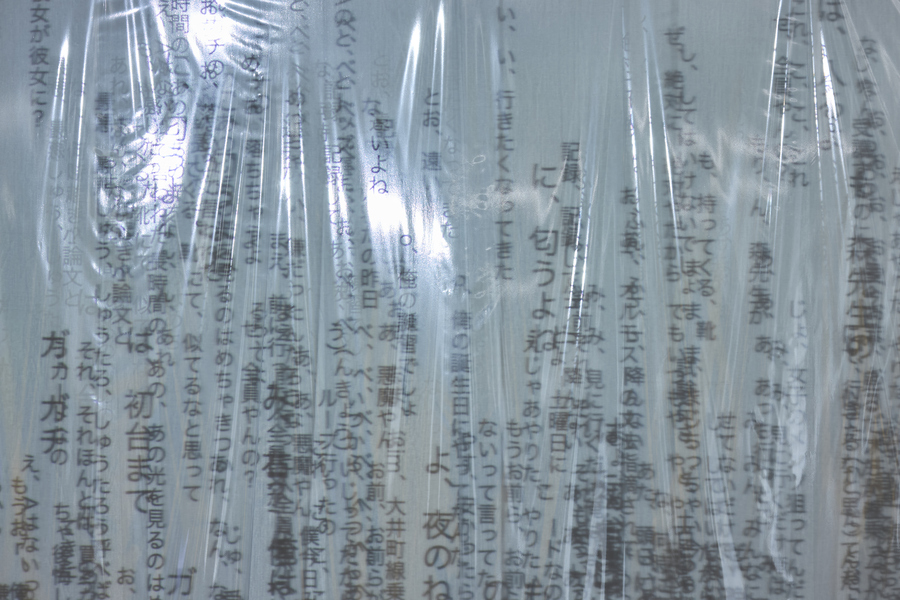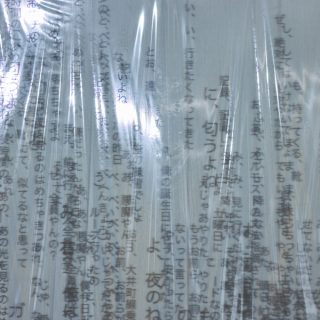学生の瑞々しい創造力をサポート──「マイナビアートスクエアアワード2025」ファイナリスト展開催
マイナビが運営するアートスペース「マイナビアートスクエア」では、初の試みとして、形式やジャンルにとらわれない新たな視点を持つ学生の作品や活動を称えるアワードを開催。ファイナリストに選ばれた4人による展覧会が9月27日まで東京・銀座で行われている。

「アート」を入り口に学生や企業、アーティストらが集い、それぞれの可能性を広げ、未来を共創することを目指すアートスペース、マイナビアートスクエアは、初となるアワード「マイナビアートスクエアアワード2025」を実施した。同スペースでは、ファイナリストに選ばれた4人の展覧会が9月27日まで行われている。
同アワードは、形式やジャンルにとらわれない新たな視点を持つ学生の作品や活動を称えることを目的に創設された。その特徴は、門戸の広さだ。大学、大学院、短期大学、専門学校などの教育機関に在学中の個人またはグループを対象にしたA部門に加え、高等学校、中等教育学校などの教育機関に在学中の個人またはグループを対象にしたB部門が設けられた。
ファイナリストは、審査員の木村絵理子(弘前れんが倉庫美術館館長)、ドミニク・チェン(情報学研究者、早稲田大学文学学術院教授)、山本裕子(ANOMALY ディレクター、日本現代美術商協会《CADAN》代表理事)による書類審査、二次審査(プレゼンテーション審査)を経て選出された。選出プロセスの中でも特に二次審査は、審査員たちが一方的に評価するのではなく、年代の異なる学生たちが相互に刺激し合い、情報公開し、批評し合う貴重な機会となった。マイナビ執行役員の落合和之は8月28日に行われた授賞式で、このプロセスを「非常に意義深い場が生まれた」と評し、「特に高校生と大学生が直接交流する機会は、双方にとって貴重な経験となったのではないでしょうか」と振り返った。
ファイナリストには、A部門(大学生部門)から江口湖夏(東京藝術大学大学院)と島田清夏(東京藝術大学大学院)、B部門(高校生以下部門)から朝田明沙(横須賀学院高等学校)、村上翔哉(三田国際科学学園高等学校)の4人が選ばれ、大賞には江口、マイナビ賞には村上が輝いた。
選抜者には特典として、最大20万円の制作補助金が支給されるほか、専門家による相談セッションなどのメンタリングプログラムが提供される。さらに大賞に賞金30万円、マイナビ賞に10万円が授与された。
今回のアワードについて、審査員の木村絵理子は次のように評した。
「初開催となった本アワードの審査の過程で印象的だったのは、表現のジャンルの多様さです。そしてB部門では、応募者それぞれにとって切実な悩みや課題と向き合いながら、表現として昇華しようとする強い意志を感じました。グランプリに選ばれた江口さんの作品・パフォーマンスには、制作の動機づけとなった事象と、そこから生まれた表現との間に大きな飛躍があったことで、暴力性と危うさを伴いながらも、自由に解放されていく感覚を抱くことができました。マイナビ賞の村上さんの歌声にも、同じ広がりを感じます。言葉では説明できない思いや感覚をいかにして他者と共有していくのか、これからも表現活動を続けてほしいと願っています」
現在ファイナリストの作品は、キュレーターに慶野結香、ゲストアーティストに、壁や境界をモチーフにコミュニケーションのあり方を問う中島伽耶子を迎えた受賞展で見ることができる。以下、アワードに参加した作家4人の各作品を紹介する。
大賞:A部門(大学生部門) 江口湖夏《家庭内用発信木版印刷自動車兼パフォーマンス機》
ベニヤ板に囲まれたスペースに黒い塗料をぶちまけ、壊れたタンスを倒しては起こす。これは、「自分が車になって木版を仕込んだ家具を轟音を立てて走り回りながら子ども部屋を『ボムだらけ』にしてしまいたい」という江口の衝動から始まったパフォーマンス作品だ。制作過程で江口は、社会的には「子ども部屋おじさん」と括られる叔父の存在が動機にあることに気が付いた。叔父は自身の母親を最期まで介護し、実家の取り壊しを見届けた。その際、散乱した家のタンスから未着用の母親の着物が現れ、それを見た叔父がふと見せた表情には、言葉では言い表せない複雑な感情と時間が滲んでいたという。
マイナビ賞:B部門(高校生以下部門) 村上翔哉《ことばを話す、読む、そして歌う》
村上は、吃音という極めて個人的で身体に刻まれた現象を、「詠む(よむ)・詠う(うたう)」という詩的行為を通して、他者に開かれた表現へ変換しようと試みた。作品の前に置かれたヘッドホンをつけると、村上自身が日常会話で発するどもりの音声が断片的に流れる。と同時に、その音声を変換した文字が時に重なり合いながら壁に映し出され、会場には村上が即興で歌う声が響く。付近にはカホンと呼ばれる打楽器が置かれており、観客はカホンを打つことで歌声と繋がりを持つことができる。
A部門(大学生部門):島田清夏《L = Σ{i=1}^{N} t刹那》
日本に義務教育が導入されたのは1872年。それまで、女性の教育機会は経済的な事情や社会背景により大きく制限されていた。そんな背景の中で生きた島田の祖母は小学校に1年しか通えず、80歳を過ぎてから島田が使い終えた教科書で文字を独学した。展示室の入り口には、文字を学び始めた祖母が書いた日記やメモ、在りし日の様子や死を記録した映像が流れる。日々の出来事をたどたどしくも力強く書き記した日記からは、文字が書けるという喜びが溢れ出る。展示室の中に入ると、花火師としても活動する島田が花火火薬で燃やした祖母の「花」の筆跡を象った作品と、その様子を撮った映像作品とが展示されている。
B部門(高校生以下部門):朝田明沙《白くなって浮いた》
公園らしき場所にブルーシートが広げられた映像が流れる。シートの上にいるのは、絵の具で汚された柔らかい布で全身を覆った朝田自身だ。だが、布を脱ごうとしてもなかなか脱げない。朝田はこの作品を通して、社会によって勝手に構築されてきた枠組みが皮膚のように自己の表面にまとわりつき、いつまでも脱皮できず成長を阻害しているという感覚を表現した。映像作品の下には、そうした圧力に抗い、脱却する意思を示すかのように、絵の具が荒々しく流し掛けられた瓦礫と何かを話し続ける女性の映像が積み重ねられている。
「空へと / In Motion with the Sky マイナビアートスクエアアワード2025 ファイナリスト展 特別ゲストアーティスト:中島伽耶子」
会期:8月28日(木)~9月27日(土)
場所:マイナビアートスクエア(東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー22F)
時間:11:00~18:00
休館日:日月祝