「コレクターが消えた」──混迷のNYアートシーン、厳しい市場環境で「競争から協調」へ
低調なアート市場が続く中、ニューヨークでは新しいギャラリーのあり方を模索する動きが生まれている。フェア参加や経費の見直し、新規コレクター獲得の取り組みはもちろん、従来の「敷居の高い」イメージからの脱却を図る動きが顕在化しつつあるのだ。その最新動向について、若手からベテランまでさまざまなディーラーに取材した。

上海のギャラリー、BANK創設者のマチュー・ボリセヴィッチは、今春ニューヨークのロウアー・イースト・サイドで半年間のポップアップギャラリーをオープンした。コロナ禍以降、ニューヨークと中国を行き来する中で、BANKの展示内容を新たな観客層に届けたいと考え始めた彼にとっては絶好のタイミングだったという。
その理由として彼が挙げたのは、アジア美術に特化した非営利団体「イニシャル・リサーチ」が2025年夏に活動を始めたこと、3月下旬にメトロポリタン美術館で開幕した「Monstrous Beauty: A Feminist Revision of Chinoiserie(怪物的な美しさ:シノワズリのフェミニスト的再考)」にBANK所属アーティストのパティ・チャンの作品が展示されたこと、そして香港の有力ギャラリーであるキアン・マリンゲのニューヨーク進出だ。
3月にオープンしたポップアップギャラリーは、マンハッタンのアートシーンから温かい歓迎を受けた。しかし季節が春から夏へと移り変わる中で、ボリセヴィッチはアート市場の縮小をリアルタイムで目の当たりにすることになった。8月中旬、ポップアップギャラリーから数ブロック離れたストーン・ストリート・カフェで取材するため彼に会うと、今年ほとんどの時間を過ごしたギャラリーの鍵をアートディーラーのナタリー・カーグに返却したところだと教えてくれた。ボリセヴィッチは、市場の変化をこう説明する。
「短期間のポップアップ営業でも異変を感じました。当初は、『確かに厳しい状況だが、すばらしいコレクターがいて支援を続けてくれるから大丈夫』という雰囲気でしたが、突如として『コレクターが消えてしまった』という状況に変わったのです」
彼の言う通り、アート界にとって今年は厳しい夏になった。例年、6月のアート・バーゼル閉幕後の時期は動きが落ち着くが、堅調だったギャラリーが相次いで閉鎖し、訴訟やフェアの中止が続くなど、市場の混乱が露わになったのだ。そして秋を迎えようとする今、いくつものギャラリーがフェア参加や展覧会企画、コレクターへのアプローチの仕方などを見直している。ニューヨークとパリに拠点を持つギャラリー・ルロンのバイスプレジデント、メアリー・サバティーノは、将来に向けて前進する術を模索する業界状況をこう見ている。
「どの分野にも周期的に課題が生じるもので、それは外的要因の場合もあれば、内部の課題もあります。今はまさに外からと内からの課題が重なっていて、皆が『この状況ではビジネスを続けられない。変化しなければ』と思っているのです」
ただ、ときには天気のように自分の力ではどうにもならず、耐え忍ぶしかないこともある。チェルシー地区の老舗ディーラー、ジャック・シェインマンにとって、止まるところを知らないトランプ大統領の貿易戦争がそれに当たる。彼の見解では、2月のトランプ関税の発表が世界経済を揺るがすまで、アート市場は着実に回復に向かっていた。
「私のクライアントにはカナダ人が多いのですが、カナダに高い追加関税が課されたことなどに対する反発もあり、アメリカは敬遠されるようになりました。こういうことが追い打ちをかけてくるのです。自分では手に負えない状況なので本当に不安ですが、それでも私たちは仕事を続けています。頑張れるのは信念を持っているからですし、アートを愛し、世の中にはアーティストが必要だと信じているからです」
フェア参加を再考するギャラリーが増加

現在の市場は勝ち組と負け組に分かれつつあり、少なくとも自制することのできる者が報いられる傾向にある。ディーラーのアレクサンダー・グレイは、「今は慎重さが重要で、どのアートフェアを選ぶかを再検討し、諸経費や出張費、接待費などの見直しを図るべき時です」と指摘し、「全ての予算項目」を精査していると付け加えた。それは、2006年にアレクサンダー・グレイ・アソシエイツを設立した直後、2年間の小規模企業経営プログラムを修了して以来の方針だという。
予算の再検討をしているのはグレイだけではない。今年8つのフェアに参加したボリセヴィッチは最近、12月のアート・バーゼル・マイアミ・ビーチには参加しないという難しい決断を下した。何年にもわたる努力の末、メジャーなフェアへの出展が叶ったギャラリー経営者としてのプライドは傷つくものの、ボリセヴィッチはギャラリーにとって正しい判断だったと考えている。彼の言葉を借りれば、今後BANKは「ただ参加するため」に出展することはない。
「来年は、(特定のフェアに)適したアイデアがあれば参加します」
そう語るボリセヴィッチは、その具体例として、オリバー・ヘリングの巨大な「マイラー(Mylar)」シリーズの彫刻2点を出品した昨年のアーモリー・ショーを挙げる。ヘリングが長年拠点としていたニューヨークで、1990年代のエイズ危機の時期に制作された初期の重要作品を出展したことが評価され、両作品は美術館に収蔵された。なお、BANKは10月のアート・バーゼル・パリには参加し、エマージェンス部門でドゥイ・ハン(Duyi Han)による環境インスタレーションの出展を予定している。
今年のアーモリー・ショーのパブリックプログラムで、ケネディ・ヤンコの巨大彫刻を核としたグループ展示を行ったのは、ベテランディーラーのジェームズ・コーハンだ。彼のギャラリーも10月にパリに行くが、アート・バーゼルには参加しない。代わりにマレ地区でポップアップギャラリーを展開し、エリアス・シメとケリー・シナパ・メアリーの個展を開く。コーハンは自らの決断についてこう説明した。
「フェアは実質的に1日限りのイベントという傾向が強まっています。そうした身を削るような状況から距離を置き、人々が訪れたくなる場所を提供したいのです」
一方、ジャック・シェインマン・ギャラリーは長年、フェア参加をアート・バーゼルの主要開催地であるバーゼル、パリ、マイアミビーチにほぼ限定してきた。
「アートフェアは時代遅れのモデルになりつつあると感じます。数が多すぎますし、主催者はギャラリーのことを気にかけているように見えて、実際のところ私たちは展示のために出展料を払うだけの存在です。入場料収入を手にするのも主催者です」
そう語るシェインマンは今年はじめ、トライベッカ地区にある19世紀の建物に1800万ドル(約27億円)をかけて190平方メートル近い展示スペースを新設し、その運営に力を注いでいる。その戦略は、10年ほど前にニューヨーク州北部に開設した拠点「スクール」での経験に基づいている。
スクールは商業ギャラリーには珍しい長めのスパンで大規模展を開催し、成功を収めてきた。トライベッカで9月5日に始まったハンク・ウィリス・トーマスの過去5年の回顧展「I Am Many(私は数多くの存在だ)」も、展示期間は2カ月間とギャラリー展としては異例に長いが、これがシェインマンの新スペースの標準になる。
経費圧縮と新しいコレクター層の開拓

ジャック・シェインマン・ギャラリーからタクシーで数分の距離にあるスウィヴェル・ギャラリーでは、創設者のグレアム・ウィルソンが白いタンクトップに作業用手袋という姿で、所属アーティストのサイモン・ベンジャミンとともに《Tidalectic No. 1(タイダレクティック No.1)》(2025)の最終仕上げに没頭していた。約320キロある樹脂の彫刻に2チャンネルのビデオを組み合わせたこのインスタレーションは、大型作品を集めたアーモリー・ショーのプラットフォーム部門で発表されている。
「みんなで力を合わせて完成させたんです。樹脂を流し込む作業だけで丸1週間かかりました」とウィルソンは誇らしげに言った。「こうした作品は、1人では実現できないものです」
2021年にブルックリンのベッド・スタイ地区で開業したスウィヴェル・ギャラリーは、フェア参加を昨年の6回から今年は10回に増やす計画で、2026年もペースを落とす予定はない。この秋だけでもアーモリー・ショー、アンタイトルド・ヒューストン、アンタイトルド・マイアミに参加する。スウィヴェルはアーティストのソロブースを出展することがほとんどだが、それは所属アーティストに対する「自信」を示すことが狙いだという。
ウィルソンの人となりを表すのにふさわしい言葉は、「自信」と「頑固さ」だろう。2年前、アート市場が下り坂に転じた頃、彼はギャラリーの所属アーティストたち(その多くは20代)に作品が売れなくなったらレジデンシーや助成金を申請するようアドバイスし、パートタイムの仕事をするのも恥ずかしいことではないと言い含めた。絶対にしたくないのは、「市場の圧力に屈すること」だった。
「クローズするしかなくなるかもしれない。そうなっても堂々と自分の足で立ち去ろうと決めたんです。こそこそ消えるつもりはありませんでした」
その自信の根底にあるのはギャンブラー精神と言ってもいいかもしれない。だが、それと同時に、ケンタッキー州のブルーカラーの家庭で育まれた厳格な労働倫理を彼は持っている。ウィルソンいわく、必要最低限のリソースでの経営を貫くスウィヴェルは、若いシェフが奮闘するHuluのドラマ『一流シェフのファミリーレストラン』のようなものだ。
実際スウィヴェルは、つい最近までウィルソンとギャラリーマネージャー、そしてパートタイムのアートハンドラーだけでやりくりしていた。新しいコレクターを開拓するためのプラットフォーム「MAD54」を創設したアイーダ・ヴァルデスが、ギャラリーのセールスディレクターとして加わったのは6月のことだ。
「全ての仕事を自分でやっているわけではない、なんて格好をつける必要は感じません。壁をパテで埋めるのも、塗装も、床の掃除も、モップがけも、トイレ掃除も自分でやってます」と彼は言う。「そんなことはやってないというふりをする必要もないと思います」
スリムな運営で経費を抑えているのは確かだが、スウィヴェルの成長(ウィルソンによれば創業以来、毎年売上高が倍増している)を可能にしている理由はその経営方針にある。顧客の大半が50歳未満の若く経験の浅いコレクターなので、彼らを育てていく必要がある反面、今後、数多くの作品を買ってもらえるポテンシャルがある。それに加えて、従来のコレクター層に見られる買い控えの影響を受けにくい面もある。スウィヴェルには経験豊富なコレクターもいるが、ウィルソンは常に、「アートがかつてないほどメインストリーム化している今は、新しい層をコレクターとして迎え入れる絶好の機会」だと考えている。
若いコレクターを魅了するには?
ハーパー・レヴァインも、こうした新規コレクター獲得に長けたディーラーだ。チェルシーとイーストハンプトンにギャラリーを持ち、来春バンコクに進出する。ダウンタウンの書店とアッパー・イースト・サイドのアパートメントギャラリーも経営する彼は、バンコクでは従来型のアートビジネスではなく、展示に食や健康、日常的な体験を融合させた新しいタイプのホスピタリティビジネスを目指すという。「私たちのテーマは親密さとホスピタリティです」と言うレヴァインは、自身のハーパーズ・ギャラリーを「作品の売買と同じくらい出会いを大切にする場所」だと強調した。
この経営哲学は、既存ギャラリーの運営にも反映されている。彼が企画するのは豪華なディナーや派手なイベントではない。小規模のパーソナルな集まり、シンプルなフード、カジュアルな雰囲気で、来場者が本音で語り合える場を提供するのだ。つまり、自己顕示欲を満足させることよりも、コレクターやアーティストが顧客としてではなく参加者として扱われていると感じる環境づくりに重きが置かれている。
レヴァインは、アートを初めて買おうとする人にとっての障壁は価格ではなく、イメージだということをよく理解している。ギャラリーはたいてい敷居が高く、冷たく、場違いなところに来てしまったと思わせることが少なくない。彼はポップアップや書店イベントなど、ギャラリーは初体験という人々を惹きつけるオープンなイベントで、そんな印象を打ち消そうとしている。そこで来場者を迎えるのは、セールストークではなく普通の会話だ。
昨年9月にロウワー・イースト・サイドで新しいギャラリー、アブリ・マーズを立ち上げたフェアチャイルド・フライズも、アートの世界に足を踏み入れようとしている新しい観客層への視点を重視している。アップルやサンローランでブランドデザイナーを務め、ファッション界に豊富な人脈を持つフライズだが、アート界での経験は浅い。しかし、その適応能力は高く、この7月にはアップステート・アート・ウィークエンドで即興的な「招待制」フェアを実現。8月下旬には、初の大手フェア参加となる12月のNADAマイアミ出展を決めている。
アブリ・マーズは、グループ展「One of One(ワン・オブ・ワン)」で秋シーズンの幕を開けた。グレイ・ソレンティ、マリオ・ソレンティ、シャニクワ・ジャーヴィスなど、主にファッション写真で知られる作家たちによる親密かつパーソナルな作品を集めた展覧会で、フィリップ=ロルカ・ディコルシアやバーバラ・エスといったアーティストとしての評価が確立されている写真家も参加している。前者はデイヴィッド・ツヴィルナー、後者はチャイナタウンのギャラリー、マゼンタ・プレインズの協力による出展だ。
フライズはこの展覧会を「ファッションとアートの架け橋」と位置付け、過去10年間で大きく重なり合うようになった2つの世界をつなごうと試みている。その意図を彼はこう語る。
「私の知り合いの多くは商業美術の世界に身を置きながらも、ファインアートに強い刺激を受け、アート界と関わりたいと願っています。ただ、とっかかりがつかめずにいるのです。これまでにない、新しいコレクター層を育てる一翼を担えるのは、とてもエキサイティングなことだと思います」
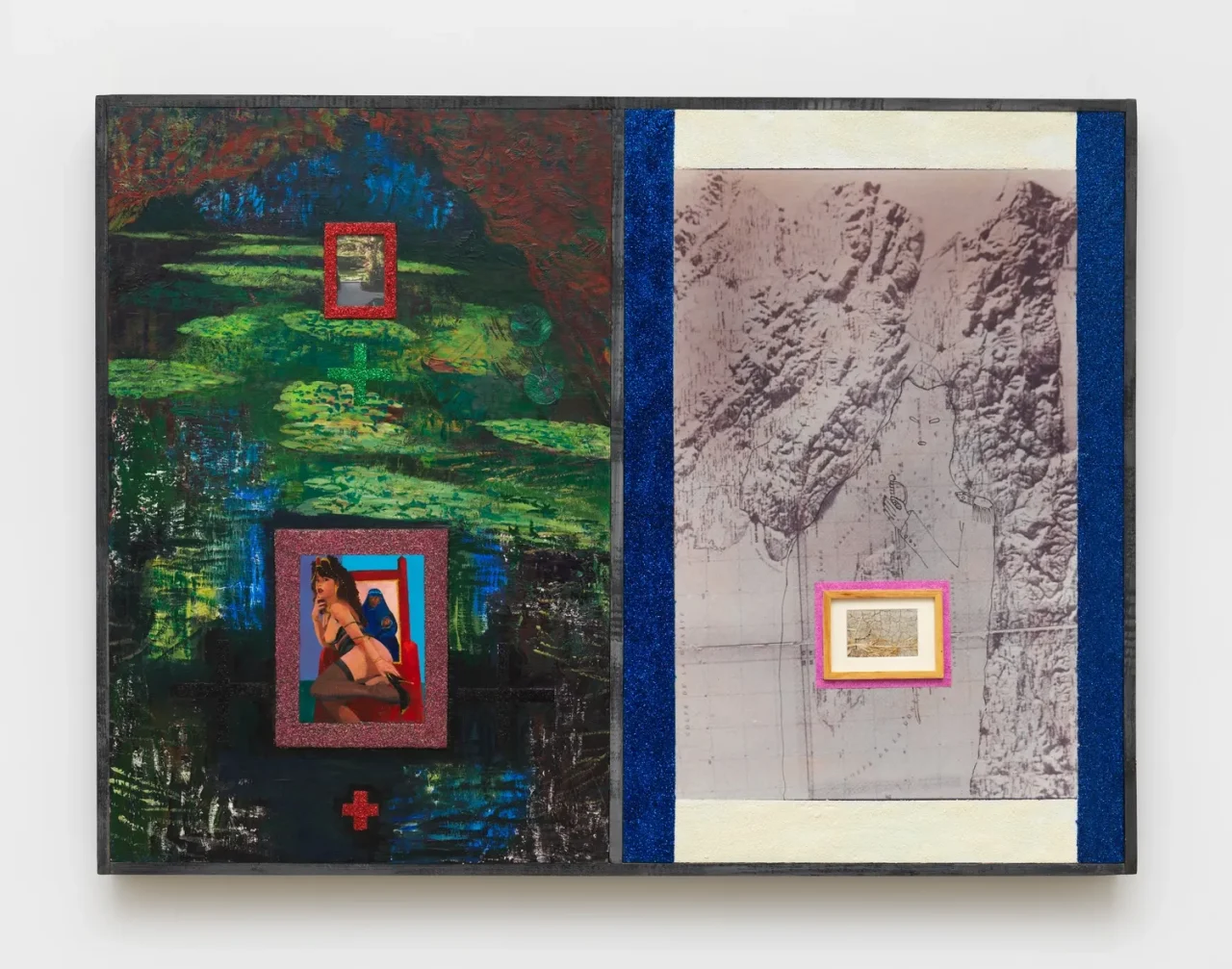
ミレニアル世代やZ世代のアート収集への関心についてはさまざまな意見があるが、マイケル・ワーナー・ギャラリーの共同オーナーであるゴードン・ヴェネクラセンは、悲観的な見方は耳に入ってこないと話す。この半年間、若いコレクターを相手にする機会が多かったというヴェネクラセンは、「彼らは真剣に議論を交わし、なぜその作品が注目に値するのかを深く理解したいと望んでいる」と語り、彼らの見識の深さを称賛した。
たとえば、顧客の1人であるロサンゼルスの若いコレクターは、フランシス・ピカビア展を6回も訪れてようやく購入に至ったという。ヴェネクラセンは、「彼には十分な知識がありました。同時に、自身にとって正しい決断を下すために時間を惜しまなかったのです」と説明する。
ギャラリー・ルロンのサバティーノによれば、中堅ギャラリーは中堅アーティストと同様、「成長痛」を経験する。中堅ギャラリーの主な問題は世代的なもので、初期に開拓した顧客は今や70代、80代、さらには90代に差し掛かっている。
「私たちはみんな同じ課題を抱えています。どうすれば顧客基盤を若返らせることができるかという問題です」
マゼンタ・プレインズにとっての解決策は、「美術館からの注目に値する」とギャラリーが考えるアーティストに継続的な焦点を当てていくことだ。たとえば秋シーズンの開幕には、ハイチ系アメリカ人アーティスト、ポール・ガルデールの追悼展を開いているが、それはガルデールの母校であるクーパー・ユニオンで最近行われた回顧展に続くものだ。
マゼンタ・プレインズの共同創設者であるオリビア・スミスは、自分とクリス・ドーランド、デイヴィッド・ドイッチュについて、「私たちはある意味アーティストです」と切り出した。「ほかにも成功の尺度はありますが、ここ数年で我われは数多くの作品を美術館に納めていますし、所蔵が決まっている作品も少なくありません。忍耐、献身、膨大な努力が必要で、ストーリーのある価値の伝え方が求められる仕事ですが、それが私たちの最優先事項で、大事にしていることなのです」
協働的なモデルに移行しつつあるアート界

一方、マイケル・ワーナー・ギャラリーのヴェネクラセンは、ギャラリーの経営モデルそのものが変わっていくと考えている。1軒のギャラリーが1人のアーティストの全てをハンドルする従来のやり方から、協力的な形態へ移行しつつあるというのだ。長年アーティストの共同代理を行っているマイケル・ワーナーのようなモデルがより一般的になると予想する彼は、パートナーシップは経営の脆弱さを示すものではなく、現実的な対処法なのだと強調する。
「アーティストが十分な作品を生み出し、ディーラーが努力を惜しまないなら、共同代理契約が機能しない理由はありません。関係者の誰にとっても間違いなくプラスになります」
ベテランディーラーのコーハンも同意見で、自身のギャラリーとケープタウンのグッドマン・ギャラリーとのコラボや、ロンドンのスティーブン・フリードマンと共同開催したナイジェリア系イギリス人アーティスト、インカ・ショニバレCBEの展覧会を例に挙げた。
「競争で共倒れになるより、顧客を独り占めすることはできないという認識に基づくエコシステムの中で活動する方が賢明です」
トライベッカには、大学のように和気あいあいとしたコミュニティの雰囲気が漂うとコーハンは言う。彼は15年以上チェルシーに拠点を置いた後、2019年に移転したが、当時はトライベッカに移るギャラリーが出はじめた時期だった。チェルシーは「熾烈な競争の場」で、「ごく一部の人を除き、コミュニティの仲間という感覚を持ったことは一度もありませんでした」とコーハンは振り返る。
ウォーカー・ストリートにはジェームズ・コーハン・ギャラリーのほかに、カウフマン・レペット、アントン・カーン、ボルトラミが軒を連ね、半ブロック先にはアンドリュー・クレプスもある。これらのディーラーにクリマンズットを加えたメンバーの協力で、コーハンはニューヨーク州北部にある約7200平方メートルの倉庫兼展示スペース「キャンパス」を立ち上げた経験がある。
「彼らと同じ通りにギャラリーを開けたのは幸運でした」と話すコーハンは、現在のような局面で生き残りを図るディーラーに求められるのは「自己改革」だと考えている。その事例として挙げたのは、ポーラ・クーパーが1980年代にミニマリズム/ポストミニマリズムからロバート・ゴーバーやエリザベス・マレーといった若手作家へ軸足を移したこと、そして、長年アルテ・ポーヴェラやトランスアヴァンギャルドを扱っていたイリーナ・ソナベンドが、1986年に当時新鋭だったアシュリー・ビッカートン、 ジェフ・クーンズ、ピーター・ハリーらを紹介する画期的なグループ展「ネオ・ジオ」を開催したことだ。コーハンはこう続けた。
「今日ギャラリーが生き残るために用いている手段は、5年後にはきっと通用しなくなるでしょう。それは全てのギャラリーが辿る道なのです。そうならないための鍵は、探求を続けることにあります。過去の栄光に浸り、そこに安住した途端、終わりが訪れますから」(翻訳:清水玲奈)
US版ARTnews編集部注:本記事の内容は、最新のアート市場動向やその周辺情報をお届けするUS版ARTnewsのニュースレター、「On Balance」(毎週水曜配信)から転載したもの。登録はこちらから。
from ARTnews


