「アート収集に未来はあるのか」──トップコレクターたちが語る、その使命と次世代への眼差し
毎年恒例のUS版ARTnews「TOP 200 COLLECORS」が発表された。一部のオークションやアートフェアで市場回復の兆しは出ているが、ギャラリーの閉鎖が相次いだ今年、トップコレクターたちはアート収集やアート界のエコシステムの将来をどう見ているのか。4つの問いに対する回答をまとめた。

市場の冷え込み、調整、低迷……どう表現するにせよ、今のアート市場は数年前までの熱狂とは程遠い。この夏には、ティム・ブラム、アダム・リンデマン、クリアリングのオリヴィエ・バビンの3人の著名ディーラーがギャラリーの閉鎖を発表した。状況は今も十分憂慮すべきだが、ジャーナリストたちはさらに未来を案じている。
ニューヨーク・タイムズ紙は5月に、「若手アートコレクターや美術館寄付者はどこにいる?」という記事を掲載。さらに6月の関連記事では、次世代は「アートよりも体験(とラグジュアリーアイテム)を重視する傾向にあり、アート収集という活動に未来はあるのか疑問に思えてくる」と不吉な警鐘を鳴らした。そんな中、US版ARTnewsは市場の現状とアート収集の未来について、有力コレクターたちに質問を投げかけた。すると、今年で36回目を迎える「TOP 200 COLLECTORS」に選出されたコレクターの回答には、冷え込んだ市場に差す光明と、希望が見出せた。
たとえばバーゼル・ダルールは、「高価格帯の冷え込みは市場の破綻ではなく調整」だとし、「真摯なコレクターにとって今は、現在進行形で価値が生み出されつつある領域、つまりキャリア形成期のアーティストたちに再び焦点を当てる機会でもある」と言う。一方、今回初めてトップ200入りしたサウジアラビアのコレクター、バスマ・アル・スレイマンはこう指摘する。「現在のアート市場の減速はチャンスでもあります。ハイエンドの作品の収集をやめるのではなく、より注意深く作品を見定めるべき時ではないでしょうか。高価な作品を一切買わないというのではなく、作品・価格・文脈の全てに納得できたものを買うべきです」
何人かのトップ200コレクターは、パトリツィア・サンドレット・レ・レバウデンゴが言うように、「収集とは責任を伴う行為」だと考えている。彼女はアート収集をこう定義する。
「芸術的探究を育み、実験が可能な環境を作るため、さまざまな人々と協力しながら進めていく取り組みです。コレクターの役割は既にあるものを支援するだけでなく、未来を形作るのを助けることだと信じています」
アル・スレイマンも同様に、「アート収集とは単に取得する行為ではなく、参加すること」だと付け加えている。
「アート収集に未来はあるのか」という問いに対し、1970年代に収集を始めたマイケル・オーヴィッツは「アートの収集が廃れるとは思わない」とした上で、「今や市場はあまりに巨大化しました。ある程度縮小して投機家たちが退場してくれれば嬉しいです」と述べた。また、このリストに名を連ねるもう1人のベテランコレクター、ラリー・マルクスは、「アート収集に未来があることを願います。そうでなければ、アーティストにも未来はないでしょう。アート収集はこれまでも多くの変化に耐えてきました」とコメントした。
今年新たにトップ200入りした40代前半のアレクサンダー・ペタラスは、また別の視点を提示している。
「若いコレクターたちは、自分たちの力ではどうにもならないジレンマに直面しています。大手ギャラリーは、若手アーティストの作品をかつてないほどの急ピッチで値上げしているため、市場に参入して日の浅いコレクターや若手コレクターは、彼らと関係を築いたり、その作品を買い集めたりする機会を得る前に市場から締め出されてしまうのです。これはアート収集の未来に悪影響を及ぼすでしょう」
多くのコレクターたちが強調したのは、所蔵作品が将来持つかもしれない金銭的価値よりも、その芸術的価値について考えることの重要性だ。ピート・スキャントランドは、それを次のように端的に言い表している。
「アート収集を、獲得すべき作品のチェックリストとしてではなく、経験やさまざまな人との関係が積み重なっていく旅として捉えるならば、時が経っても、またどんな市場環境においても、それは重要でやりがいがあり、時代にマッチした活動であり続けるでしょう」
以下、4つの質問に対するトップ200コレクターたちの回答を紹介する。
Q:アート収集に未来はあると思いますか?

アリソン&ラリー・バーグ:いつの世もアート収集には未来があります。市場だけでなく、エコシステム全体で考えることが重要です。投機的な買い手たちは、しばらく続いた活況時のような投資利益率が見込めなくなったため、今後も市場から退場していくかもしれません。ですが真のコレクターは、それよりはるかに大きな価値をアートに見出していると私たちは信じています。私たちにとってアートの真の価値とは、その永続性にあります。アート作品は、それを生み出した作家、その作家をインスパイアしたストーリー、それが象徴する歴史的瞬間や人々の活動、そして作品を収集したコレクターより長く残ります。アートは、アイデアが時代と世代を超えて伝わる数少ない方法の1つだと言えるでしょう。それは人間の存在——私たちの物語、私たちの関心や心配事、私たちが生きる土地や環境、そして私たちの生き方──を証明するものなのです。
次世代のコレクターたちがこのように考えて、アートと関わる姿を私たちは見てきました。彼らは市場への参加、そしてアーティストや美術館に対する支援を通じてそれを実践しています。よく言われるように、この世代が「物」よりも「体験」を重視しているなら、アートの存在意義は失われないでしょう。世界は猛スピードで動いており、その速度は日々加速しています。これまでと同じく、次世代のコレクターもアート作品を鑑賞し共有することで得られる「スローダウン」の感覚を大切にしているのです。
エドゥアルド・F・コスタンティーニ:アート収集に未来があることに疑いはありません。人間には、物を集め、保存したいという自然な衝動があります。対象はアートに限りませんが、その欲求は消えないでしょう。確かにこの3年ほどアート市場は困難な時期にあり、その中でさまざまな変化が見られます。テクノロジーとより深い関係を持つ新世代は、これまでのコレクターとは異なる習慣や嗜好を持っています。それでもアートは永遠であり、収集という行為もまた永遠に続いていくと確信しています。
バーゼル・ダルール:未来はあります。ただ、過去とは異なる姿を見せるでしょう。次世代はアートそのものを拒絶しているわけではなく、それにアクセスするための時代遅れのシステムを拒絶しているのです。若いコレクターたちを見ていると、彼らが驚くほど価値観に重きを置いていることを気付かされます。彼らは透明性や納得感、そして意味のある関わりを求めていて、作品の購入を単なる取引や成功の証とは見ていないのです。私がダルール・アーティスト・コレクティブを設立した理由の1つは、この世代の価値観に応えることにあります。若手コレクターにアドバイスをするとしたら、こう言います。トレンドを追うのではなく、心を動かされた作品から買い始めること。アーティストと話すこと。文脈を理解すること。そして、量より質を重視して買うことです。
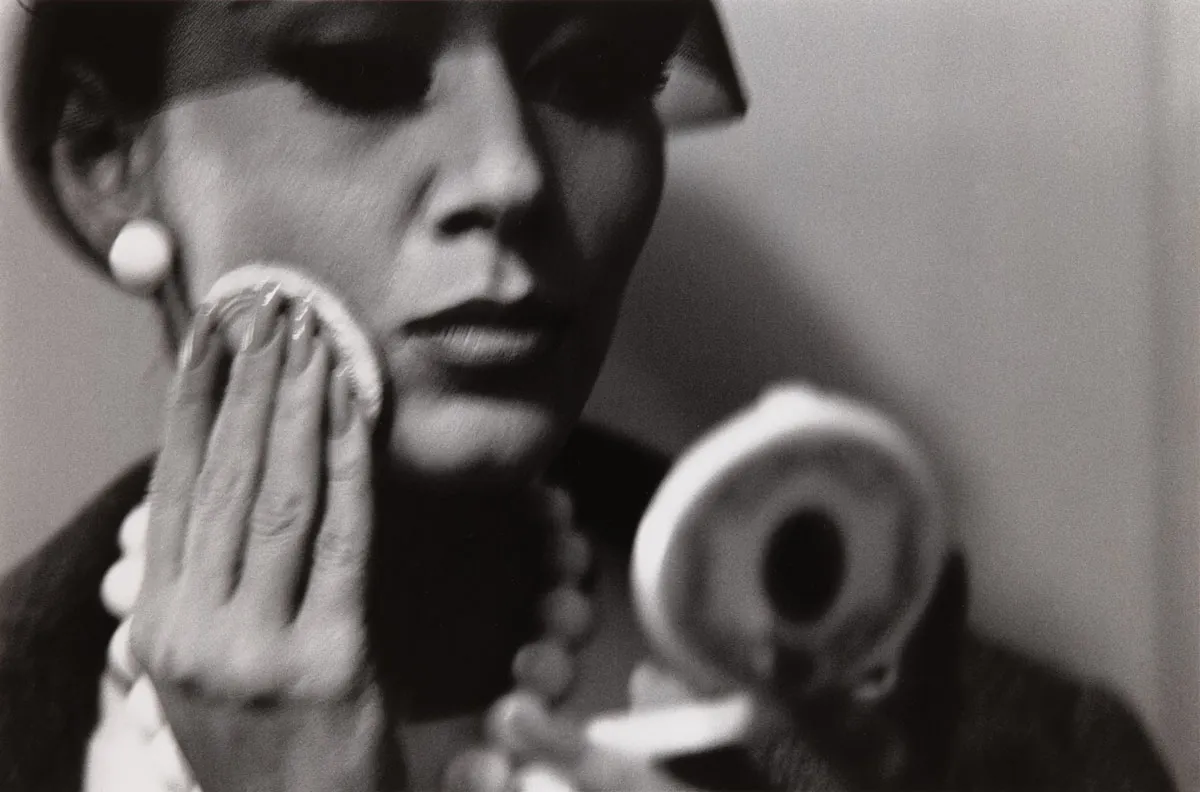
ニコラ・エルニ:多分、未来はあるでしょう。アート収集を含むさまざまな分野にソーシャルメディアが与えた最初のインパクトは薄れていくと思います。けれども展覧会巡りが好きな若い人もいますから、いずれ彼らの間で収集熱が復活することを願っています。
パメラ・J・ジョイナー:私の個人的経験は、ニューヨーク・タイムズ紙が最近報じたような状況とは異なります。私は、アートとアーティストの支援を日々の生活に組み込んでいる何人かの若手コレクターと定期的に話しています。彼らはそうした活動を通じて、美術館に強い関心を持ち、展示施設を支援することがいかに重要かを理解しています。こうした若い目利きたちは既存の伝統の一部を受け継ぎつつ、これまでの世代よりも速いペースで革新を起こしていくでしょう。この若いエネルギーが生み出す新しいパラダイムの到来に胸が躍りますし、その成果を体験できるのが楽しみです。
ロドニー・ミラー:最近、私の子どものマッケンジーとメリットがアート収集を始めました。私とは感性が異なりますが、家族で楽しみながら多くのことを学んでいます。友人の中にも、子どもたちがアートの収集を始めたという人が大勢いますし、私の収集サークルには、熱心な若手コレクター仲間が何人もいます。私が見た限りでは、パトロングループや展示施設の理事会への加入を含め、近いうちに新世代のコレクターたちの大きな波が来るはずです。

マイケル・オーヴィッツ:アートの収集が廃れるとは思いません。市場には新規のコレクターが想像以上に多く流入しています。私は一般論をあまり信じていませんし、人は興味を持ったときに自然と関わりを持つようになると思っています。1970年代に私がコレクションを始めた頃を振り返っても、同じことが言えます。レオ・カステリの顧客名簿に記載されていたのはせいぜい250人程度でした。私はカステリの招待状を収集しているので、その数が分かるのです。今は、平均的なアートディーラーのメールのリストは2万5000人に達するでしょう。私が収集を始めた頃にも、「市場はこれ以上成長するのか」という疑念はありました。しかし、市場はあまりに巨大化しましています。ある程度縮小して、投機家たちが退場してくれれば嬉しいです。
エミール・スティップ:最近ニューヨーク・タイムズ紙にこんな記事がありました。音楽評論家やジャーナリストがクラシックファンの高齢化を憂慮する現象が数年に一度起きるが、実際はクラシック音楽の聴衆の年齢層は常に高かったというのです。人は一般に年を重ねるほどクラシック音楽を深く味わえるようになるものですが、アート収集もそれと同じです。初めて絵画や美術品を購入したときから、人はアートと新たな関係性を築き始めます。作品と共に暮らし、アートについて深く考えるようになるうちに収集にのめり込む人も出てきます。でもこれには時間と成熟が必要です。幼少期からアートに親しんできた人であってもそれは変わりません。
高橋龍太郎:アート収集に未来があるのか疑問に思う人にとって、収集は無意味です。遠い未来について思い煩うかわりに、目の前の作品に魅了され、購入せずにはいられない人だけに、収集の神は微笑むのだと思います。
カール&マリリン・トーマ:作品の収集が究極の目標であるべきとは考えていません。音楽やライブパフォーマンスのように、人は何らかの形で作品に共鳴し、心を動かされたり、自分を理解してもらえたと感じたりするからこそ、作品に愛着を持てるのです。若い世代が、パーソナルかつ意味ある体験としてアートを捉えられれば、また、インスピレーションを与えてくれるもの、喜びや安らぎの源としてアートを見ることができれば、自然とそうした感情を生じさせる作品と共に生きたいと思うようになると思います。作品の値段や収集品の数を重視するのではなく、作品と個人的なつながりを築くことこそが収集の醍醐味だと考える人が増えることを願っています。
ソーニャ・ユー:潜在的なパトロンやコレクターは、アート界とのより深いつながりを求めています。アートそのものは彼らにそれを提供しますが、収集に関してはそうだと言えません。金銭面のほかにも、情報が流通する範囲が限られているなど、あまりに参入障壁が高いのでアートに興味を持ち始めた人々には参加しづらく、結果として彼らがアートに投資しようと思える環境になっていません。アート自体の体験を通じて彼らを温かく迎え入れることはできるかもしれませんが、それは大きな問題への応急処置に過ぎないのです。
アートの収集はその制作と同様、自己表現です。「あなたは、なぜ自分がアートを買うのに値すると思うのですか」という態度で接するより、もっと本人に寄り添った質問をすることで、その人らしい、熱心なコレクターやパトロンが育つでしょう。「あなたは誰かに影響されて作品を買うのですか?」「家を飾りたいからですか?」「好奇心を満たすため?」など、より個人的な問いかけをするべきです。何かがうまくいくのは、人が自分らしくあるときです。そもそも取引に関わる活動だからこそ、ビジネスライクな側面を減らしていく努力が必要でしょう。
Q: 実際に次世代のコレクターと接した経験から、彼らについて感じることは?
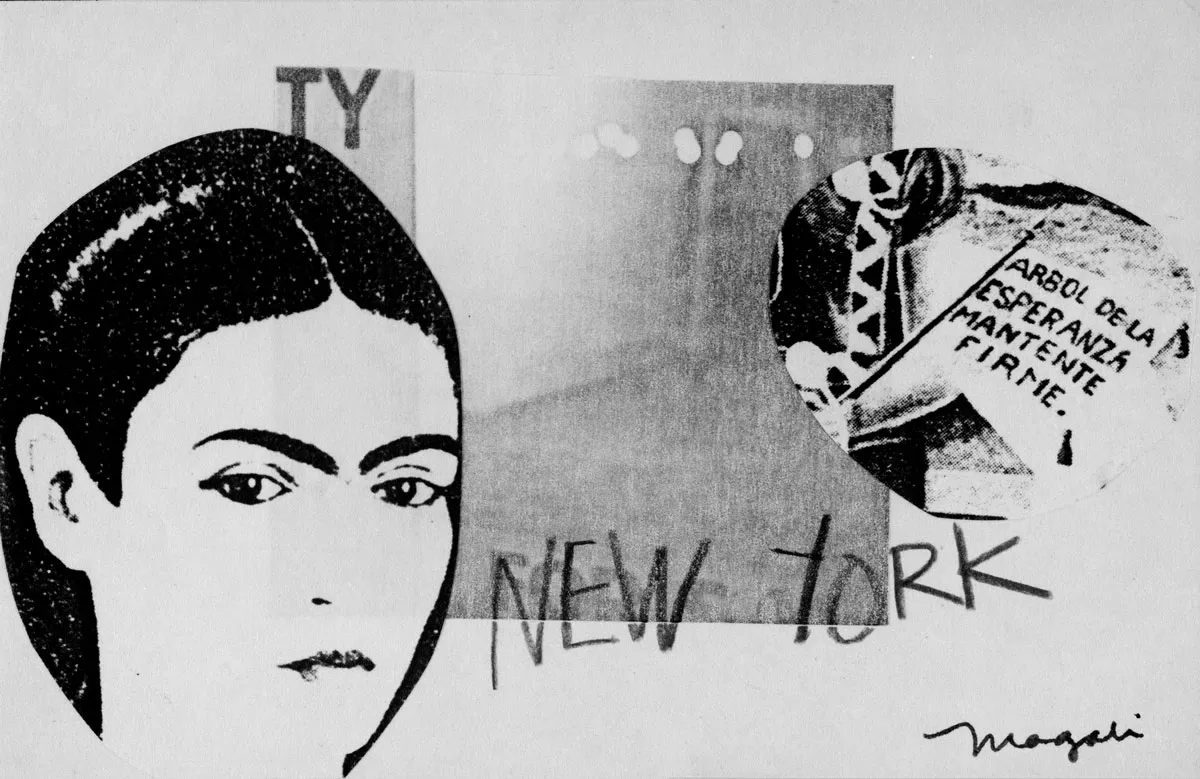
アリエル・マルセロ・アイシクス:市場のトレンドを追うよりも、透明性と革新性を重視する新世代が台頭しています。彼らは収集を「管理責任が伴う行為」だと捉えています。つまり、アーティストを支援し、新しい物語に光を当て、公共の知識に貢献する取り組みだと考えているのです。この変化はデジタルアートの領域で特に顕著です。ブロックチェーンベースのプロジェクトは、アートの来歴、流通、アクセスに関する概念を根本から変えました。所有権、取引履歴、メタデータが逐一記録され、改変が不可能なブロックチェーンは、新たな信頼性のモデルをもたらしたのです。オープンアクセスやテクノロジー面の実験を促進する戦略と、収集活動を組み合わせようというコレクターが、ますます増えています。
ロンティ・エバース:アートコレクターとなるポテンシャルを持った若い人たちが、不確実性の高い経済政治状況の影響を受けるのは当然です。彼らが体験やコレクターズアイテムにお金をかけるのは、支出を大幅に抑えつつ、すぐに満足を得られるからです。アートとその市場がもたらす喜びを理解するには、ある程度の好奇心と知性が必要です。見せ物的な売物や投機から得られる興奮はすぐに消えてしまいますが、少し勉強するだけでより多くのチャンスが訪れます。駆け出しのコレクターは興味の向くまま、これはと思う分野を探求すればいいのです。高価な作品を買う必要はありません。
デニス&ゲイリー・ガードナー:専門家ではないので、若手コレクター全般について語ることはできません。けれども、熱心なコレクターである私たちの40代の子どもたちを見ているので、次世代コレクターの傾向をある程度は把握しています。顕著なのは、子どもたちがアーティストについて学ぶ際にデジタルメディア、特にポッドキャストを多用している点です。彼らはソーシャルメディアでアーティストだけでなく、キュレーターやアートインフルエンサーもフォローしています。
また、アーティストとの関係構築を大事にしているようですが、そうしたつながりを作ることも、ソーシャルメディアの普及で以前より簡単になりました。パーソナルな意味を持つ作品に惹かれる傾向もあるようですし、主流メディアに取り上げられていないアーティストを「発見する」ことを楽しんでもいます。これがアート収集の未来について何を意味するかはわかりませんが、次世代も芸術表現の重要性を認識しているということを示唆していると思います。

グラジナ・クルチク:ポーランドではダイナミックな経済成長と現代アートの伝統が相まって、ますます多くの若い人たちが積極的にアートに関わり、確かな考えと目的意識を持ってアートを収集しています。さらに興味深いのは、文化施設の必要性を感じ、私設美術館を建てたいと考える人が増えていることです。世界に目を転じれば、各国の若者の間で似た傾向が見られると思います。新しいものに熱狂した後に過去への好奇心が高まり、現在が過去とどうつながっているかを理解したいという欲求が生まれているのです。
ジェニファー&アレック・リトウィッツ:私たちはコレクターとしての旅に、息子たちを同行させてきました。彼らは皆、世界中のギャラリーや美術館、アートイベント、アートフェアを私たちと共に訪れています。家族で視覚芸術への情熱を共有し、文化的遺産の継承と芸術へのコミットメントの意識を育めたことに喜びを感じています。
スザンヌ・マクフェイデン:私が知っている若いコレクターたちは、自分らしい芸術支援のあり方を模索しています。これは、展示施設がこれまでのような寄付者を当てにできなくなったことを意味します。軟調なアート市場や、多くの人々にとって不安定な経済状況だけでなく、いろいろと世界的な問題がある今、事態は深刻だと感じられるかもしれませんが、ここ数年続いた熱狂をリセットできる絶好の機会だとも言えます。私の意見はずっと変わりません。情報を集め、たくさんの展覧会に足を運んで「見る目」を養い、人から聞いた話ではなく自分の目を信じて購入することです。
ナンシー・A・ナッシャー、デイヴィッド・J・ヘミセガー:アート収集は、美術館や私たちのアートとの関わり方と同じで、常に進化しています。次世代には非常に大きな可能性を感じています。ナッシャー彫刻センターでも多くの若者が積極的に参加してくれていて、その姿に勇気づけられます。彼らは好奇心旺盛で思慮深く、自分たちの生活や人生にアートがどのような意味を持つのか熱心に探求しています。新進コレクターへのアドバイスはシンプルです。好奇心に従い、心を動かされるアートを支援し、作品を作った人々やそこに込められた考え方と積極的に関わってください。

プラット・“チャン”・オーサターヌクロ:私を含め、新世代のコレクターは好奇心旺盛で、オープンマインドです。収集はパーソナルな行為ですし、スニーカー、ビンテージワイン、アート・トイ、時計など、何であれ集めることには喜びがあり、私もそうした物を収集しています。しかしアートはそれらとは別の何かを与えてくれます。それはゆっくりと燃え上がるような、より深い共鳴です。アート作品は心の中に残ります。それは挑戦であり、慰めをでもあり、その2つが同時に感じられることもしばしばです。確かにアートの世界には、人を気後れさせるところがあります。特に始めたばかりの頃は、難しく思えるかもしれません。しかし一度アート収集の世界に足を踏み入れれば、それは単に何かを所有することではなく、時代や文化、世代を超えた対話に参加する行為であると気づくはずです。
セシリア&エルネスト・ポマ:子どもたちを通じて、次世代のアートコレクターとはどういうものかを目の当たりにしています。お気に入りの新進作家の作品に興味を示す彼らの姿を見て、私たちも一緒に学び、新たな才能を発見する機会を得ています。今や、私たちのコレクションは「ファミリーコレクション」になったと言えます。若いコレクターに向けたアドバイスは、私たちの子どもたちへの助言と同じです。アートを投資対象として捉えず、心に響く作品を集めること。本当に共鳴できる作品を見つけられるよう、学びに時間を割くこと。流行には特に警戒し、直感を信じることが重要です。
サラ&ジョン・シュレシンジャー:どの世代も多様な関心事を持っているものです。ただ、時間や資金が限られた若いコレクターにとって、アートの世界への入り口は多様性を欠いているように思います。一方で、本格的なアート収集には、年齢と経験、そしてアートに触れる機会の積み重ねによって培われる成熟と感性が求められます。アート収集には常に未来があると思います。人は収集から得られる経験と、それを共有できるコミュニティに属したいと願うはずです。
バスマ・アル・スレイマン:アート収集と文化支援のあり方は確かに変化しました。若い世代はアートへの関心を失ったわけではありませんが、彼らの価値観、そして彼らがアートに期待するものは変化しています。彼らはパトロンとしてアートを支えることや、文化的遺産を残すことに旧世代ほど重きを置いていません。この世代は展示施設への大規模な寄付や自らの名を冠した寄贈など、従来型の「社会還元」ではなく、インパクトや透明性を重視し、時代に合う方法でアートと関わりたいと考えているのです。
フランチェスカ・ティッセン=ボルネミッサ:若い世代は所有よりもプロセス、物を集めるよりも経験やアクティビズムに対してはるかに高い関心を寄せていると感じています。一部の人にとって、それは伝統的なアート収集のモデルへの脅威のよう思えるかもしれませんが、私はそこに大きな希望を感じています。それはアートと積極的に関わろうという意識の変化、静的な物としてのアートではなく、生き生きとしたパワーとしてのアートと関わろうという彼らの姿勢の表れだと思います。
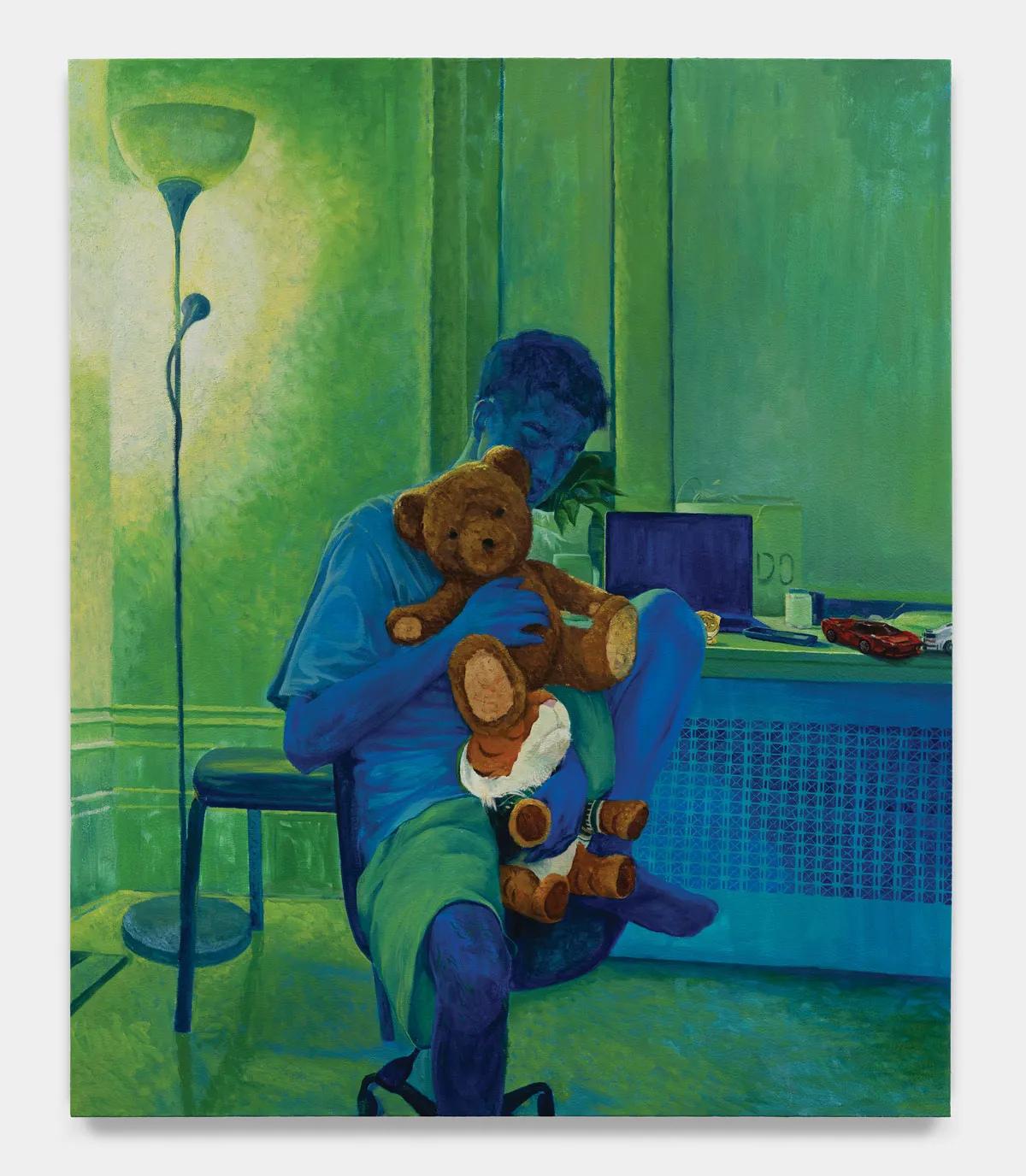
ジョセフ・ヴァスコヴィッツ、リサ・グッドマン:10年ごとに「新たなトレンド」が生まれます。人々の関心が若手アーティストから巨匠へと移ったかと思えば、再び巨匠よりも新進アーティストが持てはやされるようになります。今のコレクターは、自分が大事にされているという感覚を得たいようです。彼らは購入前に多くの質問をし、より長く丹念に作品を見て、自分が顧客として大切にされていると感じたいようだ、という話をキャラリストたちからよく聞きます。
コレクターに対する私たちのアドバイスは、以前からほとんど変わっていません。ギャラリーを訪れて気に入った作品があれば、何度もそこへ足を運んでください。全ての展覧会を好きになる必要はありません。むしろ、何が自分に合わないかを知ることが重要です。ギャラリーとの交流が生まれれば、彼らはあなたの収集活動のパートナーとなってくれるでしょう。一番大事なのは、良い投資だからではなく、その作品が好きだから買うことです。投資は金融のプロに任せましょう。「アートの富」は心に宿るものです。
ジェニー・イエ:次世代のコレクターたちは素晴らしいと思います。彼らは概して市場のメインストリームに追従せず、自分の直感を信じます。その結果、より多様で個性的なコレクションが生まれることが多いのです。
ライアン・ズラー:私は自分自身も比較的若いコレクターだと思っているので、アートや美術館をサポートする若い世代が減っているという見解には同意できません。美術館は今、運営を持続可能なものにしていくための新たなモデルを模索していますが、私はそうした動きに期待を寄せています。また、美術館支援の領域では世代の分散化も起きていて、ごく少数の超富裕層だけでなく、資金力では劣るものの、同じくらい情熱的な若手の支援者が何十人も出てきています。こうした包括的なモデルは、展示施設の公共的な性質に合致しています。
自身の所蔵作品とより深い関係を築こうとしている若いコレクターたちは、多くの場合アーティストから直接作品を購入しており、その過程で彼らと協力関係を構築しています。現代のアートは、私たちの文化のあり方を反映しているべきです。つまりこれからは、物理的な側面とデジタル的な側面の両方のアイデンティティを持つ作品がますます重要になると思います。また、絶えず進化する作品は、刻々と変化する世界に住む私たちに、より強く訴えかけてくるでしょう。
Q:収集を始めたばかりのコレクターにアドバイスをするとしたら?
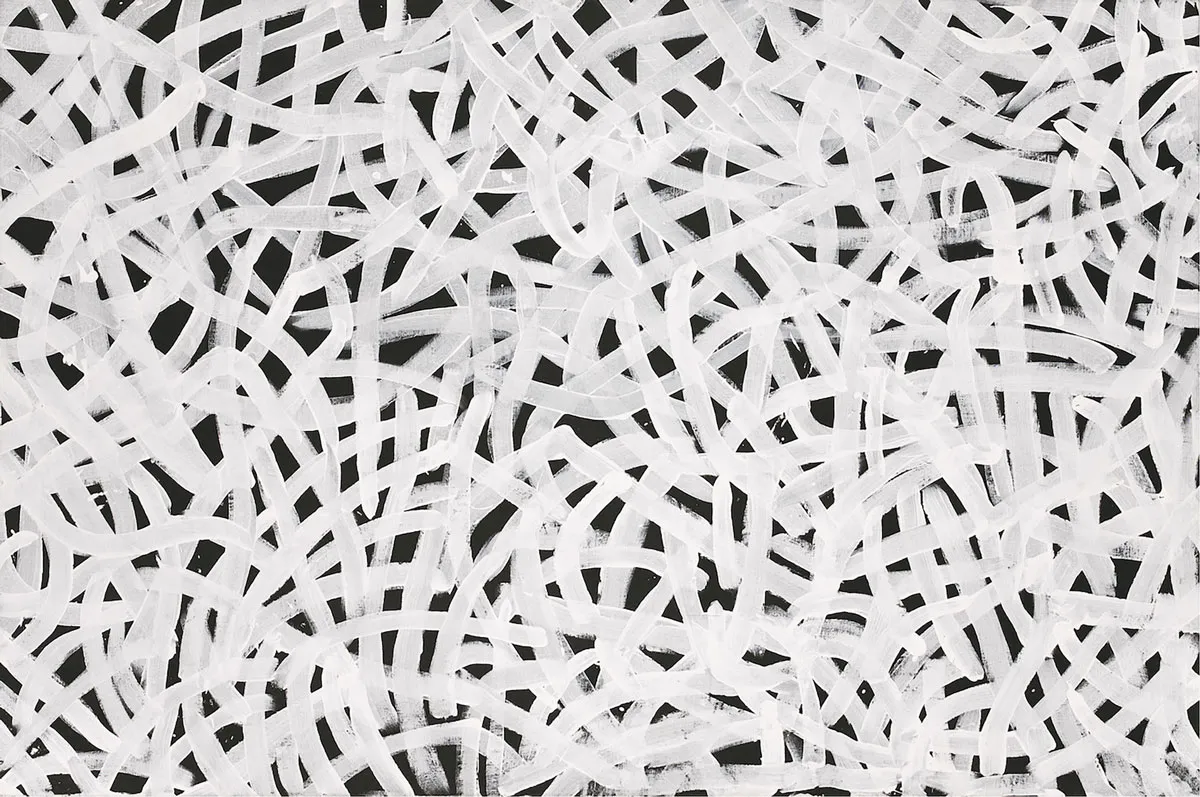
バーバラ・ブルーム=カウル&ドン・カウル: 私たちは、若い世代がアートやアートの収集に関心を持っていると信じていますし、そんな彼らを支持しています。現役アーティストが同世代のサポートを得られてこそ、アートは進化していけます。若いコレクターへのアドバイスは、自分が本当に気に入った作品を少しずつ買っていくことです。自分なりの方法で取り組んでほしいと思います。
J. パトリック・コリンズ:もし、アートが大好きで、アートと関わることで直接的・間接的に得られるさまざまなことに意義深さや満足を感じているなら、今こそコレクターとして自分を確立する時だと思います。はっきりとしたビジョンを打ち出し、独自の視点を持つアーティストやギャラリーと協力しながら、あなたらしさとこの世界の両方が反映された想像力あるコレクションを始めるタイミングは今です。これらのアート作品があなたに要求するもの、そしてそれらがあなたに与えてくれるものは、レアな革のハンドバッグや高級車を所有する経験とはまったく別物です。
また、無視できない別の力学も存在します。アートに与えられる文化的価値の多くは、「生きるという体験」と「見るという体験」を表現する作品の力、そして作品が未来へ受け継がれるに値するという点に依拠しています。そして、未来を想像するのは難しいのです。
オルテンシア・エレーロ:アートの購入について、私は常に極めてシンプルなルールを貫いてきました。自分が好きなものしか買わない──そうすれば間違いはないはずです。アートの収集を始めたばかりの人への助言は、心から好きなものを買ってください、ということに尽きます。その作品と共に暮らすわけですから。気に入らないものを毎日見なければならないのでは、意味がありません。
ミヨン・リー:アート収集は、ほかに変え難い最高の体験です。単に「モノを集める」だけでは面白くありません。私が生きてきた中で最も素晴らしい体験の多くは、まさにコレクターとしての歩みの中で得たものです。この活動のおかげで常に魅力的な人々と出会い、素晴らしい場所を訪れることができます。そして何よりも、人間として成長し続けられるのです。
ケリー&スコット・ミューラー:あなたの心や精神に響くものを購入し、財布が許すかどうかは考えないでください。
ピート・スキャントランド:新進コレクターへのアドバイスはシンプルで、次のような体験を積極的にしてほしいと思います。アーティストと会ったり、その作品とじっくり向き合ったりする時間を持つこと。簡単には理解できないかもしれないけれど、刺激を与えてくれる展覧会を見ること。展示作品の背景にある豊かな文脈と意味を示してくれるギャラリーや展示施設を支援すること。アート収集を、獲得すべき作品のチェックリストとしてではなく、経験やさまざまな人との関係が積み重なっていく旅として捉えるならば、時が経っても、またどんな市場環境においても、それは重要でやりがいがあり、時代にマッチした活動であり続けるでしょう。
フランチェスカ・ティッセン=ボルネミッサ:新進コレクターへの私の助言はこうです。アートを収集するということは、作品の所有者になるのではなく、管理者として責任を負うのだと捉えてください。私たちの未来を形作る声──既存の構造を変えようと試み、切迫感を持って活動し、自然・正義・コミュニティと関わりながら仕事をする人々──をサポートしてください。そして最も力強いアート作品の一部は、消えやすいものであることを忘れないでください。たとえば、パフォーマンスやちょっとした仕草など、人の記憶や記録媒体、観客に与えたインパクトを通じてのみ生き続ける、世界への一時的な介入です。
こうした作品が壁に飾られることはないかもしれませんが、私たちの世界の見方や行動の仕方を変える力を持っています。私にとって、ここにこそ収集の真の意味があります。それはモノへの投資だけではなく、アイデアや、アーティストがリスクを取れる環境への投資なのです。モノからではなく、問いから出発すること。そこに収集の未来があるはずです。
Q:ここ数年、ハイエンド作品の市場が冷え込む中で、多くのコレクターがより低い価格帯の作品に目を向けるようになっています。あなたはどうですか?

ペドロ・バルボサ:市場は冷え込んでいるかもしれませんが、私は気にしていません。私は常に2本柱の戦略を取ってきました。コレクションの空白を埋めるために重要な歴史的作品を獲得しつつ、それと並行して、新進アーティストや彼らを支援する小規模ギャラリーの育成にも注力しています。アートのエコシステムは、オークションハウスやメガギャラリーだけではないことを肝に銘じる必要があります。アート界の真の原動力は小規模ギャラリーや独立系スペース、そしてアーティストです。
小規模ギャラリーから作品を購入するコレクターは、単に作品を購入しているだけでなく、そのギャラリーのビジョンやプログラム、そしてその周辺のアートコミュニティに投資していることになります。そのことでギャラリーがリスクを取り、今はまだ「市場に出る」準備ができていないアーティストを支援し、重要な批評的対話を育むことが可能になるのです。これこそアート界の健全性と活気を維持する唯一の方法です。過去の遺産を売り買いするだけでなく、未来を育む責任を持たねばなりません。
アニタ・ブランチャード、マーティン・ネスビット:投機的な売買の影響で、一般のコレクターにとってアートは入手不可能なものとなっています。そのため、新進アーティストが熱心な支持者を獲得する前に、価格が高騰してしまうのです。あらゆる段階にいるアーティストを、さまざまなコレクターが支援できるよう、市場は調整されるべきだと思います。
ジェームズ・キース・“JK”・ブラウン、エリック・ディーフェンバック:私たちは通常、アーティストのキャリアの初期、あるいは比較的無名のアーティストの場合はキャリア後期の作品を購入するので、市場変動の影響をほとんど受けません。自分の興味関心と重なる企画を打ち出しているギャラリーとの関係は、非常に重要です。私たちは何十年もの間、多くのギャラリーと関係を築いてきました。
ベス・ルーディン・デウッディ:私は常にプライマリーマーケットで作品を収集してきました──そこに私の関心があるからです。もちろん、素晴らしいと思う著名アーティストもいて、機会があれば作品を購入することもあります。しかし、私の収集活動の中核は常に、直接アーティストを支援し、彼らを信じるギャラリーを応援することにあります。そこに最も大きな意味を感じてきました。次世代のコレクターには、自分らしさを大事にしながら、新進アーティストやギャラリーを支援してほしいと願っています。
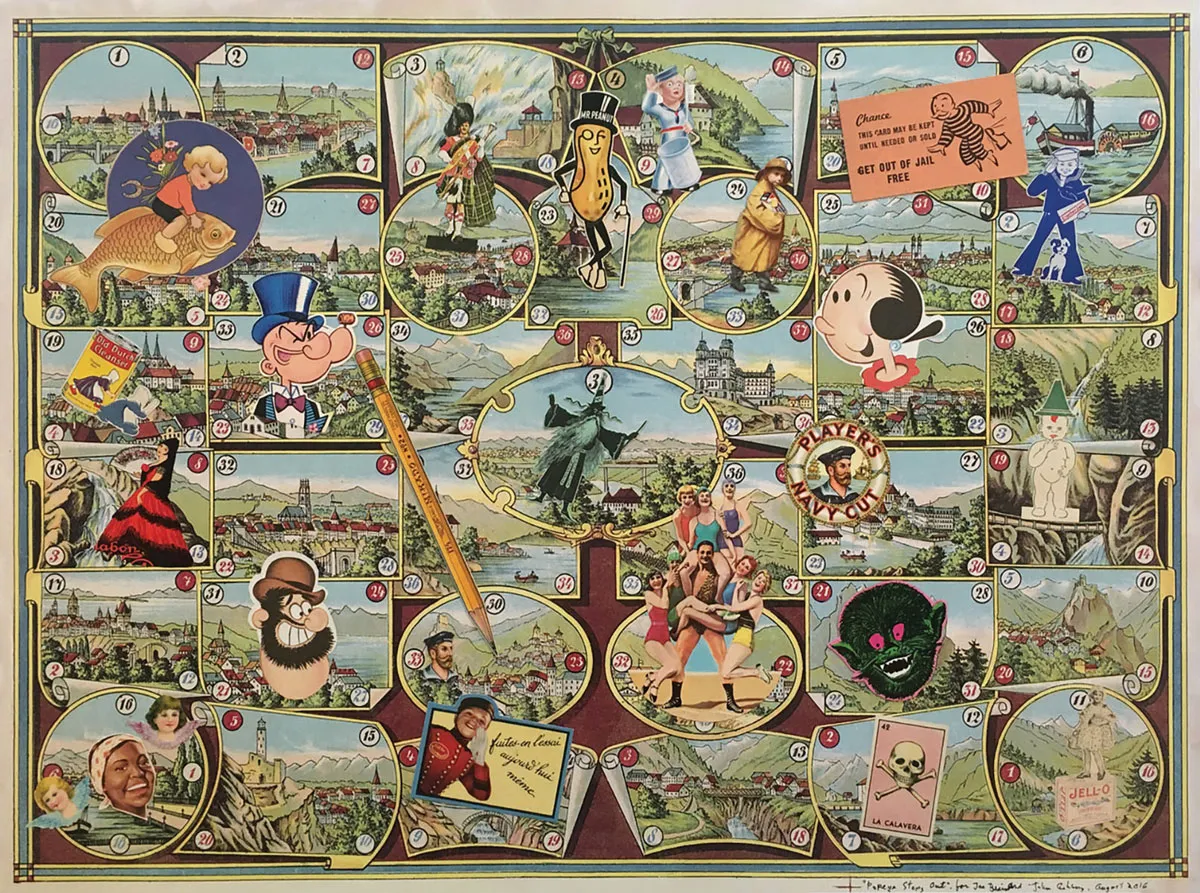
ヤン・ドゥ:私は常にキャリアの初期段階にいるアーティストを支援してきましたし、彼らのギャラリーとも緊密な関係を築いてきました。私のコレクションのカギとなる部分は実験的なアーティストや新進アーティストの作品で、それは映像作品からインスタレーション、彫刻まで多岐にわたります。新進アーティストと著名アーティスト、新しいギャラリーと大手ギャラリーを並行して支援するのが私のスタイルです。美術史的な基盤の上で新たな対話が生まれることが重要だと思うからです。隠れた名作を発見する喜びは今も変わりません。そうした作品には滅多に出会えませんが、機会が訪れたら絶対に逃しません。
エリ・クーリ:確かにそうした変化は起きていて、私自身の購買行動にも当てはまります。市場の上位層だけが意味のある収集の場ではないという認識が高まっていますし、駆け出しのアーティストを支援することは非常に大事です。彼らが時間と共に成長するのを見守ったり、その表現や技法の変遷を見届けたりすることができ、単に何かを購入するだけでなく、何かが築き上げられるプロセスの一端を担っていると感じられるからです。現在と未来を形作っている存命アーティストたちこそ支援すべき対象です。作品を購入することで、アーティストが創作活動を続け、果敢にリスクを取り、芸術的実践を前進させる助けとなります。
チーチ・マリン:私は著名作家の作品を追い求めたことはありません。常に、自分がこれだと信じるアーティストやギャラリーを支援することに焦点を当ててきました。それが低価格帯の作品であることも多いですが、そうした購入が思った以上に大きなインパクトとなります。アーティストの創作活動を支え、小規模なギャラリーの存続を助け、文化的なエコシステムを持続させることにつながるからです。ギャラリーのビジョンに共感するなら、彼らを直接サポートすることがコレクターにできる最も重要な行為の1つです。主に新進作家やマイノリティ作家を扱っているギャラリーの場合はなおさらそうです。
キラン・ナダール:バランスが重要だと思います。著名作家の作品を購入することには常に意義がありますが、キャリアの初期段階にあるギャラリーやアーティストを支援することも同じく重要です。単に低価格で買えるからではなく、才能を育み、アーティストの成長を支えるエコシステムを保全する長期的な価値につながるからです。新進・中堅アーティストと関わることで、独自のコレクションを構築できるだけでなく、アート界全体の活力にも貢献できます。
また、信頼するギャラリーのプログラムを支援することで、波及効果が生まれます。ギャラリーはその資金を使って意欲的な展覧会を開いたり、実験的な試みを行ったりできますし、創造的なリスクを取る自信をアーティストに与えることにもつながります。私にとって収集活動の最も刺激的で意義深い部分は、まさにそこにあります。
ダーリーン&ホルヘ・M・ペレス:私たちの収集活動は、有名どころから若手まで、アート市場のあらゆる領域に及びます。どこにあろうと、自分たちにとって意味のある作品を探しています。中規模・小規模ギャラリーは今、大きな課題に直面していますが、彼らはより大きなアートのエコシステムでアーティストが育つために極めて重要な存在です。だからこそ、信頼できるプログラムを組んでいるギャラリーを支援しようと努めています。

パトリツィア・サンドレット・レ・レバウデンゴ:私は常に、アーティストとしての道を歩み始めたばかりの人を、確固とした作風を打ち立てようと試行錯誤を重ねている途中で、まだ表現が固まっていない段階から支えることが大事だと信じてきました。強いビジョンを反映する作品、知的・感情的に共鳴できる作品に惹かれます。私を動かすのは、作品が発する切迫感や、それが提起する問い、そして今という時代への貢献です。
私にとって収集とは、市場での価値ではありません。アーティストへの、彼らの成長への、そして現代アートを支えるエコシステム全体に対するコミットメントとして捉えています。そうした意味で収集は責任を伴う行為だと考えています。それは芸術的探究を育み、実験が可能な環境を作るため、さまざまな人々と協力しながら進めていく取り組みです。特に、駆け出しのアーティストに投資するリスクを取っているギャラリーを信頼することも大事です。コレクターの役割は既にあるものを支援するだけでなく、未来を形作るのを助けることだと信じています。
ボブ・レニー:この点に関しては投機家たちに論じてもらいたいです。コレクションの空白を埋めるには素晴らしい時期ですね。
クリステン・スヴェオス:アート市場の冷え込みについてはもちろん認識しています。大手ギャラリーがあまりに急ピッチで新進アーティストの価格を上げる様子に以前から驚かされてきました。多くのギャラリーは持続可能性や長い目でアーティストのキャリア形成を考えることを軽視しているように思えます。アート市場の低迷の原因は、世界的な経済不安だけでなく、こうした過剰に商業的な戦略への反動でもあるのでしょう。
ベリンダ・タノト:確かにその傾向はありますし、私もそうした(低価格帯の)作品を買っています。著名作家の作品の収集にも意義はありますが、現代における収集には責任が伴うと信じています。広い意味でアートの環境を支え、エコシステムの繁栄に貢献すべきです。つまり市場のトレンドを追うだけでなく、長期的なビジョンを持ち、実験精神や地域コミュニティとのつながりに根差したプログラムを組むギャラリーへ投資することです。
私にとって収集とは、単に作品を取得するよりずっと大きな活動です。それはアーティストやギャラリー、そしてより広く文化に関わる人々と、信頼と互いへのリスペクト、そして共通の目的に基づく永続的な関係を育むことです。私は欧米以外の地域のギャラリーを積極的に支え、特にアジアや南米の女性など、過小評価されてきたアーティストがもっと広く知られるよう優先的にサポートしています。
メイ&アラン・ウォーバーグ:私たちは多様な成長段階にあるアーティストやギャラリーを支援しています。特にリスクを取るアーティスト、あるいは多様な声を代表するアーティストを優先的に支援していますが、これはより広いアートのエコシステムの健全性にとって不可欠なことだと思います。コレクターは、あらゆるレベルでエコシステムの基盤に関わることが重要です。私たちはコレクションの構築を、文化的な未来への投資だと考えています。キャリアの長短に関わらず、私たちを刺激してくれる作品を作るアーティストを支援することは、その最も直接的で影響力のある方法の1つです。(翻訳:野澤朋代)
from ARTnews


