TOMO KOIZUMIが試みる、絵画とドレスの融解と、固定観念からの解放
世界的に活躍するドレスデザイナー、TOMO KOIZUMIによる初の個展「Tomo Koizumi」が、2024年2月10日まで天王洲のYUKIKOMIZUTANIで開催されている。Tomoのアイコンとも言えるフリルをベースにした作品は絵画や彫刻のようにも見えるが、実は昨年9月にパリで「ドレス」として発表されたものでもあるという。ランウェイからホワイトキューブまで、場所に応じて概念を変える作品は、ファッションとアートの境界線を溶かしていく。

消費を加速させるファッションの世界
──今回の展覧会に先立ち、Tomoさんは昨年9月にパリでプレゼンテーションを発表されていました。パリで発表された作品は今回の展覧会ともつながっているのでしょうか?
実はパリも東京も、ベースは同じ作品なんです。ただ、パリではファッションウィークの会期中にドレスとしてプレゼンテーションし、今回はホワイトキューブの中で展示を行っています。トルソーにドレスを着せて展示してもよかったのですが、同じものを異なる形態で見せることでアートとファッションの境界線を曖昧にできると思ったんです。
──なるほど。同じ絵画作品だけれども、一方ではファッションショーという動的なプレゼンテーションの文脈の中で、壁にかけられた作品が、生身の人間=モデルによって着用されることで「ドレス」となり、それが今回の個展では逆再生される。つまり、オープニングではパリでのプレゼンテーション同様にモデルによって着用されていた「ドレス」が、人間の身体から離れ、ホワイトキューブという静的な空間の壁にピン留めされることで「絵画」になる。人が何をもって「アート」と知覚し、あるいは何を持って「ファッション」と考えるのか、という堅苦しい問いに対するTomoさんらしい軽やかな解だなと感じました。
日本でファッションの展示を行うと、展示作品に触ってしまう方が多いらしいんです。つまりファッションは着るものだから、たとえ美術館で展示されていても「触れていい」と認識される。アート作品ではありえないことです。アートにはないファッションの「親密さ」という意味でポジティブなこととして解釈することも可能かもしれませんが、同時に、アートに比べてファッションが軽んじられているということでもあると思いますし、雑に扱われてしまうのは、作り手としてはやはり悲しい。
ぼく自身、展示のためにドレスを貸し出すとグシャグシャの状態で返却されることも多いですし、ときには紛失されてしまうことも。ファッション=アートだとは思いませんが、人々の認識を変えていきたいという思いはあります。
──Tomoさんのドレスはメトロポリタン美術館にも収蔵されています。以前から、アートとして評価されることを視野に入れていたのでしょうか?
いえ、ぼくはファッションが大好きなので、あくまでファッションの延長として、アートの領域に踏み込んでいるつもりです。ただ、消耗品や実用品としてのファッションというより、美術品としても扱えるようなものに可能性を感じてきたので、歴史に残る価値のあるファッションをつくりたいと考え、制作してきました。
──その考えは、量産を避けて受注ベースでドレスを制作するというアプローチや態度にも表れているように感じます。
もちろんファッションには、いい意味での軽やかさや伝わりやすさなど、アートにはない魅力があります。でも、すぐに「商品」として消費されてしまうことに対しては、つくり手として、疲弊してしまう部分もあるんです。対するアート業界は時間の進み方はずっと緩やかで、成果もさることながら、アーティストとしての成長の過程を評価してもらえるという利点があります。
たとえばピカソを考えてみても、「青の時代」と呼ばれる時期は数年間にわたって青を基調に生と死をテーマにした作品づくりに取り組み続けていたわけですが、ファッションデザイナーは3カ月に一度新しいものを発表しつづけなければいけません。アートとファッションのはざまを漂っていくことで、自分のつくりたいものに集中できる環境をつくれたらいいなと思っています。


「作品の商品化」を避けるために
──そんなふうに考えるようになったのは、いつからですか?
2019年に初めて、マーク・ジェイコブスのニューヨークの旗艦店でショーを開催したことがきっかけとなって、制作方針について真剣に考えるようになりました。当時はブランド設立から7年ほど経っていたのですが、年に何度も新作を発表することが求められるファッション業界のスピード感のなかで自分のクリエーションを生み出すのがすごく大変だったんです。目先の新しさを追い求めるのではなく、自分が培ってきたものを大切にしたほうがいい。そんなふうに考えるようになりました。
加えて、当たり前ですがファッションショーという形態で作品を発表すると、やはりドレスが「商品」として見られてしまう。ショーをきっかけに衣装の制作依頼が増えたらいいな、とは考えていましたが、実際には有名百貨店から続々と仕入れの問い合わせが来てしまって。そもそも値段もつけていないし、量産できるものでもない。どうすればいいのか、とても悩みました。


──ファッションを見せる場で発表すると途端に「商品」として捉えられてしまう、という課題意識が、今回の展示にもつながった訳ですね。
活動のあり方について考えていくなかで、もともと自分がやりたいと思っていなかった量産品をつくるのは、中長期的な視点で考えると高リスクだと感じました。だから、むしろこれからは「仕入れられる」と思われないものをつくろう、と。自分のつくりたい一点ものの作品をつくって、美術館やコレクターの方々に購入いただく方が、ぼくのやり方には合っていたんです。
──美術館に収蔵されることは、美術史に記述されるということであり、アートとしての価値を認められることでもありますね。
ひとつは自身のクリエイションを突き詰め、オリジナルな表現を提示していることだと思います。同時に、歴史上の文脈ともつながっているものなのかな、と。説明的になるのは避けたいのですが、ファッションとしてのポップさをもちつつも、ファッションの歴史を知っている人から見ても面白さや新しさを感じられるものが残すべき作品として収蔵されていくように思います。

フリルというキャンバスが印象派を拡張する
──Tomoさんは美術大学ではなく、国立大学で美術教育を受けていらっしゃいます。そこでの学びは現在の活動の支えになっていますか?
ぼくも4年生の頃から仕事を始めていましたし、絵画のゼミに参加していたのにシルクスクリーンで印刷した布をドレスにして展示したり、そのドレスをお店で売ってしまったり……いま思うとちょっと生意気な学生だったかもしれません(笑)。
もっとも、在学中に油絵や木彫り、陶芸などさまざまな制作を体験したこと、色彩の理論について学んだことも意味があったと思います。これまでのセオリーを学びながら、どう崩すと自分のオリジナリティを出せるかを考えるようになれたと思います。
──油絵の制作にはいまでも取り組んでいるそうですね。今回の展示で油絵などを発表する予定もあったんですか?
友人の画家、佐藤允くんに教わったりして練習を続けているのですが、まだ発表できるクオリティには達していないんです。5年後くらいに何らかのかたちにできたらいいなと考えてはいます。
実は今回の展示の準備を始めた1年半前は、まだ「絵画とはこうあるべき」という固定観念に縛られていました。だから余計に、なかなか形にならず焦ったり落ち込んだりしました。その過程で、ちょっとキャンバスから離れて、いつもドレスをつくっている生地やフリルに、花や自画像を描いてみようと思い立ちました。そんな実験を繰り返していく中で、ただ思い入れのあるモチーフの具象画を描いても面白くないなと感じて、描いた生地やフリルにドレープをつけて絵を抽象化させてみたんです。そうすれば、造形的な美しさも表現できるということを発見しました。

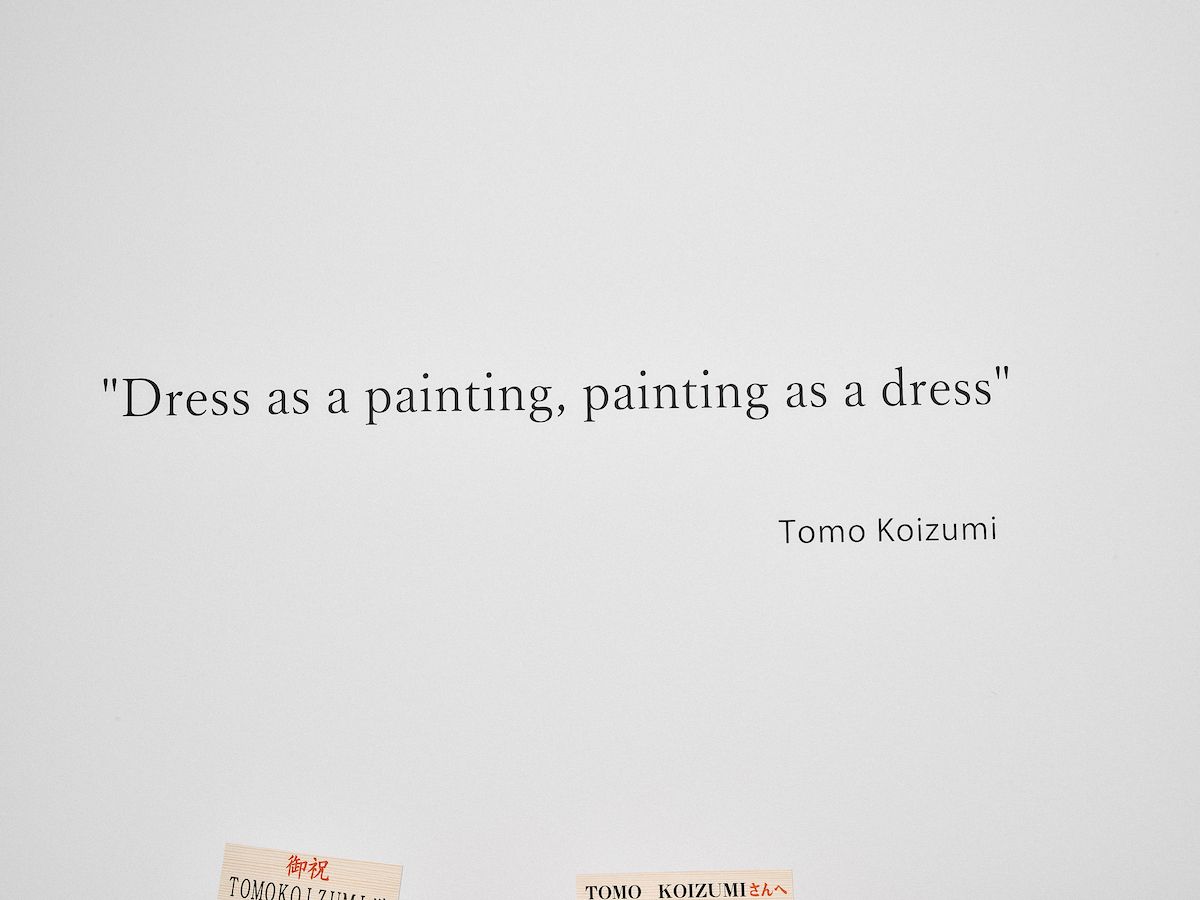
──Tomoさんのアイコンとも言えるフリルをキャンバスに見立てて、さらにそのキャンバスに動きを付けたわけですね。
今回の作品のほとんどが、筆ではなく手を使って描いています。ドレープを広げて少し距離を置いて見ると、それが絵画であることがわかると思います。
ぼくは(ピエール・)ボナールの色使いが好きなんですが、展示作品のなかには、印象派の作家が描く風景をイメージしたものもあります。印象派の絵画のなかには空気感を捉えるようなものも多いと思うのですが、フリルでできたキャンバスという、ある種、平面でもあり立体でもあるメディウムを使うことで、意図していなかったグラデーションや立体感が生まれます。フリルを使うことで、印象派の表現を拡張できるのではないかと思いました。
ドレスであり絵画でもあり、どちらでもない
──まさかフリルがキャンバスになっているとは想像していなかったのですが、ファッションの世界で追求し続けてきたTomoさんのスタイルが今回の作品にもそのまま引き継がれていて、興味深かったです。
フリルは、もはやオブセッションに近いかもしれません。とくに今回は、機械を用いて均等なフリルを作ることより、ミシンと手で有機的なラインを生み出すことに注力しました。そのほうが、予期せぬボリュームやラインが生まれるので面白いんです。画家の方が絵を描くとき、まず自分でキャンバスを貼るところからスタートすると思いますが、ぼくにとっての下地はいつもフリルなんです。
──結果として、絵画とも彫刻ともつかない作品が生まれています。
これはペインティングでもあるし、ドレスでもあります。そしてそのどちらでもない。このシリーズは今後も続けていきたいですし、さらに発展させていきたいと考えています。同時に、今回の制作で得たアイデアをドレスづくりにもフィードバックして、ドレスをつくるときのアイデアを、またアートの領域に持ち込めると相乗効果が生まれていいな、と。


──やはり「ドレス」であることが重要なんでしょうか。
ぼくは「ドレスデザイナー」と名乗るようにしてるんです。あくまでも自分がつくりたいものは「ドレス」ですから。
──テキスタイルアートの領域では、Tomoさんの作品と共鳴するようなアーティストも多そうです。今後はアートにおいても活動の領域が広がっていきそうですね。
ヨーロッパでも、テキスタイルアートがまた注目されていると聞いたことがあります。また近年、アジア系のアーティストへの注目が高まっていることは追い風かもしれません。ジェンダーの観点から見ても、ぼくのアイデンティティはクィアなので、クィアアーティストとして見られることもあるかもしれません。
こうしたアートの文脈は重要でもありますが、自分としてはあくまでも作品の魅力を前提として制作を続けていきたいです。手を動かして人の心を動かすものをつくること、美しいものをつくっていくことを大切にしていきたい。そのためには、「アート」や「ファッション」といった領域にこだわるのではなく、あちこちと適度に距離を置きながら常にマインドをフレッシュに保つ必要があると思っています。
日本の若手ファッションデザイナーのなかにも素晴らしい作品を発表している人はいますし、自分がロールモデルのひとりとなってオルタナティブなやり方を提示できたらと思っています。とくにファッションの世界では、優れた才能をもっていても商業化されてクリエイションのエッジが削られてしまうことが少なくありません。自分のクリエイションにより自覚的になることで、自分を守っていけるようになるのだと思います。

小泉智貴
1988年千葉県生まれ。千葉大学在学中の2011年に自身のブランド「TOMO KOIZUMI」を設立。2019年、初のファッションショーをニューヨークで開催し、世界的な注目を集める。翌年、LVMHプライズ優勝者の1人に輝く。2021年には、東京オリンピック開会式の国歌斉唱の衣装を手がけたほか、サム・スミスやレディ・ガガ、ビョークなどのミュージックアイコンにも、多数、衣装を提供している。
Photos: Chikashi Suzuki Text: Shunta Ishigami & Ryota Susaki Edit: Maya Nago


