パブロ・ピカソはなぜ20世紀最大の画家と称されるのか。幼年期からキュビスムの誕生まで【前編】
天才芸術家の代名詞であるパブロ・ピカソ。近年は、女性差別的な言動を批判的に捉える向きもあるが、その比類なき才能は美術界に大革命を起こし、現在に至るまで幅広い影響力を持ち続けている。ピカソの人生と業績を前後編でお送りする。

多作な天才芸術家には負の側面も
1973年4月8日、91歳のパブロ・ピカソは南仏ムージャンの丘の上に立つ屋敷で死去した。7ヘクタール近い敷地に35の部屋を擁する大邸宅で、すぐ隣にはノートル・ダム・ド・ヴィ礼拝堂がある。この礼拝堂は18世紀まで、死産した子に洗礼を受けさせるために周辺地域の人々が訪れる場所だった。
コート・ダジュールのカンヌからほど近いこの家は、ピカソが70年にわたる伝説的な画家人生で築き上げた名声と富を象徴するいくつもの屋敷の1つだった。だが、彼の人生を象徴していたのはそれだけではない。臨終のときに枕元に立っていた2番目の妻、ジャクリーヌ・ロックとの年齢差は45歳。年齢差は、ピカソがベッドを共にしたり、愛人にしたり、子供をもうけたり、精神的に虐待したりしていた多くの女性との関係に共通する特徴だ。
昨今では、好色で、良心の呵責なく女性を利用していたピカソの負の側面が注目されるようになり、20世紀美術の巨人、近代アートを生み出したエネルギッシュな天才としての評価に影を落としている。桁外れの才能ゆえに、あらゆる罪を免れることのできるスーパースター的アーティスト像の原型にもなったピカソだが、そうした生き方は、彼の仕事に垣間見られる女性嫌悪も含めて、今の世の中では受け入れられるものではない。同世代にこの手の男性は少なくなかったが、ピカソの女性観は当時の基準からしても極端なものだった。
「女には2種類しかない。女神か、ドアマットかだ」
こう言い放ったことのあるピカソは、結婚に関する考えも前近代的で、暴力的ですらあった。
「妻を変えるときは、その都度、前の妻を燃やしてしまうべきだろう。女を殺し、彼女が象徴する過去を消し去るのだ」
それでもピカソと親密になった女性たちは、ミューズとして、かつ彼を魅了すると同時に畏怖を感じさせる制作の題材として、その芸術に大きな影響を及ぼしている。
映画批評家のポーリン・ケイルがイギリスの俳優ボブ・ホスキンスを評した言葉を借りれば、ピカソは「足の生えた睾丸」で、その多作さと同じくらい性欲も旺盛だった。彼に関してはそこが難しい。ピカソを称えるには、その芸術と人物を切り離して考えねばならないからだ。とはいえ、もし彼が今生きていたら徹底的に「キャンセル」されるのは間違いないので、そんなことは無理な相談かもしれない。いずれにせよ、ピカソの偉業はあまりにも圧倒的だ。彼の功績を、あるいは人生を無視するとしたら、重要な部分を見逃してしまうことになるだろう。
識字障害を抱えながら驚くべき芸術的才能を発揮した幼少時
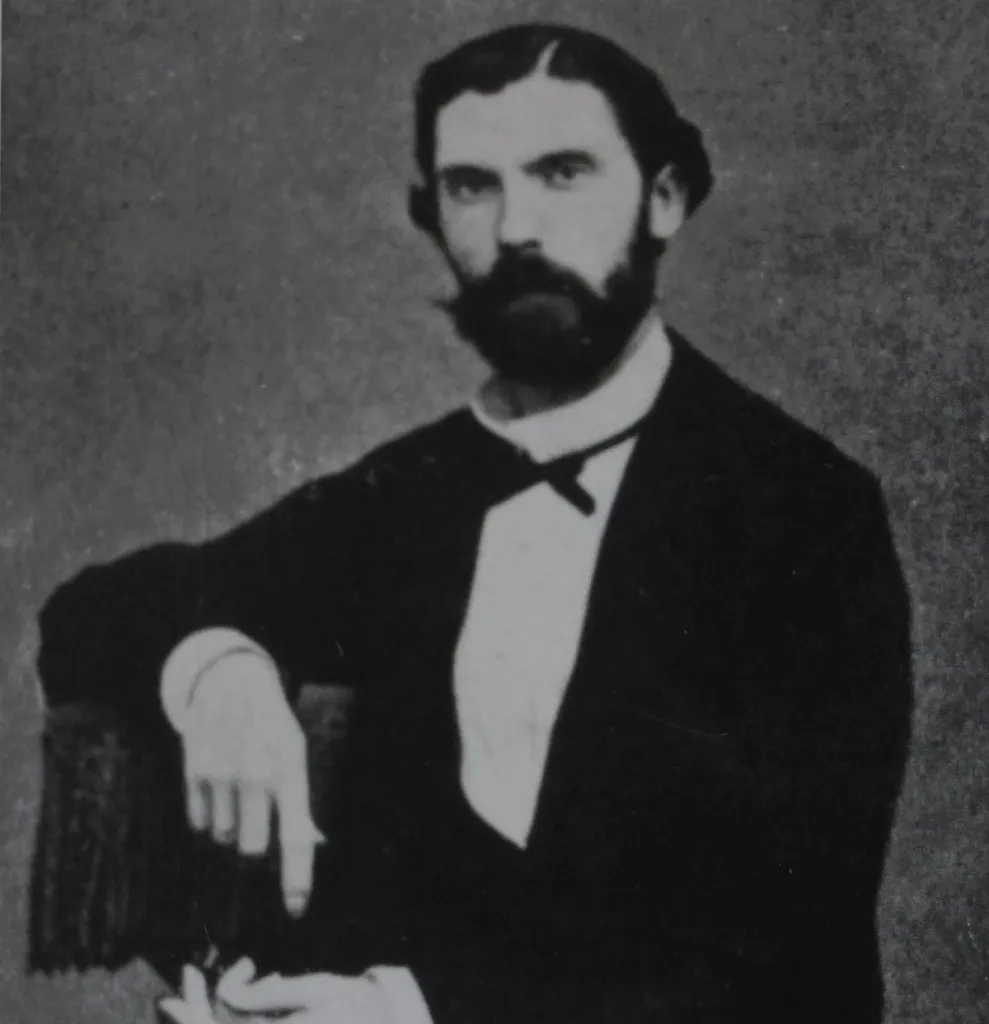
ピカソは1881年10月25日、スペイン南部の都市マラガで生まれ、パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・フアン・ネポムセーノ・マリア・デ・ロス・レメディオス・クリスピニアーノ・デ・ラ・サンティシマ・トリニダードと名付けられた。父ホセ・ルイス・イ・ブラスコと、母マリア・ピカソ・ロペスにちなんでパブロ・ルイス・ピカソと呼ばれていた彼は、やがてミドルネームを省略するようになった。そしてピカソという名は、天才芸術家の代名詞となる。
ピカソの父はマラガの美術学校の教授で、地元の美術館の学芸員だった。また、鳩をはじめ鳥の絵を得意とする画家でもあったので、ある意味、ピカソは家業を継いだとも言える。彼は幼い頃から目覚ましい芸術的才能を発揮した一方で、美術以外の科目には苦戦した。当時はまだ障害として認識されていなかったが、読み書きに困難のあるディスレクシア(識字障害)だったからだ。
出来の悪い生徒としてしょっちゅう教室から追い出されていたピカソは、その時間をノートにスケッチをして過ごしていた。読むのが苦手だったことが彼の芸術を形成したと言っていいのかもしれないが、時に対象を上下逆さまに描いたり、逆向きに描いたりしたのは障害のせいではなさそうだ。文字を読む能力の代わりに、鋭い視覚的能力が発達したのではないだろうか。
父親からデッサンと絵画の手ほどきを受けたピカソはみるみるうちに上達し、1892年に一家で移り住んだラ・コルーニャの美術学校に11歳で入学を認められた。13歳になる頃には油絵を描くようになり、その展示と販売を始めている。
カラヴァッジョやエル・グレコから受けた影響が窺える初期作品
1895年、ピカソの家族は悲劇に見舞われる。7歳だった妹コンチータがジフテリアで亡くなったのだ。それから間もなく、父ルイスがバルセロナの美術学校に職を得たため、一家はそこへ移り住んだ。ルイスは息子が受験できるよう、美術学校の入試委員を説得。受験が認められたピカソは、通常なら制作に1カ月かかる審査課題を1週間で終え、14歳で入学を果たしている。
バルセロナで才能を伸ばし、生活を謳歌していたピカソは、そこを故郷だと考えるようになった。そして、「クアトロ・ガッツ(4匹の猫)」という名のお気に入りのカフェで、そこに集う前衛芸術家たちと交流するようになる。
1897年にピカソの父とおじは、スペインで最も権威のあるマドリードの美術学校、王立サン・フェルナンド美術アカデミーにピカソを入学させることにした。この頃には16歳で入学が認められても誰も驚かなくなっていたが、ピカソはすぐに授業に飽きてしまい、欠席しがちになった。
学校に行かず、プラドなどマドリードの美術館に入り浸っていた彼は、ベラスケス、レンブラント、フェルメールといった巨匠の作品から多くを吸収した。中でも夢中になったのがカラヴァッジョとエル・グレコで、特にエル・グレコからは計り知れない影響を受けている。それがはっきり分かる作品の1つが、10年後に描いた《アヴィニョンの娘たち》(1907)だ。美術史を揺るがしたこの絵の中で、ピカソはエル・グレコの《聖ヨハネの幻視》(1608-14)に登場する人物たちを引用している。
初めてのパリ

1900年、ピカソは同郷の画家である友人のカルレス・カサヘマスとパリに行き、2カ月滞在した。その頃の作品《ムーラン・ド・ラ・ギャレット》(1900)でピカソは、繁栄を謳歌するパリの人々が夜遊びに興じる様子が描きながら、バーに集う群衆を暗闇の中に浮かび上がらせるキアロスクーロ(明暗法)の技法を使い、憂いを帯びたスペイン風のひねりを効かせている。
人物の輪郭や顔をぼかした表現は、後方で踊っている人々や左下の前景で座っている3人の女性たちに幽霊のような妖しさを与えている。半身が見切れている手前の女性の1人は、テーブルに肘をつき意味深な笑みを浮かべながら、画面の外にいる誰かを横目で見ている。これは絵のモデルをしていたジェルメーヌ・ガルガロという女性で、ピカソの友人カサヘマスは彼女に熱烈な恋をし、想いがかなわずピストル自殺をしてしまう。
その絶望的な行為は、ピカソの絵の中に永遠にとどめられた。横たわる友人の遺体をアップで描いた絵《The Dead Casagemas(死んだカサヘマス)》(1901)では、カサヘマスのこめかみに銃創がはっきりと見える。一方のガルガロは、後にピカソの愛人になった。
パリに移住。人生に大きな影響を与える重要人物たちと出会う

それからの数年間、ピカソはマドリード、バルセロナ、パリを行き来していたが、1904年にはパリに居を定める。この時期に彼は、詩人で芸術家のマックス・ジャコブ(1876-1944)と出会った。ジャコブは、ピカソの人生で重要な役割を果たした最初の人物だ。
ユダヤ系フランス人のジャコブは警官好きの同性愛者で、後にパリ郊外に作られたナチスの強制収容所で命を落としている。彼はピカソにフランス語を教え、ヴォルテール大通りのアパートで共同生活を始めたが、当時の2人は絵を燃やして暖を取るほど貧しかった。そのジャコブがピカソに紹介したのが、詩人で美術評論家のギヨーム・アポリネールで、アポリネールはピカソにジョルジュ・ブラックを引き合わせた。ピカソとブラックの2人は、のちに近代アートの一大ムーブメントを生むことになる。
ジャコブ、アポリネール、ブラックの3人は、カリスマ的なピカソを中心とした反逆的芸術家集団「ラ・バンド・ドゥ・ピカソ」の中核メンバーでもあった。このグループは過激かつ公序良俗を無視することで有名で、ピカソは有名キャバレー、ラパン・アジルの外で絡んできたドイツ人たちの頭越しにピストルを発砲したこともある。あまりの狼藉ぶりに、1911年にルーブル美術館からモナリザが盗まれたときは、ピカソとアポリネールが犯人ではないかと疑いをかけられた。
その一方で、ピカソの絵画は早くから注目を浴びていた。パリでの初期作品は、「現代生活を描く」というシャルル・ボードレールの流儀と、象徴主義の夢想を組み合わせたものだった。
底辺の人々を描いた青の時代からサーカスを題材としたバラ色の時代へ

カサヘマスの死を受け、ピカソは成熟した画家として初めて独自のスタイルを確立した。それが1901年から1904年にかけて制作された、ほとんど単色に近い「青の時代」の作品だ。「カサヘマスが死んだと知って、私は青で絵を描き始めた」とピカソは後に回想している。しかし、当時の困窮生活がもたらしたうつ病が影響していたのではないかと考える美術史家もいる。
当時は貧しく社会的地位もない青年だったピカソは、同じく社会から疎外された人々、すなわち乞食や囚人、売春婦、盲人などを題材に、カトリック的なシンボリズムに満ちた構図で絵を描いている。また、数年後に描いた《アヴィニョンの娘たち》と同様に、インスピレーションを求めてフィールドワークを行った。
たとえば、教会が運営する女子刑務所病院を訪れて制作した《L'Entrevue(面談)》(1902)には、悲哀に満ちた2人の修道女が描かれている。弱々しく儚げな人物や青みを帯びた肌など、エル・グレコの影響は、この作品だけでなく、惨めさに押しつぶされたようにうなだれる人物を描いた《老いたギター弾き》(1903)のような青の時代の代表作にも表れている。
1904年になると、ピカソは「バラ色の時代」に入る。そう呼ばれるのは、この時期の絵では赤やオレンジ、ピンクのような暖色が優位になったからだが、ほかに青や黄土色などの色も用いられている。題材に関しては、貧困にあえぐ人々に代わりサーカス団員が描かれるようになった。色彩的にもテーマ的にも以前より明るくなったものの、これらの絵画に登場する曲芸師や道化師、空中ブランコ乗りたちのほとんどは、険しい表情をしている。
かつてのサーカスには、社会に適合できない変わり者の受け入れ先という側面があった。そう考えると、青の時代とバラ色の時代に描かれているものは、別世界というわけではなく、惨めさの程度が違うだけかもしれない。バラ色の時代のピカソは青の時代の陰鬱な色彩から抜け出しているが、引き続きエル・グレコの絵のような細長い人物を描き続けている。たとえば、エル・グレコの《聖マルタンと乞食》(1597-99)を参考にした《馬を引く少年》(1905)という作品があるが、どちらの絵にも裸体で馬の横を歩く人物が描かれている。
ブラックと連れ立ってよくサーカスを訪れたピカソは、その世界への関心を深めていった。そんなバラ色の時代の絵に繰り返し登場する人物の1人が、即興喜劇「コメディア・デラルテ」のキャラクター、アルルカンだ。ダイヤ柄の独特な衣装で知られる彼は、《サルタンバンクの家族》や《アルルカンの家族》(いずれも1905年)といった作品に登場する。
バラ色の時代にピカソの精神状態が改善されたことは確かだろう。これには2つの出来事が寄与したと言われている。1つ目は、モンマルトルのバトー・ラヴォワール(洗濯船)と呼ばれた建物に、パリに来て初めて本格的なアトリエを構えたこと(のちにピカソは、自分が本当に幸せだった唯一の場所だったと回想している)。2つ目はフェルナンド・オリヴィエと恋愛関係が始まったことで、絵のモデルとして働いていたフランス人芸術家のオリヴィエとピカソは嫉妬に満ちた不安定な関係を7年にわたって続けた。オリヴィエがピカソの最初のミューズであったことは、彼女を描いた60点あまりの肖像画が物語っている。
大きな転換点となった1906年

1906年、ピカソは2点の肖像画でバラ色の時代を締めくくった。パリに住むアメリカ人、ガートルード・スタイン(1874-1946)の肖像と、パレットを持つ若い画家を描いた自画像だ。自画像の中の彼は、熟考するような表情を浮かべ、明るい未来を見定めようとするかのように画面の外を見つめている。実際、この2枚の絵は、彼の芸術的方向性と個人的な運命の転換点を示している。
小説家、詩人、劇作家として活動していたスタインは、前衛芸術の熱心なコレクターでもあった。5人きょうだいの末っ子としてピッツバーグ近郊の裕福なユダヤ人家庭に生まれた彼女は、その財力でピカソの重要なパトロンとなり、彼の地位と生活を大きく向上させていく。
スタインは、セーヌ左岸のフリュルス通り27番地の2階建てのアパートに、兄のレオと住んでいた。彼女がそこで毎週開いていたサロンには、ヨーロッパ各地やアメリカからそうそうたる芸術家や作家が集った。ピカソは1905年にスタインと出会ったが、多くの証言によれば、彼女はピカソが尊敬する数少ない女性の1人だったという。がっしりした体格のスタインは、肉体的にも知的にも手強い存在で、ピカソと同様に歴史に名を残したいという野心に溢れていた。そしてもちろん、両者ともそれを達成している。
意気投合したスタインに、ピカソが肖像画を描かせてほしいと頼んだのも不思議ではない。その申し出を承諾したスタインは、90回近くモデルとして彼の前に座らされ、ピカソが苛立ちのあまり彼女の頭部を塗りつぶしてしまったこともあったと、のちに回想している。ピカソはその後しばらくこの作品から離れていたが、結局1906年にモデルなしで完成させた。
この肖像画のスタインは、わずかに前傾して座っている。このポーズは、ピカソがルーブル美術館で見た新古典主義の巨匠ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングル(1780-1867)による《ルイ=フランソワ・ベルタンの肖像》(1832)を参照したものだ。裕福な美術品コレクターで、王党派を支持する新聞の創設者だったベルタンは、ピカソの絵のスタインと同じく堂々とした体格をしており、彼女と同じように椅子に座り、脚の上に両手を置いている。
この頃すでに、ほかの芸術家の作品を悪びれずに真似るピカソの傾向は明らかだった。彼は「良い芸術家は真似をし、偉大な芸術家は盗む」と言ったとされる。その言葉に従えば、彼の最大の盗みはこのすぐ後に行われることになる。それが、ピカソの作品で最も重要な絵画、《アヴィニョンの娘たち》(1907)だ。
《アヴィニョンの娘たち》とアフリカ彫刻の時代
1907年の夏に完成したピカソの《アヴィニョンの娘たち》は、近代アートの原点とも言える作品だ。この絵は2つの場所、すなわちピカソのアトリエとトロカデロ民俗学博物館で生まれたとされる。制作中に博物館を訪れたピカソは、フランスが植民地から収奪したアフリカの部族の仮面を見る。その影響で、この絵は当初の構想とはまったく違うものになった。
かつてピカソがアトリエを構えていたバルセロナの歓楽街にある娼館を舞台にした《アヴィニョンの娘たち》には、客に裸体をアピールする5人の女性(そのうちの1人はフェルナンド・オリヴィエがモデルとなっている)が描かれている。この絵の習作でピカソは、女性たちのほかに2人の男性を描いており、そのうちの1人は医学生だとメモに記していた。しかし、トロカデロ民族誌博物館の展示を見た後、ピカソは2人の男性を消し、3人の女性の顔を儀式用の仮面に似せて描き直している。
この作品は青の時代とバラ色の時代の両方を組み合わせた色彩で、絵の具の扱い方にはセザンヌの影響がはっきり見てとれる。より重要なのは、ピカソがセザンヌの筆致を参考にしながらも、三角形や菱形の構成で人物と背景を表現していることだ。そこでは透視画法的な遠近感が完全に取り払われ、画面の下部のテーブルに置かれた静物はのっぺりとした平面のように見える。さらに、右下の仮面をかぶった女性は、鑑賞者に背中を向けながらあり得ない角度で頭を回転させ、こちらを見ている。
《アヴィニョンの娘たち》は最初のキュビスム作品だと考えられているが、のちにアフリカ彫刻の時代と呼ばれ、1909年まで続いた時期の皮切りとなるものでもあった。制作に取り組んでいた頃、ピカソはアフリカ美術の収集も始めており、その後の3年間でさらにアフリカ色の強い作品群を生み出している。
その中には自画像を含む肖像画や女性のヌードの習作もあったが、こうした異文化の帝国主義的なつまみ食いはピカソの専売特許ではない。たとえばマティスも、アフリカのオブジェに魅了され、それを引用した作品を制作していた。そして、1909年になるとアフリカ美術の影響は薄れ始め、ピカソはまた別のアプローチを取るようになる。この方向転換の推進力になったのが友人のブラックだった。
分析キュビスムの誕生と総合的キュビスムへの移行
ジョルジュ・ブラック(1882-1963)は、パリ近郊のアルジャントゥイユで生まれ、ノルマンディー沿岸の港町ル・アーヴルで育った。父と祖父はペンキ塗りや室内装飾を生業とする職人で、彼は家業を継ぐことを期待されていた。
しかし、ブラックは職人になるための訓練を受けながら夜間に美術を学び、最終的にはパリのアカデミー・アンベールに入学した。気まぐれなピカソと控えめなブラックは気質的に正反対だったが、なぜかそれがうまく混ざり合い、美術史を急加速させた分析的キュビスムへと向かう燃料になった。
ブラックは、ピカソが《アヴィニョンの娘たち》を描いた年に彼のアトリエを訪ねている。それまで野獣派とされていたブラックだが、ピカソの革新的な作品を見て衝撃を受け、ピカソとともにその後の4年間で《アヴィニョンの娘たち》の表現をさらに発展させていった。そこから生まれたのが分析的キュビスムだ。
2人の画家はキュビスムという共同事業に全身全霊で取り組み、どちらか一方が描いた絵は、もう一方の合意が得られるまで完成したことにならなかった。この時期に描かれた2人の絵にほとんど見分けがつかなかったり、ブラックが2人の共同作業を「ロープでつながれた登山者」に例えたりしたのも不思議ではない。
ピカソとブラックは、主に静物画に取り組みながら抽象に近い表現を追求した、対象物と背景は平面的な形として同じレイヤーに畳み込まれ、奥行きの感覚は排除された。対象物はさまざまな視点から同一画面に描かれており、多くの場合、視線の移動を示唆する変化するパターンとして表現された。キュビスムは、視点を定めて静的に情景を描くのではなく、見ることの運動性を喚起したのだ。
しかし、それ以上に大きな意味を持つのは、ブラックが新聞紙や壁紙の切れ端をカンバスに貼り付けるコラージュの手法を考案したことだった。だまし絵というジャンルをメタ的に解釈したような、一見シンプルなこの手法は、20世紀のアートに多大な影響を与えた。それはアートと現実世界の距離を縮め、後のアーティストたちが用いることになるアプロプリエーション(*1)の源流となる。
*1 「流用」「盗用」の意。過去の著名な作品、広く流通している写真や広告の画像などを作品の中に文脈を変えて取り込むこと。

1914年までに分析的キュビスムの可能性を探究し尽くしたピカソとブラックは、総合的キュビスムと呼ばれる段階へ移行する。一般の鑑賞者にとっては見分けにくいかもしれないが、それぞれのアプローチには大きな違いがある。
分析的キュビスムでは、茶色、灰色、青といった地味な色彩ばかりが使われていた。この時点では、見る者の目を楽しませることより、新たな絵の見方を定着させることに注力していたからだ。一方、総合的キュビスムでは鮮やかな色が取り入れられ、テクスチャーが加えられ(コラージュもそのための1つの方法だった)、構図はより平坦でシンプルになった。
彫刻でもキュビスムで革命を起こす
絵画で有名なピカソだが、並行して制作していた彫刻作品でも20世紀美術に大きな影響を与えた。1909年にはフェルナンド・オリヴィエの胸像を、アフリカの時代と分析的キュビスムの中間のようなスタイルで制作している。とはいえ、粘土を使って作られたこの作品は、彫刻技法としては極めてオーソドックスなものだった。
ピカソは彫刻家としての正式な教育を受けていないが、結果的に立体作品に対する先入観を持っていなかったことがプラスに働いたと言える。実際、1912年に制作した《ギター》が彫刻の分野で起こした革命は、《アヴィニョンの娘たち》が絵画の分野で起こした革命に匹敵するものだ。
厚紙や紐、針金で作られた《ギター》は、複数の平面を貼り合わせたりつないだりして、今にもバラバラに解けてしまいそうに見えつつも、対象物の全体を表現している。キュビスムを立体物に変換したこの作品は、固い塊から彫り出されたのではなく、組み立てられたものだ。そのことが、彫刻の制作方法に大きな地殻変動をもたらした。
同様に、《アブサンのグラス》(1914)も後々まで幅広い影響を及ぼしている。大部分はブロンズを鋳造して作られた作品だが、最後の仕上げとして、ピカソは本物のアブサンのスプーン(砂糖の上からこの酒を注ぐのに使う)を置いた。こうして、ファウンドオブジェ(*2)を使ったアートという新しいジャンルが生み出された。
*2 自然にある物や日常生活で使われる人工物(特にアートに転用されたもの)。
一時代が幕を閉じる

ピカソが世界的に有名な画家になった1920年代の初め、彼にとって1つの時代が終わり、別の時代が始まろうとしていた。彼はもはや、仲間たちとモンマルトルを荒らしまわる貧しい反逆者ではなく、かつて親密だった友人たちも周りからいなくなった。第1次世界大戦の西部戦線で戦ったアポリネールはスペイン風邪でこの世を去り、ジャコブはカトリックに改宗してロワール渓谷にあるベネディクト会の修道院に入るためパリを離れている。
ピカソは彼らの不在を、キュビスムの傑作《3人の音楽家》(1921)で永遠にとどめた。バラ色の時代によく描いていた即興喜劇コメディア・デラルテのモチーフを再び取り入れながら、自分自身をギターを弾くアルルカンとして、アポリネールは縦笛を吹くピエロとして、ジャコブを楽譜を手に持つ修道士として描いている。
それまでの20年間でピカソは芸術を一変させた。《3人の音楽家》は間違いなく、その時代を郷愁とともに振り返る作品だ。しかしそのときの彼は、さらに半世紀にわたって作品を生み出していくことになるとは想像もしなかっただろう。(翻訳:野澤朋代)
from ARTnews


