川内理香子 Rikako Kawauchi

紙に鉛筆と水彩絵具で描いたシンプルなドローイングで知られる川内理香子。美大在学中の2015年に、資生堂ギャラリーの空間をドローイング作品のみで埋め尽くし、最年少でshiseido art egg賞を受賞し注目を集めた。以降、油彩によるペインティングから、針金、ゴムチューブ、ネオン管、樹脂といった様々な素材を用いた立体へと、表現の幅を広げているが、物の輪郭や境界となり得る「線」に対する繊細な感受性は一貫している。食と身体への関心を起点とした人体や食品といったモチーフや、神経や血管を想起させるような脈動する線が象徴的だ。また、クロード・レヴィ=ストロースの『神話論理』から着想を得て、自他の境界が複雑に入り交じる神話の世界を題材に制作を続けている。2020年に画集『drawings』(WAITINGROOM)を刊行した。
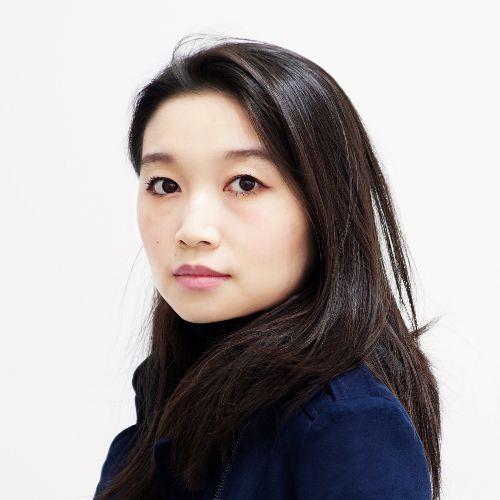
1990年東京都生まれ、東京都在住。2017年多摩美術大学大学院美術研究科絵画専攻油画研究領域修了。主な展覧会に、21年個展「afterimage aftermyth」(六本木ヒルズA/Dギャラリー)、個展「Empty Volumes」(WAITINGROOM)。22年VOCA賞、21年TERRADA ART AWARD 2021寺瀬由紀賞受賞。 Photo: Mie Morimoto
作家ウェブサイト
「制作の原点にあるのは、自分という存在の曖昧さを認識させる、身体の“他者性”」
川内理香子は、鉛筆と水彩のドローイング、油彩のペインティングから、針金、ゴムチューブ、ネオン管、樹脂といった素材を用いた立体まで、幅広い表現を用いるアーティストだ。2021年のTERRADA ART AWARD ファイナリスト展では、それら複数メディアの作品が有機的に結びつき神話の世界を彷彿とさせる展示空間を生み出した。またVOCA展2022で大賞に当たるVOCA賞を受賞。さまざまな表情を見せる川内作品のテーマについて聞いた。
食べることが突き付ける、自己の身体の曖昧さ
──川内さんは、平面から立体まで、いろんな素材を用いて作品を発表しています。制作のきっかけや、共通するテーマについて教えてください。
「食への関心から、身体をひとつの大きなテーマとして扱っています。私は幼い頃、食べるという行為が億劫(おっくう)になった時期がありました。人は空腹時には集中力が切れ、お腹がいっぱいになると体が重くなったり思考が鈍ったりします。食べることによって、自分の身体の生々しさを突きつけられるような感覚があったんです」
「臓器や筋肉といった自分を成り立たせている一番根本的な身体は、自分の意志の外にあります。自分の中に、自己ではコントロールできない部分があるのなら、自分ってなんなのだろう、と考えるようになりました」
「また私たちは、食べるという行為を通じて、自分の体の外にあるものを体内にとり込みます。血肉となって私を構成しているものは、元は私ではないものなんです。食べるという行為は、否応なく自分という存在の曖昧(あいまい)さを認識させます。身体の他者性と言えば良いでしょうか。そこに感じる居心地の悪さが、制作の起点になっていると思います」
──川内さんのドローイングの中に登場する人体とも食物ともつかないモチーフは、そうした興味から生まれているのですね。近作のペインティングでは、神話のモチーフが登場します。今おっしゃったテーマとは、どこで繋がっているのでしょうか。
「複層的なイメージを持つモチーフに惹(ひ)かれるんです。血管は木の根のように見えたり、臓器が果実に見えたり、身体の構造と食物は不思議な相似形を成すことがあります。小さい頃から食べ物の絵を描いていましたが、形状への興味も大きかったように思います」
「近作の『Mythology』シリーズは、クロード・レヴィ=ストロースの『神話論理』から影響を受けています。食に関する文献を読みたいと思っていたときに、同書の中の『生のものと火を通したもの』というタイトルに出会いました。レヴィ=ストロースは、さまざまな地域の神話を分析し、そこに登場する事物の中に、人間の身体や食の表象を読み解いています。私の作品に登場するモチーフも、神話の中で人間の身体や食を暗示するものなんです」
ドローイング作品の重み、素材との対話
美大在学中の2015年、shiseido art egg賞を最年少で受賞した川内。資生堂ギャラリーの空間をドローイング作品のみで埋め尽くした展示が話題を呼んだ。2020年に刊行した初の画集『drawings』も、2012年以降のドローイング作品をまとめたものだ。
──ドローイングを表現手段のメインにしている作家は比較的珍しいと思います。川内さんはドローイングという表現手段をどのように考えていらっしゃいますか。
「ドローイングって、一般的には、何かのためのスケッチとか、作品制作の前段階のもの、という認識があるようですね。私自身はドローイングもペインティングも同じ重みのある表現だととらえています。ですから、shiseido art egg の展示プランも、私の中では自然と生まれたものでした。展示の反響を通じて、改めて世間一般のドローイングに対する評価を知りました」
「私の場合、本画制作にあたってトレースする下絵のようなものは、ほぼ無いと言って良いかもしれません。あまり完成のイメージを決めすぎずに、鉛筆や筆の先が画面に触れたときの感触とか、その時の身体のコンディションや、その瞬間に出てきたイメージや思考に従って描いています。ネオン管の作品も、針金で原寸大の模型を作って、ガラス管の加工を業者さんにお願いしています」
「油彩でも粘土でも、融通が利かなかったり、思いも寄らない状態になったりした時に、自分がそれにどう応えていくか。作品は、そういう素材とのコミュニケーションの蓄積だと思っています。針金をこう曲げようと思っても、自分が思っていたものと違う形になることが多いです。でもそれがきれいだなと思えたらそれを取り込み、その上で次はどう曲げようと考えながら作品をつくっていきます」
──川内さんの作品は、平面でも立体でも素材の可塑(かそ)性に目が向きます。昨年(2021年)の個展「Empty Volumes」(WAITINGROOM)で発表した針金や粘土を用いた作品群は、まさに素材の中に形態を探っていくような川内さんの制作の姿勢が垣間見られたように思います。
「針金を用いた作品は以前から取り組んでいましたが、粘土と鉄の彫刻は、新しい素材に挑戦した作品です。引き続き、制作していきたいと思っています」
線を引く──その瞬間の身体を作品の上に『凝固』させる
──ドローイングに顕著ですが、川内さんの作品はいずれも線に対するこだわりを感じます。川内さんは、線によって何を表現しようとしていますか。
「線は、作者の身体性が最も如実に表れるものだと思っています。腕の長さや姿勢など、個人の身体的特徴によって生じる表情がありますし、素早く手を動かして引いた線だとか、ここでひと呼吸置いたのだろうというような、その線を生み出した身体のさまざまな情報がわかりますよね」
「線には、その瞬間の身体の動きが、ひいては精神性までが表れるものだと思っています。自分の思考や身体は、日々刻々と状況の中で変化する流動的なものですが、私は線を引くことで、その瞬間の身体を作品の上に『凝固』させているという感覚があります」
──川内さんが作家活動を続けていく上で大事にしていることはなんですか。
「直感と言って良いのかわかりませんが、自分のやりたい気持ちに素直であることを大事にしています。いつも頭のどこかで作品のことは考えていますが、制作する気分になれない時は、無理に作品と向き合わない。本を読むなど、別のことをして過ごします」
「それから、何を食べるかということをなおざりにしないようにしています。自分が食べるものは、その後の体調や活動に影響を及ぼします。だから、今日何を食べるかという選択は、とても重要なことだと思っています」
──川内さんの今後の予定を教えてください。
「2月12日からドイツで個展を開催します。残念ながら今回は現地にはうかがえず、作品のみがドイツに行きます。国内では、3月にVOCA展。それから7月上旬に、銀座 蔦屋書店(GINZA SIX 6F)のアトリウムでペインティングを中心とした個展を予定しています」
<共通質問>
好きな食べ物は?
「りんご。フルーツが好きで、特にりんごはよく食べます」
影響を受けた本は?
「レヴィ=ストロースの『神話論理』大系。ヘミングウェイの短編も好きです。日本文学なら夏目漱石の『それから』が好き」
行ってみたい国は?
「エジプト。古代美術が好きなので現地で見てみたい。アンフォラ(古代ギリシャ・ローマの陶製の壺〈つぼ〉)の装飾やラスコーの壁画なども好きです」
好きな色は?
「赤。自分がきれいだなと思って選び取る色に、赤系統の色が多いんです」
座右の銘は?
「一期一会。空の色や雲の形が二度と同じではないように、その瞬間にしか生まれない線や造形があります。作品って、一瞬一瞬の奇跡の積み重ねだと思っているんです」
(聞き手・文:松崎未来)


