「セーフティオレンジ」にご用心 ロードコーンや囚人服の色から見る米国の現代社会
道路工事や建設現場で目にする鮮やかなオレンジ色というと、どんな色合いが思い浮かぶだろうか? 文化・メディア理論の専門家、アナ・ワトキンス・フィッシャーはその著書で、このオレンジ色を新自由主義的「自己責任」の象徴だとしている。この色の持つ意味と、それを使ったアート作品が映し出すアメリカ社会の影に関する考察を紹介する。

「もし、米国文化の現状を色にたとえるなら、それはセーフティオレンジだろう」
ミネソタ大学出版の定評ある「Forerunners(先駆者)」シリーズから1月に出版された『Safety Orange(セーフティオレンジ)』で、著者のアナ・ワトキンス・フィッシャーはこう述べている。セーフティオレンジは、日々の暮らしにおける危険や災害について、政府が市民に注意を促す手段と読み取れるというのが、彼女の考え方だ。そして、安全性に関する責任の所在は、自治体ではなく一人一人の市民にある。
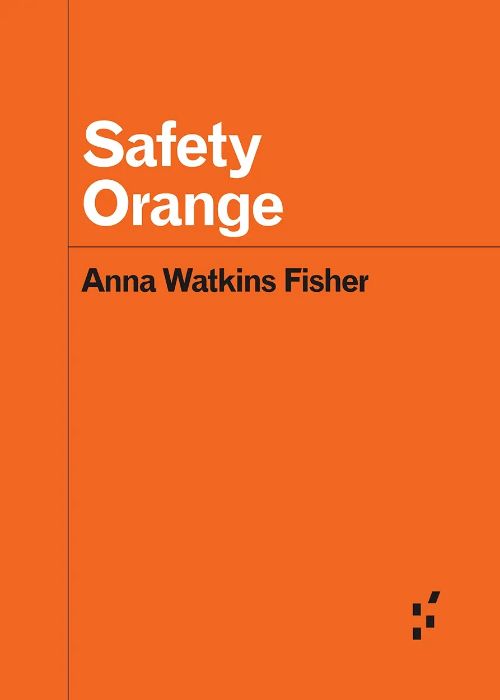
たとえば、工事中であることを示し、歩行者の立ち入りを禁止するロードコーン(パイロン)や通行止めテープは、安全な代替通路が提供されているかどうかに関わらず、通行者自身に道路上の障害物の回避責任を負わせる手段だ。また、新型コロナ感染者数をグラフや地図で示すことがあるが、そこで使われるオレンジ色は感染者数の多さを表すだけで、一体どうしたら一段階下の黄色に引き下げることができるかを教えてくれるものではない。
ワトキンス・フィッシャーの本に目を通すと、オレンジ色のレンズを通したアメリカ社会が見えてくる。 前の大統領は顔がオレンジ色なのが有名だったが、ボロボロになったインフラの修復を図る現大統領の施策によって、今はあちこちにオレンジ色が広がっている。著者によると、少なくとも 8つの州(オハイオ、インディアナ、モンタナ、ネバダ、ペンシルベニア、マサチューセッツ、テキサス、フロリダ)には、こんなジョークがあるそうだ。
「州の花? オレンジ色のロードコーンだよ」
もちろん、より良い未来を約束するものでなければ、真にアメリカ的とは言えない。だからこの色は、(あまり説得力はないかもしれないが)自分たちの街はもっとましな建物を作るために改良されている最中だというシンボルにもなり得る。ワトキンス・フィッシャーが書いているように、セーフティオレンジは「維持できない環境で営まれる生活」を示す色なのだ。
これまでも、マギー・ネルソンの『Bluets(青い花)』(2009)やアン・カーソンの 『The Autobiography of Red(赤の自伝)』(1998)など、特定の色に関する著作はあった。だが、ワトキンス・フィッシャーの著書は、それとはまったく異なる。彼女が選んだ色はロマンティックなものではなく、その解釈が比喩に依存することもない。それに、この本の内容が文学的ではなく、デザインの歴史を紐解くものになっているのは、セーフティオレンジが完全に人工的な色だからだ。
セーフティオレンジは、1950年に米国の技術マニュアルや連邦規則集で、警告を示す手段として初めて採用された。青空が広がる晴れの日でも、曇りの日でも、緑の森の中でも、あらゆる自然環境で目立つ色として考案されている。すると、ハンターたちもこの色を着用し始めた。自然の中に潜む動物と人間を区別するのに役立つからだ。
元は特定の目的のために作られたものだが、抜群に視認性の高いこの色の記号論的意味合いは次第に複雑になっていった。ワトキンス・フィッシャーは、緊急性を示しながらも「不思議と具体性に欠ける」「情報提供のない情報」だと表現している。警戒させることが目的なのにも関わらず、あまりにも世の中にオレンジ色が溢れてしまったがために、その目的が果たせなくなっているのだ。何もかもが緊急事態だったら、何も緊急ではなくなってしまう。これは、いかに今の時代の脅威が「慢性的に内在している」かを表している。
ワトキンス・フィッシャーは自らの研究で、破壊的な肯定という複雑な手法をよく用いる。ブラウン大学の歴史ある現代文化・メディア学部で博士号を取得した彼女は、現在ミシガン大学で教鞭をとっているが、その理論は現代アートの作品を通して考察されることが多い。彼女が好んで取り上げるのは、固定観念や文化的な決めつけを過剰に演出したり風刺したりすることで、そうした思い込みがいかに愚かで不合理であるかを指摘し、批評するような作品だ。
最も著名な評論「Manic Impositions: The Parasitical Art of Chris Kraus and Sophie Calle(躁病的強制:クリス・クラウスとソフィ・カルの寄生的アート)」(2012)では、彼女が「パラサイトフェミニズム」と呼ぶ戦術を解説している。ワトキンス・フィッシャーは、クラウスとカルの作品が、それぞれ依存的で無力な女性のステレオタイプを演出していると指摘する。彼らの作り上げる女性は、常に受け身であるがゆえに肯定感を他人に求める存在だ。そして、そうした女性に寄生される男性にとっては脅威にもなり得る。
また、『Safety Orange』の最終章では、セーフティオレンジを「公共の安全という公約を国家に守らせる方法」として利用し、そのレトリックをアップデートしようとするアートプロジェクトを取り上げている。そこでは、アマンダ・ウィリアムズやオブジェクト・オレンジ、マイケル・ラコウィッツなどによるオレンジ色を用いた作品を通して、反黒人主義を土台に成立した社会構造の中で、公共の安全が本当は誰のためにあるのかが考察されている。

中でも最も切実な作品は、ラコウィッツの《A Color Removed(取り除かれた色)》(2015-18)だ。イラク生まれのラコウィッツは、12歳のタミル・ライスが警官に銃で撃たれて殺された事件への抗議として、クリーブランド市内からオレンジ色ものをかき集めてギャラリーに寄付してほしいと呼びかけた。タミルを撃った2人の警官は、彼が遊んでいたおもちゃの銃にレプリカを示すオレンジ色のキャップがなかったことを理由に自らの正当性を主張した。結局、2人は無罪になっている。
ラコウィッツが、クリーブランドのフロント・トリエンナーレ2018のために制作したインスタレーションには、ありとあらゆるオレンジ色のものが並べられた。その中には、タミルの母親、サマリア・ライスがポスターボードにいくつものオレンジ色のおもちゃを貼り付けたものや、地域コミュニティから寄付されたオレンジ色のロードコーン、ハロウィンの飾り、チートスの包み紙などもあった。
ラコウィッツの作品を読み解く中でワトキンス・フィッシャーが示したのは、国が黒人にセーフティオレンジを適用する場合、彼らを保護する対象ではなく、危険で管理すべき対象として見ることが多いという事実だ。同様に、囚人服にはオレンジ色が多く、障害物があることを示すオレンジ色のバリケードは、抗議活動をする人々の排除にも使われる。
美学や批評理論に関する書物が、難解なだけでなく、日常生活で重要だと考えられる事柄からかけ離れているように感じる今の時代、『Safety Orange』の内容は特筆すべきものと言えるだろう。アート作品であれ、米国という国家であれ、日々暮らす中で目にするものであれ、物事の見方を変化させる説得力のある論考を、この本は示してくれている。(翻訳:山越紀子)
※本記事は、Art in Americaに2022年8月1日に掲載されました。元記事はこちら。


