「とにかく練習あるのみ」──人気画家ジョナス・ウッドが語る、成功までの道のり
ロサンゼルスを拠点に活動するアーティスト、ジョナス・ウッドは、風景やインテリア、器、植物、そしてスポーツをモチーフにしたペインティングで知られる。現在、20年分のドローイング作品を紹介する展覧会を開催中のウッドに、これまでのキャリアや制作方法などの話を聞いた。
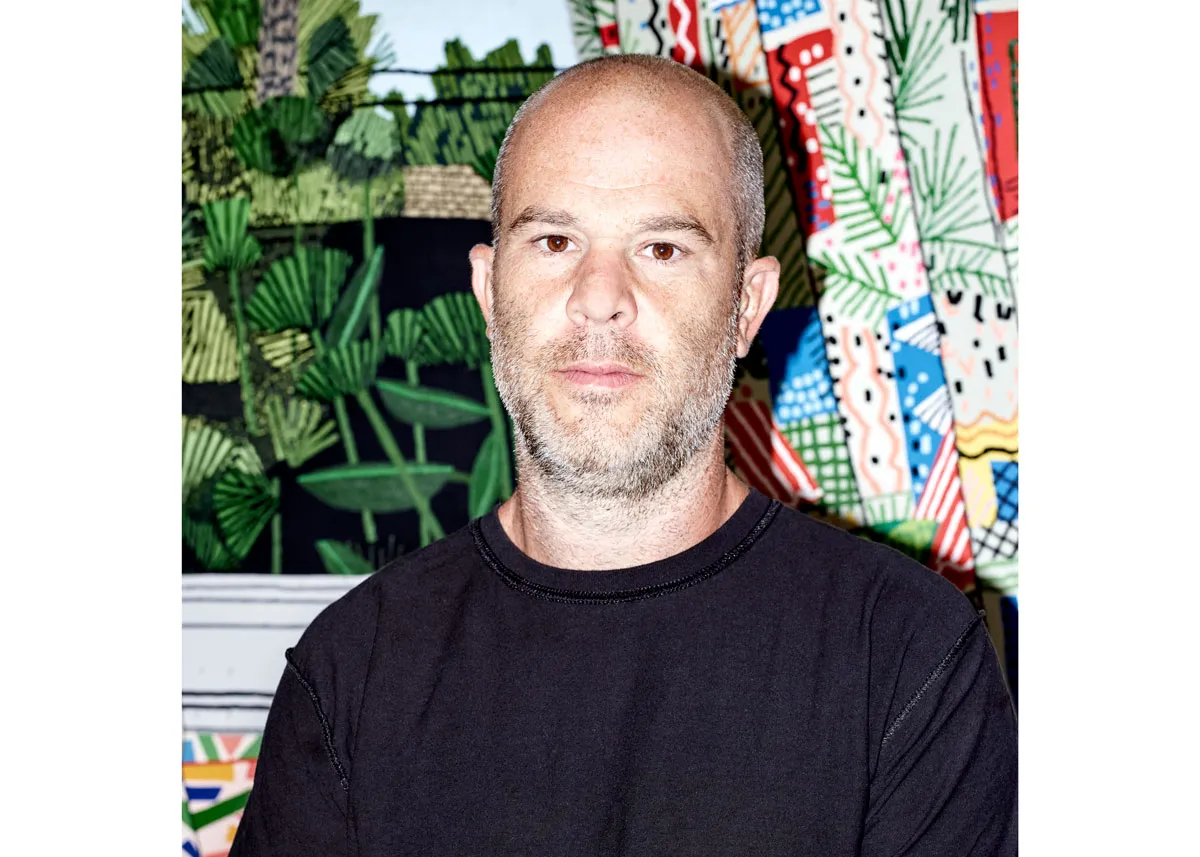
ジョナス・ウッドの最近の展覧会に、ナーマド・コンテンポラリーがスイスのグシュタードで開催した「Henri Matisse & Jonas Wood(アンリ・マティスとジョナス・ウッド)」がある。ウッドとマティスの作品を比較したこの展覧会には、著名なキュレーターで美術史家でもあるヘレン・モールズワースによる解説文が添えられていた。
ウッドがアーティストとして成長していくのに、ペインティングと同じくらい重要だったのがドローイングだ。そのドローイング作品に焦点を当てた最新の展覧会「Drawings 2003-2023」が、ニューヨークのギャラリー、カルマで開催された(なお、この展覧会は11月にロサンゼルスのカルマへの巡回が予定されている)。紙を支持体とした100点のドローイング作品が年代順に並ぶサロン形式の展示では、彼の幅広い主題や、豊かな色彩と筆致を堪能できる。
以下のUS版ARTnewsによるウッドへのインタビューで彼は、自身のルーツや美術大学での経験、卒業後の歩み、キャリア形成やアーティストとして実績を残すために役立ったアドバイス、そしてヴィヴィッドな作品を生み出す制作プロセスについて答えてくれた。

「どうしたら腕を上げられるか」を考え続けた
──今回の展覧会では、2003年から23年の間に制作されたドローイングを展示しています。なぜこの20年間に焦点を当てようと思ったのですか?
ワシントン大学の大学院を出て、アーティストとしてロサンゼルスに住み始めてから今年の7月で20年になるので、その間に描いたドローイングを集めてみたんです。カルマの創設者であるブレンダン・デュガンは歴史に残るような素晴らしい展覧会をいくつも手掛けているし、僕も何か違うことをしたかったんです。
──大学院を出た後は仕事をしながら自分の道を見つけていく人が多いですが、あなたが駆け出しのアーティストだった頃のことを教えてください。
ワシントン大学を卒業したのは2002年。その後、妻でアーティストのシオ・クサカ(日下翅央)とマサチューセッツ州のマーサズ・ヴィンヤードに短期滞在して、半年後にロサンゼルスに移住しました。ニューヨークに住むか、それともロサンゼルスがいいか悩みましたが、結局友人が1人いたロサンゼルスに引っ越して、ペインティングやドローイングの制作を始めました。
当時は、「どうやって絵を描く訓練を続けていけばいいのか」、「どうしたら腕を上げられるか」をずっと考えていました。ドローイングは、そのための主な手段。大学院を出てからも制作を続けるにはどうしたらいいか、教える者の目がないところで訓練を続けるにはどうすればいいか、恩師たちから貴重なアドバイスをもらいました。
学生時代は、自分のやっていることを見てくれて、批評してくれる仲間や教授陣がいます。教授たちから「どんなアーティストが好き? そのアーティストたちは何を描いていた? 彼らはどのように練習していた?」と問われ続けたこともあり、僕は、絵を描き続けるために練習という言葉に集中したんです。

──ほかにどんなアドバイスがありましたか?
大学院時代には、数年前に他界した教授のデンジル・ハーレーに師事しました。ハーレーは若者を鼓舞することに長けていて、僕に挑戦し続けるよう鼓舞してくれました。ワシントン大学はUCLAなどのカリフォルニアの有名大学のように、ずば抜けた才能の学生たちがしのぎを削り、大学院を修了したらすぐにギャラリーで展覧会が開けるような、プロのアーティスト養成を軸とする教育体制ではありませんでしたから。
ワシントン大学は、アートを実践していくための手段として美術の教授になることに重点を置いていましたが、僕はアーティストとして自立していきたいという思いが強かった。いずれにしても、優れたアーティストがたくさんいるロサンゼルスのような場所でも、教授のアドバイスは役に立つものでした。そして、ロサンゼルスに来てすぐに(アーティストの)ローラ・オーエンスのスタジオ・アシスタントの仕事を得たことも、僕の道を切り開く一助となりました。
アシスタントとして多くの学びを得る
──どうやってアシスタント仕事に就いたのですか?
ローラのところで1年半近く働きました。さっき、カリフォルニアに移住することに決めたのは友人がいたからだと話しましたが、その友人とはアーティストのマット・ジョンソン。彼は力量のある彫刻家で、実は高校の同級生。マットはすでにアーティストのチャールズ・レイのアシスタントとして働いていて、UCLAでローラの授業を受けたこともあったようです。僕がロサンゼルスに越してきてから2カ月ほど経った頃、アシスタントを探していたローラが何人かの大学院生に声をかけた中にマットもいて、彼が僕を紹介してくれたんです。
アシスタントとして最初に関わった仕事は、ローラが(2004年の)ホイットニー・ビエンナーレのために制作していた絵画作品でした。仕事を始めて数週間するうちに、やっと彼女がどれほどすごい人なのかが分かってきました。みんなからも、「あそこで働いているの?」と感心されました。僕はたまたま運が良くて、信じられないような天才と巡り会え、ほかでは得難い経験ができたと思います。
ローラからは、大学院で学んだのと同じくらい多くの貴重な学びを得ました。彼女はいろいろな題材を幅広く描いていますが、それを見て、こんなに自由にやっていいんだと解放される思いだったし、デッサンや絵画の技術も高く、すごく勉強になりました。2000年代半ばには、僕の妻も並外れた彫刻家のチャールズ・レイのもとで4年近く働いていたので、2人とも、恵まれた環境で仕事ができていたと思います。

──私もUCLA卒業後の最初の仕事は、デヴィッド・ラシャペルのアシスタントでした。優れた作家のそばで仕事をすると、アーティストになるための要件を実感できますよね。ところで、夫婦で話し合って一緒にロサンゼルスに移住すると決めたということですが、創作活動でも夫婦でアイデアを出し合うことはありますか?
僕は静物画を描いていて、シオは器を作っているから、彼女の作品を借りてそれをモチーフに絵を描くのはごく自然な流れでした。2006年にブラック・ドラゴン・ソサエティ・ギャラリーで、2007年にはアントン・カーン・ギャラリーで個展を開きましたが、「この器は何ですか?」と聞かれることも多かったです。
一心不乱に絵を描いている僕に、彼女はとても協力的です。2005年からはスタジオを共有し、部屋は別々ですが同じ屋根の下で仕事をしています。長い間一緒に仕事をしてきたので、お互いの仕事に対して意見を言ったり、建設的な批評をしたりして、影響を与え合っています。
ドローイングを大量に描くのはなぜか
──ドローイングをたくさん描いていますが、いつもスケッチブックを持ち歩いているんですか?
スケッチブックは持ち歩いていません。人によって解釈は違いますが、僕は、ペンでも水彩でも色鉛筆でも、画材は何であれ、紙の上に描いた絵は何でもドローイングだと考えています。たとえば、ローラ・オーエンスは絵の具を使って描いた絵なら、何でもペインティングだと捉えているし、僕は紙の上に描いたものはすべてドローイングだと思っているんです。
僕は、ペインティングの準備のために、あるいはその参考にするための詳細な習作として、かなりの量のドローイングを描きます。ペインティングは、スケッチをもとに描くことが多いです。スケッチを参考にしながら、それをペインティングの中で解釈しようとしているんだと思います。
──ドローイングがペインティングに変換されると、イメージがより力強くなることが多々ありますね。
同感です。個人的には、ドローイングとは可能な限り最高のペインティングを描くことを促してくれるものだと思います。

──あなたが作品の中で描いている物や場所などは本当に幅広くて、見ているととても豊かな、心が躍るような気持ちになります。ロサンゼルスの光の捉え方にも感心します。
社会に出てすぐにロサンゼルスに来て、その美しさに魅せられました。着いたとたんに気分が良くなったし、故郷に帰ってきたような気がしたんです。西海岸は、光だけでなく人も独特で、僕の人生はそこで大きく変化しました。自分はマサチューセッツ州出身ですが、東海岸はどこか硬派で現実的なところがある。それに比べ、西海岸はかなりのんびりしていて陽気です。ロサンゼルスに移ってきた時、見たことのない植物がいろいろあって、それを描くことに夢中になりました。光もスタジオの光源として最高で、何よりも色彩が素晴らしい。色が互いにどう作用するのかをいつも考えてきましたが、ここではすべてが僕の関心事や、絵を描く上で大事にしていることと重なりました。そういったことが僕の心を活性化してくれるんです。当時の僕は「どうすればもっと自分を高められるか」「どうすればアーティストとして今より成功できるのか」を真剣に考えるようになっていました。
スポーツを題材にした作品を制作する理由
──あなたの作品にはスポーツのモチーフがよく出てきますが、それはなぜですか?
学生時代にある教授が、心から没頭できる題材を選びなさいとアドバイスしてくれました。僕は大のスポーツ好きで、子どもの頃からいろんなスポーツをやってきた。アスリートが何かを成し遂げるのを見るのが好きなんです。
最初は主に、ポートレートの練習としてスポーツ選手を描いていました。毎回友人を説得して写真を撮らせてもらい、それを描いていたんですが、知らない人やファンとして崇拝している人物を描くのは、まるでルールが違います。僕はいろんなものを写真に撮っては自分の作品に取り込んでいくのですが、テニスコートを描くようになったのは、テニスの試合を見ている時に部屋の電気を消してテレビを撮影した写真が気に入ったからです。

──日常のふとした瞬間に生まれたアイデアというのがいいですね。
テニスコートの絵では、構図や抽象性、反復性が大切です。それに、宙に浮いたバスケットボールやテニスボールを見ると幸せな気分になる。植物やインテリア、ポートレート、スポーツ、風景など、自分が好きなものを描くようにしています。最初からこうしたものには魅力を感じていたし、うまく作品にできたから、それを描き続けてきたんです。
──純粋に情熱を注げる対象を描き続けてきたのは誠実だと思います。
ロサンゼルスに来た当時は誰にも期待されていなかったので、何でも好きなことができました。それに僕はいつも、絵画はより精密でなければならないと考えていたんです。ただ、自分は生活の中にあるものを描く具象画家ではあるけれど、フォトリアリストではない。むしろ抽象画家のように、絵は何にでもなれると思っています。
コレクターやキュレーターの好みに迎合しなかったというのもあります。ロサンゼルスに移住して最初の3、4年は全然売れなかったから、周りの意見に左右されずに、自分のアイデンティティを確立できたのは幸運でした。1つのタイプや1つのルックに固定されるのではなく、さまざまな絵を描いていいという考え方が心地よかったし、若いうちから枠にはまらないよう強く意識していました。多種多様なモチーフを一緒に見せるのは意図的にやってきたことで、今も続けています。

制作に使用している画材やプロセス
──制作にはどんな画材を使っていますか? アーティストならきっと興味があると思います。
水彩絵の具で淡い下塗りをすることが多いですね。通常はウィンザー&ニュートンですが、もう少しいい絵の具を使うことも。色鉛筆で気に入っているのはプリズマカラーです。
──プリズマカラーの150色セットを持っていますか?
プリズマカラーは全色揃えているし、これまでに発売された色は1つ残らず持っています。生産終了になったものもあるから、切れたらデッドストックを探さないといけないんです。
油絵の具では、ガンブリン、アクリル絵具ではノヴァカラーが好きです。主な支持体はカンバスかリネンで、紙はどんなに水彩絵の具を重ねてもシワにならず、波打たない、加熱圧縮した一番厚い水彩紙で、ほとんど厚紙に近いものを使います。フランスのメーカーから61×40インチ(約155×102cm)の巨大な水彩紙を送ってもらっているんです。自分の分が少なくなってしまいそうだから、メーカー名は秘密です。
その紙のサイズに合わせて大きな絵を描く時もあれば、小さくカットして使うこともあります。今も昔ながらのプロジェクターを使って制作しているので、透明なシートにいろんなものをトレースして投影するんです。その写真を撮り、写真の一部をトレースして継ぎ合わせ、イメージをつくっていきます。今回、カルマの展覧会でニューヨークに来るにあたっては、スケッチをするために小さなメモ帳をいくつか携行しました。あと、トレースするための透明シートも購入しました。

──最後の質問です。今回の個展は、あなたにとってどんな経験になりましたか?
最高の気分です。没入感があって、説得力がある展示になったと自負しています。先日、妻が言っていたんですが、20年前から僕の作品を見てくれている人なら、おそらくこの展覧会の作品はすべて目にしたことがあると思います。というのも、出品作品のほとんどは、ペインティングの形で発表したことがあるからです。少なくとも60枚のドローイングはペインティングになっています。
これまでの展覧会でもドローイングを散りばめたり、展示室の1つをドローイング作品に充てたりしたことはありますが、ドローイングを主役にした展覧会は初めてだったので、僕にとって制作活動のバックボーンとなっているものをみんなと共有できて、本当に嬉しいです。(翻訳:野澤朋代)
from ARTnews


