担当キュレーターが語る「私たちのエコロジー」展。アーティストの洞察や批判に私たちが学ぶこと
森美術館で2024年3月31日まで開催中の「私たちのエコロジー:地球という惑星を生きるために」展は、エコロジーという大きなテーマの下、環境保護に留まらない現代の問題を多角的にとらえつつ、美術館やアートが地球に対してもつ役割について考えた現代アートの展覧会だ。その企画を担当した森美術館アジャンクト・キュレーターのマーティン・ゲルマンと同館キュレーターの椿玲子に話を聞いた。

「環境に配慮した展示デザイン」を実践する
──「私たちのエコロジー:地球という惑星を生きるために」展は、作品もさることながら、剥き出しの壁も印象に残りました。
マーティン・ゲルマン:環境負荷を考えて、展示壁や壁パネルの一部は前回の展示で使用したものを再利用し、塗装仕上げを省いています。アメリカ人アーティストのダニエル・ターナーによる新作が描かれた壁は、ガイドツアーをするとみなさん一瞬どちらが作品なのか迷ってしまうみたいです(笑)。ほかにも100%リサイクル可能な石膏ボードや再生素材を活用した建材の使用、資材の再利用など、「環境に配慮した展示デザイン」を実践していることが今回の展覧会の特徴です。
椿玲子:エコロジーをテーマとする以上、展示にかかわるあらゆる要素、例えば使用する素材や資材の運搬、仮設構造物の建設および解体などが環境に与える負荷についても考えなければならないと感じました。この展覧会を上辺だけのポーズで終わらせないためには、開催方法からきちんと見直す必要があったんです。日本において再利用やリサイクルの概念が古くから文化に根付いていることが、今回の展示の循環を考えるにあたって自然とそうした要素を取り入れられた背景にあるのかもしれません。
ゲルマン:建築の分野でも、サステナビリティの面から再利用を重視する傾向が強まっています。「脱植民地化」と並んで「脱炭素化」を柱に掲げた2023年のヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展でも、数多くの事例が紹介されました。何かをゼロからつくり、会期が終わればすべてを取り壊すのではなく、既存の構造をクリエイティブに利用する方法が模索されているんです。

作品ではなく、アイデアを運ぶ
──今回は展示スペースの半分以上が新作とのことですが、作品の輸送について心がけたことはありますか?
ゲルマン:既存の作品を国内外から輸送する代わりに、日本でコラボレーションするというアプローチをとりました。これは輸送にかかる環境負荷を低減するだけでなく、日本の状況を国際的な文脈に絡めて提示するための試みでもあります。ダニエル・ターナーの新作《気圧計ワニス》(2023年)もそのひとつです。彼はインドにある世界最大規模の船舶解体場で解体された日本籍のケミカルタンカーの気圧計を粉砕し、その粉を用いて「壁面彫刻」と呼ぶ作品を制作しました。今回の展示でわたしたちが大切にしたのは、「アーティストやそのアイデアから人間同士のつながりを育むこと」です。
──モニラ・アルカディリの《恨み言》やニナ・カネルの《マッスル・メモリー(5トン)》もそうした例のひとつですよね。
椿:はい。モニラは日本で美術を学んだクウェート人アーティストで、日本人が自分のルーツを重要視する姿に触れて、自分も自身のルーツを探るようになったそうです。そのなかで、自身の祖父がクウェートの天然真珠の採集船で乗組員を鼓舞する歌手だったことを知り、真珠に興味をもったと言います。実はかつてクウェートでは真珠採取業が一大産業でしたが、日本の養殖真珠が流通するようになったことで大打撃を受けました。しかしその後、石油産業によって持ち直し、発展したという歴史があります。モニラは、日本とクウェートをつなぐものとしての真珠をテーマに作品をつくろうと考え、三重で真珠の養殖についてリサーチしたんです。その結果生まれたのが、養殖真珠をテーマに人間の自然への介入と搾取について描いた《恨み言》(2023年)でした。

80年前の作品が訴える環境問題
──今回の展示は4章構成ですが、第1章「全ては繋がっている」では環境や生態系と人の関係、そして第4章「未来は私たちの中にある」では、アクティビズムから先住民の叡智、フェミニズム、AIや集合知(CI)、スピリチュアリティまで、さまざまな視点が盛り込まれています。
ゲルマン:エコロジーについて考えることは、世界のあらゆることについて考えることでもあるというメッセージです。エコロジーという大きな傘の下で、さまざまな社会的・経済的問題、テクノロジーや植民地主義にももちろん目を向けています。
──第2章「土に還る」では高度経済成長期の日本の作品が充実していることも印象的でした。
ゲルマン:この章では、高度経済成長期における日本の自然災害や工業汚染、放射能汚染などに触れ、日本人アーティストたちが1950年代から80年代にかけてこうした環境問題にどう向き合ってきたかを紹介しています。これはモダニズムに対する批判であるとともに、数十年前のアーティストたちがすでにこうした問題に反応していたことを強調する試みでもあります。アーティストは、必ずしも直接的な解決策を提示する立場ではありませんが、常に画期的でユニークな視点を提供してくれます。合理化された思考を打ち破り、新しい思考の道を切り開いています。そうしたアーティストのインサイト(洞察)にもっと注目してほしいというのが、わたしたちキュレーターの願いです。

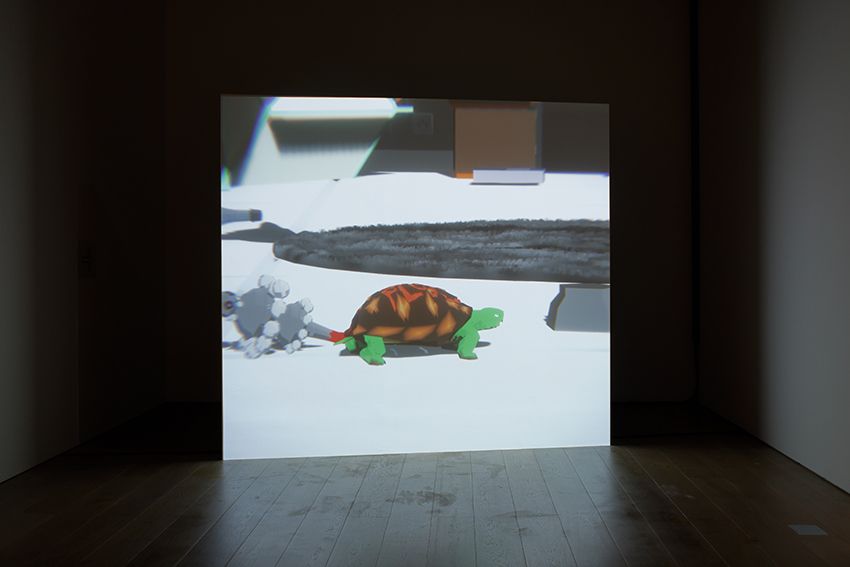
人間中心主義と植民地主義は切り離せない
──アート界では、エコロジーに関する問題意識は広く共有されてきたと思われますか?
ゲルマン:アーティストとっては長年にわたり差し迫った問題だったと思います。とはいえ、アート界全体で広く議論されるようになったのは、特にここ10~15年くらいのことでしょう。例えば、今回の展示のキーワードのひとつにもなっている「アントロポセン(人新世)」[編註:人類の活動が地球環境や生態系に多大な影響を与える時代を指す地質区分]という言葉がアート界隈の議論で本格的に聞かれるようになったのは2010年前後です。2013年にはベルリンの世界文化の家(Haus der Kulturen der Welt)がアートの文脈において人新世をめぐる知の共有を目指して「Anthropocene Curriculum」というプログラムを立ち上げ、キャロリン・クリストフ=バカルギエフがキュレーションした2012年の「ドクメンタ13」では、間接的にではあるもののポストヒューマニズムと多種多様なポリティクスというテーマが通底していました。
椿:もっと早い例では、1989年にパリのポンピドゥーセンターで開催された展覧会「Magiciens de la Terre」(大地の魔術師たち)があります。西洋諸国と非西欧諸国のアーティスト100人の作品を並べて展示し、植民地主義という点からも現代アートのシステムのあり方を問うた展示でした。
ゲルマン:「Magiciens de la Terre」は非西洋的なアイデアをアートの言説の中に編み込んだという意味で、非常に重要な展覧会と言えます。同様の態度は「私たちのエコロジー」展のテーマにも関わっています。展示を通じて語られるポストヒューマニズム(人間中心主義からの脱却)とポストコロニアリズム(植民地主義からの脱却)は、ときに正反対の概念でありながら、切り離せない関係にあるのです。そしてこのふたつの概念が並ぶことで、多様なバックグラウンドや視点をもつわたしたちが同じ惑星に住んでいることを思い出させてくれるのです。
──今回の展示は、「環境によいかどうか」という視点だけで捉えるとこぼれてしまう様々な視点を集めたものであるようにも感じます。
ゲルマン:SDGs(持続可能な開発目標)という言葉からもわかるように、わたしたち人間は開発や成長を望みますが、それ自体、持続可能性とは相反するものです。これは大きな課題です。世界最多の人口を抱えるインドで、欧米諸国のようにより便利な生活を望み、冷蔵庫やクルマを求める人たちに、これ以上成長するなと言えるでしょうか? それは無理な話でしょう。「私たちのエコロジー」展で、マニラ生まれのアーティストであるマルタ・アティエンサは、観光業の興隆による地上げと海洋資源の枯渇という二重の脅威にさらされる漁民たちをとらえた写真を展示しています。これは漁民たちの声を届ける試みであり、このような成長が持続可能であるわけがない、という批判でもあるのです。

美術館同士の対話を誘発する
──企画やアーティストたちとのやりとりを通して、おふたり自身の視点や認識に変化はありましたか?
ゲルマン:いままで触れてこなかったさまざまな領域と突然かかわりをもつことで、多くの学びがありました。例えばスウェーデン出身のニナ・カネルは、北海道産の5トンの貝殻を床に敷き詰めたインスタレーション《マッスル・メモリー(5トン)》(2023年)を制作しました。北海道におけるホタテ貝の大量廃棄の問題と、それを建材として再利用するためには大量のエネルギーが必要となるという矛盾をテーマにした作品です。この作品を制作するにあたり実際に北海道を訪れた彼女は、貝殻の洗浄がベトナム人労働移民によってなされていることに気づきます。その瞬間、作品はさらに別の意味もはらむようになります。今回の展示では、こうした気づきが無数にあり、そうした気づきの一つひとつが、様々な問題にまったく新しい認識を与えてくれました。
椿:企画をしながら、展覧会が環境や循環に対して何ができるかも深く考えました。最初は無力感に苛まれることもありましたが、同時に展覧会には視点や考え方を変える効果があると気づかされました。そのなかでも、人々の感性を変えることを考え始めました。何を良いもの、魅力的なものと感じるかという意味の感性です。例えば、これまで気に留めていなかった素材を無駄にしない行為やリサイクルする努力を美しいと感じるようになることは、視点の転換です。こうした認識の変化こそが重要であり、それが理解や行動につながると思います。

──今回の展覧会を踏まえ、今後に向けてさらに取り組みたいことはありますか?
ゲルマン:この展覧会で取り組んだエコロジーに関する挑戦は、すぐに終わるものではないと思います。今回「モノよりネットワーク」を掲げてアーティストたちとのつながりを重視した展覧会づくりをしてきましたが、これをさらに拡大させる試みは続けていきたいです。
椿:より多くの施設とコラボレーションしたいです。例えば、今回は「私たちのエコロジー」展の関連企画として、銀座メゾンエルメスフォーラムで「エコロジー:循環をめぐるダイアローグ」が開催されています。単発の展覧会をつくるだけでなく、ほかの美術館との対話を通じてより多くの組織を巻き込むことは有意義だと考えています。またパンデミック以降、わたしたちはこれまでのアプローチを見直し、日本の美術館のコレクションに注目するようになりました。日本の美術館の多くは80年代後半から90年代前半に多額の予算をかけて建設され、素晴らしいコレクションを揃えています。しかし、現在は予算の制約に直面しており、その資源も十分に活用されているとは言えません。こうしたコレクションを循環させ、その意義を見せていくような取り組みも行なっていきたいと思っています。


