Art Squiggle Yokohama 2024が開幕! ARTnews JAPAN編集部が選んだベスト展示5選
若手アーティスト16組のアーティストによる作品をフィーチャーした芸術祭「Art Squiggle Yokohama 2024」が開幕した(9月1日まで)。今年の同芸術祭のなかで、ARTnews JAPAN編集部が注目した5つの作品を紹介しよう。

横浜・山下ふ頭4号上屋を舞台に、新しいアートフェスティバル「Art Squiggle Yokohama 2024」(以下、アートスクイグル)が始まった(9月1日まで)。タイトルの「Squiggle」とは、くねくねと不規則に曲がった曲線やなぐり書きを意味し、ここでは、アーティストたちの作品制作の旅における迷いや試行錯誤を表現する言葉として用いられている。
関東甲信では平年よりも1日早く梅雨明けが発表された7月18日に行われたプレスプレビューで、主催の株式会社マイナビ執行役員の落合和之は、山下ふ頭は「かつては国内外をつなぐ経済の要であり、多様な文化交流の場だった」ことから、アートスクイグルが「来場者たちの様々な価値観と参加アーティストたちの価値観とが交差するユニークなアート体験を提供したい」と期待を語った。
その言葉の通り、アートスクイグルで得られる鑑賞体験は、美術館やギャラリー、あるいは他の芸術祭でのそれとは随分と異なる。正直、長きにわたる実践を経て自らの言語を確立したアーティストたちの作品に触れたときのような深い感動は、ここでは得難いかもしれない。しかし、新旧作を再構成した作品も含め、ここでコミッションワークを発表した8組の若手アーティスト(そのほとんどが90年代生まれだ)による作品からは、自分たちの「迷いや試行錯誤」を見せる場を与えられたことの意味を真摯に考え、探求し、その役割を果たそうという誠実な態度が伝わってくる。そうした彼らの「スクイグル」には、彼らが日々向き合っているに違いない、アートってなんだっけ? という根源的な問いも含まれる。確かに、なんなんだっけ? と、巨大な倉庫空間の中で自由に思考/試行する彼らの作品を見ながら考えることこそ、はるばる山下ふ頭の突端まで足を運ぶことの価値と言えるだろう。
というわけで、ここからは、ARTnews JAPAN編集部が選んだ5つの作品を紹介していこう。
GROUP《港 / Manicured Cactuses》

建築コレクティブのGroupは、「サボテン」を資材とする家具によって構成された空間をつくりだしていた。本展の会場となる山下ふ頭=港を起点とするリサーチのなかでモチーフとして選ばれたサボテンは、16世紀に渡来品として日本へ輸入されたもの。サボテンを断ち切ることでつくられたテーブルや風呂はどこか痛ましくも思えるが、南米では建材で使われることもあり、日本における竹と近しい存在といえるかもしれない。
しばしば建築や家具は木材や石材を素材としながらも人工物として自然とは対置されがちだが、Groupが生み出すサボテンの家具はいまなお生きており、会期中も少しずつ成長しつづけている。日本ではもっぱら観賞用として流通するサボテンを資材として扱う試みは、まさに本展が志向する試行錯誤を体現するものであり、私たちが慣れ親しんだ家具や資材の概念に揺さぶりをかける。会期後は実際に家具としての販売も予定されており、特定の期間・場所を前提とした展覧会のフォーマットに留まらず生成変化を続ける作品形態は建築やアート作品のあり方を考えるうえでも示唆に富んでいる。
山田愛《流転する世界で》

会場中央に位置する円形の展示スペースのカーテンをめくって中に入ると、京都の石材店で生まれた山田愛のインスタレーション《流転する世界で》が広がる。すべての物は絶えず生まれては変化し、移り変わっていく様を表す「生生流転」という言葉から名付けられた本作は、自身が2022年から制作している《円相》シリーズを発展させたインスタレーション。
展示空間の中央には墓地に敷かれる無数の玉砂利が巨大な円盤の上に整然と並べられており、用意された長椅子に腰掛けて作品を見ると、薄暗さと空間内に漂うお香のような香りが相まってどこか別世界に飛んで行ってしまいそうな感覚をおぼえた。「作品の鑑賞を通して、それぞれが現在の立ち位置を見つめ直せるような体験を生み出したい」と山田が語るように、過去を振り返り、未来に思いを馳せながら「流転する世界」においてどんな人生を歩んでゆくのか、暗がりの中で考えてみるのもいいだろう。
河野未彩《HUE MOMENTS》
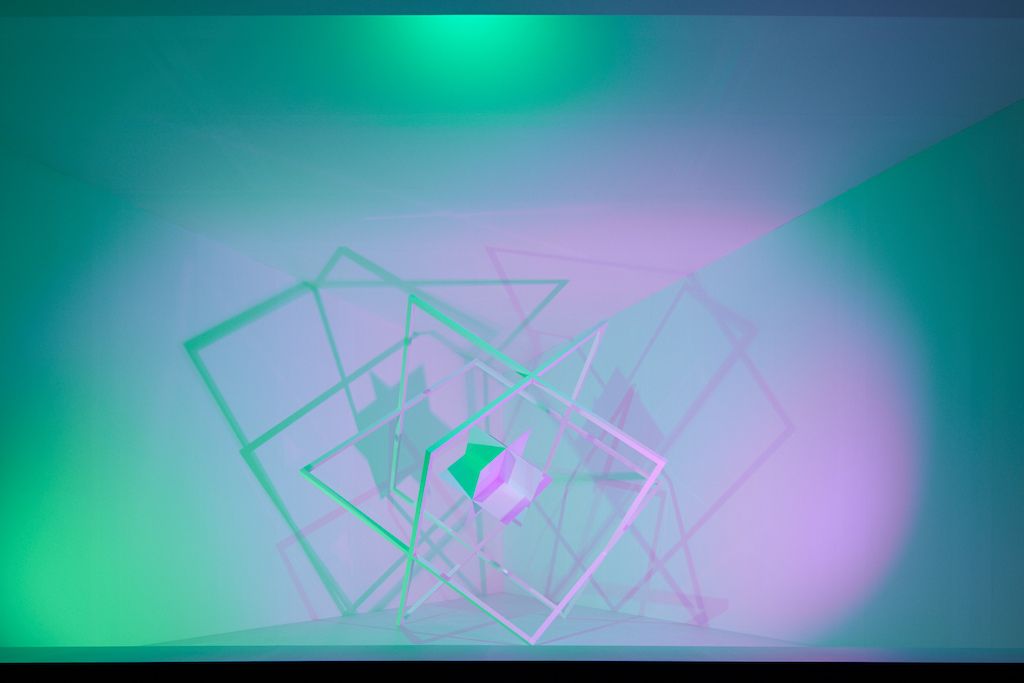
光とそこから生まれる影、変化する色相をテーマにしたインスタレーション。大きな多面体のオブジェに複数の光源で多方向から光をあてることで、色鮮やかな影をつくりだす。つい時間を忘れて絶えず変化する色と光の様相に目を奪われてしまう。この作品の作者である河野は過去、光の三原色の原理を応用して白い光のなかに色鮮やかな影をつくる「RGB_Light」という製品をデザインしており、実はその実物も展示室の外に置いてある。今回のインスタレーションと「RGB_Light」、どちらも極めて具体的な光の物理現象を起点にしているにも関わらず、まったく異なる作品に昇華されているところが面白い。ちなみに、インスタレーションの光源はそれぞれ異なるループの周期をもち、会期を通して一度たりとも同じ組み合わせになることはないという。一期一会の光を楽しみたい。
川谷光平

写真家として活躍する川谷光平の展示は、アドバルーンから吊られた写真やスタジオの背景紙のように展示された写真、布に印刷された写真など、本人が原典と位置付ける撮影データから、サイズもメディアもさまざまなかたちでアウトプットされている。写真の展示と聞いて想像するそれとは異なる様相を見せる彼の展示は、写真の撮影から発表までのプロセスを、川谷自身が3DCGソフトでCGを作りながら設計した思索的な試みだ。そこから生まれた展示空間は来場者も作品に巻き込んだ、まさに今回のテーマにある「やわらかな試行錯誤」に溢れたものだった。これが彼の今後のキャリアにどうつながるのか、期待したい。
光岡幸一《Hyahbling Star》

会場の右側の壁面に掲げられた、3枚の大きなブラックシート。プレビュー開始直後には、それらには真っ暗な夜空を見上げた風景が描かれているだけだったが、しばらくすると、真ん中の一枚が取り替えられていた。そこには、まるで夜空にぽつりと浮かぶ滲んだ星のような鳥のフンの痕跡が。聞けば、会場の外に組まれた高さ3メートルほどの「止まり木」でひと息ついでに、鳥がその下に敷かれたシートに落としたものだという。
これまでも鳥のフンによる星屑ドローイングに何度か挑戦してきたが、一度も成功したことがないのに「これは奇跡!」と嬉々と語る光岡幸一の作品《Hyahbling Star》(2024)は、山下ふ頭を訪れる海鳥たちとのコラボレーション作品だ。コラボとはいえ、光岡は自ら筆をとることを放棄し、「画家役」を鳥たちに委ねている。だから9月1日までの会期中に、作品が完成するかどうか、どんな作品になるかは完全に鳥次第。

アートスクイグルでは、各作家のブースに作品の参考書籍や道具などを展示する机が置かれているのだが、光岡のそれには、巨大な将棋の駒にスケートボードのウィールがつけられた謎のオブジェが置かれており、《Hyahbling Star》には何ら関係のないようにも見える。しかし彼曰く、それらは「偶然性」が引き起こした「なんかいい」「美しい」ものとして共通しているという。
偶然性と聞けば、1960年代初頭に世界中に広がった前衛芸術運動の一つ「ハプニング」が思い浮かぶが、光岡の作品の多くは「ハプニング」的だ。ただし、光岡作品にはフルクサス作品が内包していたような「反芸術」などの強い態度やメッセージは感じられない。それよりももっとゆるーく、「誰でも知っていることでも、見方を変えればこんなに感動できたりするんだ」(アーティスト・ノートより)というささやかな感動を多くの人と共有したいという素直な動機から、自らの作品が疲弊しがちな現代社会の「止まり木」となることを望んでいるのかもしれない。


