韓国フェミニスト・アートの50年──キュレーター、キム・ホンヒが語る女性アーティストたちの抵抗と連帯の歴史
2024年に世界経済フォーラムが発表したジェンダーギャップ指数で世界146カ国中94位に位置する韓国では、フェミニズム運動が活発に展開される一方で、それに対するバックラッシュも少なくない。他方で、現代アートの領域では若い世代を中心に盛り上がりを見せ、グローバルな舞台で女性アーティストが注目・再発見される機会も増えている。本連載では、そんな韓国におけるフェミニズムとアートの交差点を探る。第1回は、韓国のキュレーター、キム・ホンヒに話を聞いた。

「今、韓国のフェミニスト・アートがこれまでになく脚光を浴びている」
キュレーター・美術史学者・評論家のキム・ホンヒは、著書 『フェミニズム・アートを読む〜韓国女性アーティストの抵抗と脱構築(原題:페미니즘 미술 읽기:한국 여성 미술가들의 저항과 탈주)』の序文でそう記している。キム・ホンヒは30年以上にわたり美術界に身を置き、アーティストと協働してきた。英語版 は『Korean Feminist Artists: Confront and Deconstruct』 として英国PHAIDONからも刊行。内容こそ同じだが、異なる編集方針のもと、図版や判型が大きく異なる2冊の書籍として、2024年9月と10月に発売された。キムはフェミニズムのトピックを「体の美術」「ケア政治学」「ディアスポラ美術」「抽象美術における女性性」など15項目に分け、トピックごとに価値観を共有する作家2〜3人をマッピング。世代を超えたチームワークを浮かび上がらせながら、合計44人の女性アーティストを紹介している。ジェンダー間の不平等や女性の抑圧といった日本においても切実な問いに対し、アートとフェミニズムにいまなにが可能なのか。隣国の動向からヒントを探る。
フェミニスト・アートは「流行」ではない
──まずは、「フェミニスト・アート」の定義についてお聞きしたいです。著書で紹介されている多様なアーティストのなかには、一般的なフェミニズムの文脈上に位置づけられない作家も含まれていますが、どう定義されているのでしょうか。
私はフェミニスト・アートを、フェミニズムを受容した言説として同じ線上で考えています。まずフェミニズムとは変化を渇望する呼びかけであり、流行ではありません。時代によってその姿を変えながら、フェミニズムは着実に存続してきました。それは、世界が変化するための意志を反映した概念だからです。
次に、単数ではなく複数で存在するということです。さまざまな声が交差し発火しながら、フェミニズムのなかで生じる葛藤まで織り込んだもの。だからこそ、より多くの人にとって議論の対象となり、同時に魅惑的なのです。最後に、フェミニズムとは人間について論じるための有効なツールです。イデオロギー的な運動やジェンダーバトル、ジェンダー戦争ではなく、人々を目覚めさせ世界を変える力をもっている。これらをフェミニスト・アートの定義であり美徳だと考えていました。
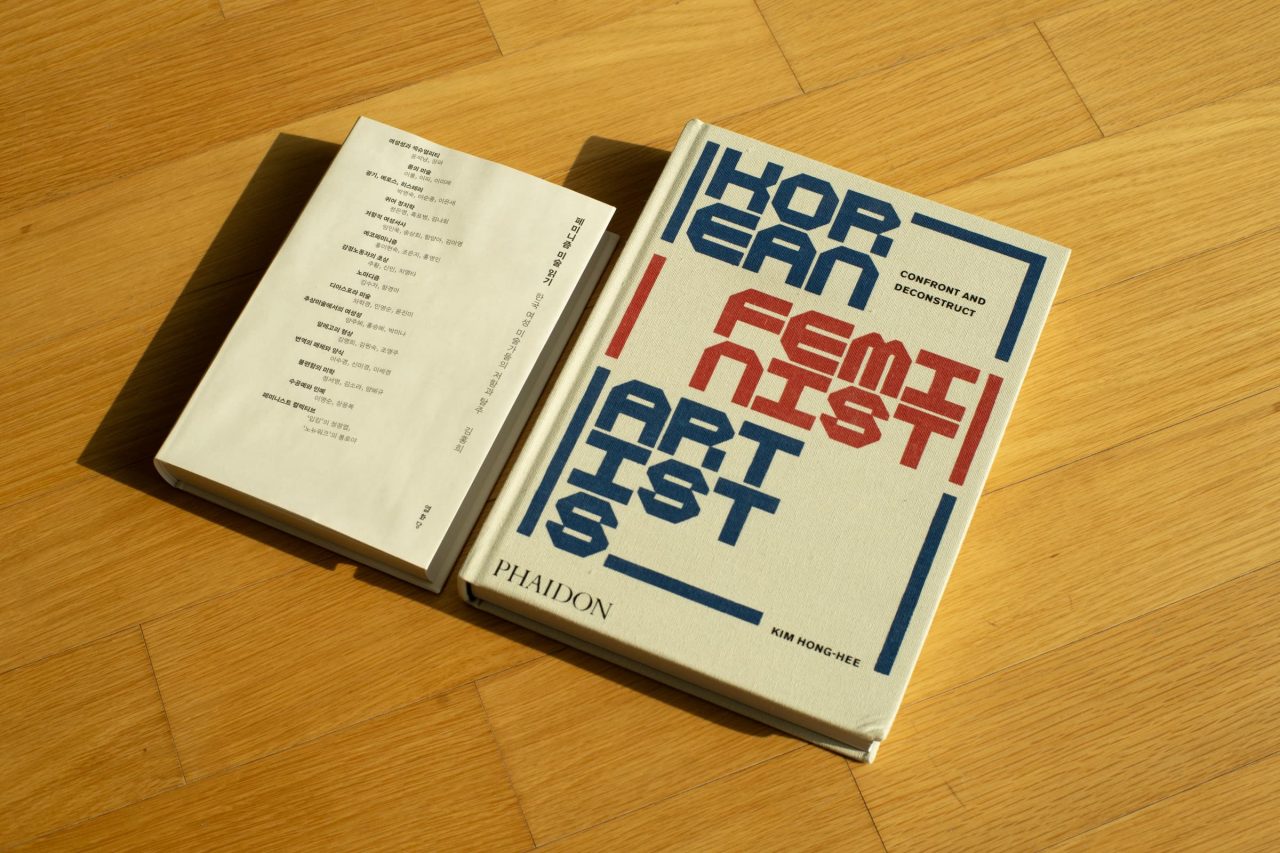
──韓国では、2015年前後から社会に蔓延する女性嫌悪や抑圧に反発する形で、フェミニズム運動が再浮上しました。アート界においても若手の女性作家が注目を集め、過去の女性作家が再評価される動きが活発になっています。こうした変化が生まれた背景についても教えてください。
2016年、江南駅殺人事件[編注:2016年、34歳の男性が見知らぬ23歳の女性を駅内のトイレで殺害した事件。女性嫌悪殺人事件として大きな波紋を生んだ]を発端とした韓国における大規模な#metoo運動が、フェミニズム、そしてフェミニスト・アートが再び注目を集めるきっかけとなったのはご存知の通りです。関心が高まるとともに展示の機会も増え、フェミニズムをテーマに探究する女性アーティストも次々と登場しました。しかしながら、その動きと並行してバックラッシュも激化しています。拒絶反応が根強いなかで、フェミニズムの現状がどうなっているのか、今後どの方向へ進むのか。こうした問題を真剣に見つめる機会が必要だと感じたことが、『フェミニズム・アートを読む』の執筆にもつながりました。
──改めて、韓国のこれまでのフェミニスト・アートの流れについても整理できたらと思います。
1970年代には布や裁縫技術など女性的とみなされた素材や技術に注目し、男性的モダニズム美術に挑戦した「表現グループ」が登場しました。アーティストたちは抽象的で形式主義的なモダニズム美学を拒絶し、形象美術と女性美学を強調する表現を実践しました。しかしながら、女性性を生まれつきのものとする、初期段階の素朴なフェミニストに留まることになりました。1980年代に入ると、女性の抑圧や社会的不平等をイシュー化し、反モダニズムを実践した民衆フェミニズムの時代へ進みます。代表的な作家として、家父長的な社会現実を描いたキム・インスン(1941〜)や、40代を過ぎて自身の実存経験も反映しながら作品を制作したユン・スクナム(1939〜)が登場し、女性にとって過酷な近現代史を批判的に捉えた作品を発表しました。1990年代はそうしたモダニズム美術の解体が進み、1970年代の非モダニズム、1980年代の反モダニズムに続き、脱モダニズムの時代へ進み、新世代の作家によるポストモダン・フェミニズムが全盛期を迎えます。彼女たちは日常的に慣れ親しんだテーマを解体・再構築して、複合的な美学を発展させながら表現の幅を大きく広げました。
──フェミニスト・アートの先駆者たちですね。そこから2000年代はどう変わってきていますか?
2000年代に入ると、多文化主義とグローバリズムの影響を受けながら、アイデンティティの問題を扱う作家が増えました。1990年代初めから現れたキム・スージャ(1957〜)などはその代表で、女性性を文化的移住や離散(ディアスポラ)などのイシューへと発展させました。脱植民地主義の観点から、コリアン・アメリカン(在米韓国人)の作家たちにも注目が集まり、脱構築主義的な感性でフェミニズムの地平をより拡張させました。
さらに2010年代後半以降は、ソーシャルメディアを通じて急進的にリブートされた、いわゆるネットフェミ(オンラインフェミニスト)が台頭します。アート業界もオンラインフェミニスト・コミュニティなどと接続しながら、政治的アクティビズムと美学的フェミニズムが融合していきました。これが、韓国における現代フェミニスト・アートの大まかな流れですね。
──韓国における社会的な動きと、かなり密接に連動していますね。この流れのなかで、キムさんがお考えになる重要なアーティストは誰でしょうか?
名前を挙げた作家のほか、イ・ブル(1964〜)、ヤン・へギュ(1971〜)など世界的に著名な作家はもちろん、フェミニズムを拡張している存在として中堅的なポジションのキム・ソラ(1963〜)をご紹介したいです。日常の出来事や非言語的、身体的な行為をテーマにビデオやサウンド、テキスト、インスタレーション、パフォーマンスで表現しています。掃除の行為に着目したデビュー作、一種の掃除報告書のかたちをとった《極めて格別な黄色業務報告書》(1997)で注目を集め、以後も代替的な制度の企画者の立場で、清掃会社、旅行代理店や銀行を設立しながら、既存の制度や構造に挑戦する方式で発表を続けてきました。コンセプトアートの形式を借りながら、私たちの生きる現実をひねったり、ひっくり返したりするような手法で体制を批判しているんです。キム・ソラは人間を総体的に捉えるヒューマニズムによって新しいフェミニズムの境地を示したといえますね。
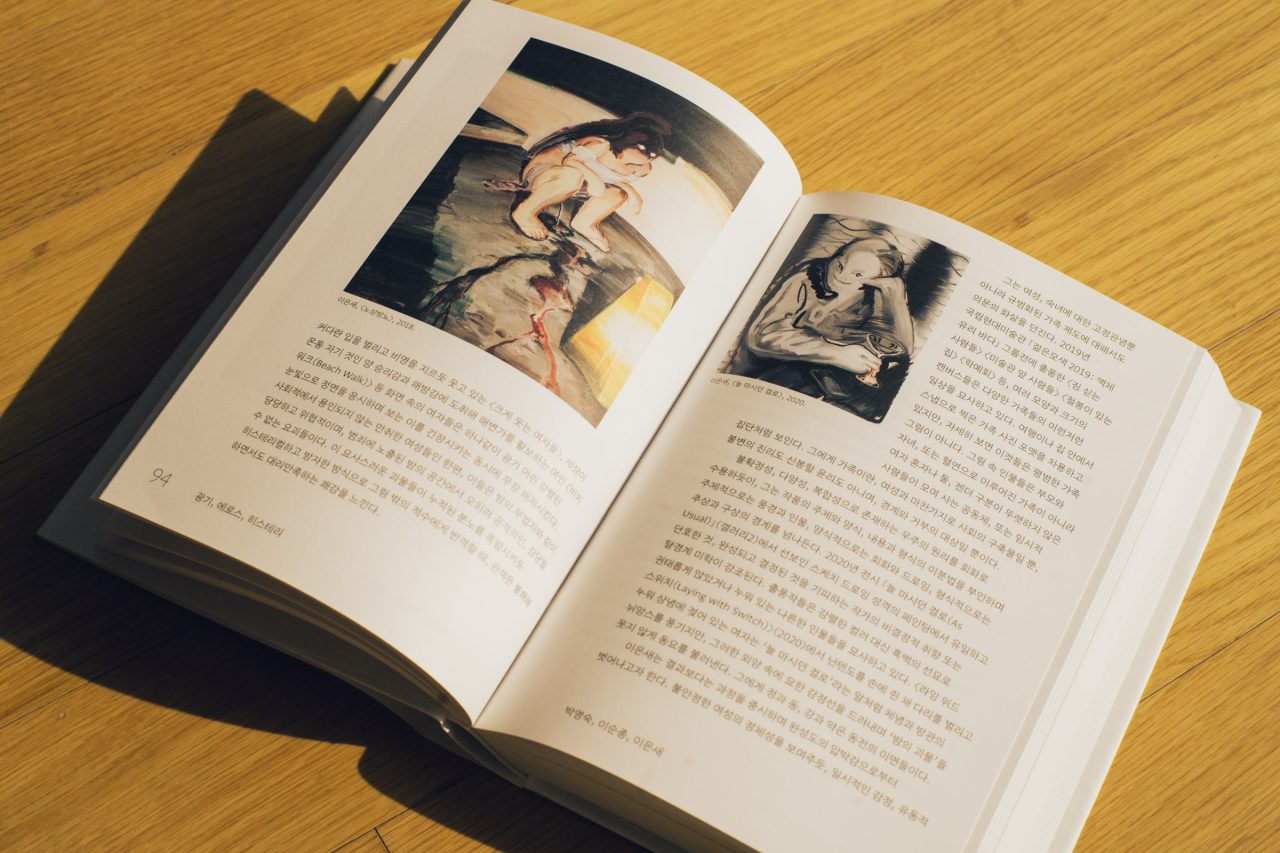
グローバルなフェミニズム運動との隔絶
──韓国のフェミニスト・アートは世界的な動きともつながっていたのでしょうか。たとえば、1971年にアメリカの美術史家リンダ・ノックリンが論文「なぜ偉大な女性芸術家はいなかったのか」を発表し、いかにアート界で女性が抑圧、周縁化されてきたかを明らかにし、大きな転換点となりました。韓国はそういった他国の動きから影響を受けていた側面もあったのでしょうか?
先ほどご紹介した1980年代の民衆フェミニズム芸術は、グローバルな潮流よりも、軍事独裁政権や政治的状況への反発を背景に生まれた、韓国独自の動きでした。その後1990年代のポストモダン・フェミニズムの登場は、欧米圏に比べて10年以上遅れています。世界的な動きと本格的に連動し始めたのは、2010年代中盤以降のネットフェミニズムの台頭からです。この時期以降は、タイミング的にも、感情的にも同時代的にグローバルな発展が可能になったといえるでしょう。
──1990年代のポストモダンフェミニズムは、韓国ではどう展開されていたんでしょうか?
1990年代の韓国美術界は、大きな変化と重要な活動が相次いだ時期ですね。経済の急成長に伴い、大衆消費文化が定着することでポストモダンのムードが広がりました。ノマディズムや後期植民地主義、グローバリズム、そしてフェミニズムといったキーワードが浮上し、従来の美術館での展示に代わって弘大の「サムジスペース」(2009年3月に閉館)や「ループ」、仁寺洞の「プロジェクトスペースサルビア」などのオルタナティブスペースが誕生したり、1995年には光州ビエンナーレとヴェネツィア・ビエンナーレ韓国館が立ち上がるなど意義ある活動が盛んになるなかで、新世代の作家たちが国際的にも活躍し、美術界の主流へと台頭していきました。若手作家たちは「脱イデオロギー」を掲げ、政治や社会の現実よりも、消費社会のスペクタクルや日常性に注目し、関係性やコミュニケーションの問題に取り組みました。同時に、身体、ジェンダー、セクシュアリティをめぐる身体政治学や性同一性をテーマとすることで、ポストモダン・フェミニズムを牽引していったのです。
──そんな状況下で、キムさんは1994年に1970〜90年代の女性作家22人の作品を集めた展示、「女性、その違いと力」を企画されていましたね。
はい。「女性、その違いと力」展は、その名の通り、女性美術の「違い」と「力」を示すために企画しました。当時、美術界には女性アーティストの作品が正当に評価されにくい性差別的な文化が蔓延していました。美術に関わる人なら誰もがそれを実感していたほどです。男性作家だけでなく、女性作家自身ですら「美術=男性のもの」と疑うことなく受け入れていたのが実状でした。
私自身、ひとりの女性評論家として、「なぜこうなのか?」と疑問を抱いていました。女性作家たちとともに活動し、対話を重ねるなかで、フェミニスト・アートの必要性について共感を育んでいきたいとも思っていました。展覧会が成功するかどうかにかかわらず、女性美術の違いや特性を示す機会自体が、フェミニスト的な発言となると考えたんです。
──他国と比較すると、韓国におけるフェミニズムにはどんな特徴があるのでしょうか?
先ほど、2020年以降は世界と連動するようにしてフェミニズムが発展しているとお伝えしましたが、そのうえで韓国には自生的な側面があると思います。特に、いまの韓国のフェミニズム運動は法的な改革を強く求めるかたちで発展し、具体的に成果をあげることを目指しています。中絶の合法化やデジタル売春の処罰強化などがその例ですね。このような現実が女性作家にインスピレーションを与え、生まれた作品を通してまた社会意識に変化をもたらす形で、アートと社会が相互に作用していると言えるでしょう。
キーワードは「コレクティブ」と「拡張性」
──これまでの変遷を踏まえて、キムさんが注目している若い世代のアーティストはいますか?
メディアアーティストのキム・アヨン(1979〜)は、とても目覚ましい活躍を見せています。近年の代表作は女性配達員たちの仕事と生活の変化を描いた《デリバリー・ダンサーズ・スフィア》(2022)ですが、韓国の近現代史で起こった事件を世界の文脈で捉えて、相関関係をマッピングするように描き出しています。関連資料を収集し、それをモンタージュ、ブリコラージュしながら意訳して再構築しているんですね。初期には写真で、のちに映像作業へと発展しながら、体制の歴史を批判しました。現実・超現実の境界を曖昧にすることで、魅力的かつ疑問を抱かせるような作品を発表しています。
──さまざまな試みが活発に起きながらも、日本も同じく、フェミニズムをめぐる困難はまだまだ多く存在しますよね。その現実に対して、これからのフェミニストアートはどんな形で抵抗を続けるのでしょうか。
そうですね、社会は依然として男性中心的であるのが現状です。この意識は家父長主義、そしてアジア特有の儒教伝統に由来する、とても根強い価値観。「ガラスの天井が破られていない」という言葉は、フェミニズムがこれからも存続しなければならない理由です。
アートがこの壁を乗り越えるために、女性たちの個人的な制作はもちろん、コレクティブな活動がとても大事なんです。韓国ではコレクティブとして活動する作家がますます増えています。美術界の矛盾と限界に立ち向かい戦う命題によって、男性たちよりもはるかに抵抗的な運動をしています。力の弱い周縁的な女性作家が作家として生き残るために、お互いに支え合う必要性があるんです。
──フェミニスト・アートそのものの題材や表現はどう変化すると見ていますか?
キーワードは「拡張性」です。前にも述べたように、フェミニズムは単数ではなく複数で存在し、さまざまな声の交錯的なナラティブであり、解決できない問題を抱えた複雑なシステムなんです。だからこそ、フェミニズムは問題的であるとともに魅力的。これからも同性愛やクィア運動も含め、さらに拡大していくと思います。最近も美術館でフェミニズムに関連した展示が盛んですが、クィアに関する企画も少なくありません。2018年にはソウル市立美術館で「イーストビレッジニューヨーク:脆弱で極端な(原題:이스트빌리지 뉴욕 : 취약하고 극단적인)」、2023年には全南道立美術館で、ノンバイナリーの黒人作家リチャード・ケネディの個展を開催しました。フェミニズムをクィア言説によってさらに拡大させる、勇敢な試みだったと感じています。
──ご自身の活動としては今後どのようなことに取り組んでいく予定でしょうか?
「拡張性」のひとつかもしれませんが、この本のフォローアップとして男性アーティストの研究を行いたいですね。たとえば裁縫など女性的と見なされてきた女性的な感受性で作品をつくる男性作家を取り上げることで、作家の性別ではなく、作品にあらわれるジェンダー的な価値や感性に注目したいと思いました。そこに見えてくるのは、「男性の作品」に内在する女性的なジェンダーのあり方です。これは、かつて「男性的な表現」とされてきた抽象美術のなかに、女性的な要素を見出そうとした議論ともつながります。男性であるからといって、父権的で普遍的な「男性らしさ」が当然のように期待されることに疑問を投げかけたい。むしろ、男性的な表現はジェンダーの枠組みで問われてこなかったのではないか──男性作家の作品のなかにある女性性を読み取ることは、フェミニズムの視点をより広げていく試みでもあるはずです。
Text: Ruka Kiyama Interpretation: Reiko Fujita Edit & Photo: Shunta Ishigami


