尿に浸したキリスト像──写真家アンドレス・セラーノの戦い
アンドレス・セラーノの《Immersion (Piss Christ)》(1987)は、自らの尿で満たした容器にキリストの磔刑像を入れて撮影した挑発的な写真作品だ。保守政治家や宗教団体からは「意図的な冒涜」として激しい非難が巻き起こったが、そこには信仰に対する二律背反的な思いなど、重層的なテーマが見出せると美術評論家のルーシー・リパードは反論する。保守派勢力 vs.アート界との激しい「文化戦争」真っ只中の時代に、リパードが『アート・イン・アメリカ』誌1990年4月号に執筆した記事を再掲する。

キリスト教団体を激怒させた宗教的イメージの破壊
アメリカ人アーティストのアンドレス・セラーノは、1984年以来、複雑な図像学を発展させながら、同時並行的にいくつものテーマに取り組んできた。彼は、カトリック信徒として育てられた自身の体験や価値観を作品の中で問い直しながら、神聖な図像の商業化を批判し、キリストが本来象徴する思想に一風変わった方法で敬意を表している。個人的な興味関心によって生み出されたにもかかわらず、彼の作品に見られる官能的な表現や物憂げに輝く色彩、迫力あるスケール、そして強烈な内容は、1980年代のアンビバレントな空気を的確に映し出している。
宗教的画像を破壊するセラーノの衝撃的な作品は、皮肉にもそれ自体が自由の象徴となった。反道徳的な表現に目を光らせていたアメリカ家族協会(*1)は、1989年4月に彼の写真作品《Piss Christ》に目を付け、神への冒涜だと非難している(同様にロバート・メイプルソープの作品をわいせつだとした)。これをきっかけとして、共和党上院議員のジェシー・ヘルムズや統一教会など、宗教的正義を掲げる人物や団体からアート界に厳しい目が向けられるようになった(原注・出典1)。
*1 American Family Association(AFA):アメリカのキリスト教原理主義団体。
アメリカ家族協会と同じく、セラーノは信仰と肉体の問題に並々ならぬ執着がある。しかし同協会とは違い、彼は自らの信仰を解体し、破壊しにかかる。だが、組織化された宗教に反発する一方で、信仰心は捨てていない。かつて「カトリシズムと思春期は相性が悪い」と語ったセラーノは(原注・出典2)、13歳の時に教会に通うのをやめてしまったが、カトリック信徒として育った多くの人々と同じく、幼少期に植え付けられた価値観は払拭しがたいと感じていた。
彼は自身の作品についてこう語っている。
「カトリックの生い立ちに対する自分の中の整理できていない感情に着想を得ていて、作品制作を通して神とのつながりを再定義し、より私的な関係を築いている。私にとって芸術とは、あらゆる虚飾を捨てて魂に直接語りかける、道徳的・精神的な義務なのだ」(原注・出典3)
こうした西洋の芸術家にとって最も重いテーマを扱うセラーノの作品には、しかし、圧倒的かつ魅惑的な美しさがある。それらは斜に構えたような抽象的でコンセプチュアルな現代アートの手法で作られているが、同時にエモーショナルな高い熱量が感じられる。
保守派が槍玉に挙げ、検閲対象となった《Piss Christ》もそうだ。タイトルの「piss(尿)」という言葉で制作過程を明かさなければ、人々の逆鱗に触れることはなかったかもしれない。木とプラスチックでできた小さな十字架は、大きく引き伸ばされた写真の中で不穏さを漂わせているが、その壮麗な赤みを帯びた黄金色の輝きは、圧倒的な存在感を放っている。表面に漂う気泡はまるで星雲のようだ。しかし、この作品のタイトルが、その見え方をがらりと変えてしまう。文脈を変えるだけで、見慣れた文化的記号が反抗の証、あるいは嫌悪すべきものに変化するのだ。
形式的な伝統の破壊
宗教的な安らぎを与えてくれるイメージを破壊したいと語るとき、セラーノがアート界の主流であるポストモダニズムの側に立っていることは明らかだ。彼のこの戦略は、宗教に対する個人的な不信感を反映している。それと同時に、具象表現における写真の役割に関する昨今の議論を意識したものでもある。ポストモダニズムの主要なアーティスト(および批評家)たちは、彼らが反対していると主張する文化と同じ価値観を、むしろ広めてしまうことが多々あるように見える。そんな中、おそらく周縁に置かれたアーティストだけが、真の変化を引き起こせるのかもしれない。
北アメリカにおいて、セラーノのような有色人種のアーティストは、メインストリームの文化と自身のルーツである(複雑に混じり合った)文化の間で危なっかしくバランスを取りながら、そのどちらについても深い知識を身につける必要に迫られている。階級と人種、抽象と具象、写真と絵画、信仰心と不信心の間の境界線を問い直すセラーノの作品は、多くの発展途上国の研究者が求めている「多声的対話」の一部を成していると言えるだろう。

宗教的な題材は1980年代に流行したが、よく言えば懐疑的、悪く言えばシニカルなポストモダニズムにとって、信仰心は忌むべきものだ。信仰心は、主に有色人種による芸術の中に見られる。彼らにとって、それは生き残るための戦術にとどまらない。信仰心や政治的信念を一方では単純素朴なものとして、他方では危険なほど操作しやすいものとみなす社会に漂う、精神的空虚さへの抵抗でもあるのだ。
複雑な宗教の問題に、信仰者として取り組む勇気を持つアーティストはほとんどいない。だからこそ、セラーノが扱う宗教的題材の破壊的な性質を十分に理解できたのが、原理主義的なキリスト教徒たちだけだったことは驚くにあたらない。彼らは常に作品の持つ意味に神経を尖らせているが、多くの鑑賞者にとって意味は二の次だ。セラーノいわく、自分の作品は直感的かつ本能的に出てきたもので、いくつもの解釈が可能な多面性を持つために自分自身でも正確に意味を捉えきれないという。そうした主張は、作品の過激さを和らげ、検閲をかわす彼独自の方法なのかもしれない。
セラーノの大判のチパクローム(*2)プリントは、「社会通念への反発」という単純なラベリングだけでは済まされない複雑さがある。英語以外の言語を排除しようとする、時代に逆行した排外主義が日増しに勢力を増すアメリカ社会において、具象的であると同時に抽象的でもあるセラーノの作品は、視覚的なバイリンガルだと言える。また、単純な愛国主義が蔓延する時代における文化の不安定さを表してもいる。セラーノはこう言っている。「イメージを反転させ、見慣れたものを抽象化することで、形式的な伝統を破壊したい。写真だけでなく、私自身の経験や社会の現実を問い直すために」(原注・出典4)。
*2 スイス・チバガイギー社の傘下にあったイルフォード社が開発した画像形成プロセス(のちにイルフォクロームに名称変更された)。パールのような独特の光沢が特徴。
複雑な生い立ちとカトリックの影響
「昔から、物事を白か黒か判断するのが苦手だった。私は混血だから」。そう語るセラーノは、中国人の曽祖父を持ち、ブルックリンのウィリアムズバーグ地区にあるイタリア人街で、祖母とアフリカ系キューバ人の母に育てられた。工場労働者の母は英語を身につけることはなく、精神病に入退院を繰り返していた。また、商船の乗組員だったホンジュラス人の父親と過ごす機会はほとんどななかったという。最後に会ったのは23年前で、ホンジュラスにいた父親を探し出し、束の間の面会を果たしたときだった。
「私はいつも自分の中の二元性を受け入れてきた。作品にはそれが反映されている。私の作品に一貫したテーマがあるとすれば、それはこの二元性、あるいは矛盾だろう」(原注・出典5)。
セラーノは、色濃いラテン文化の中で、決して幸福とは言えない幼少期を過ごした。それがアーティストになりたいという長年の願望を叶える原動力となり、過激な図像の源になったのかもしれない。しかし、彼の回想によると、家には美術品や磔刑像はなく、母親が「聖母像と、キリストとその聖なる心臓を描いた絵を何枚か持っていたくらい」だったという。幼い頃からずっとアーティストになりたいと考えていた彼は、12歳で地下鉄に1人で乗れるようになると、学校の見学で訪れたことのあるメトロポリタン美術館に足しげく通うようになった。
「実は、最初は画家たちの人生に魅了され、絵を描くことよりも美術史に興味を持っていた。私の作る宗教的なイメージは、ルネサンス美術に負うところが大きい」と語る彼は、15歳の時に学校を中退。その2年後の1967年に17歳で復学し、ブルックリン美術館のアートスクールで2年間、アフリカ系アメリカ人の画家カルビン・ダグラスに師事した。絵画や彫刻に惹かれつつも、自分にはその分野の才能が欠けていると感じたセラーノは、写真を始めた。当初はポートレートなどを撮っていたが、次第に創作活動から離れ、広告代理店でのアシスタント・アートディレクターなどさまざまな職を経て、1983年に再び制作を開始している。
「最初の頃はカラーの風景写真を撮っていたが、ある時から自分の頭の中にある情景を撮りたいと思うようになり、生肉を使うようになった。そこに、死につながる何かがあると感じていたからだ。この肉のシリーズは、生と死を同時に表現していたと言える。そうやって、自分でも気づかないうちに宗教的な作品を作っていたが、2、3年してやっとそれを自覚した。こんなに、宗教的なイメージに対する執着が自分の中にあるとは思わなかった。これはラテン系特有なものなのかもしれないが、アメリカ的というよりはヨーロッパ的なものでもある。映画監督のルイス・ブニュエルには通じ合うものがあると感じている。『皆殺しの天使』(1962年)でカトリックの教会に羊の群れが入っていくシーンは忘れがたい(原注・出典6)。ヨーロッパのアート、特にデュシャンからも影響を受けた。彼は自由な精神の持ち主で、類を見ない挑発者だ。若い頃は彼の反逆精神に大いに共感したものだ」
矛盾と両義性への大胆な挑戦
1983年、33歳の時に優雅で風変わりな「絵画風」の写真作品を制作し始めたセラーノは、それまでの美大生の延長のような仕事を脱し、一気に成熟を遂げた。これらの作品が初めて公開されたのは、1984年に開かれた展覧会「Artists Call Against U.S. Intervention In Central America」(*3)でのこと。背景の前に物や人物を配置した当初の作品は演劇的な要素が強く、シュルレアリスム演劇のスチール写真のようだった。たとえば、《Memory》(1984)では、赤い衣をまとい、仮面をつけた聖職者のような人物が子牛の死骸を差し出し、その横で幼い少年が目をそらしている。
*3 「アメリカ合衆国の中米への介入に抗議するアーティストたち」の意。
この幻覚のようなイメージは、アメリカを後ろ盾に持つ権力者を支援する腐敗と、民衆を癒し勇気づける「解放の神学」(*4)の間で引き裂かれる、中米の教会の残虐性と無垢を示唆している。また、彩色された木の棒に乗せられた鹿の頭に向かって頭を下げている赤毛の女性を写した《Anti-Christian》(1985)は、異教徒の自然崇拝を暗示するものだ。
*4 1960年代頃に中南米で興った、貧困問題や人権など社会問題の視点を取り入れたカトリック教会の改革運動。
初めて排除の対象となったセラーノ作品は《Stigmata》だ。私は1985年に、彼と彼の妻であるアーティストのジュリー・オルトに、Printed Matter(*5)のショーウィンドウに飾る作品を共同制作してほしいと依頼した。それに応えて作られたのがこの作品だった。写真の中では、裸の女性が白い革の手錠をかけられ、手が血まみれになっている。これは、聖なる烙印を押される(stigmatize:「汚名を着せられる」という意味もある)という「自然」現象を経験するのは男性よりも女性の方が多いという説に言及している。しかし、作品が近隣の苦情を受けたため、私たちは店の中からしか見えないようその向きを変えた。その上で、作品の「存在または不在」に触れたステートメントを通りに向けて貼り出した。
*5 この記事の執筆者、ルーシー・リパードがニューヨークに設立したアートブックなどを扱う書店。

グロテスクなイメージに込められた重層的なテーマと批判
セラーノの作るドラマチックなイメージには静かな批評が組み込まれているが、往々にしてそれは曖昧だ。たとえば、生肉と血の使用は原始的あるいは退廃的ともとれるし、批判的あるいは不気味ともとれ、犠牲、養育、拷問など、さまざまな解釈を引き出すことができる。初期の作品《Meat Weapon》(1984)は、彼の友人の黒人俳優、ローレンス・フィッシュバーン(フランシス・フォード・コッポラの『地獄の黙示録』に機関銃を持って登場した)をモデルに起用した中世的な趣のある写真だ。赤いニット帽をかぶったフィッシュバーンが子羊の足をマシンガンのように構えているこの作品は、自慰行為、戦争、セクシュアリティといった、文字通り肉欲に関するテーマを連想させる。皮肉たっぷりなユーモアは戦闘的なものというよりは、単に意表を突く性質のものだ。
視覚的要素とタイトルが言葉遊びのようになっている作品も多い。たとえば、子牛の頭を台座に乗せた作品には、スペイン語で「牛の頭」を意味する《Cabeza de Vaca》という、文字通り見たままのタイトルが付けられている。冗長な感じを与えるが、実はここにはもう1つの意味が込められている。Cabeza de Vacaというのは、有名な征服者コロナド以前の15世紀にメキシコ北部やブラジルを探検したスペイン人の名前でもあるのだ。大皿に乗せられ、差し出された征服者の首は、征服の犠牲となった人々と重なり合い、現代に向けて幾重もの意味を反響させる。
キリストの受難を意味する《The Passion》(1984)では、子羊の死骸の上にキリストの悲劇的な頭部が乗せられ、生けにえの子羊の比喩を文字通り表している。また、《The Rabble》 (1984)では、たくさんの鶏の足が十字架を囲んでいる。家の形をしたアクリル樹脂の容器に動物の脳を詰め込んだ《Locked Brains》(1985)は、閉鎖的な考え方に対する風刺だ。1987年に制作された風景画のような《Blut und Boden》(ドイツ語で「血と土」。民族と祖国を意味し、ナチスのスローガンとして使われた)の不吉な赤い「空」は、愛国心と土地、暴力と感傷的なナショナリズムの問題を、物質的な形で提起している。
首に縄をかけられ顔を歪めたコヨーテの頭部を写した《The Scream》(1986)は、ムンクの有名な作品と同じ「叫び」というタイトルが付けられている。コヨーテの苦悶の表情は、センチメンタリズムに陥ることなく動物界の掟と人種差別的リンチを表している。セラーノ独特の両義性を持つこの作品において、コヨーテは獲物と捕食者の両方を象徴しているのだ。ちなみに、このコヨーテはセラーノが仕留めたわけではなく、メイン州の農家から20ドルで買い取ったものだという。1987年の作品《Dread》は、ラスタ(*6)のドレッドヘアを背面からクローズアップで撮影した写真だ。力強さを感じさせるヘアスタイルの人物が見る者に背を向けるこの作品は、古典的で控えめな方法で人種差別を非難し、抵抗者の誇り高さを表現している。
*6 ラスタファリ運動の略。1930年代にジャマイカの労働者階級と農民を中心にして発生した宗教的思想運動。

セラーノは、作品の中でさまざまな特殊効果の実験を試みている。画家が絵の具や絵筆を使うように光や照明を用いる彼は、写真の機械的、技術的な側面にはあまり興味がないようだ。1984年から86年にかけて制作した《Fallen Christ》(1986)と《Heaven and Hell》(1984)では、背後からの光で不穏さを演出している。後者は、画家のレオン・ゴラブをモデルにした劇的な作品で、枢機卿に扮したゴルブが、両手を縛られ頭を反らせた血まみれの裸婦に背を向けて立っている。
女性と枢機卿の姿は対照的だが、どちらが天国でどちらが地獄を表しているのか判然としない。痛めつけられた女性を登場させた理由を、セラーノはこう語っている。
「教会の女性に対する姿勢、もっと言うと一般の人々に対する姿勢には、何かひどく欠けているところがある。この聖職者が背を向けているのは、彼女の苦しみなどどうでもいいと思っているか、それに気づいてすらいないからだ。両者の間には深刻な分断がある」
とはいえ、この作品の性的な含みについて彼は説明しきれていない。セラーノはこの作品を通して、教会の女性の身体(と心)に対する残酷で冷たい扱いという問題に焦点を当てているが、これほどあからさまにエロティックな表現を使う必要があったかどうかは疑問が残る。
血液や尿など体液を使った抽象的作品へ
1986年の後半から、セラーノは体液を使った作品の制作を開始する。この「生命に不可欠な液体」に人々は、「視覚的、象徴的にいくつもの意味を見出している」と彼は考えている(原注・出典7)。最近発表された作品の多くは完全に抽象的な作品だが、ミニマリズムや幾何学的構成、単彩、表現主義など、さまざまなスタイルが取り入れられている。
《Blood Cross》の中にそびえる十字架のオブジェは、十字架型のアクリル容器を血液で満たしたもの。このオブジェは聖金曜日(*7)に作られたそうで、「犠牲」を象徴している。セラーノは「磔刑、さらにキリスト教は煎じ詰めると犠牲について説いたものだ」と語っている。この作品は、病や傷を治す赤十字を思い起こさせつつ、カトリックの残酷な歴史にも言及している。これと対をなす《Milk Cross》は、慈愛に満ちた教会の母性的な側面を表すとともに、西洋の宗教組織が標榜する自制心と白ユリのような「純粋さ」を表現している。血で半分満たしたアクリル製の水槽に、子牛の心臓を入れた《Two Hearts》(1986)は、彼の作品の中で体液の存在感が増してきた過渡期の作品だ。
*7 キリストの復活を祝う復活祭(日曜日)前の金曜日で、十字架に架けられたキリストの受難と死を記念する日。
セラーノ初の純粋な抽象作品である《Milk, Blood》(1986)は、宗教的象徴と同じくらいアートにおける象徴主義(ピエト・モンドリアン、カジミール・マレーヴィチなど)からも影響を受けている。この作品は、同じ大きさの赤と白の長方形を2つ並べた絵画のように見える。だが実際にはタイトルが示すように、それぞれ赤と白の液体が入った2つのアクリル製タンクを撮影した写真だ。そこでは、写真の平面的な「硬さ」と、被写体の液体の「柔らかさ」の間に明白な緊張感がある。この作品に続き、1987年には《Blood and Milk》と幾何学的な《Circle of Blood》という、やはり赤い色を使った作品が発表された。
1988年になると、セラーノは新しい色をパレットに加えたいと考えるようになった。「尿は自然な選択だった」とのちに彼は語っている。独特の濃密な輝きを放ち、血やミルクよりも「受け入れられにくい」ため、過激さの度合いも増した。1988年の「Piss and Blood」シリーズのように、タンクに溜められた尿に血液が注がれると、夕焼けのように華麗な薄膜が現れる。こうした流し込みを用いた作品では、黙示録的な「風景」や、人影のような形も生み出されている。《Winged Victory》(1988)(*8)に写っているのは古典彫刻ではなく、キリストの頭部と胴体が取れてしまった磔刑像から偶然に現れた形だ。血にミルクを注いだり、ミルクに血を注いだり、ミルクと血を並べたりすることで、セラーノは1つのイメージの中に滋養と苦痛の概念を混ぜ合わせている。
*8 ルーブル美術館の大階段の踊り場にある有名なギリシャ彫刻《サモトラケのニケ》(翼を持つ勝利の女神の像)の英語名。
セラーノが特に得意とするのはスケール感だ。彼の写真の中のフォルムは、広大で捉えどころのない空間に存在している。それらは逆光の巧みな利用で拡大され、画面の前面に押し出されている。目に見える部分を最小限に抑えながらも、そのディテールを極めることで、被写体につきまとう逸話的な要素を排除し、圧倒的なシンプルさを達成している。こうした写真の持つ力強さは、いくつかの要素から成り立っている。1つは、形式的な明快さ。もう1つは、うっすらと漂う悪夢のようなよそよそしさだ。また、前面に打ち出されているわけではないが、彼の多民族・多文化的なルーツとの重要なつながりがあり、権威の象徴としてのカトリックに対する相反する思いもある。これこそが彼の作品の核心(crux:文字通り十字架)を成すものだ。
セラーノの関心は、写真で「絵画」を作ることにある。彼はそれを、絵の具の質感を真似るというよくある方法ではなく、従来、写真と関連づけられてきた3次元のイリュージョンを否定することで行う。たとえば、彼のモノクローム作品には液体で満たしたタンクのフレームが写っているものがある。モチーフを並べた様子がわかるこの作品は、まさに伝統的な静物画として見ることもできるのだが、そこでは被写体となる物と背景の間の距離、そして形態と内容の間の距離も(ある程度)排除されている。
《Blood Stream》のような「表現主義的」な作品では、モノクローム作品のハード・エッジ絵画(*9)のように対象を持たない抽象性が、やや薄まっている。伝統的で叙情的な抽象画のように見えるこの作品は、実は注がれた血液の軌跡を捉えたアクションフォトだ。この作品の構図は、最終的に液体の物理的特性によって決定されている。60年代のプロセス・アート(*10)を参照したこの写真でも、セラーノはタイトルで自ら文脈を提示し、液体の動きに込められた複雑な感情を示している。「混血」の比喩的表現として見ることができる《Blood Stream》は、混ざり合う行為の現場を捉えた作品なのだ。
*9 明確な輪郭を持つ色面や線などで構成される、平面的な抽象画。
*10 物体としての作品そのものよりも、それが作られる過程や、展示される中でそれが変化していく様子に焦点を当てた1960-70年代のアートの傾向。
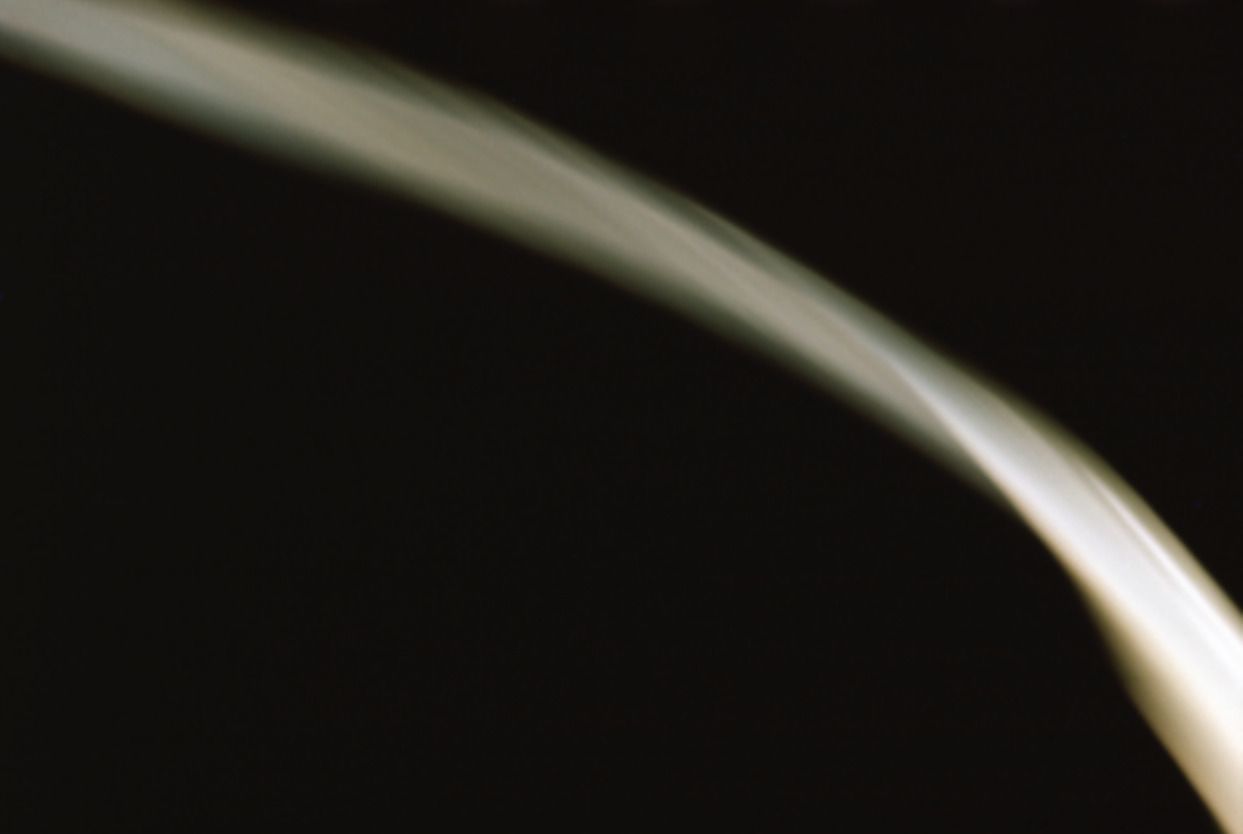
体液や排泄物への嫌悪感に挑戦
射精された精液が飛んでいく様子を捉えた「Ejaculate in Trajectory」シリーズ(1989)は、セラーノが手がけてきた中で最も叙情的な作品だろう。液体を注ぎ入れる作品と同じく、このシリーズの制作過程は制御が難しい。彼は素早い動きを捉えるために、カメラにモータードライブ(高速連写を可能にするフィルムの自動巻き上げ装置)を付けたそうで、大真面目な調子でこのシリーズは「どこか科学的なところがある」と話している。
このシリーズには、黒地に浮かぶ白っぽい斜線など、タイトルからイメージする爆発的な勢いを感じさせる画像もある一方で、優雅な弧を描いているもの、コンスタンティン・ブランクーシの彫刻《空間の鳥》を思わせる静謐な作品もある。これらの作品でも、ひとたびその制作過程を知れば、芸術と創造性、着想(conceptionには「受胎」の意味もある)、写真と複製(reproductionには「生殖」の意味がある)など、いくつもの言葉遊びが浮かび上がってくる。
セラーノが扱っている最新の液体は経血だ。セラーノによると「精液の写真とのバランスをとるため」に作ったもので、「そうでないとマッチョな方向に偏ってしまう。このシリーズ作品は、生殖をめぐる女性の権利の問題に言及している」という。具体的には、「Red River」シリーズ(1989)では使用済みの生理用品が接写されている。絵画的というよりは彫刻的な立体感があり、中には胎児のような形が見えるものもある。
当然ながらと言うべきか、これは彼が手がけた中で最も不人気なシリーズだ(ある写真ワークショップでセラーノがこのシリーズを見せた時、観客からは不快感を表す声が漏れた。尿や精液もさることながら、女性特有の生理現象はひときわタブー視されているといえる)。確かに、ほかの体液に比べ、彼はこの被写体をうまく美化しきれていない。たとえ接写したとしても、ブヨブヨした使用済みナプキンをフォトジェニックに見せるのは難しい。これを見て私の脳裏に浮かんだのは、女性の自然な身体機能をタブー視する社会に反旗を翻した、初期のフェミニスト・アートの作家たちに浴びせられた非難の声だった。

セラーノは、自然と文化、身体と精神という既存の枠組みに揺さぶりをかけるが、経血を使った作品では特にこれが強調されている。カトリックや原理主義者の、キリストや罪人の肉体への執着に焦点を当てた身体論的(原注・出典8)な考え方がある。彼はそれを踏まえた上で、人々が自分自身の身体やそこから出てくる物質に感じる気持ち悪さや、社会で共有されている体液への嫌悪感に挑戦しているのだ。
これまでの彼の作品は、切断された身体部位や、エジプトのオシリス神などの死と再生の物語を参照していた。体液の作品はそれと同じように、排泄物に神聖さを見出す世界各地の伝統文化に倣っている。たとえば、アメリカ先住民のホピ族には尿や排泄物の踊りや、聖なる道化との陽気な「性交」の儀式などの伝統があった。しかし、イギリス系のキリスト教原理主義者たちはこうした伝統に拒否反応を示した。その結果、古くから伝わる先住民の宗教儀式の多くは、西洋的な感覚では野蛮だとみなされ、19世紀末からかけて20世紀初頭にかけて禁止されてしまった。
「私にとって、黒というのはひとつの色なのだ」
セラーノは現在、黒人であることをテーマにしたポートレートのシリーズを制作しており、ジャン・ジュネの戯曲『黒人たち(原題はLes Nègres)』にちなんで「The Black」というタイトルを付けている。
「これは、不可視性と周縁性をテーマにしている。黒人のモデルたちは黒い服を着て、暗い背景の前にいる。照明が当たる範囲を極端に狭くすることで、顔の正面だけが浮かび上がり、他の部分は黒い背景に溶け込むようにしている。この作品には独特の優雅さがある。私にとって、黒というのはひとつの色なのだ」
ニューヨークのギャラリー、Greenberg Wilsonで1988年に開催された「Piss Deities」展(悪名高い《Piss Christ》はここで初めて展示された)でセラーノは、ジュリー・オルトとレオン・ゴラブをモデルにした2点の「ストレート」ポートレートを逆さに展示した。これには、宗教、愛国心、文化的な偶像崇拝によって人間が抽象化され、象徴的な存在になること(彼いわく「実生活とは別の次元に置かれること」)への批判だ。とはいえ、アート界の文脈では、この反転は必然的にゲオルク・バゼリッツの逆さまの絵画を想起させ、批判として成功したとは言えなかった。
この展覧会には、ローマ法王の横顔を描いた2枚の肖像画を尿に浸した作品も展示されていた。これについて彼は、「以前見た、ベルトルッチかパソリーニの映画に着想を得た。最後の方のシーンで、ムッソリーニの失脚が、法王の大きな胸像が倒される様子で表現されていた」と説明している。セラーノは、こうした作品は挑発を目的としているわけではないと言う。
「確かに今の教会の方針には問題があるとは思う。でも、私が常に意図しているのは、美しいものを作ることだ」。
この展覧会では、《Piss Christ》と《Piss Pope》に加え、《Piss Elegance》(ギリシャ・ローマの古典様式を模したアールヌーボー彫刻)や《Piss Satan》も展示され、同じく有機的な輝きを放っていた。今のところ、古代信仰の信者と悪魔崇拝者から苦情は出ていない。
《Piss Elegance》(小便エレガンス)という悪ふざけのようなネーミングはともかく、古典彫刻などを被写体にしたセラーノの作品は、キリスト教のシンボルを扱った作品のようには強く心に響かない(もちろん、これは単に非カトリックである私が、カトリック的なイメージに潜むセクシュアリティや暴力に惹きつけられているだけなのかもしれないが)。1989年の《White Christ》 は、宗教用品を売る店で買ったキリストの石膏像の頭部を牛乳と水に浸したもので、色彩的にもテーマ的にも非常に地味だ。この作品について、ある下院議員から十字架を精液の中に沈めたと非難されたセラーノはこう語った。
「彼らは白い肌のキリストを求めている。自分たちのものだと呼べるキリストをね。私はそれに応えているんだ。彼らがこの作品から何を読み取っても構わない。きっと何かを読み取るだろうが」(原注・出典9)
わいせつは見る者の目に宿る
セラーノの作品においてセクシュアリティは明示的なテーマではないが、彼の作品はアメリカ特有の単純で偽善的な神経を逆撫でした。それは、潔癖さを良しとするピューリタニズムと、その裏に潜む他人の性事情への異常な執着だ。セラーノとロバート・メイプルソープの作品は、人々をひどく困惑させた。保守派政治家のジェシー・ヘルムズは、この作品について妻と話すのが「恥ずかしい」と記者に語っている(原注・出典10)。どうやら、このバプティスト派の上院議員は、わいせつは見る者の目に宿るということを知らないようだ。
一方で、セラーノとメイプルソープをめぐる論争は、アートと一般の人々の間に横たわる断絶を示唆するものでもある。確かに彼らの作品は、ヘルムズらによって本来の文脈から切り離され、理不尽とも言える攻撃を受けた。その一方で、多くの現代アート作品は正しい文脈の中でさえ大衆の反感を買うだろう。セラーノは《Piss Christ》を重要な転機として捉えており、アート界の文脈ではそれは素直に受け止められている。
しかし、こうした作品が作家のスタジオやギャラリーを出て、より多くの人々の目に触れるようになったらどうだろうか。そこで衝突が起きる可能性を無視するのは、あまりに世間知らずというものだろう。キリスト教保守派の多い南部の田舎では特にそうだ。セラーノは、政治的に洗練された都会のアーティストだ。この数カ月間の出来事に、彼が純粋に驚き苦悩している様子から改めて浮き彫りになったのは、どんなに善意のアーティストでも、鑑賞者の感覚からかけ離れてしまうことがあるということだ。
ドナルド・ニューマンの「Nigger Drawings」展(原注・出典11)から10年(執筆当時)経った今、アートと難しい社会問題との関係性にはいまだに多くの課題がある。こうした問題は、ハイアートの「言説」においては、概して避けられているのが現状だ。アートをめぐる言論空間では、「道徳」という言葉は嘲笑の対象とされるか、大げさな表現だと受け止められるか、右派の専売特許とみなされている。
セラーノは、「マイノリティ」であること、あるいは「ハイブリッド」なアイデンティティを持つということはどういうことかという、難しい問題を探究している。しかし、彼は当事者として自分自身を打ち出す正攻法はとらない。そのかわりに、人格形成に寄与した文化的表象と対峙するという、間接的な方法をとる。
彼は、ゴヤからブニュエルまでの芸術家を引き合いに出しながら、「暴力的であり美しくもあるスペインの芸術の伝統に強い絆を感じている」ことを認めている。その伝統は、ラテンアメリカ的なフォルムにも受け継がれ、さらに今ではそこにアフリカやアメリカ先住民の影響も加わっている。セラーノのイメージは、私たち全員に押しつけられた支配的な物語に対し、批判的かつ柔軟な関係を取り結ぶ。彼の作品は、見慣れた宗教表現を批評し、それに歯向かうだけでなく、ラテン系のアーティストに対する世間の固定観念をも裏切ってみせるのだ。
解決できない/すべきでない矛盾を露呈
アート界の規範や階級によって分断されているこの社会には、宗教的な深みと社会的な意味を兼ね備えた芸術の居場所はほとんどないも同然だ。セラーノの芸術は、ある種の疎外感の核心を突いている。文化的、人種的、階級的な文脈の中で立ち現れるこの複雑な疎外感は、最近になって多くの美術館を席巻している多文化主義の機運の中でようやく認識され始めたところだ。
「宗教はシンボルに大きく依存している。アーティストとしての私の仕事は、シンボルを操ることを極め、その可能性を探ることだ」とセラーノは語っている(原注・原注12)。そんな彼の政治的な洞察力は鋭い。なぜなら、極右もまた1980年代を通して、国旗から男性器、十字架まで、シンボルの持つ力を発見してきたからだ。そう考えると、右派がアートに攻撃の矛先を向けたときにセラーノがターゲットにされたのは不思議ではない。芸術と政治の場でこの10年間でも稀に見るほど白熱した、シンボリズムをめぐる戦いに引きずり込まれたのが彼だったこともそうだし、「不敬な」図像などいくらでも見つかるアート界において、彼の作品が表現の自由の代表としてかつぎ出されたことも納得がいく。
セラーノは、アメリカ家族協会やジェシー・ヘルムズ、あるいはニューヨークの上院議員アル・ダマト(上院の議場で《Piss Christ》などの図版が掲載されたカタログを破り捨てるというパフォーマンスを演じた)のような人物を怒らせるために作品を作っているわけではないと断言している。その一方で、鑑賞者が自分の頭でものを考えないよう画策・宣伝する一派が存在することも承知している。
「こうした利権団体の規模は小さいが、(メディアや美術館などの)責任者に圧力をかけることで多大な影響力を行使している。キリストの名の下に巨額の利益を得る産業が存在するが、こうした団体を誰が監督しているのか知りたいものだ。彼らはテレビやラジオ放送、そして美術館などから道徳に反するものを排除するのに躍起だ。だが、宗教界では誰が不道徳の基準を定めているのだろう?」(原注・出典13)
アート作品として単純に美しいということはさておき、セラーノの作品は答えよりも多くの問いを意図的に投げかけてくる。彼の作品は、従来のアートの見方とは違う見方をするよう鑑賞者に求める。違いを尊重することでセラーノは、解決できない、また解決すべきでない矛盾を露呈させるのだ。彼の作品はさらに、私たちが子供の頃から刷り込まれてきた「趣味の良さ」という既成概念が、社会秩序の幻想に基づいていることを示す。私たちはもはや、そうした秩序があるとは信じられなくなったし、信じたいとも思えなくなった。私たちは今、支離滅裂で無秩序な文脈の中でアートを見ている。それは既存のルールに従うよりもはるかに難しい。(翻訳:野澤朋代)
原注・出典
1. ニューヨーク・トリビューン紙、ワシントン・タイムズ紙、インサイト・マガジン誌によると、アメリカ家族協会による懸念の声にいち早く反応したのは、文鮮明の統一教会だった。1989年5月に発行された統一教会の出版物がこれについて取り上げている。
《Piss Christ》は、政府機関である全米芸術基金(NEA)の協賛で開催されたアート・コンペで最優秀賞に選ばれたが、キリスト教への冒涜だと批判が巻き起こり、保守派政治家の圧力によりNEAの予算が削られる事態に発展した。この全米芸術基金(NEA)に対する検閲問題に関する最も良い記事は、アート・イン・アメリカ誌1989年9月号に掲載された「The War on Culture」(キャロル・ヴァンス執筆)と、ニュー・アート・エグザミナー誌1989年夏号に掲載された「NEA Under Siege」(ニコルス・フォックス執筆)だろう。私自身もゼータ誌1989年10月号でこの問題について記事を書いた。
なお、1989年10月、議会は「わいせつな」芸術や「真面目な文学的、芸術的、政治的、科学的価値」を持たない芸術に対し、政府の支援を制限する法案を承認。アート界との対立をさらに深めた。
2. 引用元が記載されていないセラーノの言葉は、1989年10月18日に筆者が行ったインタビューからのもの。
3. セラーノによる1989年の未発表の声明。
4. 同上。
5. 1989年8月16日付ニューヨーク・タイムズ紙の記事「Artist Who Outraged Congress Lives Amid Christian Symbols」(ウィリアム・H・ホーナン執筆)の中のセラーノの言葉。
6. ミネアポリスで発行されていたアートペーパー誌1989年9月号に掲載された記事「Interview with Andres Serrano」(スーザン・モーガン執筆)は、ゴヤとセラーノの作品の間にいくつかの興味深い類似性を見出している。ブニュエルの映画のタイトルにもなった「Exterminating Angel(邦題:皆殺しの天使)」はゴヤの時代の保守的な秘密結社の名前。
7. セラーノは血と内臓を近所の肉屋から仕入れ、使用するまでアイスボックスで保存している。悪臭を放つ素材は尿だけで、それも非常に暑い日に使用した場合に一時的に匂うだけだという。
8. Victor Zamudio Taylorが発展させてきたこの概念については『Ceremony of Memory』 (Center for the Contemporary Arts, Santa Fe, N.M., 1988)を参照されたい。
9. ローマ法王は《Piss Christ》に対する不支持を表明しているが、おそらく彼は自分自身が果たした役割を知らないのだろう。セラーノは、対立関係にある原理主義的プロテスタントとカトリックを共通の怒りで結びつけ、キリスト教会の統一という偉業を成し遂げたのだとニコルス・フォックスは指摘している。
10. 1989年7月18日付ニューヨーク・タイムズ紙の記事「Jesse Helms Takes No-Lose Position on Art」(モーリーン・ダウド執筆)より。
11. 「The Nigger Drawings」は、1979年にニューヨークのArtists Spaceで開催されたドナルド・ニューマン(活動名としてはファーストネームのみを使用)の個展のタイトル。抽象的なドローイングを集めたこの展覧会のタイトルは、展示作品そのものとは全く関係なく、純粋にセンセーショナリズムを狙ってつけられた。黒人アーティストに対して非常に侮辱的なこの展覧会は、有色人種のアーティストや進歩的な団体から非難された。この一件によってアート界は人種差別の問題と真摯に向き合うようになり、「アーティストは社会的責任を免除された存在だ」という考えが見直されるようになった。
12. 1989年8月16日付ニューヨーク・タイムズ紙の記事「Artist Who Outraged Congress Lives Amid Christian Symbols」(ウィリアム・H・ホーナン執筆)の中のセラーノの言葉。
13. Artpaper誌1989年9月号の記事「Interview with Andres Serrano」(スーザン・モーガン執筆)の中のセラーノの言葉。
from ARTnews


