宮津大輔 連載「アート×経営の時代」第1回 金融商品としてのアートのパワー
アートはビジネスに必須だ――という認識は、この数年で、日本にもすっかり定着したように見える。では実際に、日本の企業はアートをどうビジネスに利活用しているだろうか。バブル後によく言われたCSR(企業の社会的責任)としてのアート支援ではなく、アート的思考でもなく、「経営戦略として」アートを採り入れる動きはあるのか。アートコレクターで、多数の著書もある横浜美術大学学長の宮津大輔氏が、連載で読み解く。

私とARTnewsの出会い
この度、ARTnews JAPANで「アート×経営の時代」を連載することとなった。私とARTnewsの出合いは、かれこれ20年以上も前にさかのぼる。現在も続く米国版同誌恒例の企画「The World’s Top 200 Collectors」の中で、次世代を担うコレクターを紹介する「The Next Wave」の5人に選ばれたからである(『ARTnews Summer 1999』138~139ページ)。最初の一点である草間彌生の《Infinty Dots》(1953年)を購入してから、5年が経っていた。しかも、表紙を飾っていたのも、私のコレクションする草間彌生《無限の網》(1965年)という、一介のヤング・コレクターにとっては望外の出来事。今回、このように思い入れが深いARTnewsの、日本版ローンチに際し拙稿を寄せる機会に恵まれたことは非常に感慨深い。
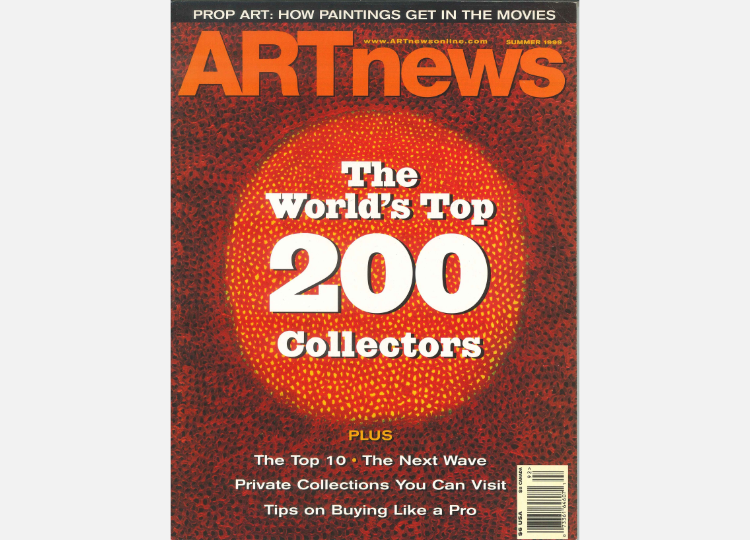
アート×経営の時代
最近では、予測不能で混沌(こんとん)とした「VUCA」(Volatility、Uncertainty、Complexity、Ambiguityの頭文字を取った造語)時代を生き抜くために、ビジネスマンに向けた論理+感性からなるアート的思考を学ぶための書籍やワークショップが人気となっている。歴史をたどってみれば、15世紀ルネサンスの時代には、「アート(芸術≒感性や直感)」と「サイエンス(科学≒理論や理性)」は同根と考えられており、それらを二項対立視するものではなかったといえよう。
個人的には時代の趨勢(すうせい)でしばらく分離していた両要素が、21世紀の今「アート×テクノロジーの時代」(2017年発刊の拙著タイトルでもある)を迎え、再び結び付きを強めているように思えてならない。先端技術を用いてアート作品を創作する、チームラボやライゾマティクスといった「最先端テクノロジー・アート創造企業」の祖先が、ヘリコプターの原理(図案化され、過去には全日空のシンボルマークにも採用されている)を考案、水圧ポンプや蒸気砲を発明・設計した科学者であり、芸術家のレオナルド・ダ・ヴィンチであったことを思い起こせば合点がいくのではないだろうか。
真のアートとは極めて論理的でありながら、時に常軌を逸脱した表現により我々を未知の領域へと誘(いざな)うアンビバレントな存在である。新型コロナウイルスのパンデミックという変数やスタグフレーションという景気動向、そしてAIが人間を超えつつある技術進化の現状。このような環境下においてこそ、優れた現代アートだけが有する独自の思想が、エクセレント・カンパニーの先進的取り組みを後押しするものと考える。日本企業が世界でサバイブするためには、日本独自の創造性に富んだ経営哲学が必要不可欠であり、本連載ではそうした事例を紹介していく。

金融商品としてのアートが有する強大なパワー
初回は、アート作品が持つ直接的なパワーについて述べたい。
ドイツとフランス、そしてスイスの3カ国が国境を接する地点に位置するバーゼルは、永世中立国スイスにおける交通の要衝であり、1930年以来国際決済銀行の本部も置かれている。また、毎年春に開催される世界的な宝飾品と高級時計の見本市であるバーゼル・ワールドや、初夏(6月)の風物詩ともなっているアートバーゼルを始めとし、多くの見本市や博覧会も開催されている。更に、同市及びその近郊には、30軒を超える美術館や博物館が存在。中でも1661年創立の世界で最も古い公共美術館と言われるバーゼル市立美術館と、スイス随一の集客力を誇るバイエラー財団美術館(1997年設立)は非常に名高い。後者は、敏腕ディーラーとして名をはせたエルンスト・バイエラーとその妻・ヒルディが蒐集(しゅうしゅう)したコレクションを所蔵・展示している。
そのバイエラーが2名のギャラリストと共に、1970年に設立したのが2020年に50周年を迎えたアートバーゼルである。アートフェアの黎明(れいめい)期からその地位を確固たるものとした同フェアが、より大きな飛躍を遂げたのは、1994年リード・パートナーにUBSを迎えた時からといえよう。その後、2002年からはアートバーゼル マイアミ・ビーチ(12月)、そして2013年以降はアートバーゼル香港(3月)を含めた包括的な協賛を継続実施している。UBSはスイスのチューリヒとバーゼルに本拠を置くスイス最大の銀行で、主な事業領域は、投資銀行、証券、そして富裕層向けのウェルス・マネジメントであり、その運用資産は1.7兆スイスフラン(約155兆円)にも上るといわれている。

一方、毎年10月にロンドンで開催されるフリーズ・アートフェアは、2003年にアート専門誌「フリーズ・マガジン」によって初めて開催され、2012年からはフリーズ・ニューヨーク(5月)、2019年にはパラマウント・ピクチャーズ・スタジオでフリーズ・ロサンゼルス(2月)も開かれるようになった。今やその威勢は、アートバーゼルに肩を並べつつあるといっても過言ではないであろう。同フェアのグローバル・リード・パートナーは、フランクフルトに拠点を置くドイツ最大の銀行グループであるドイツ銀行(Deutsche Bank)が務めている。同行は総資産1兆3480億ユーロ(約168兆円)を誇り、1995年以降その事業主軸を商業銀行から投資銀行へと移しつつある。
両行は決してCSR(企業の社会的責任)の観点からのみ、アートフェアを支援しているわけではない。世界中から富裕層が集まるトップレベルのアートフェアは、売買や保険、送金、作品輸送のサポート、更には新規顧客の開拓に至るまで重要なビジネスの場であるといえる。更にUBSは3万5000点超、ドイツ銀行もおよそ5万6000点のアート作品を、コレクションしていることでも知られている。それらは企業としてのブランディングや社員の福利厚生面のみならず、数年前の中国における不動産投資と同レベルのリターンをもたらしているのである。
なおドイツ銀行は、マイナス金利導入による利ざやの急激な減少や高騰する人件費などにより、2015~2017年まで3期連続の最終赤字に陥っている。2018年には、ようやく黒字転換したものの、ライバル行に比べ収益力の見劣りは否めず、他行との統合交渉や大胆なリストラを進めているようである。ドイツ銀行がその経営基盤強化策の一環として、保有するコレクションを売却するようなことがあれば、アート市場に対する影響は計り知れないものとなるだろう。

国策としてのアート・コレクション
こうしたアート作品の力を最大限に利用し、国家の生き残り戦略にいかしているのが欧州の小国・リヒテンシュタイン公国である。小豆島とほぼ同じ国土面積の同国は、侯爵家が経営母体のLGTリヒテンシュタイン銀行による金融業に加え、500年の長きにわたり優れた芸術作品によるコレクション形成をファミリービジネス、ひいては国家事業として連綿と営み続けてきたのである。
その価値は、総額3600億ポンド(約55兆円)と試算される英国王室に次いで、個人コレクションでは世界第2位といわれている。2012年に東京・国立新美術館で開催された「リヒテンシュタイン華麗なる侯爵家の秘宝」展(会期:2012年10月3日~12月23日)で、その一端をご覧になった方も少なからずおられよう。
同国はタックスヘイブン(租税回避地)制をとっているため、プライベートバンキングの秘密口座が富裕層の脱税に悪用されていると、経済協力開発機構や各国から厳しい批判を受けている。以前、ドイツが不正入手した情報を基に、LGTリヒテンシュタイン銀行の預金者を脱税容疑で摘発した際には、報復措置として侯爵家コレクションから、ミュンヘンのノイエ・ピナコテーク(新絵画館)への 160点以上の作品貸し出しを急きょ中止している。大国ドイツを相手に、金融とアートを武器に大立ち回りを演じるしたたかさには驚きを禁じ得ない。

バブル期に日本が犯した過ち
一方、我が国では1990年5月製紙会社の経営者であった斉藤了英が、サザビーズ・ニューヨークのオークションでフィンセント・ファン・ゴッホ(Vincent Willem van Gogh, 1853~1890年)による《医師ガッシェの肖像》(1890年)を8250万ドル(約124億5000万円)で、その2日後にはピエール=オーギュスト・ルノワール(Pierre-Auguste Renoir, 1841~1919年)の《ムーラン・ド・ラ・ギャレット(の舞踏会)》(1876年)を7800万ドル(約119億円)で立て続けに落札した。
この2点は当時の最高落札価格の記録を塗り替えると共に、バブル期におけるジャパン・マネーのすさまじさを世界中に印象づける結果となった。その後バブル崩壊や斉藤の贈賄容疑による逮捕を機に、融資団である邦銀と総合商社の主導で「斉藤王国」は解体される。ゴッホとルノワールの名作は、買値の半分以下と噂(うわさ)される金額で再び海外へと還流。《医師ガッシェの肖像》の行方は、現在に至るまでようとして知れない。
歴史に「たら」と「れば」は禁物であるが、もしも邦銀に欧州のプライベート・バンク並みの見識があれば、今頃は大きな利益、あるいは住友グループによる「安宅コレクション」(国宝2点、重要文化財13点を含む、旧安宅産業株式会社が収集したおよそ1000点に上る東洋陶磁コレクション)救済と同レベルの名誉をもたらしていたことだろう。
また、後にF1「アジアGP」(1993年)開催会場となった日本オートポリスの社長であった鶴巻智徳は、同年ピカソによる「青の時代」を代表する作品《ピエレットの婚礼》(1905年)を、5167万ドル(約75億円)で落札している。同社や鶴巻の資産管理会社が傾くと、作品は建設会社やノンバンクの手を経由し、現在は、ある大手信託銀行の倉庫に存在すると、まことしやかに囁(ささや)かれている。果たして数奇な運命をたどった名品は、数年後アート市場をにぎわすことになるのか。邦銀の真価が、問われることにもなろう。もともとコンディションが良くない作品だけに、適切な環境下で保管されていたのかどうかが非常に気がかりである。
さて、次回以降はアート作品も持つ有形・無形のパワーを、その経営戦略にいかすことで成功を収めている企業の事例を紹介していきたい。
(次回へ続く)



