「世の中は信用していないけど、結局ぼくは人間が好き」──加藤泉がアーティストであり続ける理由
11月24日にオープンしたばかりの麻布台ヒルズの「Gallery & Restaurant 舞台裏」で、加藤泉が日本初披露となるアルミ鋳造の大型作品を展示している。国内外で高い評価を受ける作家に話を聞いた。

開業したばかりの麻布台ヒルズの中で、ひときわ異彩を放っている薄暗い一角がある。「ギャラリー&レストラン舞台裏」と名付けられたその空間に近づくと、中に設置された足場のような檻のようなものの中から、鈍い銀色の光をまとった2.5メートルほどの生物らしきものがぬっと現れる。さらに近づくと、大きな4つの石を積み上げたようなこの生物には、ゴツゴツした表面にフラットな黒い瞳や半開きの口が与えられていて、どうやらヘソらしきものもあることがわかる。ぐるりと観察してみても、石にしては光沢があるなという以外にはやはり石にしか見えない外見に反して、石らしい重量を感じないどころかむしろ妙な浮遊感すらあることに、違和感と好奇心はさらにむくむく膨れだす──。
島根県の出雲文化圏で生まれ育った加藤泉の作品はこれまで、それが絵画であるか立体作品であるかに関わらず、ときにアニミズムと関連づけられながら(本人もそれは過去のインタビューで認めている)「原始的」「有機的」「不気味」「キモカワイイ」などという言葉で表現されてきた。特に立体作品では石や木などの自然のマテリアルを用いることが多く、近年では、それらにプラモデルをくっつけたり、自然石を型取って鋳造するなど、「半自然」な作品にも挑戦している。
今回、「舞台裏」を舞台に発表された作品は、そうした加藤の「現在地」を明らかにするものと言えそうだ。もともとは屋外で設置されることを前提に生み出された本作を日本で初披露する加藤に、様々な質問を通して、「なぜアーティストをやり続けるのか」という根源的な問いを投げかけてみた。
自然物と同じ強度の作品をつくりたい

──まずは今回の作品に使った素材やテーマについてお聞かせください。
この作品は、自然石を型取りした鋳型にアルミを流し込んで鋳造したものです。もともと自分が気に入った石を6つほど型にとってあって、今回はそのうちの4つを使いました。
──自然石をアルミで再現するという発想はどこから生まれたのですか?
石を使った作品は以前からつくっていました。昨年にはワタリウム美術館にて「寄生するプラモデル」と題した展覧会を開いたのですが、それに向けて準備をしていたとき、自分が過去につくった石の作品をプラモデル化しようとひらめいて、実際に制作したんです。そして今回制作した作品は、自然石を使ったものでありながら、鋳造という部分でプラモデルとも繋がりをもっていて、いままでの仕事の流れを汲んだ作品となっています。
自然石はそれぞれが違った形をしていて、同じものはふたつとありません。それを敢えて型にとって量産可能な状態にするというところに美術的な面白さがあると思っています。あと、アルミという素材は自然石に比べて軽いので、今回のように建物内に搬入することもでき、展示の場を選ばなくて済む効果もあるんです。
──すべてが真新しい麻布台ヒルズの中で、この空間だけがとても暗くて不穏な雰囲気です。作品もたった1点しかありません。
今回の話をもらったとき、ピカピカと明るいお店に囲まれるんだろうと想像しました。だったらむしろ、薄暗くて閉塞的な空間にしてしまった方が面白いだろう、と。作品のサイズも、この空間に搬入できるギリギリの高さなので、まるで作品が閉じ込められているようなイメージです。
──サイズ自体にも意味が込められていると。
絵画にしても立体作品にしても、大型の作品を作るにあたって、もともと小さいサイズのものをただ拡大しても全然ダメなんです。例えば写真であれば、小さい写真を拡大すると粒子が粗くなって新たな面白さが付加されることがありますが、絵画においてはそういった現象は起きないわけです。粒度も変わらないし、ただ間伸びした退屈な作品が生まれるだけ。そういう意味で、作品のサイズはぼくの仕事において非常に重要で、大きさには必ず意味があります。

──今回の作品ではないですが、加藤さんの「ヒトガタ」の作品では、ジェンダーを示す記号が描かれます。制作のどの時点でジェンダーを決定しているんでしょうか?
確かにぼくがヒトガタの作品で描くのは、大人の女/男、あるいは子どものどれかに振り分けられます。それは、性別があることで「なんでおっぱいがついているんだろう?」といった具合に、受け手が思考するきっかけや要素を与えることができるから。ただし、そこに例えば服などを描きこんでしまうと具体的になりすぎて、解釈の余地がなくなってしまう。だから、受け手に自由に考えてもらうためには、シンプルなかたちのなかになるべく複雑な情報を入れる必要がある。ジェンダーはそのための要素のひとつです。優れた美術作品というのは、受け手の自由な思考を促すものだと思っているので。
加えて、男女あるいは子どもを使い分けることで、同じテーマでも3パターンの作品をつくることができます(笑)。
──確かに3倍つくれますね(笑)。「複雑な情報を入れる」とはいえ、加藤さんの作品を読み解く記号的なものとしては、ほかにあまり手がかりはありません。以前、作品に「物語」を与えることはないとおっしゃっていましたが、制作の過程においても全く想定されていないんでしょうか。
ないですね。制作の過程においては素材とやりとりをしているだけで、そこに様々な形や色、線が加わることで作品が出来上がっていく。優れた美術作品とは、鑑賞者に何かしらの思考を促すものだと思うんです。そのために、どうしたら情報をより複雑にできるか、ということをいつも考えています。情報量という観点で、自然物と同じくらいの、あるいはそれを超えるくらいの強度をもったものをつくりたい。今回、自然石を使った理由もそこにあって、石がそもそも備えている複雑な情報を引き継ぎながら、新しい作品に仕上げることを目指しました。
──作品に登場する生物の表情についてはどうでしょう? 加藤さんの作品に登場する生物は総じてあまりに呑気な顔をしているので、たまにイラっとさせられることがあります(笑)。
そう思わせることができたなら、ぼくの勝ちですね(笑)! 作品の解釈は観る人によって変わって当然なので、きれいだと思う人もいれば汚いものだと感じる人もいる。受け手に何らかの思考や感情を喚起させられた時点で、アーティストの勝ちじゃないですかね。
自分にしかつくれないものを、常につくりつづける

──約30年のキャリアにおいて、アーティストとしての在り方に変化はありましたか?
自分なりの美術のやり方に向き合って練習してきたおかげで、その積み重ねが徐々に実ってきたという実感はあります。とにかく練習をやめないことがすごく大事で、今では刀を持った刺客に襲い掛かられたとしても、うまく身を躱して斬り返すことができるようになった。そうやって技術が身につくと、今度はやりたいことやできることが増えてきて、すごく忙しくなりました(笑)。
──ということは、苦しい戦いをしていた時期もあるということですね。
ペインターの多くが30代でスランプに陥っているんですが、ぼくも例外ではありませんでした。当時は出口のないトンネルをひたすら走っているような感覚があって、とても辛かった。でも、あるとき突然、そのスランプを抜け出すことができたんです。まるで大空に解き放たれたような、どんな方向へも自由に動けるような感覚で。そもそも自分は攻撃型のアーティストだと思っていますが、以来、どんな敵が来てもなんか大丈夫な気がするというか、落ち着いて対峙できるようになったと思います。
──キャリアを重ねるなかで特に意識してきたことはありますか?
言葉にすると陳腐に聞こえてしまいますが、オリジナルな作品をつくることですかね。先ほども言ったように、アートの目的は観る人に何かを考えさせることですが、これを実現する方法はアーティストの数だけ存在していて、先人の真似をしてもまったく意味がない。ぼくが絵を描くときに筆を使わないのも、ぼくよりも上手く筆で描ける人がいるから。ほかの人がやっても同じだと思うものには手を出さない、このジャッジを下すことがとても重要だと思っています。

──オリジナルであるというのは、相対的なものでもあると思います。その上で、美術史を参照することは重要なのかと思いますが、いかがですか?
美術史を含め、大きな意味での歴史にはあまり興味がないんです。改ざんもあるだろうし、結局は「勝者の歴史」だと思っているから。一方で、自分のなかで積み上げていくもの、という意味での歴史はとても重要視しています。アートといっても、ただアイデアを羅列していくだけでは意味がない。自分のなかで「これでやっていく」という覚悟があり、そこに向かっていく練習の過程があってはじめて意味が生まれると思っています。少しでも練習しない期間があると、それまでの歴史も崩れてしまうし、そういう意味でアーティストはアスリートにも似た存在なんです。
──そんなアーティストとしての歴史を積み重ねていく中で、加藤さんがこれまでで一番励みになった批評はなんですか?
二つあります! 一つは2007年の第52回ヴェネチア・ビエンナーレのときです。スタジオで作業しているところに、その年の芸術監督であり当時MoMAのキュレーターだったロバート・ストーが出品候補探しで訪問してくれて、まだ制作途中だったぼくの絵を指して「これを出してくれ」と言ってきたんです。完成した作品でもないのに? と聞くと、「だって、いままでの作品はもう知っているから」と。当時はわからなかったんですが、最近になってこの言葉が身に染みるようになってきました。結局のところ、いまの作品がいちばん大事なんです。過去の作品の価値や、これから活動を続けていく意義も、いまの作品がどう評価されるかによってすべて変わってくる。だからこそ、新しい作品をつくり続けることが大切なんだなと思います。
もう一つは、パリのギャラリーでのオープニングで、おそらく有名なアートコレクターのおじいさんに、「東洋でも西洋でもない、あなたの絵だね」と言ってもらったこと。とてもシンプルな言葉ですが、ほかの誰でもないぼくだけの絵だと認めてもらえたことがすごく嬉しかったですね。
世界がどうなっても、アーティストとして生きていく
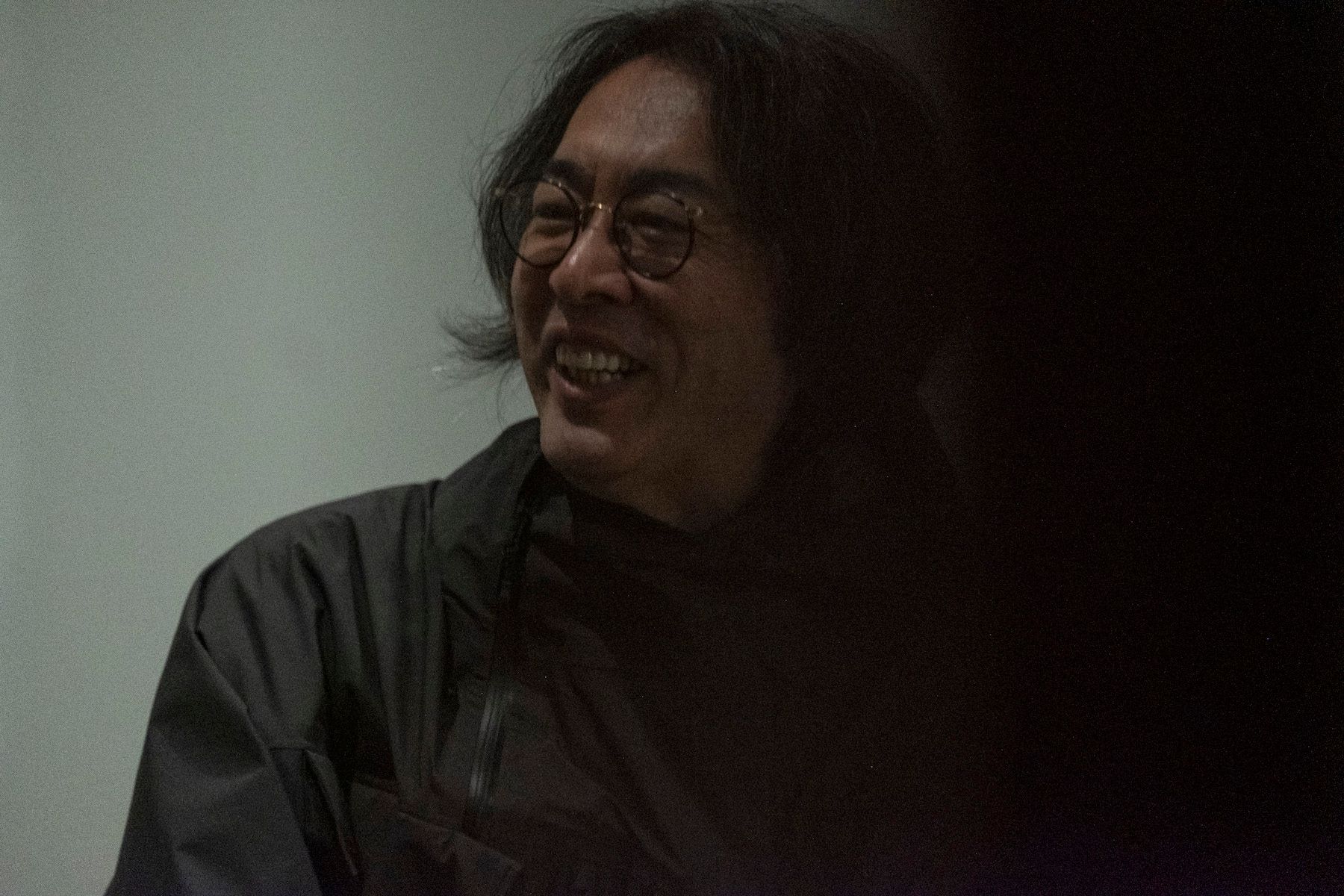
──加藤さんは折に触れて、「日本は後れている」とおっしゃっています。その真意をうかがいたいのですが。
日本が「後れている」と感じるのは、アート業界に限った話ではありません。後れているというのは、例えば欧米のあり方が「最先端」で「正しい」という意味ではなく、日本には、今の世界が永遠に続くと信じて疑わない人が多いという意味です。若い日本のアーティストたちを見ていると、外に出ようとせず、小さなコミュニティを形成して、その中で生きることに心地よさを感じている人が多いように思います。時間を止めたいのかもしれませんが、世界がこれだけ動いているのに自分たちの時間を止めてしまったら、後れを取るのは当然です。
ぼくはアート業界しか知らないけど、それでも国外で仕事をしていると、世界が変動していることをひしひしと感じます。実際に世界では戦争が起きていて、どんどん「動いている」し「変わっている」。それなのに、日本ではあまりに多くの人が、日本における今の状況がずっと続くと思っている。そんなわけないのに。
──その「変動する世界」の流れに対して、加藤さんはどんなふうに身を置いているのでしょうか。
その流れに乗っている感じですかね。流されているのとは違って、流れに乗りながらも自分のやることをやっている感覚です。結局、アートをやるってことは、世の中を信じない、ということだと思ってて。つまり、外では戦争をやっていて自分も巻き込まれているのに、どうしても何かをつくりたくて飯盒の内側に絵を描いてしまう、そんな行為こそがアートだと思うんです。世界がどうなろうと自分はアートをやって生きていく。この覚悟があってこそのアーティストだし、アートは「なんかいい感じに生きていく」手段なんかじゃない。もうそれしかできない、やらざるを得ないんだ、というわけでもないなら、敢えてアートをやらなくてもいいじゃないかと思ってしまう。
──世界の流れのなかでアートに向き合うことが大切だと。
資本主義とか社会主義とか、人間がつくったシステムを評価するのってとても難しいじゃないですか。どの宗教が正しくてどれが間違っているとか、どの正義に最も普遍性があるのかとか、そんなことはわからないし、何を信じればよいのかわからなくなることがあります。だからこそ批評が大事だし、アートを含む文化というのは、そうした批評の役割を担っていると思っています。社会のいろんな場所にアートがあった方がいいというのは、そういう意味であり、文化をつくる人がいなければ、人間はいとも簡単に、自らを滅亡させてしまうでしょうから。
──加藤さんご自身も、そうした使命感がありますか?
ぼくは世界を信じてはいないし、ひとりでいるのが好きだけれど、それは人間のことを意識しているからで、結局は人との繋がりを必要としている。根っこでは人間のことが好きなんですね。ひとりでスタジオに籠って、ひとりで釣りに行って……そんな生活に終始していたら、よい作品はつくれない。
だからやっぱり、ぼくも人類の役に立ちたくてアートをやっているんだと思います。今回のような商業施設を含め、いろんなところにアートを設置することで、ひとりでも多くの人に世界について考えてもらいたい。アートは必ずしも世の中の全員が必要としているものではないし、進んで美術館に行く習慣がない人でも、なんとなく立ち寄った場所でアートに触れることで、世界について新たな視点をもつかもしれない。人生が変わるような気づきを得るかもしれない。アートがそういうキッカケになってほしいというのがぼくの想いです。

加藤泉|IZUMI KATO
1969年島根県⽣まれ。1992年、武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業。卒業後の90年代末より画家としてのキャリアを本格始動し、2000年代以降は絵画作品に加え、木や石、布、ソフトビニール、プラモデルなど多様な素材を用いながら創作の幅を広げている。東京・香港を拠点に世界各地で作品を発表。
https://izumikato.com/
Photos: Tohru Yuasa Interview & Edit: Maya Nago Text: ARTnews JAPAN


