生きている土を使って「仲間」を作っているのかもしれません──やまわきてるりと土との対話
いま日本では、伝統工芸と現代アートをつなぐ試みが各所で行われている。11月2日から5日に京都で開催される「日本の美術工芸を世界へ 特別展『工芸的美しさの行方―うつわ・包み・装飾』」もその一つ。本展の参加アーティストであり、土の「柔らかさ」をユーモラスな造形に表現するやまわきてるりに話を聞いた。

土の妖精なのか、未来から来た土偶なのか──おおらかな空気を纏ったやまわきてるりの作品に出会うというのは、「未知なる生命体」に出くわしてしまったような体験に似ている。でも、恐れる必要はない。多くの場合つぶらな目が与えられたそれらは、あざとい愛嬌を振り撒いているわけでも、庇護を求める視線を送ってくるわけでも、あるいは近づいた途端に牙を剥いてくるわけでもなく、ただそこにいる。言葉を交わさずとも不思議な安心感を与えてくれる古い友人のように。
この謎の生命体の生みの親であるやまわきが現在制作を行うのは、金沢の山間にある施設、金沢卯辰山工芸工房だ。ここは「金沢の優れた伝統工芸の継承発展と文化振興を図るための工芸の総合機関」として1989年に設立された若手育成のための研修施設であり、陶芸、漆芸、染め、金工、ガラスに対応した充実の設備を擁している。現在は、審査に通った約25人ほどがここで技術と表現を磨いており、現在35歳のやまわきは、インドネシアの芸術大学や笠間陶芸大学校を経て3年前からこの施設で制作に励んでいる。
彼女の制作現場に立ち会ってまず驚いたのが、伸ばした土を大胆かつラフにスリップ状に手でちぎっていく潔さだ。そんな雑にちぎって大丈夫?というこちらの余計な心配をよそに「断面がラフな方が、土の柔らかさが伝わる気がして」と笑う様子から、彼女が土との対話を心から楽しんでいることが伝わってくる。
「ちょうど自分の人生のフェーズとも重なるからか、最近、ものを作るって出産や子育ての経験に近いのかなと想像することがあります。最終的には、自分の手を離れるじゃないですか。作品が売れることは生きていくために必要だから喜ばしいことだけれど、別れるのは寂しい。大事にしてもらってね、と送り出します」
この研修施設での最後の年を過ごす彼女に、現在までの道のりやこれからのことなど話を聞いた。

──やまわきさんが陶芸をはじめてから、まだ5年だと聞いて驚きました。土との出会いを教えてください。
そもそもバティックなどの染め物に興味があり、1年半の語学留学ののち、奨学金を得てインドネシア国立ジョグジャカルタ芸術大学工芸学科で1年を過ごしましたが、あまりしっくり来ませんでした。その後ワーキングホリデーでポルトガルに滞在した際に、ギャラリーと間違えて偶然入った陶芸スタジオのオーナーの方から「明日から来なさい」と誘われ、導かれるままに初めて土と向き合いました。驚いたのは、土って布みたいに扱えるんだ、ということ。言語もわからず見よう見まねでしたが、今まで取り組んだことのある素材の中で、土が一番体に合っていると感じました。
──体に合っている、というのは?
土というのは、中にいる微生物が元気じゃないと粘りが出ないんです。例えば私は、自分の体調がホルモンに左右されているなと感じることがあるのですが、それと同様に、土のコンディションも微生物に左右されている。触っていると、今日はちょっと調子悪いな、と分かったりして、「ああ、土も同じ生き物同士なんだ」と実感します。加えて、様々な工芸の中でも直接素材にこれほどまでに触れるのって、土くらいだと思います。ガラスは直に触って成形できないし、金属も工具が必要ですが、土は直接手で作ることができます。陶芸は、そんな土の「柔らかさ」やその痕跡を留めて表現できる。それが私に合っていたんだと思います。

──作業を少し拝見した限り、あまりに自由にスピーディーにちぎったり積んだりしていて驚きました。
基本的には縄文土器と同じような技法を用いています。ぐにゃぐにゃして見えるかもしれませんが、一応、規則性はあります。でも、整えすぎない方が土の柔らかさを生かせますし、柔らかいからこそ大きな作品になると輪郭が次第に揺らいできて、自分の意図を超えた造形が立ち現れたりするのが面白い。水さえあれば土は本人たちが勝手にくっついてくれるので、とてもシンプルな素材でもあります。大型の作品になるともっと焼成の経験値が必要なので、それを今、色々と実践しているところです。
──ポルトガルから帰国後、笠間陶芸大学校で正式に陶芸を学んでいます。
ポルトガルの陶芸スタジオで、なぜ陶芸の源流でもある日本で勉強しないの? と聞かれたんです。確かにその通りですし、同時に、私はいつも世界に興味があるので、陶芸であれば世界中にあるから様々な機会や人と出会えるということも、背中を押してくれました。陶芸を通じて、いろんな場所で異なる背景の人たちと交流していけたらいいな、と。

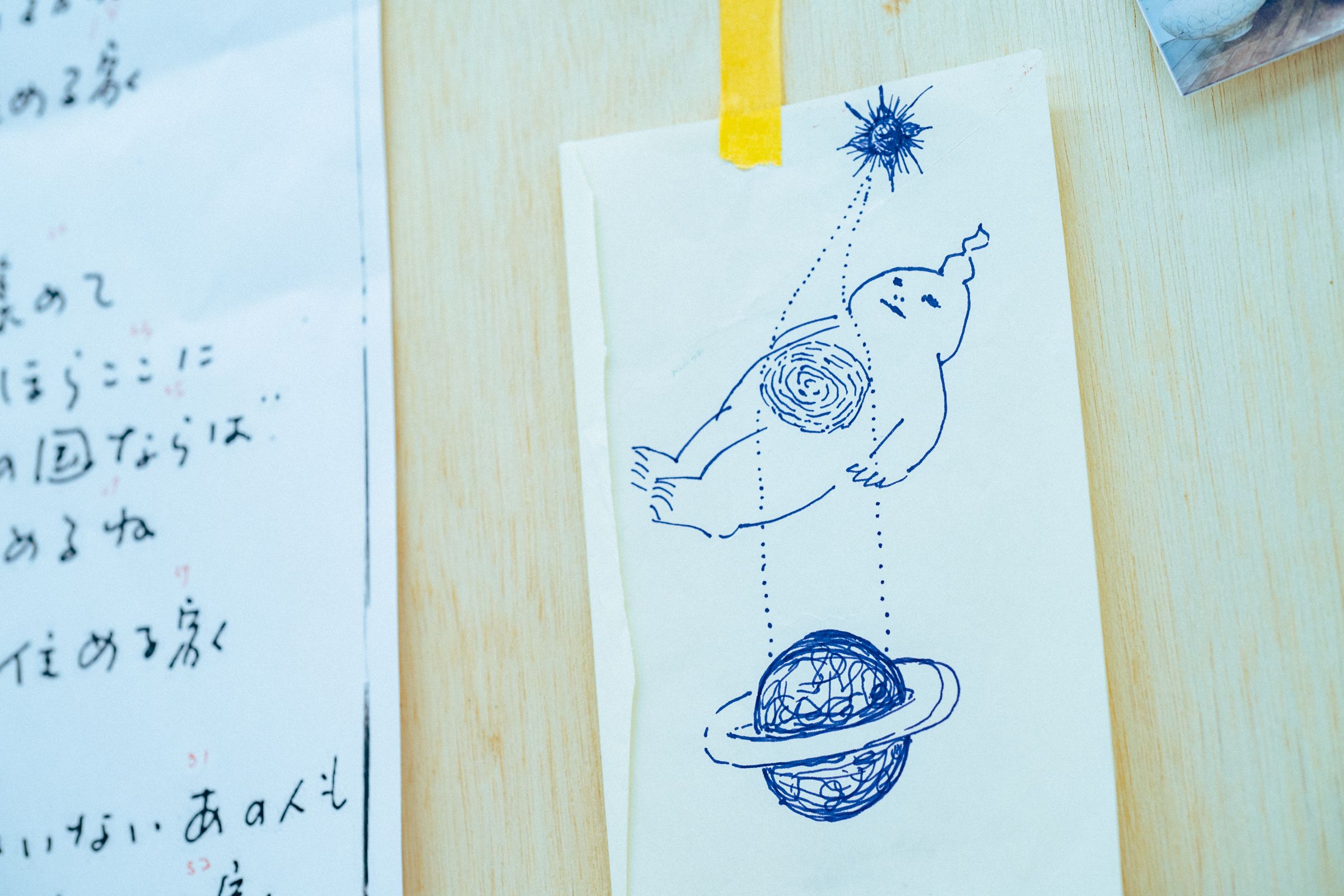
──器が原型であることを示唆する造形であるものもありますが、やまわきさんの作品は土偶や埴輪のようにも見えます。一体何を作っているのでしょう?
私の作品は目がついてる生き物のようなかたちが多いのですが、強いていうなら「仲間」を作っているのかもしれません。作品を制作しながら、その時考えていることや自分の気持ちを消化している感覚もあります。インドネシアやポルトガルで過ごしたときに、信仰が人々の拠り所になっていることを実感しました。それが人の強さや優しさにつながっていると感じたんです。でも、私を含めて日本人は信仰心が希薄になりつつあるように感じています。それが自分の弱さや孤独感の原因なんじゃないかと思ったことが、仲間を作るきっかけだったのかもしれません。私の作品は、たましいの容れ物としての「からだ」のような存在。窯から出すと、あ、生まれたって思うんです。
──あえてラフな表面や完璧ではないかたちにこだわるのはなぜですか?
もともと、洗練されていない土着的なものが好きなんです。あとは前述の通り、土の柔らかさを表現に留め置くために今のテクスチャーに行き着きました。子どもの落書きをそのまま具現化したような、作為を感じさせない構造を追求してきたのは、私の作品が「彫刻」になることを避けたかったから。実家は画材屋を営んでいたとはいえ、アートと近い場所にいたわけでも、もともとアーティストになりたいと考えていたわけでもなかったんです。でも、最近は少しその考えも変わってきて、「あれ、これはやはり彫刻と呼べるんじゃないか」と思うことが増えてきました。


──インスピレーションは?
自然の中で過ごすのが好きなので、山登りしたりサーフィンしたり、作品のインスピレーション探しを言い訳に、しょっちゅう自然を旅しています。でも実際に、自分の体験から得た感動や感情なしに制作することは私にはできません。だから私の場合は、工房にこもって自分の表現をひたむきに磨くこと以上に、人生体験を大切にしなければと思っています。
今の世の中には技術もアイデアも溢れていて、誰もまだ見たことのない完全に新しいものをゼロから作ることなんて可能なのか、という時代において、では自分と他者を分つものってなんだろうと考えると、やはり私だけの経験なんだと思うんです。作品を制作する過程で、あれ、これってあのアニメのキャラクターに似てない? と自分でも思うことがありますが、かつて大好きだったものや自分を形成してきた経験が作品に滲み出ていくのは自然なこと。自分が実際に考えたこと、体験したこと、苦しかったこと。そういうことの積み重ねでしか自分らしさは獲得できないのではないかと思いますし、それが私を制作に突き動かしている原動力だと思います。
──今後、ご自身の作風がどんなふうに発展していくと思いますか?
これまでも、実際にものを作る中で新しいアイデアやアプローチ、材料に挑戦するなど、自然に発展してきた感があります。決まったことを繰り返し続けるのは単なる「作業」になってしまって飽きがちですが、陶芸は奥が深いので、研究する楽しさが今もずっと続いています。
今後、挑戦してみたいのは、実際にオーディエンスが抱きしめたり乗ったりできる作品でしょうか。作品を通じて人との関係性を構築していくのが好きなので、ただ鑑賞するだけではなく身体的に触れ合えるような作品を作ってみたいです。野外彫刻のような。それを土だけで実現するのは難しいかもしれませんが、そのときは他のメディウムに挑戦するいい機会になるかもしれません。
Photos: Kaori Nishida Text & Edit: Maya Nago


