アーティストたちの言葉で振り返るTokyo Gendai──トークセッション「Art Talks」より
アーティストたちは、作品を通してどのようなメッセージを伝えたいのか。先日開催されたTokyo Gendaiのトークセッション「Art Talks」で語られた、アーティストたちの言葉を中心にご紹介したい。彼らの言葉は、私たちの日々の暮らしに対して新たな視点を与えてくれるかもしれない。

「都市の美しさの陰にいる労働者たちの存在に気付いてほしい」

韓国国立現代美術館キュレーターのスージュン・イと、タイ生まれのアーティスト、サリーナ・サッタポン、モデレーターとしてARTnews JAPAN 編集長の名古摩耶が登壇した。スージュン・イは、Tokyo Gendai「Tsubomi ’Flower Bud’」のキュレーションを担当。国籍や世代、文化的アイデンティティが異なる女性アーティスト4名にスポットライトを当てる展示を行った。サリーナ・サッタポンはその展示作家の1人。
サッタポンはタイ北東部の少数民族出身のアーティスト。現在は東京藝術大学でグローバルアートプラクティスの博士課程で学びながら制作活動を行っている。「Tsubomi ’Flower Bud’」には、工事現場で用いられる鉄パイプの資材で組んだ足場にたくさんの大きなプラスチックバッグを吊り下げた《Balen(ciaga) I belong》を出品した。数年前、ラグジュアリーブランドのバレンシアガがこのバッグを模した高級版を発売してトレンドとなったが、そもそもは非常に安価で、サッタポンの出身地タイだけでなく様々な国の労働者階級の人々にとって、商用あるいは日常生活の「マストハブ」だ。

名古が、鉄パイプの足場にプラスチックバッグを吊り下げた意味について問うと、サッタポンは「鉄パイプの足場とこのバッグは労働者階級を表しています。人々は美しいビルが建ち並ぶ都市の輝きにばかり目が行きがちですが、それを作ったり、維持したりする労働者たちの存在に気が付いてほしかったのです」と話した。
またサッタポンは、同フェアのSAC Galleryでも作品を展示していた。こちらは4点の真っ白なスクリーンが壁に据えられており、スクリーンの前に取り付けられた高さがさまざまな特殊なプラスチックパネルを通して見ると、スクリーンには人々の暮らしの一場面が映っているというもの。この作品についてスージュン・イは「自ら移動したり、腰をかがめなければパネルを通して映像を見られない。他の人の暮らしは、そのような努力をしないと知ることが出来ないということだと思った」と感想を語った。サッタポンは、「社会問題は見えないもの。アートはそれを見えるようにするためのツールなのです」と答えた。
「思い切って壊してみると、面白い世界が広がる」
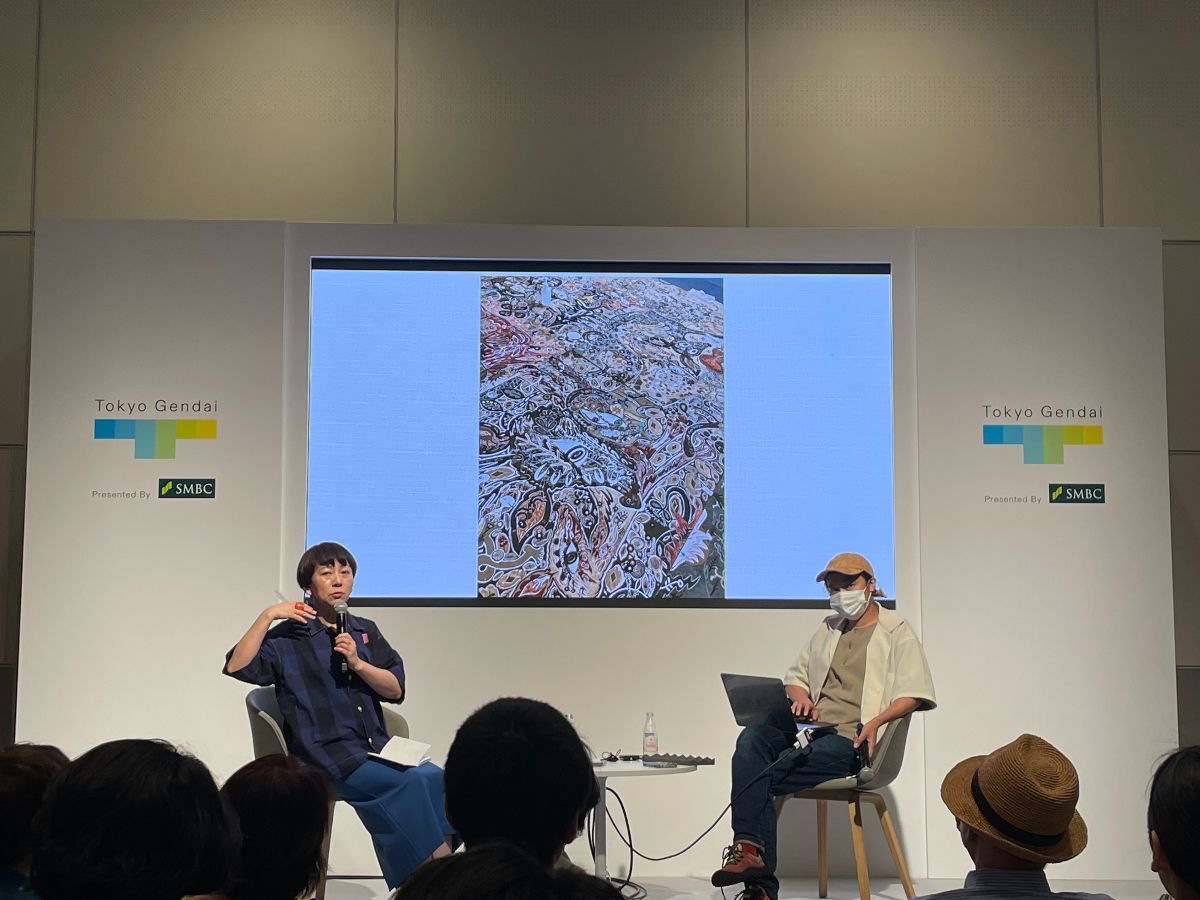
土、水、埃、小麦粉、テープ、ペンなど身近な素材を用いて絵画を制作する淺井裕介と、横浜美術館館長・横浜トリエンナーレ組織委員会総合ディレクター蔵屋美香が登壇。このほど横浜美術館が収蔵した大作《八百万の森へ》の話題になった。同作は横浜信用金庫からの寄付金を財源に制作され、画材である土も、同信用金庫の支店の人々の協力のもと横浜各地から集めた。また、「その土地で出会った人たちに手を入れてもらっている」という淺井の作品制作には、蔵屋をはじめ多くの横浜の人たちが協力したことを紹介した。
作品制作について淺井は、モチーフを「押し合いへし合い」するような形で描いていくと語った。だが、完成間近に「絵が壊れる」瞬間が訪れることがあるという。その時には、たとえ地元の人たちが描いてくれたモチーフだとしても、一度消して描き直す。そのことで「面白い世界が生まれる」のだという。

蔵屋は、淺井の作品は無数の動植物が入り組んでいるが、知覚現象で視野の中にふたつの対象が存在するとき、ひとつは形として目に映り、もうひとつはその背景を形成しているように捉えられる「図と地」がはっきりしていると評した。これは意図したことなのかと問うと、淺井は「観客の視点を捕らえる役割の動物の目から描き始めます。皆さんが絵を見る時に、絵の中の動物もまたこちらを見ているぞ、というふうにしたくて」と明かした。
淺井は近年、土そのものの美しさに着目し、抽象画にも挑戦している。今年の7月にはインドのラダックという高地で地上絵を制作予定だ。これは20歳からの夢だった。「地上絵は、地上に立つ人間の目線からみると溝。でも、僕には描いているという手ごたえを一番感じるものなのかもしれないと考えています」とコメントした。
「トライ&エラーを繰り返す、そのフェーズがとても楽しい」

ミュージシャン「アルヴァ・ノト」としても知られるドイツのアーティスト、カールステン・ニコライとライゾマティクス代表の真鍋大度、モデレーターとしてキュレーター、展示プロデューサーの内田まほろが登壇した。ニコライと真鍋は、真鍋が2008年に発表した「顔に電気信号を流して表情を動かす動画」を見たニコライがコラボレートを申し込んだ時からの縁だ。ニコライは当時を「大度のプロジェクトは顔がかなり痛かった」と振り返りつつも、「5年後に子どもたちが似たような技術のアプリを見せてくれた。大度は先を行っていた」と評価した。
内田が、ニコライにアーティストになったきっかけを聞くと、「私が若かった頃はサウンドをビジュアル化するという概念はありませんでした。1990年にドイツが統合され、私が通っていた東ドイツの大学には一斉にコンピューターがやってきました。そんなある日、読んだ本の中に人間が聞こえる音の周波数は20万ヘルツだという記述があった。私はもっと高い周波数の音が聞こえるはずだし、そうでなくても感じることはできると思いました。自分の耳を使いながらオシロスコープを使って波形を見て、コンピューターを使って編集することで幅広い周波数の音を可視化することが出来たのです」と明かした。

音を可視化する作品のパイオニアのニコライに対して後続世代である真鍋は、「先人たちがやってきたことを尊敬しつつ、僕は同じことは出来ないので違うことを探さないとならないというのはあります。ですのでトライ&エラーを繰り返すのですが、そのフェーズがとても楽しい」と話し、ニコライは「私たちは科学者でなく、大学の研究にあてはまらないものを探求しています。そのプロセスはとても自由で面白いものです」と同意した。
ニコライは2023年に死去した坂本龍一と20年間にわたり、9枚のアルバムを共に制作した。その共同作業について、「彼との20年は振り返るととても短く感じるが、生産的だった。私は作品を文書化するのは得意ではないのだが、運の良いことに、龍一のおかげでこれらの仕事のアーカイブを持つことが出来ました。彼は多忙にもかかわらず、興味のあるミュージシャンには自らEメールでリミックスの依頼をしていました。龍一は常にアクティブなリスナーで、好奇心にあふれ、オープンマインドな人物でした」と振り返った。
「最後には自分自身と闘わなければならない」

金沢21世紀美術館館長の長谷川祐子と、現在は東京と上海を拠点に活動するアーティスト、ルー・ヤンが登壇した。ルーは、2017年に発表した、自身の姿をスキャンして生まれたアバターに、脳に繰り返し電気刺激を与えることで、脳の働きを正常化するTMS治療器を付けた《Delusional Mandala by LuYang》など、科学、宗教、医学、ゲームやポップカルチャーといった幅広い分野から着想を得た映像やアニメーション作品を発表している。
ルーが2020年に制作した《The Great Adventure of Material World》は、コンピューターゲームだ。ゲームは全部で9レベルあり、プレイヤーはこれまでのルーが発表してきたキャラクターと戦いながら強固な武器を探していく。だが最後の敵はもう一人のプレイヤー、つまり自分だ。これは、ルーの「全てを破壊することは出来ない。最後は自分自身と闘わなければならない」という思いが込められているという。
DOKU Hello World from LuYang on Vimeo.
長谷川が、ルーが影響を受けた日本のアニメを聞くと『GANTZ 』(原作・奥浩哉)の名が挙がった。2019年に発表した、自らを3Dスキャンしたアバターを「器」とし、バリ島のダンサーなど、様々な人の動きを受容してきた《Doku / 独生独死》にも多大な影響が与えられているという。また、「正義の味方として描かれないブラックヒーローにも興味があります、それは、考え方が違うというだけで、絶対的な正義は存在しないと考えているからです」と話した。ルーは初期から、自らの身体を作品に使用し続けてきた。その理由については、「私の作品は死んで地獄の炎に焼かれるなど、タブーと呼ばれるものに触れる作品もある。そういった時に自分の身体を使うのが一番便利だったからです」と話した。
また、長谷川は、このセッションの前にルーがお寺で説法を受けたことを明かし「ルー自身も仏教のお坊さんのような感じがする」と話した。ルーはうなずきつつ、「私は現代美術のことはよく分かりません。仏教哲学に興味があり、修行をやっているような感覚があります」と答えた。


