世界のトップコレクターに聞く「不確実な時代のアート収集」──市場の問題やコレクターの役割
毎年恒例のUS版ARTnews「TOP 200 COLLECORS」。今年はアート市場の低迷と、その構造的な問題に関するさまざまな議論が交わされる中での発表となったが、トップコレクターたちはこうした状況をどう捉えているのだろうか。US版編集部が投げかけた3つの問いに対する回答をまとめた。

アート市場が揺らいでいる。しかしこの表現は、あまりに控えめすぎるかもしれない。今年の春、あるディーラーは私にきっぱりとこう言った。「いまの市場はクソですよ。違うという人がいたら、その人は嘘をついているんです」。ディーラーやアドバイザーは誰もが同じ考えのようで、中には大統領選の年であることが1つの要因だという声もあった。
夏にあちこちで話題になったのが、アートアドバイザーのジェイコブ・キングによる短いレポートだ。彼は今の市況を見て、「投資マインドセット」(美術品を購入する際の判断基準が「値上がりする可能性はどの程度か」という1点にのみ集約されること)が暴走していると指摘。これ自体は特に新しいことでも、アート市場に限ったことでもないとしつつ、今やアートの買い手たちの間でこうした投機的な考え方が「ごく普通の態度」になっているとキングは主張する。つまり、それについて話すことがもはやタブーではなく、下品なことだとも思われなくなっているというのだ。
不確実な時代におけるアート収集にとって、これはいったい何を意味するのだろうか? 購入される作品の数は減少しているかもしれないが、トップクラスのコレクターたちはこの1年もアートを手に入れ続けている。そして、US版ARTnewsの「TOP 200 COLLECTORS」に加えるに値するコレクターは、まだまだ大勢いる。2024年版のリスト作成にあたり、編集部は取材と調査を重ね、新たに数十名の候補を選んだ。今の市況を考えれば予想外に多い人数だ。年一度のリスト改訂は今年で35回目になるが、今回も年ごとの変化をよく反映した結果になった。
では、TOP 200 COLLECTORSは今の市場をどう見ているのか。我われは大きく3つの質問を投げかけた。それに対する個々の回答は以下で見ていただくとして、一部をかいつまんで紹介しよう。
ホイットニー美術館の理事会でバイスプレジデントを務めるミヨン・リーは、アート市場をオランダ黄金時代に起きた「チューリップ・バブル」に比えている。エイミー&ジョン・フェラン夫妻は、相場サイクルが見られるどんな市場も「投機を呼ぶ」と指摘。インフレ前に金利が低く抑えられていたことも1つの要因だったとし、「市場が調整し、投機筋が退場するのは、市場が健全性を取り戻す良い兆候」だと付け加えた。アニタ・ブランチャードとマーティン・ネスビットは、もっと単刀直入にこう述べている。「残念ながら、ギャラリーはアーティストの育成より儲けを重視してしまうことがあり、結果的にそれが若手作家のキャリアを傷つけることになります」
コンセプチュアル・アートのコレクションで知られるペドロ・バルボサや、オールドマスターと19世紀初頭の作品を中心に収集しているジョン・ランドーのように、必ずしも市場で注目されるとは言えない分野の収集家は、自分たちのようなコレクターは投資へのリターンを期待しているわけではないと語る。「そうした作品を心から好きで、そこから刺激を受け、それとともに生きていきたいという強い気持ちがないとできないことです。作品の中には、最終的に支払った金額以上に値上がりするものもあれば、同程度で推移するものもあり、値下がりするものもありますから」
世界的なアートフェアや、大手ギャラリーの展覧会、大規模オークションが再開される秋以降、市場がどう動くかは依然不透明だ。しかし、真摯なコレクターの多くは、市況に関係なくアートの収集を続けるだろう。そうした姿勢を象徴するのがロンティ・エバースの言葉だ。「いずれにせよ、名高いコレクションの多くは市場が弱い時期に築かれました。偉大なコレクションはそれ自体がコレクターのお手本となり、コレクターを鼓舞するのです」
US版ARTnews編集部からの質問と各コレクターの回答は以下の通り。
Q1. 近年、投機的な買い手が美術品収集のイメージを悪くしたと感じますか?
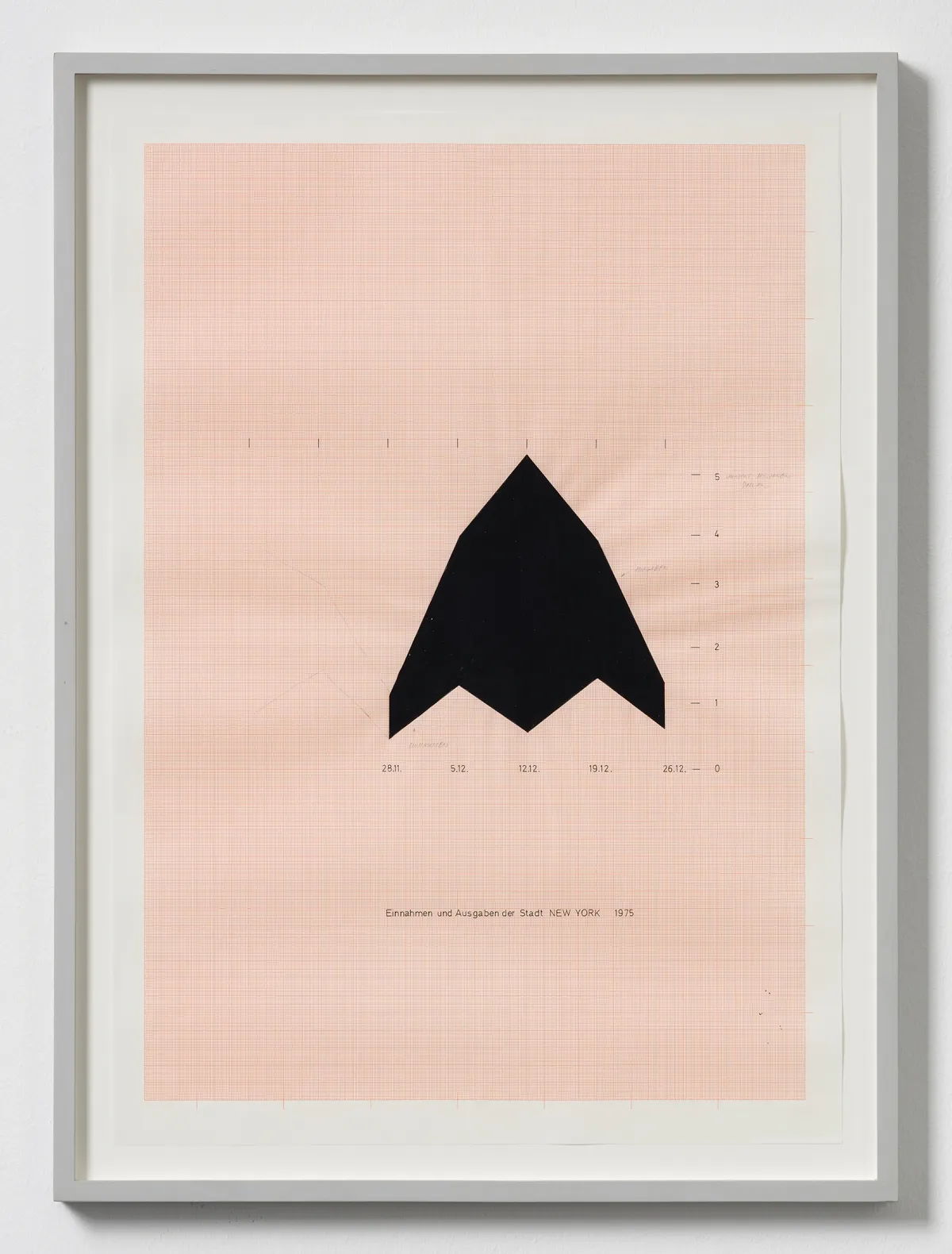
ペドロ・バルボサ:コンセプチュアル・アートのコレクターにとって、アートは資産ではありません。そのため、この分野には投機筋もいません。また、コンセプチュアル・アートのコレクターの間では、若手、古株を問わず、対話が非常にうまくいっています。私たちは皆、アイデアや意見を交換することに熱心です。
アニタ・ブランチャード、マーティン・ネスビット:アートコミュニティからすぐに去っていくコレクターもいますが、私たちは自分たちのことを、第一に文化の支援者かつパトロンであり、第二にアートコレクターであると考えています。真のコレクターは文化の発展に寄与したいと願うもので、常にアート界の一員であり続けます。金銭的な投機などの動機がある人たちは、自分たちの都合がいいときだけアートシーンに入ってきて、用が済めば出ていくでしょう。
アート市場に投機家が入ってくる唯一の難点は、長期的なアート支援に関心のある人々が作品に手が届きにくくなることだと思います。セカンダリー市場で大きなリターンを得ることが目的の投機家がアート市場に入ってきて大金を使えば、新しいコレクターの購買活動が妨げられてしまう。あまりに作品が手に入りづらくなれば、その意欲は削がれてしまいます。残念ながら、ギャラリーはアーティストの育成より儲けを重視してしまうことがあり、結果的にそれが若手作家のキャリアを傷つけることになります。
エストレリータ&ダニエル・ブロツキー:ラテンアメリカのような地域、特にギャラリーや美術館の少ない国では、コレクターがアーティストのキャリアを支える上で重要な役割を果たしています。少なくともラテンアメリカ諸国に関しては、アート収集を投資と見る傾向はアメリカほど強くないと思います。むしろ、私が知っているコレクターの大半はとても寛大で、展覧会や奨学金などに資金を提供して自国以外のアーティストも支援しています。たとえ流行から外れていて、市場で注目されていなくても、自分がいいと思うアーティストを応援するのです。
投資目的のコレクターとは違い、私たちは単に作品を入手して大切に管理するだけでなく、アーティストや彼らが拠って立つ多様な文化に対して責任を持たなければならないと思っています。コレクターは、自分が所有する作品についてリサーチし、知識を深め、アーティストのキャリアを支援し、彼らが活躍できる豊かなアートのエコシステム作りに貢献することが重要だと思います。美術館の展覧会に作品を貸し出したり、この分野の研究を支援したりすることで、人々がこれまで馴染みのなかったアーティストの作品に親しめるよう、新しく知的な方法で議論の枠組みを広げることが私の喜びなのです。

ジェームス・キース・“JK“・ブラウン&エリック・ディーフェンバック:投機的な買い手たちによって、優れたアーティストの作品が手に入りにくくなったり、質が疑わしい作品の価格が異常に押し上げられたりすることがあります。経験豊富なコレクターは、良い作品とそうでない作品の両方を見抜くのを助けてくれ、それ以外にも有益なアドバイスをしてくれます。私たちも、収集を始めた頃にベテランコレクターから評判の良いギャラリストを紹介してもらいました。美術館のキュレーターや館長などとも慈善活動などを通じて一緒に仕事をし、コレクションを構築するのに協力を得てきました。そうやって積んできた経験を、私たちは主に美術館や非営利団体を通じて若いアートファンと共有しています。
パトリシア・フェルプス・デ・シスネロス:「コレクター」という言葉があまりに大雑把に使われていることが問題だと思っています。私にとってコレクターとは、アート作品の金銭的な価値と同じくらい、それが作られた文脈や、所有者としての責任を重視する人のことを指します。とはいえ、さまざまな人がいろんなきっかけで収集の道に入ってくるということも理解しています。金銭的な面に惹かれて収集を始めた人たちが、続けているうちにアートが持つ独特な魅力に目覚め、単なる所有欲や損得勘定を超えた本質により深く関わるようになればと願っています。
ベス・ルーディン・デウッディ:私は投機家がコレクターのイメージを悪くしたとは思いません。彼らがさらに多くの作品を収集し、どんどんアートを支援してほしいと願っています! 私はこれまでずっと、誰もが自分の好きなアートを買うべきだと考えてきました。作品の価格帯や種類はさまざまですが、大抵の人は自分が心地よいと感じる分野を見つけられるはずです。コレクターや、これから収集を始めたいと考えている人は、自分が住んでいる地域の美術館と積極的に関わって、できるだけ多くのアートに触れることが重要だと思います。
ロンティ・エバース:アートの収集は長期的な戦略に基づいて行うものです。トレーダーのような投機的な買い手は、金融の世界でより大きなリスクをアートの世界で取っているのでしょうか? アート界の不健全な力学を助長しているのは彼らだと私は思っています。いずれにせよ、名高いコレクションの多くは市場が弱い時期に築かれました。偉大なコレクションはコレクターのお手本となり、コレクターを鼓舞するのです。
ニコラ・エルニ:いつの世も、アートは投機の対象となってきました。市場は上がったり下がったりしますが、偉大な作品は生き残ります。
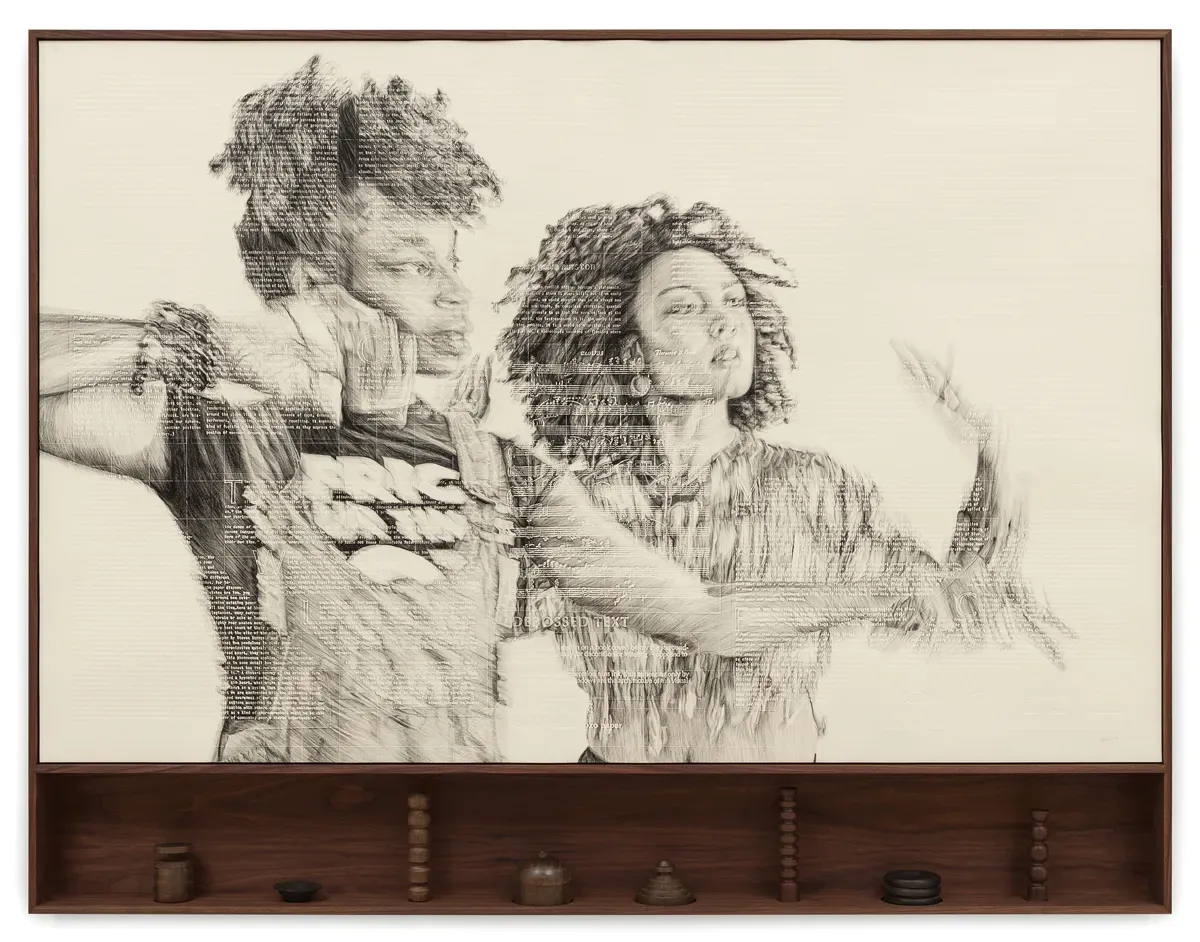
エリー・クーリ:アート市場には、いわゆる投資家や転売屋と呼ばれる人たちが常に出入りするものですし、それは誰にも変えられません。彼らは参入してきては、過剰な投機によって火傷を負い、退場していきます。真の意味での収集とは、時を経るごとに情熱が深まっていく長期的な活動です。
グラジナ・クルチク:コレクターとして、美術館の創設者として、長年アート市場に参加してきましたが、私は昨今のいくつかのトレンドは問題だと思いつつも、アートの未来については心配していません。アート作品は、オルタナティブ投資の金融商品、または暮らしを彩るアクセサリーのように扱われることもあります。けれども、アーティストは今も深遠で批評的な作品を作り続けていますし、使命感に満ちたアート施設が姿を消したわけでもありません。こうした現象は昔からずっとあったものですが、今は特にそれが顕著になっているだけだと思います。
バーバラ&ジョン・ランドー:まともな頭があれば、投資目的でオールドマスターや19世紀初頭の作品を収集しようとは考えないはずです。そうした作品を心から好きで、そこから刺激を受け、それとともに生きていきたいという強い気持ちがないとできないことです。作品の中には、最終的に支払った金額以上に値上がりするものもあれば、同程度で推移するものもあれば、値下がりするものもありますから。
作品に対する愛が収集の主な動機であれば、価格の推移は検討事項として重要ではあっても、決定的なものにはならないでしょう。16世紀から18世紀にかけてのヴェネチア派の一流作品を20点、あるいはギュスターヴ・クールベの傑作を15点手に入れて深い満足を覚える人もいれば(私たちは何十年もかけてそれを達成しました)、そういうことにまったく意味を見出さない人もいる。全ての物事に言えることですが、意味を見出すことが重要で、それこそが収集であり、人生だと私たちは考えています。
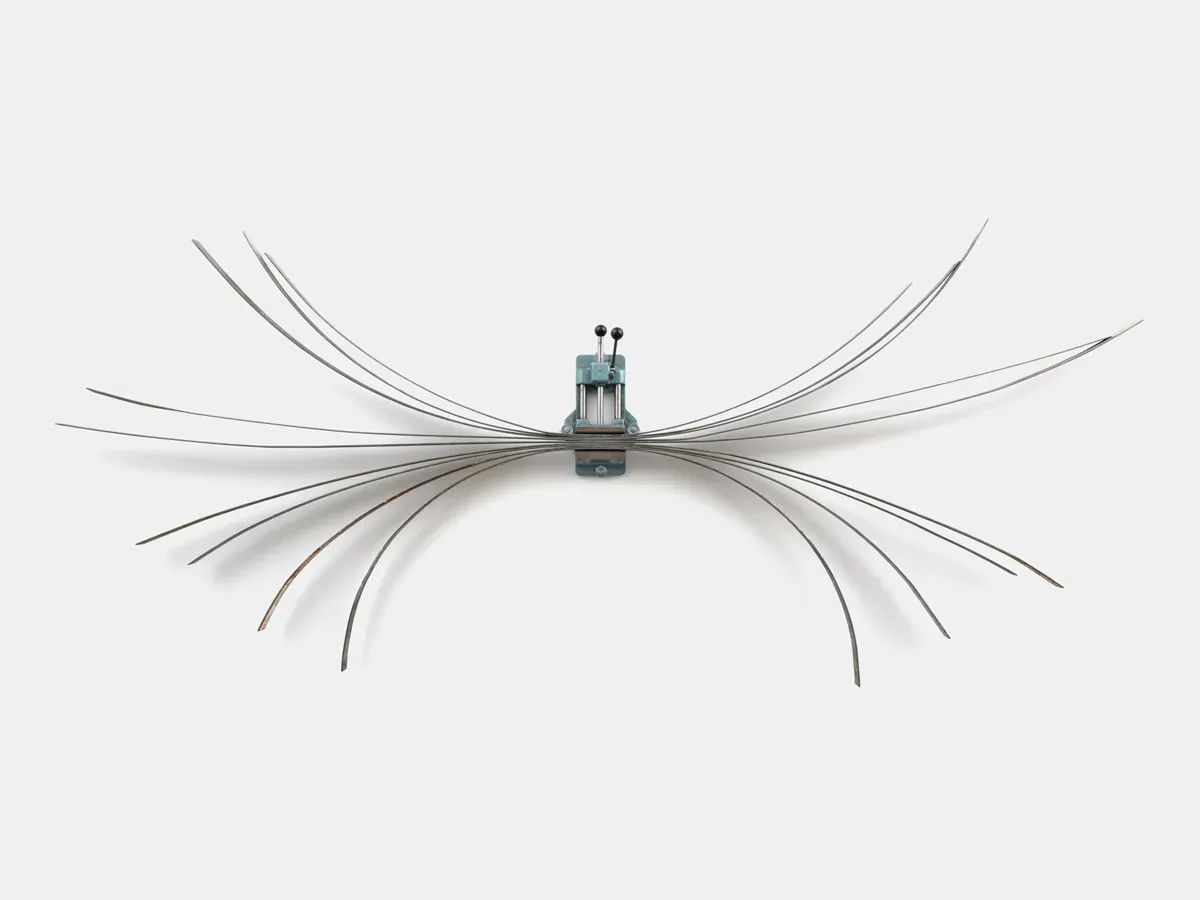
ミヨン・リー:チューリップを投機の対象とする人たちさえいたのですから、アート市場に金銭的な動機で入ってくる人がいても不思議ではありません。でも、アートを見ることに純粋な喜びを感じる人の方が多いはずだと思っていますし、コレクションを始めたばかりの若い世代にもそういう人たちはいます。私の家にも若いコレクターたちが訪ねて来てくれますが、彼らからは旺盛な好奇心と情熱が感じられます。市場の力学に抗い、自分自身に忠実な作品を作り続けられるかどうかは、アーティスト次第だと思います。
スザンヌ・マクフェイデン:後輩コレクターたちと話して感じるのは、彼らが情報に飢えているということです。いろいろ聞かれる中で投機や市場の話も出ますが、そんなときにアドバイスするのは「耳ではなく目で買うこと」です。できるだけ多くの作品を実際に見て、自分で自分の興味対象を見つけること。美術館やキュレーター、関心のあるアーティストと積極的に関わり、支援すること。そしてその知識を使って確固とした有意義なコレクションを築くこと。どれを実行するときにも市場との関係を考える必要はありません。
可処分所得が多かったり、注目を浴びていたり、言い寄ってくる人が多かったりすると、意思を貫くのは難しいかもしれません。そういうときには先達の導きが役に立ちます。私は助言を求められた場合は、雑音に振り回されないようにと指南しています。優れたコレクターはアート界に利益をもたらします。思慮深い決断としっかりとした管理によって築かれたコレクションは、年月を経ても魅力を失わず、誰もが手に入れたいと願うものです。一朝一夕には実現しませんが。

アンドレア&ジョゼ・オリンピオ・ペレイラ:残念なことに、アートは以前にも増して金融資産として見なされるようになっています。コレクターは作品そのものよりも、アーティストのバリュエーションが上がるかどうかに関心があるようです。私がいつも講演などで強調しているのは、喜びを得るためにアートを買うことが大事だということです。心を動かされる作品を探すべきです。もしも作品の価格が上がれば喜ばしいことですが、それはあくまでも副次的なもので、作品を所有する喜びの方が重要です。
エイミー&ジョン・フェラン:経済と同じようにアート市場にも周期性があり、そして、周期性は投機につながります。投資目的でアート市場に参加する人は、コレクターではなく投機家です。アート市場における本当の問題は、数年前まで金利が低く抑えられ、作品購入の際に過大なレバレッジをかけられたことだと思います。私たちは投資として美術品を購入したことはありません。市場が調整し、投機筋が退場するのは、市場が健全性を取り戻す良い兆候です。私たちは、アートと真剣に向き合っているコレクターたちが、最近の投機筋によって市場から遠ざけられるとは考えていません。
ピート・スキャントランド:アートアドバイザーのジェイコブ・キングは、(話題を呼んだ短いレポートの中で)真っ当なコレクターなら誰もが知っていることを指摘しています。それは、美術品は世界一流動性の低い資産だということ。手っ取り早くリターンが得られると思ってアートの収集に手を出す人は失望することになるでしょう。市場が縮小している今、不純な動機でコレクターになった人々は、もっと簡単に儲けられるアセットに移行していくはずです。
流行りは移り変わりますが、本当に素晴らしい作品は時の試練に耐えるものです。また、市場サイクルのような短いスパンではなく、数十年単位で見れば、アートの収集に興味を持つ人の数は今後も拡大し続けると私は信じています。人生を変え、豊かにしてくれるアートには人を惹きつける磁力がありますから。投資として作品を買ったことは一度もありませんが、金銭的なリターンではなく精神的なリターンで測る限り、私のコレクションは素晴らしい投資になっていると信じています。
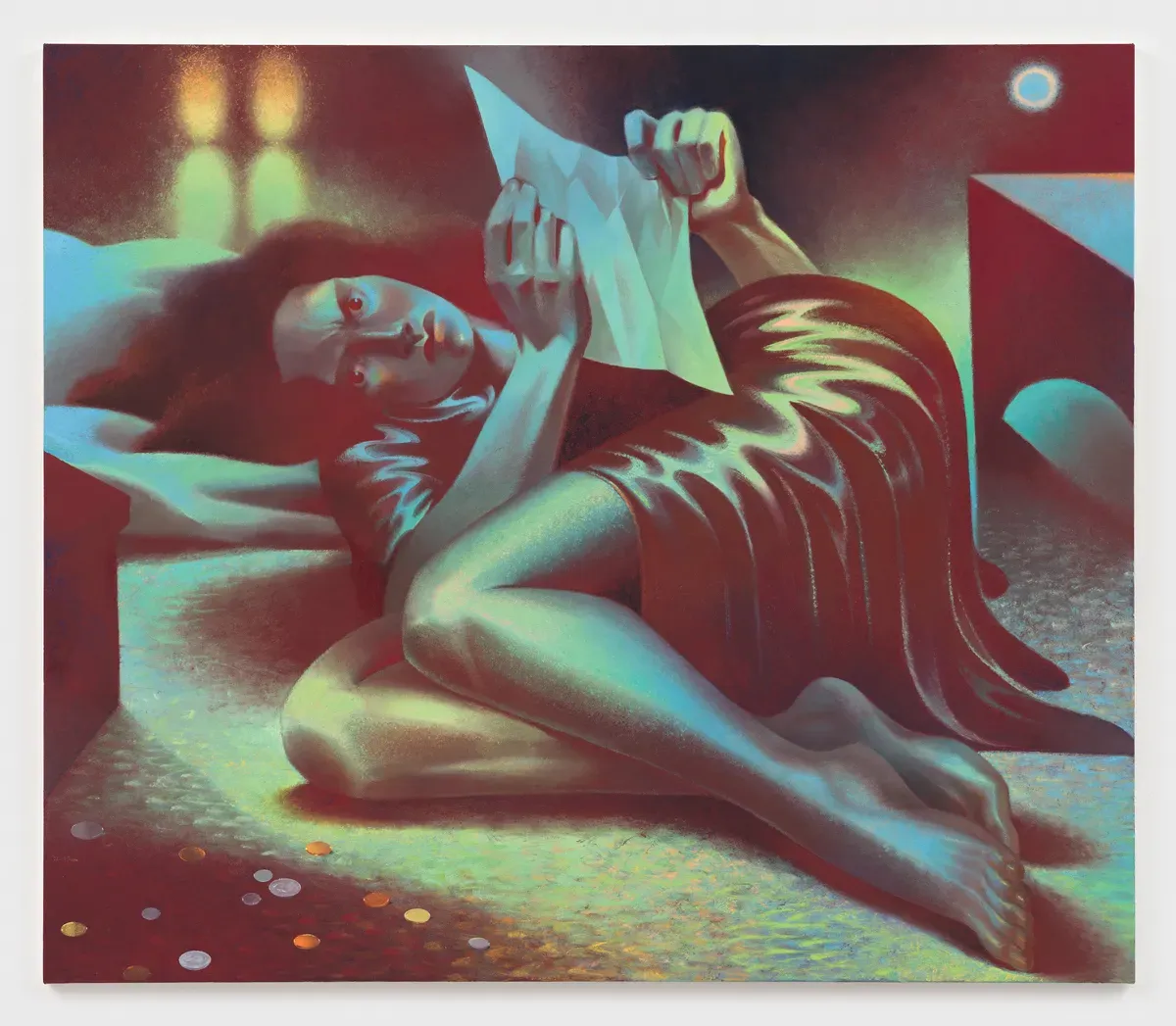
ジョーダン・シュニッツァー:投資や投機目的でアートを購入する人がいたとしても、それはその人の自由です。しかし、せっかくほかの分野でたくさんお金を稼いだのなら、自分が本当に好きだと思う作品を買ってはどうかと思います。美に囲まれ、自分自身や社会について深く考えさせられる作品と向き合って暮らすほうがいいと思うので。
サラ&ジョン・シュレシンジャー:ジェイコブ・キングの視点はリスペクトしていますが、彼の意見に全面的に同意するわけではありません。アートの世界には周期があり、コロナ禍によって一時期は例外的な動きもありましたが、それは長続きしませんでした。私はアートを収集するもっと長期的な理由があると心から信じていますし、アートのエコシステムを信じています。コレクターである私たちは素晴らしい作品を預かる者として、展覧会や寄付、そしてさまざまなアートプログラムの支援を通じて1人でも多くの人々にアートのことを知ってもらいたいと強く思っています。
高橋龍太郎:投機家の動きに興奮したり動揺したりしてコレクションをやめてしまう人がいるとしたら、その人はアートが好きなのではなく、お金が好きなだけなのだと思います。買うと損をする可能性もあるけれど、それを補って余りある魅力がアートにはある。新世代のコレクターは、そういう考え方ができる人であってほしいと思います。そのためには、好きな作品を長く手元に置いておくことが重要です。そうすれば、いつかお金はあなたを振り返り、微笑み返してくれるでしょう。
カール&マリリン・トーマ:アートは資本主義ではないし、私たちはアートを金銭的な投資とは考えていません。私たちは、心に訴えかけてくる作品を購入します。そして一度それを手に入れたら、作品の管理者としての大きな責任が生じますし、できるだけ多くの人がそれを見られるように努めなければなりません。
ジョセフ・ヴァスコヴィッツ、リサ・グッドマン:市況が良くないときにコレクションを始める人たちの動機は、芸術への愛、コミュニティへの情熱、アーティストと直接会ったり支援をしたりすることの楽しさなど、どれも真っ当なものです。市場低迷を理由に去っていく人たちは、一部のギャラリーやアドバイザーからは惜しまれるかもしれませんが、アートをIPOのように扱う人たちが生む混乱は迷惑でしかありません。人は忘れっぽいので、数年後にはまた同じことを話していることでしょう。私たちの慈善活動では、メンターシップとパートナーシップを重視しており、新進アーティストだけでなく、ギャラリーやコレクターにとってもそれが大切だと考えています。
ウー・ティエジュン:私の考えでは、アートのコレクションは目的を持って体系的に行われるべきです。やみくもな収集や単なる投資目的の収集には意味がなく、体系的な収集とはまったくの別物です。収集というのは目的志向で、体系的で、継続的な実践であると私は考えています。駆け出しのコレクターには、まずは特定のカテゴリーやトピックに焦点を当てるなどして目標を定め、体系的に収集することを勧めています。こうしたアプローチによって、コレクションに意味が生まれるからです。

ソーニャ・ユー:不動産や株、時計、そしてアートと、投機家はどの分野にもいます。投機家や投機的な考え方が存在するとはいえ、私はアートが持つ変革的な力を信じていますし、アートがさまざまな文化や価値観を反映し、批評や議論のためのプラットフォームになっていると信じています。先達からのアドバイスも重要ですが、情報や文脈についての知識を和解コレクターに与えることが、金銭的なものにとどまらない、より深い投資につながると思います。人は楽しいと感じれば積極的に関わろうと思うものです。私にできるアドバイスは、口だけではなく自ら行動し、楽しむこと。そして自分自身を深く理解し、アート界や、アートの世界で目覚ましい活躍をする人たちから学べることを常に吸収し続けることです。
ライアン・ズーラー:これからは、AIを使ったアーティストがますます増え、驚くような作品がもっと見られるようになると思います。彼らは、新しい機械学習ツールを思いもしない方法でフルに活用したアート作品の最初の世代となるでしょう。サーペンタイン・ギャラリーで開催されるホリー・ハーンドンの展覧会は、こうした次世代ツールでどんなことができるかを示す好例となるはずです。
Q2. メンターシップ(後輩にアドバイスやサポートを与えること)はコレクターの責務の1つだと考えますか?
スザンヌ・ディール・ブース:芸術の分野においてメンターシップは非常に重要だと考えています。それと同じくらい私が重視しているのは、アート作品とともに生活し、所蔵品をほかの人々に見てもらえるようにし、大切に管理するということに関して模範を示すことです。そして常々、好奇心を持ち、質問をして常に学び続け、自分の周りの世界と関わるようにと言っています。変かもしれませんが、私は自分のことをコレクターだとは思っていません。私は文化的・歴史的遺産保存の専門家であり、ナパ・バレーでブドウを栽培し、受賞歴のあるオリーブオイルや人気ワインを造る醸造家でもあります。私の暮らしの中にあるアート作品は、私の魂を養い育ててくれる個人的な情熱の対象なのです。
マイケル・フォーマン、ジェニファー・ライス:新進コレクターをメンターとして導くことは重要だと考えていますし、私たち自身が模範となるように努めています。私たちは所蔵品をほかの人々が見られるようにし、集めている作品がいかに私たちの興味関心やコレクション全体と結びついているのかについて話しています。アートの収集はあらゆるレベルで実践できますし、それは単にモノを手に入れることではなく、アーティストや作り手との関係を築いていくことでもあります。作品を購入することによって私たちのコレクションがさらに充実し、かつアーティストのキャリアが花開くという相互補完的な側面を大切にしています。
チーチ・マリン:私はメンターシップを自分の収集活動の一環として考えています。アーティストが無名の頃から作品を集めるのが好きですし、アート収集は投資のためではありません。自分が気に入ったもの、これまで見てきた中で最高の作品だと思うものを集めています。
ライアン・ズーラー:ウリ・シグ(スイス出身で中国現代アートの主要コレクター)のような素晴らしいメンターたちがアートの世界で私を導いてくれたこと、そして今も導いてくれていることに感謝しています。だからこそ、自分もこの道に入ってきたばかりの若いコレクターたちのメンターにならねばという責任を感じます。ボラティリティが大きい今だからこそ実験を重ね、現代アートの収集についてのパラダイムやバリューチェーン、経済モデルを変えていけると信じています。

Q3. 拠点としている国・都市のアートシーンの特徴について教えてください。
パトリシア・フェルプス・デ・シスネロス:私たち家族は50年近く前からドミニカ共和国に家を構え、長年にわたって地元のアーティストたちと関わってきました。ドミニカ共和国ではこの10年、アートのコミュニティが着実に育ってきています。特にサントドミンゴのアルトス・デ・チャボン美術学校や、サンティアゴ・デ・ロス・カバリェロスにある美術館、セントロ・レオンの周辺でそれが顕著です。このコミュニティは、地元の社会問題や諸課題と深く関わり、支援が必要な人を助けながら、美しく洗練されたコンセプトの作品を生み出しています。
デニス&ゲイリー・ガードナー:シカゴにおける視覚芸術のエコシステムは非常にユニークだと思います。有名な大学がいくつもあるのでアーティストの卵が大勢集まってきますが、幸い卒業生の約半数がシカゴに残ることを選択し、この街のアートシーンに活気を与えています。シカゴは芸術活動に対して非常に協力的な街で、アーティストのキャリアを支援する公や民間の助成金が複数ありますし、ケリー・ジェームズ・マーシャル、シアスター・ゲイツ、ニック・ケイヴ、ダウッド・ベイなど、今まさにキャリアの頂点に立っている著名アーティストの本拠地でもあります。さらには、アート施設を熱心に支援している大物コレクターたちも数多く住んでいます。エコシステムを構成する個々のグループが互いに接点を持ち、その間の隔たりが少ないという点でもシカゴは際立っていると思います。
ギエルモ・ゴンザレス・グアハルド、ヤナ・サンチェス・オソリオ:メキシコシティは若くてクリエイティブな人々にとって素晴らしい場所です。現代アートの一大拠点に成長したメキシコシティは現在も変革期にあり、この街のアートデスティネーションとしての魅力を発見する人も増えているようです。国立人類学博物館や著名な壁画家たちの作品など、メキシコシティは昔から多くの文化的ランドマークで知られていましたが、近年は現代アートの中心地としても認識されるようになりました。私たちはオリビア財団を開設することで、この街の豊かな文化的歴史をさらに発展させたいと考えています。

ケント・ケリー:成長と刺激がアトランタのアートシーンを活気づけています。ハイ・ミュージアムやスペルマン・カレッジ・ミュージアムのような展示施設はその中心的存在として素晴らしい展覧会を開催し、地元コミュニティとアートのつながりを生み出しています。数年前に始まったアトランタ・アート・ウィークは、人種や年齢、アートの嗜好を超えて、この街のアートコミュニティを1つにまとめました。
今年はアトランタで初となるアートフェアも開催されました。ゴート・ファーム・アーツ・センターやアトランタ・セレブレイツ・フォトグラフィーのような場所でアーティストのスタジオスペースが増えたことも大きな先行指標です。この街では以前から音楽や映画などの産業が盛んでしたが、今はアート分野が活性化する環境が整いつつあります。それがどんな成果を生むのか正確に予測するのは時期尚早ですが、アトランタは今後アート界により大きな貢献をしていくでしょう。
エリー・クーリ:ドバイを拠点とするアートコレクターとして、私はこの街の未来は明るいと思っています。アラブ首長国連邦(UAE)のアートシーンは急速に進化しており、美術館や文化事業への投資も盛んです。国際色豊かな環境は、多様な芸術交流やコラボレーションを促進し、世界から注目を集め、ダイナミックな文化的環境を育んでいます。
グラジナ・クルチク:アルプスで現代アートの美術館(スーシュ美術館)を運営していると、その土地が持つ圧倒的な美しさと人里離れた環境が、アートと鑑賞者の間に独特の関係を育んでいると実感します。スイスのエンガディン渓谷は100年以上前から芸術家たちの楽園として知られていて、数多くの文化施設や美術館、ギャラリー、スタジオがあります。人々はここに来ると、普段以上に時間をかけて、より熱心にアートを鑑賞しているように感じます。
リー・リン:私は西湖や茶畑、美しい山々などで知られる中国南東部の都市、杭州で育ち、今もそこに住んでいます。杭州は中国有数の美術大学である中国美術学院の所在地でもあります。多くのアーティストが学び、今も暮らしている杭州では、若者文化も活気があります。しかし、杭州にはまだ現代アートの美術館がそれほど多くありません。私たちの美術館BY ART MATTERSは、多様な展覧会や教育プログラムを提供するアート鑑賞のプラットフォームでありたいと考えています。

スルタン・スード・アル・カセミ:幅広い体験ができることがシャルジャ首長国(UAE)のアートシーンを特別なものにしています。イスラム美術を見たり、オリエンタリズム絵画を探求したり、現代アラブ美術について学んだり、世界的な現代アートに囲まれたりと、さまざまなことができるこの街には真に活気ある多文化的な環境があります。芸術的な対話を促進し、多様な声を支援するUAEの確固たる姿勢には、特筆すべきものがあります。シャルジャのアートシーンを際立たせているのは、こうした多様性と開放性で、文化の領域で周辺地域の手本となっています。
パトリツィア・サンドレット・レ・レバウデンゴ:トリノはかつてイタリアの主要な工業都市でしたが、今は現代アートのハブとなっています。イタリアを代表する現代アートフェア、アルティッシマが開かれる11月は特に賑やかで、世界中からコレクターやギャラリー、アートファンが集まります。フェア期間中は美術館や財団、ギャラリーなどが力を合わせ、この街の芸術的な活気を反映したいくつもの素晴らしい展覧会を開催します。サンドレット・レ・レバウデンゴ財団でも、マーク・マンダースの大規模な展覧会を予定しています。マンダースは駆け出しの頃からずっと注目し、支援してきたアーティストで、彼の作品はたくさん所蔵しています。彼がどんな新作をトリノに持ってきてくれるのか、今からとても楽しみです。
カール&マリリン・トーマ:ダラスのコレクターたちは昔から、自分の所蔵品を一般の人々にも見てもらえるよう努めてきました。ほかの大都市よりもそうした機会が多く、そのようなコミュニティの一員でいられることに感謝しています。
ウー・ティエジュン:私は3000年以上の歴史を持つ南京の出身です。かつて金陵と呼ばれたこの街の豊かな芸術的遺産は中国だけでなく、世界に大きな影響を与えました。だからこそ私は、この地域の美術品の収集に力を入れてきたのです。南京は千年以上前から仏教の中心地でもあり、仏像は私のコレクションの中で重要な位置を占めています。南京は中国の北部と南部の文化が混じり合う都市だということもあり、宋の時代の磁器や明の時代の家具などを体系的に収集しています。こうした重要芸術品を通して、私たち(徳基美術館)は南京芸術の真髄を紹介し、東洋の究極の美学を鑑賞できるようにしています。(翻訳:野澤朋代)
from ARTnews


