訃報:フルクサス・メンバーで音の革新者、刀根康尚が死去。「表現者が規範から逸脱するのは自然なこと」
5月13日、ノイズミュージックの第一人者で、フルクサスのメンバーとしても活躍した刀根康尚が死去した。90歳だった。
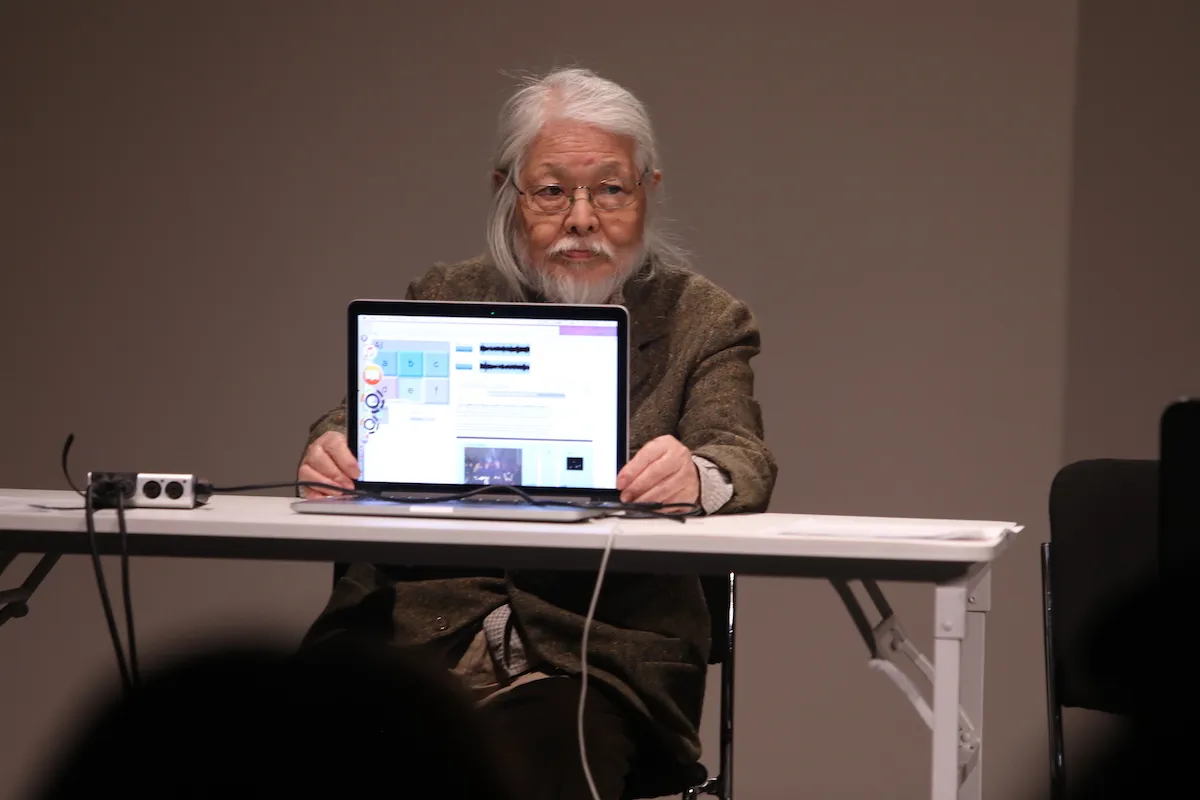
芸術運動「フルクサス」に参加し、日本初の即興演奏集団「グループ音楽」を設立した、音楽家であり前衛芸術家、評論家の刀根康尚が5月13日に在住するアメリカで死去したと発表された。90歳だった。
彼の死は、2023年に刀根のアメリカ初の回顧展を開催したアーティスツ・スペースによって明かされた。死因は老衰だという。
1935年に東京で生まれた刀根は千葉大学国文科に進学し、日本文学を専攻。在学中は評論家である栗田勇の下でシュルレアリスムを研究し、1957年に卒業した。刀根はかつて、当時のことをニューヨーク近代美術館(MoMA)のブログで、「少し頭でっかちだったので、最初は音楽を演奏するというよりも理論面で仕事をするつもりでした。しかしある時点でのめり込んでしまい、東京芸術大学音楽学部の学生たちと交流し、音楽を演奏し始めたのです」と振り返った。
そして大学卒業の翌年、作曲家の一柳慧を通じて知り合ったジョージ・マチューナスの誘いでフルクサス運動に参加。同時期に即興演奏も始め、1961年、彼は日本初となる即興演奏集団「グループ音楽」を共同設立した。このグループは短命だったものの、刀根はそこで従来の楽譜ではなく、音楽的な指示を視覚的に書き表した「グラフィック・スコア」を考案。同年に発表された《弦楽のためのアナグラム》と題された作品では、様々な大きさの黒と白の円がグリッサンド(滑奏音)の長さに対応して振ってはいるが、音をどのように生み出すかは最終的に演奏者の解釈に委ねている。これはジョン・ケージによって制作された楽譜の作品に影響されたものだった。
刀根の代表的なキャリアの1つとなったフルクサス運動は、1960年代にジョージ・マチューナスが提唱し生まれた。様々な芸術的媒体を融合させ、芸術と日常の経験の間の溝を埋めることに焦点を当てており、オノ・ヨーコ、武満徹、ヨーゼフ・ボイス、ナム・ジュン・パイクらが参加している。マチューナスは刀根のスコア『弦楽のためのアナグラム』を出版し、それが国際的な評価に繋がった。1967年頃からは美術批評家として『美術手帖』に寄稿するようになり、高松次郎、赤瀬川原平、中西夏之などにより結成された「ハイ・レッド・センター」とも活動した。
刀根は1972年にアメリカに移住。その頃にはノイズのような音楽を制作することに注目しており、彼自身、こうした作品を「宿主のない寄生虫」と呼んでいた。アメリカではジョン・ケージらとも交流しながら独自の音楽を追求していった。その手法は、氷などの素材で楽器を改造するパフォーマンスを行ったり、CDを傷つけて白色ノイズの波を生み出すなど型破りなものばかりだった。彼の目標は、明らかに非正統的な音楽制作方法を活用することによって、音楽を伝統から遠ざけることだった。かつて彼はアーティストのクリスチャン・マークレイに、「アーティストが規範から逸脱するのは自然なことだ」と語っている。

彼の作品は、実験音楽に興味を持つ人々に広く知られている。2023年に『アナザー・マガジン』に掲載された刀根の特集記事には、「彼は音楽を永遠に変えた」という見出しが付けられていた。その中で彼の回顧展のキュレーターであるダニエル・A・ジャクソンは、刀根は作品を通して「多くの作曲家や音響実験家のための扉を開いた」と語った。
また、刀根はナム・ジュン・パイク、ジョージ・マチューナスをはじめ、シャーロット・ムーアマン、センガ・ネングディ、マース・カニンガムなど多くの重要なアーティストと共同制作を行ってきた。共にフルクサスで活動したアーティストのオノ・ヨーコは、2013年にウォール・ストリート・ジャーナル紙の取材に対し、「彼の音楽を聴いたり譜面を読んだりすると、アジア音楽に抱いていた一般的なイメージが完全に破壊されることに人々は驚くでしょう。彼はアジア人ではありません。火星人なのです」と語った。
キャリアの後半、刀根はデジタル技術に注目し、音響圧縮方式のMP3を使った「MP3デビエーションズ」プロジェクトを発表。晩年はAI技術も取り込み、そのロジックを自身の制作の推論に使用するシステムを開発した。
彼はキャリアを通して、常に音楽が世界をどのように再形成できるかを考えていた。2014年に公開されたニューヨーク近代美術館(MoMA)のブログで、刀根は次のように話している。
「私は、音が単なる表現に陥ることを避けています。コンサートホールの座席位置に関わらず、聴衆全員が同じ音を聴けるようなホールを設計したいというのは間違っていると思うのです。このような願望は、人々の世界観に根ざしており、その世界観は『音楽とは何か』という仮定に基づいているに過ぎないのです」(翻訳:編集部)
from ARTnews


