南島興評:学校を再発明せよ! 現代美術、過去10年への応答
今、世の中で起こっている様々な出来事を、美術の専門家の視点から見るとどうだろう。横浜美術館の学芸員、南島興が、2人の若手批評家の評論を読み解きながら、2010年代とはどういう時代だったのか、そして学校という枠組みについて改めて考える。

2010年代の課題
いま手元には、ふたつの批評がある。日本「最後」の評論賞となった群像新人評論賞2021を受賞した2作、渡辺健一郎 「演劇教育の時代」と小峰ひずみ「平成転向論」である(*1)。
*1 「群像」2021年12月号、講談社、2021年
この賞の終焉をもって、大手の文芸誌から評論・批評の賞が姿を消した。それが2022年の美術批評も含めた評論・批評の現在地であることは改めて共有されるべきだろう。だが、ここで私が強調したいのはその点ではない。
両作が演劇教育と政治運動、それぞれ異なる主題を扱いながらも、日本のとりわけ現代美術に対して2010年代から現在に残された課題を浮き彫りにするとともに、その克服への糸口を提案していたことである。それはいわゆる観客参加型アートが観客に強いていた「不自由さ」と、現代美術という一種の専門知と社会を繋ぐ言葉のあり方にかかわるものである。
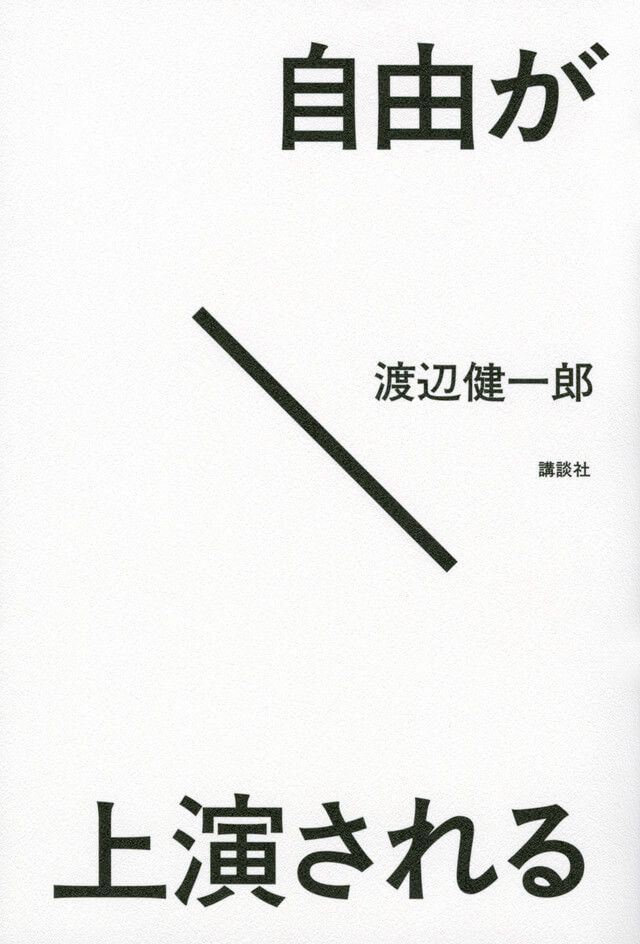
渡辺健一郎著『自由が上演される』(講談社)
私はコロナによる社会的な混乱が落ち着き、東京オリンピック2020が終わった22年はやっと過去10年の振り返りができる時機であると考えている。本稿では渡辺と小峰の論考に沿う形でその一端を明らかにしてみたい。まずは彼らがどのような仕方で、2010年代を振り返っているのか、順に見ていくことにしよう。
渡辺健一郎は2012年以降に教育現場に導入されたアクティブラーニングや演劇型のワークショップの形をとりながら行われ、学生の主体性や協働性を引き出すことを目標とする「演劇教育」について論じている。今日そうしたタイプの教育は、学校という枠組みを越えて、あらゆる社会的実践のなかで重宝されている(日常のワークショップ化、社会のワークショップ化)。
しかし、渡辺によれば参加者の自由な発言や行為を促すはずの演劇教育は、原理的にある不自由さを参加者に強いているという。なぜなら、例えば、アクティブラーニングにおいてファシリテーター的な役割を担う教師による「あなた(たち)の自由を尊重します」という参加者への発言は、その言説空間の外側をはじめからシャットアウトしてしまうからだ。この不自由さを解消した形で実現可能な演劇教育のモデルを提案するのが、渡辺の狙いである。
そのために渡辺は主に哲学史上の言説を様々に参照するが、なかでも重要に思われるのはジャック・ランシエールの「無知な教師」、そして非常にわずかな引用であるがそれゆえに核心的なジャン・リュック・ナンシーの「表象」という語の再解釈である。一つ目の無知な教師とはなにか? それはあるオランダの大学教師ジョゼフ・ジャコトの史実に基づいている。
彼が担当したフランス文学の講義において、自身はオランダ語が、学生はフランス語の読み書きができない状態から、互いの言語の対訳の復唱を繰り返すだけで、学生たちは次第にフランス語の体系を理解していった。教師は無知にもかかわらず、教育は成立してしまっているのだ。無知な教師とは知識をもっている教師が、無知な学生にその知識を伝達するとされる伝統的な教育の原理に否を投げかける例なのである。渡辺はそこに2つ目のナンシーの議論を加える。
ナンシーは一般的に「再現前化」を意味するrepresentationの「re」を反復ではなく、強意の意味に捉えてその単語が現前していること自体の現前を意味すると解釈している。ジャコトの例に引き付ければ、無知な教師がなにかを教育することができるのは、教師は教師として、学生は学生としての役を演じることで、授業はひとつの上演として認識されているからなのである。私の理解では、それによってはじめて参加者である学生たちは自分たちのいる言説空間の外部を想像することができるようになる。
日本の現代美術にとって2010年代とは「美術を社会に開く」10年であった。日本各地で開催された芸術祭と地域アートや広い意味でのリレーショナルアートとの関連のなかで数多く実施された観客参加型アート(観客の「参加」や「協働」を促す芸術実践)はその象徴である。芸術祭の総体的な活況には、ひとまずその成果は現れているだろう。渡辺の論考からはそうした現代美術の動向がアクティブラーニングと同時代現象であることへの気づきがまず与えられる。
観客参加型アートとは多くの場合、芸術の実践にかかわる人や物、場所の構成に配慮することで、観客が主体的に作家の活動に関与し、その参加自体が作品を形作るという信念のもとに成立している。この環境の働きかけによって観客の参加者化を促すなかにある「不自由さ」に敏感であろうとするのが渡辺の問題意識であることは言うまでもなく、それに対する応答こそが今まさに参加が起きている状況=上演に対する意識、そしてその上での外部の確保なのである。渡辺によれば、ここに観客の自由の有無は賭けられている。
SEALDsと鷲田清一、2つのベクトル

小峰ひずみ著『平成転向論 SEALDs 鷲田清一 谷川雁』(講談社)
もうひとりの小峰ひずみは、2010年代の世界的な政治運動とも共鳴する形で登場した、著者とも同世代のSEALDsに対する批判と、彼らのありえたかもしれないあり方を哲学者の鷲田清一が見せた(非)転向、すなわち哲学研究者からエッセイストへという態度変更に求めている。その間には谷川雁への重要な迂回があるのだが、結論だけを抽出するのなら、政治的な運動のために必要なのは生活の場所で政治の言葉を語ることと、政治の場所で生活の言葉を語ること、2つのベクトルの往還である。
しかし、SEALDsには後者しかなく、2016年の解散後はそれぞれ「スキル」を身に付けるため、もとあった日常にただ帰ってしまった。この点を小峰は批判している。たしかに彼らは自分たちの日常の言葉を使ってそのまま政治の場に立った。けれど政治の言葉をもって日常へと下降することはしなかったのだ。小峰によれば、それを実践してみせたのが鷲田のエッセイスト化と臨床哲学の実践、またそれに伴う哲学カフェ普及の活動であった。
この小峰の2つのベクトルは、過去10年で特に重視された現代美術と日常の場としての社会とのコミュニケーションに関わる言葉を整理するものであるだろう。一方では政治/美術について、日常の場所で語ろうとし、他方では自分たちの日常について、政治/美術の場所で語ろうとした。SEALDsの道は後者であったが、これは国内の美術動向からすれば、意外にも当事者性の問題にぴったりとあてはまる。作家自身が何をどんな権利において表現するべきなのか、これは2011年の東日本大震災後にきわめてセンシティブかつ重大な課題として多くの現代美術作家にも突き付けられた問いであった。対して、鷲田清一が進んだという前者の道はどうだろう。こちらは美術という専門語の世界を日常の場へと開いていく活動を指している。まさにそれは10年代に美術界が総出をあげて向かった方向性ではなかったか。
前述の通り、美術を社会に開くこと、この至上命題に向かって、既述の芸術祭は開催されてきた。そこでは「現代美術では」から始まる説明とは別の仕方で、美術について考えるための言葉を紡ぐことが目指されたはずだ。なかにはSNSを舞台としたネット炎上の的にもなったものもあったが、それへの対応は常に美術の専門語を日常語に言い直していく作業であった。だとすれば、その10年が過ぎ去った今、私たちの手元にはいったいどんな言葉が揃っているのだろうか。この10年で、現代美術は日常との間にどんな関係性を築き、どんな言葉を使えるようになったのだろうか。小峰の2つのベクトルの整理はそうした見直しを迫るものである。
観客参加型アート、当事者性、地方芸術祭。渡辺と小峰の批評は、2010年代を特徴付けるこれらの現代美術の動向と課題を共有し、独自の応答を試みているように映る。こうした同時代性について、美術、演劇、哲学などの垣根を超えて、議論を交わすことは重要だろう。したがって、ひとまずは、僭越ながら美術関係者にも両作を読まれることをお薦めしたい。
学校という概念の再発明
ただし、ひとつだけ付言したいことがある。両作に共通したあるひとつの隠れた問題意識についてである。それは明示されておらず、もはや明示するほどの期待もかけられてはいないものだ。しかし、私はそれこそ演劇教育、政治運動、そして現代美術に通じている、真に同時代的なテーマなのだと考えている。
それは学校の再発明である。あまりに凡庸だろうか。いや、これはもともと現代美術の中心的な課題への応答であったはずだ。2006年のある国際展に際して発表されたテキストを引用しよう。

越後妻有 大地の芸術祭より 田島征三「鉢&田島征三 絵本と木の実の美術館」 photo 秋元茂
「最近の大規模な国際展のタイトルを見てみれば、『文化的差異の生産』、『植民地化の課題』、『現在との決定な対立』、『都市の諸条件』など、それらの展示の主催者や参加者の側で彼らの仕事を具体的な社会プロジェクトや積極的介入として捉えてほしいという欲望が強まっていることにすぐ気が付く。
このような言葉遣いや位置取りが一般化し、かつ芸術的な実践は、自動的に社会のなかである積極的な役割を果たすことが期待されているようである。しかし、どんなに野心的であろうとも、展覧会はそのような関与にとって最も有効な乗り物なのだろうか?」(*2)このように問い掛けたのは、マニフェスタ6のキュレーターの1人を務めたアントン・ヴィドクルであった。
*2 Anton Vidokle Exhibition as School in a Divided City
2022年であれば、人新世やポストヒューマン、エコロジー、フェミニズム、またはグローバルサウスとの不均衡などが付け加えられるが、国際展の基本的な方向性には大した変わりはないだろう。この疑問から察せられる通り、ヴィドクルは、それらについて考える最良の乗り物がこれまで通りの展覧会とは考えていない。このテキストが「Exhibition as School in a Divided City」、つまりある分断された都市における「学校としての展覧会」と名付けられている通り、彼を含めたキュレーターチームは続く箇所で「going back school」と呼び掛けることになる。学校をモデルとして展覧会を組織し直すことは、まずもってこの10数年の現代美術の中心にあった問題意識であったのだ。そのことは改めて強調しておきたい。
さて、両作の議論ではどうだろう。渡辺の理路において重要なのは「無知な教師」の例であった。渡辺はジャコトが無知であるにもかかわらず、ランシエールが彼のことを教師と呼ぶことに着目し、「教師」という役割を学生と共有することから上演の意識化へと議論を進めていく。ただし、演劇教育が日常化した場において、それが上演であるという意識を発生させる外部はどう調達されるのかを考えなければならない。そのためには教師と学生の関係性だけでなく、互いの間に内と外を切り分けるフレームワークが共有されている必要があるはずなのである。
たしかに渡辺が着目するようにジャコトは教師であった。が、彼は「大学」の教師であった。この事実も見逃すべきではないだろう。それは大学という権威の裏付けのためではない。内と外を便宜的に区別するフレームワークの組み立てのために強調すべきなのである。渡辺は演劇教育にかかわる人々への呼びかけにも映る形で、その論を締めることになるが、同時に私は日常化した演劇教育を区切るために「学校」という空間と組織の再編成への呼びかけもされるべきではなかったかと思うのだ。
小峰は、SEALDsのメンバーがただ日常へと帰ってしまったことを批判した。では彼らの日常とは何であろうか。SEALDsが「自由と民主主義のための学生緊急行動」の英訳「Students Emergency Action for Liberal Democracy」の略称であることは、小峰もスキルを身に付けるべきステイタスとそれが前提とする能力主義の観点から批判的に着目している。とすれば、彼らが学生である限りにおいて、彼らの帰る日常は学校生活であるとまずは捉えてよいだろう。

越後妻有 大地の芸術祭より クリスチャン・ボルタンスキー+ジャン・カルマン「最後の教室」photo T.Kuratani
私の印象では、SEALDsは学生を謡いながら、彼らの活動における学校の影は驚くほどに薄い。彼らを応援した全共闘世代では大学こそが主戦場となったこととはまったく対照的である。SEALDsはその代わりにSNSを駆使して、国会前に集まった。ネットと路上という2つのストリートを舞台とした。あるいは、そうせざるを得なかったのだ。
2007年の大学設置基準の改正に象徴される制度改革による大学側の変化は、SEALDsの活動形態には如実に影響を与えていることだろう。学生である彼ら自身もまた学校を「スキル」を得る場所だと認識していたとすれば、なおさらである。彼らは学校を拠り所にすることができなかったし、その代わりを作り出すこともしなかった。小峰の図式に援用すれば、彼らが日常のなかで政治を実践する場所は、第一に学校であったにもかかわらず。したがって、ありえたかもしれない政治運動体としてのSEALDsを考えるとき、そのような場として学校を作り変えていくことが日常のなかに潜りこむための努力として必要であると言えるだろう。
もちろん学校には期待できない、というのが大方の意見だろう。今日、学校は外部を想像するどころか、内部の村的な共同体意識に縛られていじめやハラスメントを防ぐことが難しいし、大学の制度厳密化の動きは加速していくだろう。それに美術教育を見てみても、昨年公表された表現の現場調査団の白書(*3)に明らかなとおり、大学内での教育がいかにハラスメント的な言動に近接し、実際に被害に遭われた方やいまも悩みを抱えている方の多いことか。この現実をみれば、いま学校という場には期待しない方がいいだろう。そう思われるのも無理はない。
しかし、だからこそヴィドクルが「学校として」展覧会を構想したことは参考になるだろう。そもそも既存の教育システムの中に従事しているわけではない者たちに第一にできることは学校否定でもないし、学校改革でもない。できるのは学校という「概念」を使って、例えば展覧会を拡張しようとする試みであり、展覧会という形での提示を通じて、学校という概念の再発明をはかることのはずなのである。
渡辺と小峰の「学校」についても同じである。字義通りの意味ではなく、ひとつの拡張可能な概念として考えるべきだろう。それは学校を装うことで、誰かが知識のある教師として振舞うためでも、新しい権威を打ち立てるためでもなく、観客の自由を確保し、美術の専門語を日常のなかに開く拠点をつくるために。そして現代美術が問うべき政治的・社会的なテーマに最良な乗り物を準備するためにも。その効果については別途、推し量られるべきだが、その発想は鷲田の哲学カフェやヴィドクルの「学校としての展覧会」という形で実践に移されてもいる。
2022年になって、2010年代を振り返る目にかかった靄はやっと晴れ掛かっている。いまになって見えてきた、過去10年へのひとつの応答は、学校という概念への見直しを通して可能であるかもしれない。
さあ、学校という概念を再発明しよう。
展覧会名:越後妻有 大地の芸術祭 2022
会場:新潟県越後妻有地域(十日町市、津南町)
会期:4月29日(金)~11月13日(日)
休祭日:火・水曜
電話 : 025-761-7767( 「大地の芸術祭の里」総合案内所 )


