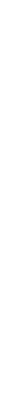それぞれ異なる専門領域を背景に活躍する研究者や著名人が、各々の立脚点から同じ美術展を鑑賞、批評するクロスレビュー。第2回は、21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3で3月13日まで開催中の「メンズ リング エキシビション イヴ・ガストゥ コレクション」を取り上げる。フランス・パリで骨董(こっとう)商だったコレクターのガストゥ氏が収集した、男性用の指輪約400点の展覧会だ。17世紀のヴェネチア共和国元首の印章から、カソリックの司祭が儀式で用いたもの、1970年代に米国でバイカーたちが好んだものまで。「歴史/ゴシック/キリスト教神秘主義/ヴァニタス(空虚)/幅広いコレクション」の5テーマに沿って、時代も背景も多様な指輪が紹介されている。キリスト教美術の専門家である立教大学教授の加藤磨珠枝氏(美術史家)が鑑賞した。
「メンズ リング エキシビション イヴ・ガストゥ コレクション」~私小説のようにコレクターの人生をたどる
21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3 加藤磨珠枝(美術史家、立教大学教授)評
指輪とは円環状の小さな装身具に過ぎないのに、その象徴性たるや、冠とならぶほどの長い歴史がある。たとえば、聖書の『創世記』には、エジプトのファラオが自分の印章指輪(スタンプのように押して認証、封印するハンコのような指輪)を人に与えることによって、王の権限そのものを授ける物語(41章42節)が登場するし、古代ローマでは、公共の場で指輪をはめることは、祭司や元老院議員、高官らにのみ許された特権とみなされた時代もあった。その風習がやがて一般市民にも広がり、婚約の際に花嫁に贈ったり、結婚、誕生日などの記念品としてお互いの絆や忠実さを示したりするようになる。それは権威の象徴、あるいは誓約や絆のあかし、場合によっては魔除けのような呪術的な力の源として用いられてきた。
現代の日本では、結婚指輪や一部のカルチャーを除いて、もっぱら女性用の装身具としてのイメージが一般的であることから、「男たちの指輪」という展覧会タイトルは、あえてその通念から一線を画す表明のようにすらみえる。
 メンズリング展の会場 © L’ECOLE Van Cleef & Arpels
メンズリング展の会場 © L’ECOLE Van Cleef & Arpels
聖堂のような空間でコレクターのまなざしを追体験
約400点に及ぶ出品作は、イヴ・ガストゥ(1948~2020)という先駆的なデザイン感覚で名をはせたフランスの骨董商兼ギャラリストが蒐集(しゅうしゅう)したプライベートコレクションからなり、彼の嗜好(しこう)が十二分に反映されたものだ。あらかじめ述べておくと、これらは男性に捧げられた指輪が中心ではあるものの、女性専用のもの、ユニセックスのものも混在しており、この男性コレクターのまなざしを追体験する私小説のような展示となっている。それゆえ、彼の人生とともに、この展示を読み解いていくこともあながち的外れではないだろう。
東京ミッドタウン内のデザイン複合施設21_21DESIGN SIGHTの一角をなすギャラリー空間は、窓からの自然光を抑えて、神秘的な妖しい人工光に満たされたモダンな聖堂内を思わせる。鑑賞者は回遊式の動線を自由に往来しながら、以下の五つのテーマ「歴史/ History」「ゴシック/ Gothic」「キリスト教神秘主義/ Christian Mystique」「ヴァニタス(空虚)/ Vanitas」「幅広いコレクション/ Eclecticism」を巡っていく。これらの各タイトルを見ただけで彼の独特な世界観が浮び上ってくるようだ。
 《聖職者の指輪》ゴールド、ダイヤモンド、アメジスト (1900~30年頃)© L’ECOLE Van Cleef & Arpels
《聖職者の指輪》ゴールド、ダイヤモンド、アメジスト (1900~30年頃)© L’ECOLE Van Cleef & Arpels
神に愛を捧げた独身男たちの持ち物
展覧会カタログによれば、イヴ・ガストゥと指輪との出会いは少年期にさかのぼる。幼い頃の彼が、故郷の町、南仏のカルカソンヌで見た宗教行列で、司教の指に輝いていた美しい指輪に魅了され、それに接吻(せっぷん)するために何度も列に並んだという逸話は、まるで映画のワンシーンのように印象的だ。20世紀を生きたフランス人の目利きがどんな体験を通じて、指輪に関心をもったのかを知る上で興味深い。
「キリスト教神秘主義」のコーナーでは、彼が少年時代に憧れた《司教の指輪》や《聖職者の指輪》の実物が展示され、コレクションの原点を示している。司教をはじめ、キリスト教指導者が身につける指輪は、彼らが聖職に就く儀式(叙階式)で授けられる聖具の一つである。それは聖職者の位を示すと同時に、神とその花嫁である教会との象徴的な結婚のしるしとして、二重の象徴性(教会の権威、神との結合)を帯びている。ローマ・カトリック教会では現在にいたるまで、聖職者には独身が義務付けられ、かつ司祭職は男性しか認められていないため、これらの指輪はまさに神に愛を捧げた独身男たちの持ち物である。
 左:《聖職者の指輪》ゴールド、アメジスト (1960年頃) 右:《聖職者の指輪》ゴールド、アメジスト (1900年頃)© L’ECOLE Van Cleef & Arpels
左:《聖職者の指輪》ゴールド、アメジスト (1960年頃) 右:《聖職者の指輪》ゴールド、アメジスト (1900年頃)© L’ECOLE Van Cleef & Arpels
実は、聖職者の指輪については、贅沢(ぜいたく)や虚栄心を避けるため簡素なデザインが好まれる場合もあるが、本コレクションで目を惹(ひ)くのは、金の台座に高価なダイヤモンドや天然真珠を脇石に添え、中心に大きな紫のアメジストを嵌(は)め込んだ豪奢(ごうしゃ)な宝飾品である。その高貴な色彩から最も聖なる宝石とされたアメジストとダイヤの輝き、金の台座に彫金されたイエスの燃える心臓や荊冠(けいかん)の造形は耽美(たんび)的で、これに接吻する少年の追憶はあまりに官能的である。
歴史のロマンと文化の重層性
「歴史」のセクションでは、ガストゥが成長過程で身につけたヨーロッパの教養が披露される。地中海交易で繫栄し、千年以上の歴史を築いた都市国家ヴェネチアの統治者が身につけた《ヴェネチア元首(ドージェ)の指輪》は、ルネサンス時代の原作にもとづく19世紀のレプリカであるが、その規格外の大きさ(正確な記載はないが表面の直径が4センチメートルほど)とそこに刻まれた精緻(せいち)な紋章は彼の絶大な権力を象徴する。開閉式の蓋(ふた)からのぞく内部は空洞で、そこには手紙を封印するための蜜蝋(みつろう)や、宿敵を葬り去るための毒を隠したとも伝えられ、歴史ロマンを感じさせる逸品である。
 《ヴェネチアドージェの指輪》シルバー、カーネリアン 19世紀 © L’ECOLE Van Cleef & Arpels
《ヴェネチアドージェの指輪》シルバー、カーネリアン 19世紀 © L’ECOLE Van Cleef & Arpels
その他にも18世紀後半から流行した新古典主義の美学を体現する古代風カメオ《ナポレオンの横顔の指輪》やインタリオ、またこれらへの反抗として始まったロマン主義の芸術では、中世ヨーロッパのキリスト教世界、騎士道や隠者たちの夢や幻想を描いた作品群。さらにイノシシの牙を中心に埋めこんだ《狩猟の指輪》や、「キリストの血」と称される碧玉(へきぎょく)の一種を用いたものなど、様々な文化的背景から制作された作品が並ぶ。ここに選ばれた指輪は、造形上はまとまりのないジャンルを形成しているが、西洋美術史の流れを知る者にとっては、15世紀から18世紀にかけて王侯貴族や文人たちの間で流行した「驚異の部屋」(ヴンダーカンマー、多種多様な珍品を集めた博物陳列室)の伝統に連なるコレクションとして、西洋文化の重層性をより深く理解できるように仕組まれている。
 《狩猟の指輪》金鍍金シルバー、骨 (19世紀) © L’ECOLE Van Cleef & Arpels
《狩猟の指輪》金鍍金シルバー、骨 (19世紀) © L’ECOLE Van Cleef & Arpels
大衆化され消費された中世イメージ
本展でコレクターの趣味が炸裂(さくれつ)するのは、「ゴシック」と「ヴァニタス」の二つのセクションである。厳密に言うと、このゴシックという名称は美術史的には正確ではない。なぜなら出品された指輪群は、本物の中世美術ではなく、それを霊感源として19世紀に再解釈されたネオゴシック(あるいはゴシック・リバイバル)から、20~21世紀の映画やアニメ作品などを通じて、大衆化し消費された中世イメージまでをも含んでいるからだ。イヴ・ガストゥは来日したことはなかったが、日本のMANGAやKAWAII文化、フィギュア芸術のファンであることを公言してはばからなかった。
 《ガーゴイルの指輪》シルバー (1960~70年頃) © L’ECOLE Van Cleef & Arpels
《ガーゴイルの指輪》シルバー (1960~70年頃) © L’ECOLE Van Cleef & Arpels
彼が精選した《ガーゴイルの指輪》(1960~1970年)をはじめとする数々のゴシックリングには、19世紀フランスの小説家ヴィクトル・ユーゴーの『ノートル=ダム・ド・パリ』にも描かれ、建築家ヴィオレ・ル・デュクが復元を目指したゴシック建築から、20世紀アメリカのマーベル・コミック映画のゴシックホラー世界、そして日本の漫画『ベルセルク』をはじめ、数々のアニメ作品で引用され大衆化されたゴシック趣味が相まみえている。
 《指輪》ホワイトゴールド、ダイヤモンド、アメジスト、 ルビー/リディア・クーテル作 一点もの (2006年頃) © L’ECOLE Van Cleef & Arpels
《指輪》ホワイトゴールド、ダイヤモンド、アメジスト、 ルビー/リディア・クーテル作 一点もの (2006年頃) © L’ECOLE Van Cleef & Arpels
パリで活躍する現代宝飾アーティスト、リディア・クーテルが2006年に制作した《指輪》は十字軍をテーマにしたもので、ホワイトゴールドの台座に深紫のアメジスト、その上にダイヤモンドとルビーをちりばめた騎士の剣が置かれ、指輪の縁には、十字軍への参加を呼びかけるラテン語銘文「民の声は神の声 Vox populi, vox dei」が刻まれている。この幻想的なデザインは、ファンタジーとリアリティの境界を曖昧(あいまい)にする自由奔放さと高価な宝飾品の工芸的伝統を兼ね備えている。
バロックから現代に至る「死」の主題の系譜
 ヴァニタスのテーマのリング 写真:ベンジャミン・チェリー © L’ECOLE Van Cleef & Arpels
ヴァニタスのテーマのリング 写真:ベンジャミン・チェリー © L’ECOLE Van Cleef & Arpels
現世の空しさを意味する「ヴァニタス」セクションは、頭蓋(ずがい)骨をアレンジした指輪(スカルリング)であふれかえっている。死すべき宿命をわれわれに瞑想(めいそう)させる「メメント・モリ/ 死を想(おも)え」の見慣れた主題であるが、この展示が新鮮だったのは、17世紀バロック時代に花開いたテーマが、19世紀イギリスのヴィクトリア朝時代には死者のための《哀悼の指輪》として普及し、さらに現代にまでいたる系譜をつまびらかに示している点だ。
髑髏(どくろ)のイメージは多くの宗教でしばしば死後の世界と関連付けられてきたが、20世紀の2度の世界大戦を経た後に、アメリカのバイカー集団「ヘルズ・エンジェルス」や退役軍人のバイカーたち、音楽界ではロッカーたちがスカルリングを身につけることで、それが社会の反逆者、死を前に自らの勇気とタフさを誇示する自由な精神のエンブレムとなっていた様子を実感させてくれた。1948年に南仏で生まれたイヴ・ガストゥが、こうした欧米若者文化の洗礼を受けたことは容易に想像がつく。
 写真:加藤磨珠枝撮影
写真:加藤磨珠枝撮影
「よそよそしい」異文化との出会い
オランダの現代作家アンドレ・ラッセンが制作した《髑髏の指輪》(1960-70年頃)は、イヴ・ガストゥがパリのギャラリーでも好んで身につけていたものである。吸血鬼の頭蓋骨の牙が黒いヘマタイトを咥(くわ)える独創的なデザインは、コレクションのなかでも最も重要な作品のひとつと言われている。
 《髑髏の指輪》ホワイトゴールド、ヘマタイト/アンドレ・ラッセン作 (1960~70年頃) © L’ECOLE Van Cleef & Arpels
《髑髏の指輪》ホワイトゴールド、ヘマタイト/アンドレ・ラッセン作 (1960~70年頃) © L’ECOLE Van Cleef & Arpels
展覧会の幕を閉じる「幅広いコレクション」では、彼の異文化との出会いが指輪を通じて描かれる。西アフリカの《ドゴン民族の指輪》《ユダヤ教徒の結婚指輪》、チベットの仏像や日本の古銭をあしらった指輪など、異質なものに対する好奇心、フランス的な異国情緒を感じさせるが、それらは依然としてよそよそしい存在であり続けているようだ。こうして、決して広くはないギャラリー空間を一巡りすることで、わたしたちは指輪をめぐる彼の人生の物語をともに終えることになる。
 幅広いコレクション 写真:ベンジャミン・チェリー © L’ECOLE Van Cleef & Arpels
幅広いコレクション 写真:ベンジャミン・チェリー © L’ECOLE Van Cleef & Arpels

美術史家、立教大学教授。愛知県生まれ。専門は西洋中世美術。1992~1996年ローマ大学大学院に留学後、2000年東京藝術大学美術研究科博士後期課程修了、博士(美術)。2016~2017年オックスフォード大学客員研究員として渡英。愛知芸術文化センター愛知県美術館専門委員、奈良美智財団評議員、大塚国際美術館准学術委員、日本学術振興会学術システム研究センター専門研究員などを兼務。現代美術批評も手がける。編著書に『Yoshitomo Nara: Drawings 1984-2013』 (Blum & Poe, Los Angeles) 、『西洋美術の歴史2 中世キリスト教美術の誕生とビザンティン世界』(共著、中央公論新社)、『ヨーロッパ中世美術論集1 教皇庁と美術』(編著、竹林舎)、C・デ・ハメル『世界で最も美しい12の写本―「ケルズの書」から「カルミナ・ブラーナ」まで』(共訳、青土社、第8回ゲスナー賞銀賞受賞)、同『中世の写本ができるまで』(監修、白水社)など。

展覧会名:メンズ リング エキシビション イヴ・ガストゥ コレクション
期間:2022年1月14日(金)~3月13日(日) 会期中無休、予約不要
開館時間:10:00~19:00
会場:21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3
住所:東京都港区赤坂9-7-6 東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン内
お問い合わせ:0120-50-2895 (レコール事務局)