それぞれ異なる学問領域を専門とする研究者や批評家、著述家が、各々の立脚点から同じ美術展を鑑賞、批評するクロスレビュー。今回は、東京・竹橋の東京国立近代美術館に続いて、10月15日から愛知・豊田市美術館でも始まる「ゲルハルト・リヒター展」を取り上げる。ドイツに生まれ、子ども時代にナチス下で第二次大戦を経験し、今年90歳を迎えた現代アート界の巨匠リヒター。彼の画業60年を約120点の作品で概観できる本展を、どう読み解くか。戦争と戦後処理について思索し続けてきた作家、赤坂真理氏と、筑波大教授でアートにも造詣(ぞうけい)が深い精神科医の斎藤環氏の論考を踏まえ、フランス文学者の鹿島茂氏が論評する。
「ドイツ人ゆえの反復行為」の象徴表現が「ビルケナウ」~現代アーティストにとってのタイトルとは
@東京国立近代美術館 鹿島茂(フランス文学者)評
展覧会場を巡りながら全然関係ないことを考えた、と、こう書き出すのが、このARTnews JAPANの定形になってしまったようだが、今回も、ゲルハルト・リヒター展の会場で私の頭に浮かんだのは、「抽象芸術にとってタイトルとはなんだろう?」という疑問だった。
* * *
私の世代にとって、最初の抽象芸術との出会いは、作品そのものとの出会いではなく、作品が引き起こしたスキャンダルとの出会いであった。具体的にいうと、「雪解け」の時代の1962年、モスクワのマネージ展覧会ホールで開催された現代ソヴィエト前衛芸術展を訪れた共産党書記長ニキータ・フルシチョフが「ロバの尻尾で描いたような絵だ」とネイズヴェスヌイの作品を酷評したのをきっかけに、ソ連の前衛絵画が批判にさらされるようになったという「ロバの尻尾事件」である。これがニュース映画などで世界中に拡散され、田舎の中学生だった私も抽象絵画というものの存在を知ったのである。
ことのついでに言っておくと、フルシチョフがネイズヴェスヌイの作品を罵倒(ばとう)するのに使った形容はじつは「ロバの尻尾」ではなく、「犬の糞(ふん)」であったという説もある。「ロバの尻尾」というのは、第一次大戦直前に結成された芸術家集団「ダイヤのジャック」の最左翼グループが名乗った立体未来主義運動体の名称であって、これをネイズヴェスヌイたちがリバイバルし、グループ名にしたという経緯があるのだ。つまり、フルシチョフが「ロバの尻尾」という言葉を使ったとしても、それはネイズヴェスヌイらの抽象絵画の比喩としてでなく、アヴァンギャルド集団の名前としてだったということになるのだが、結局のところ、真相はいまだに不明である。
ちなみに、この「ロバの尻尾事件」には後日譚(たん)がある。フルシチョフは失脚後、失意のうちに死んで「赤の広場」にも埋葬されなかったが、そのフルシチョフの息子からネイズヴェスヌイに対し、ノヴォデヴィチ修道院の父親の墓に建てる記念碑の制作が依頼され、ネイズヴェスヌイはこの提案を受けて、記念碑を制作したという。この記念碑はネットを検索すれば出てくる。
* * *

ゲルハルト・リヒター《ビルケナウ(CR: 937-1)》 2014年 油彩、キャンバス 260×200cm ゲルハルト・リヒター財団蔵
© Gerhard Richter 2022 (07062022)
言葉が不可欠な抽象芸術
さて、リヒターを論ずるのに「ロバの尻尾事件」とはこれいかにといぶかしくお思いの読者がおられるかもしれないので、ここらで軌道修正をしておこう。
私がロバの尻尾を引き合いに出したのは、もし、ロバの尻尾に絵の具をつけて、それが尻尾から飛散する絵の具をキャンバスで受けた絵画があったとしても(実際に事件の後にこれをやった芸術家がいたらしい)、もし、そのロバが昔のアメリカ製ホームドラマ「ミスター・エド」のように(ただし、エドはロバではなく馬だったが)人語を解し、さらに一歩進んで、自分の尻尾作品にタイトルを与えることができたなら、それは立派な抽象絵画となるが、ロバがロバであって人語を解さないなら、それはロバの尻尾作品に終わると言いたかったからにほかならない。つまり、抽象芸術とは、タイトルを付けなければ成り立たない、言葉を不可欠とする芸術であるということなのだ。
これについては、斎藤環氏が展覧会評で、作品にタイトルをつけるという行為の意味についてリヒターがインタビューで「[タイトルを含めて]自分たちが作り出すコンテクストにおいては芸術なのです」と述べたのを引用しながら、こう論じていることが参考になる。
「これらの発言は『ビルケナウ』への注釈としては十分ではないかも知れないが、きわめて示唆的ではある。画家は本作において『コンテクスト』と『タイトル』が決定的な意義を持つことに十分に自覚的だ。これはデュシャン以降、つまり『レディメイド』以降の作家の態度としては、まったく《正統》なものではないだろうか。
現代美術においては『作品』は、すでにそれ自体が自立した美や価値を帯びることを要請されない。作品のタイトル、時代と社会、作家の名前と評価、そうした要素が相互に連携しあうことで、作品の意味や価値が決定づけられる」
ここでは、コンテクストはさておいて、タイトルについてまず考えてみよう。
タイトルがなければ「作品」にならない現代アート
しかし、それには、芸術家が芸術家とし自立したのはいつからなのかということを知る必要があるだろう。
思うに、それは芸術家が作品にタイトルを与える権利を得てからのことだろう。だから、近代以降ということになる。
もちろん、「無題」というタイトルもありうるが、「無題」もまたタイトルの一つであり、タイトルがない「作品」は存在しない。というよりも、芸術家がタイトルを与えない限り、「作品」としては成立しえない。芸術家もまたタイトルの命名権を得てはじめて芸術家として自立したのである。
* * *
言葉やタイトルに呪縛される現代アートの「宿命」
さて、この前提から出発して、現代アートを見てみるとどうなるのだろう?
タイトル命名権の行使という要素がより強まっているのではないか? なぜなら、「現代美術においては『作品』は、すでにそれ自体が自立した美や価値を帯びることを要請されない」のだから、もしタイトル命名権が行使されなければ、作品は作品とはなりえないということになるからだ。すくなくとも、マーケットで作品として流通しえない。
この点についていえば、現代アート以前のアート(つまり、具象的なアート)は、制作者が不明でも、マーケットはある程度の価値を付与することは可能である。しかし、デュシャン以降は、作品にタイトルが与えられていなければ、それは「作品」ではない。たとえばデュシャンの《泉》に「泉」というタイトルが与えられていなければただの便器にすぎない。
これはいったい何を意味するのだろうか?
それは、現代アートが進化すればするほど、アートはタイトルに、さらにいえば言葉に呪縛されるようになったということだ。
いっぱんに、現代アートの歴史は、アートを従属させていたあらゆる要素(歴史、宗教、物語性、現実への参照性をもつ具象、説明的テクスト、その他)を放逐し、それらから自らを解き放ってひたすら純化していく過程であった。ところが、まことに逆説的ながら、ひとつだけ、タイトルだけは放逐することができなかった。というよりも、放逐不可能ゆえに、言葉への依存度がそれだけ深まっているとさえ言える。
そして、それは、現代アートが誕生した時点からの「宿命」であった。なぜなら、誕生したばかりの現代アートは「アブストラクトアート」とか「コンセプチュアルアート」と呼ばれたからである。「抽象」や「概念」ほど、言葉の本質と密接に結びついたものはない。
* * *
言葉と現代アートとの関係を考察する
というわけで、私がゲルハルト・リヒター展の会場を巡りながら考えていたのは、言葉と現代アートとの関係であったのだが、展示されたリヒターの作品はまさにお誂(あつら)え向きというか、この関係について考察を深めさせるものばかりであった。

ゲルハルト・リヒター《モーターボート(第1ヴァージョン)(CR: 79a)》 1965年 油彩、キャンバス 169.5×169.5cm ゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)
とりあえず、初期の代表作の一つである《モーターボート(第1ヴァージョン)(CR: 79a)》(1965年、油彩、キャンバス)から行こう。
日本と同じように高度成長期にあった西ドイツで発行された写真雑誌に掲載された、 避暑地の湖でモーターボートの疾走に歓声を上げる若い男女の風俗写真あるいは広告写真をもとにして描かれたフォト・ペインティングである。
一つ明らかなことは、もとの写真を撮影したカメラマンは被写体となったモーターボート、ないしは歓声を上げる男女に対していささかも「芸術的な感興」を抱いてはいなかっただろうということだ。冷戦の最中に遊び興じる男女にある種の批判的視線はあったかもしれない。あるいは水上を疾走するモーターボートの素晴らしさを強調する写真が撮れたという広告カメラマン的な誇りもあったかもしれない。だが、「これが芸術だ」という意識は絶対になかったはずである。なぜなら、もしそうした意識が感じられたならリヒターはそれをもとに油彩を描こうとは思わなかったはずだからである。いいかえると、もしもとの写真がアンリ=カルティエ・ブレッソンのような「決定的瞬間」の「作品」であったり、あるいはロベール・ドアノーのような「ほほえましい人生のひとこま」を切りとった「作品」であったりしたなら、リヒターは食指が動かなかったにちがいない。つまり、もとの写真が芸術とは無縁のものであるにもかかわらず、その写真を見たリヒターが、「芸術的な感興」とはいえぬまでも「なにかしらの思い」を感じたからこそ、これを「作品」にまでもっていこうという決意が生まれたのだ。すでに作品であるものをふたたび作品にするのはパロディという別な方法に依るしかない。
タイトル自体は無意味、命名したことに意味がある
この意味で、《モーターボート(第1ヴァージョン)(CR: 79a)》が「モーターボート」と命名されていることはいかにも象徴的である。つまり、それはタイトル自体にも意味はなく、ただ、命名権そのものが強調されているのであり、タイトルではなく命名権それ自体が浮き上がってくるということなのだ。
《パーティー》(1963年)、《8人の女性見習看護師(写真ヴァージョン)》(1966年/1971年)も同じである。芸術写真ではない「ただの写真」をリヒターが見た瞬間に「感じたもの」が重要であり、写真そのものには重要さはない。換言すれば、多くの写真の中からそれらの写真をリヒターが選びだし、特権化し、それをフォト・ペインティングにした(あるいはそれを写真に撮った)ということ自体が「芸術性」の根拠となるのだが、じつは、それだけでは足りない。リヒターがそれらに「タイトル」を与えるという行為がなければ、作品は作品とならない。ただし、これもまたそうだが、それらのタイトルそのものには意味はない。《モーターボート》《パーティー》《8人の女性見習看護師》といったタイトルをリヒターが与えたということの方に意味があるのだ。
しかし、こういうと当然、次のような反論も出てくるだろう。リヒターが作品のもとにした写真は広告写真や風俗写真ばかりではなく、自身が撮影した家族のプライベート写真も多いではないか、ならば、それらの写真にも意味はないのか、というものである。
これに対しては、こう答えるしかない。もちろん、撮影時にはなんらかの意味(ある種の感興なり情動)はあっただろう。しかし、リヒターが家族写真をもとにして作品をつくりあげた時点で、その意味は消えた。代わって、家族写真を見たときのリヒターの心の動きが浮上する。そして、その代置はリヒターが命名権を行使したときに決定的なものとなる。
この意味でとても示唆的であるのは、《カラーチャート》シリーズと《アブストラクト・ペインティング》である。

ゲルハルト・リヒター《4900の色彩(CR: 901)》 2007年 ラッカー、アルディボンド、196枚のパネル 680×680cm パネル各48.5×48.5cm ゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)
たとえば、《カラーチャート》について、画材屋に並んでいたカラーチャートを見たときのことをリヒターはこう述べている。「これよりも美しいものを自分で作ることなんてできない! すでに完璧な絵画なんだから」
また、《アブストラクト・ペインティング》は、「自身のパレットにたまたま載っていた絵具を、あるいは絵画の一部を撮影して、その細部を拡大して描くという」技法である。
すなわち、キャンバスに向かって、なにかしらの絵を描こうとしていたリヒターは、キャンバスに描かれた絵よりも、そのための準備としてパレットの上で混ぜた絵の具のほうが美しいと感じて、それをそのまま作品にすることにしたというわけだ。
いずれにしても、「作品」は、対象となるものに対して、「美しい」という感動ないしはなにかしらの情動を覚えた瞬間のリヒターの心の状態そのものにある。よって、これを写真に写し取ったのだ。
「命名権の行使」のために介在する決定的なジャンプ
だが、ここで素朴な疑問が起こる。リヒターはなぜ写真に撮るということ自体を「作品」とせず、撮った写真をもとにこれをもう一度油彩で描いて、それを「作品」としたのかということだ。写真で撮っただけでは、それは写真家の「作品」としては成立しえても、画家の「作品」としては不十分と感じたからなのだろうか?
ここでもまた、風俗写真ないしは広告写真としてのモーターボートの写真と、リヒターの作品としての《モーターボート》との関係、あるいは家族写真と、リヒターの作品としての《エマ(階段上のヌード)》との関係と同じものがあらわれてくる。
つまり、カラーチャートやパレットの上の絵の具に感動してそれを撮影した写真と、それをもとにして油彩で描かれた「作品」との間には、「命名権の行使」のための決定的なジャンプが介在し、これが作品化行為そのものとなっているのだ。
この関係をより露骨に示したものが、実際の写真の上に絵の具を塗るという「オイル・オン・フォト」の、タイトルとして日時を冠した一連の作品である。
写真と油彩の往還作業

ゲルハルト・リヒター《1998年2月14日》 1998年 油彩、写真 10.0×14.8cm ゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)
この「オイル・オン・フォト」については、赤坂真理氏が次のように述べているのが参考になる。
「最初にリヒターの作品を図版集で見た時、最初に目を引かれたのは、スナップ写真に絵の具を置いたものだった。その『置き方』、その『絵の具物質』のことを、何と言ったらよかったろう。異素材コラージュともなんとも言えない印象があり、忘れられなくなった、引かれたというより、それがわたしの心に『入った』。入ってどかせなくなった。
写真を模写することに取り憑(つ)かれているリヒターとしては、写真そのものの上に絵の具を置くことは、めずらしかったのではないか。絵の具はここで、何かを描く媒質というよりは『物質そのもの』として、写真世界に在った。また、わたしの目が吸い寄せられたのは、ことさらにそういう写真だった。絵の具は何かを描くのではなく、あくまで異物として、空間に流し込んで固めたように、置かれていた。それはかつて流動体であり今は固体であり、かつて動いていたし、今でも動きそうでいて、固まってそこに在る、『何か』」
これはまったくの想像だが、リヒターはいつものように家族写真をもとにして、それを眺めたときの情動を、油彩で写真をそっくりになぞることで表現しようとしているうちに誤って写真の上に絵の具をこぼしてしまったのではないか? そして、そのときに写真の上に置かれた絵の具を見て、その絵の具の物質性のほうが自分が描こうとしている油彩よりもはるかに美しいと感じたのではないだろうか? だから、その「写真プラス絵の具」そのものを作品として命名権を行使し、これを「作品」としたのである。
だが、ことはこれで終わらなかったはずだ。おそらく、いや間違いなく、リヒターは写真の上に置かれた絵の具という「作品」を写真に撮らずにはいられなかったはずなのだ。そして、それをもとにして油彩を描こうとしたにちがいない。さらにその油彩を今度は写真に撮り……
この一連の往還作業それ自体に対して命名権を行使して「作品」となったものが《ビルケナウ》であると考えるとわかりやすいのではないだろうか?
命名により反復行為を終わらせ、作品を完成させ、作品から解放される

ゲルハルト・リヒター《ビルケナウ(CR: 937-2)》 2014年 油彩、キャンバス 260×200cm ゲルハルト・リヒター財団蔵
© Gerhard Richter 2022 (07062022)
もとになったのは、1944年夏にアウシュヴィッツ強制収容所でゾンダーコマンド(特別労務班)によって撮影された4枚の写真である。リヒターはこれに触発され、写真の一枚一枚をスケッチし、次に絵の具で塗り込める。そこには記憶の封印という行為の暗喩があるかもしれない。あるいは、ビルケナウ(白樺の谷)というアウシュヴィッツの別名を比喩するような絵の具の重ね塗りの技法があるのかもしれない。
しかし、真に重要なのは写真→油彩表現→写真→油彩表現という反復行為のほうである。ひとことでいえば、反復行為によってあらわされるものよりも、反復行為そのもののほうに意味がある、より正確にはリヒターがそう考えたのである。なぜなら、それはリヒターが練り上げた芸術表現であると同時に、どこかにドイツ人という出自のからんだ反復強迫的な要素もあったからだ。
だが、だとすると、ここで困ったことが生じる。反復行為をどこで終わらせればいいかという問題が出てくることである。反復行為によってあらわされるものよりも、反復行為そのもののほうに意味があるとすれば、反復行為を終わらせることができなくなってしまうのではないか?
この問題はリヒターにとって、ほとんど解決不能な問題と映ったにちがいない。であるがゆえに、作品化に40年もの年月を要したのだろう。
だが、決断の時は来なければならない。命名権の行使のリミットが寿命という制限によって迫ってきているとリヒターは感じたのだろう。かくて、「ビルケナウ」というタイトルが与えられた。そして、これにより、リヒターはようやく「作品」を完成させると同時に「作品」から解放されたのである。
となると、リヒター芸術にとって、最終的に問題となるのは、やはり命名権の行使の瞬間ということになる。
なぜタイトルは「ビルケナウ」だったのか
ではいったい、リヒターは、命名権の行使という「作品化」の最終段階において、なにゆえに「ビルケナウ」というタイトルを与えたのか?
これについては、斎藤氏に一つの解答がある。
絵画というものは、基本的に隠喩という象徴表現と神話性が高いとされる。「この絵は究極的には何を意味しているのか?」という問いかけに答えるのが象徴的なタイトルを与えるということ、つまり隠喩による命名権行使ということだ。
だが、この隠喩による命名権行使には一つの問題がある。
それは「過剰な象徴化がしばしば現実から乖離(かいり)してしまうという点だ」(斎藤氏)。ようするに、隠喩というかたちで象徴化されることが繰り返されるうちに、もとになった現実のイメージは陳腐化し、記号として流通するだけで何のインパクトももたないものになってしまうということである。
現代芸術というものは、こうした隠喩に基づく命名権の行使を拒否したことに始まる。デュシャンの《泉》が典型だ。

ゲルハルト・リヒター《ビルケナウ(CR: 937-3)》 2014年 油彩、キャンバス 260×200cm ゲルハルト・リヒター財団蔵
© Gerhard Richter 2022 (07062022)
では、隠喩ではない命名権の行使にはどのようなものがありうるのか?
部分によって全体を表現する換喩に基づく命名権の行使が一つの方法であると斎藤氏はいう。
「この[ビルケナウという]画面単体では、本作の価値は完結しない。むしろ本作は、制作のプロセスとコンテクスト、さらに言えば事後的な批評やナラティブの集積によって補完されることで、はじめてその真価を発揮するのである。
その意味で、本作は『ホロコースト』を象徴するような『全体』ではない。プロセスとコンテクストによってホロコーストに接続している『部分』でしかない。その意味でリヒターは、本作を『換喩』として成立させることに腐心していたとすら思われる。自身のスキルと名声とを総動員して、『リヒターのビルケナウ』が、ただちにホロコーストを意味するような文脈を創り上げるということ」
ふーむ、ほぼ正解のような気がするが、少し違うような気もする。
「ビルケナウ」というタイトルは「部分」か?
どこが違うのかというと、それは斎藤環氏が「ビルケナウ」というタイトルを、制作のプロセスやコンテクスト、あるいは後的な批評やナラティブの集積と「同資格」で換喩と捉え、「全体に対する一部」と見なしているように思えることだ。
これは、現代芸術においては、タイトルをつけるという命名権の行使のみが「作品化の完了」を保証するというわれわれの立場とは異なる。
たしかに、「ビルケナウ」は、地名という部分によってホロコーストという全体を表現する換喩ではある。また、タイトルも、プロセスやコンテクストと同じ資格で作品という全体を構成する部分にすぎないという見方にも道理はある。
だが、「ビルケナウ」というタイトルは、果たして、そうした「部分」にすぎないのだろうか?
私は先に、「モーターボート」を引き合いに出して、リヒター芸術にとって、タイトルそのものよりも(それはむしろ無意味だ)、タイトルを付けるという命名権の行使のほうが重要だといった。だとすると、ここは「ビルケナウ」ではなく、意味をほとんど欠いた日時がタイトルでもよかったことになるが、現実には「ビルケナウ」という、ある種の強い意味をもったタイトルがつけられたのである。
では、その意味とは何なのか?

ゲルハルト・リヒター《ビルケナウ(CR: 937-4)》 2014年 油彩、キャンバス 260×200cm ゲルハルト・リヒター財団蔵
© Gerhard Richter 2022 (07062022)
「ドイツ人ゆえの永遠の反復行為」を象徴的に示すタイトル
「ビルケナウ」とは、リヒターにとっては、終わらせることのできない反復強迫的な永遠の反復行為の隠喩、つまり象徴表現ではないのだろうか? 「ビルケナウ」が「アウシュヴィッツ強制収容所でゾンダーコマンドによって撮影された4枚の写真」を象徴する隠喩的なタイトルなのではない。「アウシュヴィッツ強制収容所でゾンダーコマンドによって撮影された4枚の写真」を見たことがきっかけになり、おそらくは自身がドイツ人であるがゆえにほとんど反復強迫的に自動的に開始されてしまったリヒターの永遠の反復行為を象徴的に示すのが「ビルケナウ」というタイトルなのではなかろうか?
つまり、「ビルケナウ」は換喩ではなく、むしろ隠喩なのである。
タイトルの命名権の行使のみが、現代アーティストに残された唯一の芸術的権能だとするならば、やはり、リヒターが、長い逡巡(しゅんじゅん)のすえに命名権を行使して「ビルケナウ」というタイトルをつけたことの意味は思っているよりもはるかに大きいのである。

フランス文学者。元明治大学教授。専門は19世紀フランス文学。1949年横浜市生まれ。1973年東京大学仏文科卒業。1978年同大学大学院人文科学研究科博士課程単位習得満期退学。元明治大学国際日本学部教授。1991年『馬車が買いたい!』(白水社)でサントリー学芸賞、2000年『職業別パリ風俗』で読売文学賞評論・伝記賞。膨大な古書コレクションを持つ古書マニア。東京都港区に書斎スタジオ「NOEMA images STUDIO」を開設。書評アーカイブサイト「ALL REVIEWS」主宰。『渋沢栄一 上下』(文藝春秋)、『渋沢栄一「青淵論叢」 道徳経済合一説』(講談社)、『渋沢栄一: 天命を楽しんで事を成す』(平凡社)など渋沢栄一に関連する著作も多い。近著に『日本が生んだ偉大なる経営イノベーター 小林一三』(中央公論新社)、『フランス史』(講談社)『失われたパリの復元-バルザックの時代の街を歩く-』(新潮社)など。最新刊は『稀書探訪』(平凡社)。著書一覧はこちら。(顔写真は鈴木愛子氏撮影)

展覧会名:ゲルハルト・リヒター展
会場:豊田市美術館(愛知県豊田市小坂本町8丁目5番地1)
会期:2022年10月15日(土)~2023年1月29日(日)
開館時間:10:00~17:30(入場は17時まで)
休館日:月曜日(ただし2023年1月9日は開館)、2022年12月28日~2023年1月4日
料金(当日券):一般:1,600円、高校・大学生1,000円
(前売り券):一般:1,400円、高校・大学生:800円、中学生以下無料
販売場所:豊田市美術館(9月4日まで)、T-FACE B館2階インフォメーション(10月14日まで)、オンライン(10月14日まで)
※オンラインチケットは100円割引、20名以上の団体は200円割引(他割引との併用不可)
※豊田市内在住または在学の高校生、豊田市内在住の75歳以上、障がい者手帳をお持ちの方(介添者1名)は無料(要証明)
※その他、観覧料の減免対象者及び割引等については豊田市美術館へお問い合わせください。
公式サイト:https://richter.exhibit.jp/
※東京・東京国立近代美術館での展示は2022年6月7日(火)~10月2日(日)で終了


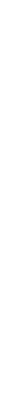
 ゲルハルト・リヒター《エラ(CR: 903-1)》 2007年 油彩、キャンバス 40×31cm 作家蔵© Gerhard Richter 2022 (07062022)
ゲルハルト・リヒター《エラ(CR: 903-1)》 2007年 油彩、キャンバス 40×31cm 作家蔵© Gerhard Richter 2022 (07062022)









