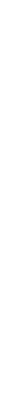それぞれ異なる専門領域を背景に活躍する研究者や著名人が、各々の立脚点から同じ美術展を鑑賞、批評するクロスレビュー。第3回は、京都市京セラ美術館で6月5日まで開催中の「森村泰昌:ワタシの迷宮劇場」を取り上げる。他者に扮して撮影したセルフポートレートで知られる森村の、1984年以来のインスタント写真約800点を軸にした展覧会だ。ロボット学者の石黒浩・大阪大教授と、文化社会学者の谷本奈穂・関西大教授による批評を踏まえて、フランス文学者の鹿島茂が読み解く。
「森村泰昌:ワタシの迷宮劇場」~時代様式が変わっても森村アートは自立している
京都市京セラ美術館 鹿島茂(フランス文学者)評
森村泰昌の「ワタシの迷宮劇場」を観(み)ながら、常に頭に浮かんでいたのは、パスカルの「パンセ」のこんな言葉だ。
「《わたし》とはなんだろう?(中略)
ある女性をその美貌(びぼう)のゆえに愛している者は、その女性を愛していると言えるだろうか? 否である。なぜなら、もし天然痘が流行して、その女性を殺さずに美貌を殺したとすると、その男は女性をもう愛することはないからだ。
また、人がわたしの判断力や記憶力ゆえにわたしを愛したとするなら、その人はわたしを愛したと言えるだろうか? なぜなら、わたしは、わたし自身を失うことなくそうした性質を失う可能性があるからだ。このように、その《わたし》というものが体の中にもなく、魂の中にもないとすると、それはいったいどこにあるのだろうか?」(『パスカル パンセ抄』拙訳、飛鳥新社)
たしかにパスカルのいう通りで、「わたしとはなんだろう」と考え出すと、わけがわからなくなるのだが、しかし、「ワタシの迷宮劇場」を観たことにより、一つの答えが見つかったような気もするのだ。
 森村泰昌《ワタシの迷宮劇場 M002》(1994-95年頃)© Yasumasa Morimura(写真はすべて京都市京セラ美術館提供)
森村泰昌《ワタシの迷宮劇場 M002》(1994-95年頃)© Yasumasa Morimura(写真はすべて京都市京セラ美術館提供)
顔こそがワタシの自己同一性を保証する
意外かもしれないが、それは、「ワタシとは顔である」ということだ。顔こそが「ワタシ」が「ワタシ」であることの自己同一性を保証する要因なのである。
だが、こういうと、パスカルの言っているように、病気なり事故なりで顔がまったく変わってしまった人はどうするのだという反論が出てくるだろう。またメイクや美容整形で顔を大きく変えてしまうことも可能なのだから、顔は自己同一性の保証にはならないという考えもありうる。こうした反論に対してはこう答えよう。病気なり事故なり、美容整形なりで変わってしまった顔をもっているわたしがわたしなのだと。いいかえれば、顔がわたしに所属するのではなく、わたしが顔に所属するのであると考えると、かなりな程度まで、わたしとはなにかという問いに答えたことになるのではないだろうか?
 右が、「なりきり」メイクをしている森村の映像。森村泰昌《夢と記憶が出会う場所》2022年 🄫 Yasumasa Morimura 撮影:三吉史高
右が、「なりきり」メイクをしている森村の映像。森村泰昌《夢と記憶が出会う場所》2022年 🄫 Yasumasa Morimura 撮影:三吉史高
オリジナルに「なりきること」に最大限の努力
森村泰昌の作品は、名作絵画や名作映画、あるいは名作写真や決定的瞬間の写真の中に入りこんで、そこに描かれたり写されたりしている人物になりきることを目的としている。展覧会場に設置されたコーナーでは、森村泰昌が自分のアトリエで延々と「なりきり」メイクをしている映像が流されているし、「なりきり」のために使われた衣装も展示されている。メイクにおいても衣装においても、オリジナルにできる限り似るように最大限の努力が払われていることはまちがいない。
コメントを寄せられたお二方も、この「他者になりきること」にまずは注目している。
ロボット研究家の石黒浩氏は、森村氏の「ひとりの人間の中に分け入れば、多種多様な『ワタシ』が入り組みあい迷宮をなしている」という言葉に反応し、次のように記している。
「私自身も、自分以外の存在になるためのアバターの研究をしている。アバターとは遠隔操作で動かすロボットやCGキャラクターで、それに乗り移って人と関わることができる。アバターの姿形が、自分に似ていれば自分になれるし、誰か他人に似ていれば他人になったような気分になることができる。また、かわいいキャラクターの姿形を選べば、気分までかわいいキャラクターになって、何か生まれ変わったような気分で人と関わることができるのである」
 森村泰昌《ワタシの迷宮劇場 M158》(1994年)© Yasumasa Morimura
森村泰昌《ワタシの迷宮劇場 M158》(1994年)© Yasumasa Morimura
森村アートが時代に「追い越される」との考えは早計
また、コスプレや美容整形などの社会現象の研究者である谷本奈穂氏も「他者になりきること」に熱中する現代に注目し、今回の展覧会の眼目として挙げられている「何者かに成り代わることで自己を解体し、一個人における複数の顔を露呈する森村の表現」が、広範な社会現象として多くの人に共有されていることを指摘している。コスプレ素材あるいは加工アプリを使うなら、自分ではないものになりきることは可能だし、それに快楽を感じている人も思っているよりもはるかに多いのだ。
さらに、谷本氏は、この「他者になりきること」という欲望がむしろ平俗化し、いや、平俗化しすぎたことにより、別の次元の現象がそこから生じていることを明らかにしている。
「今では『一人の体の中に複数の《ワタシ》がいる』というのは、芸術家が可視化するまでもなく、多くの人が文化の中で実践していることである。むしろそれ以上に、ワタシが一つの身体に内在するものではなくなっていることが重要な変化かもしれない。 現実空間で/ウェブ空間で/現実とウェブの溶け合った空間で、ワタシはすでに複数の身体性を持つ存在なのである」
谷本氏はこの最後の「複数の身体性」に注目し、社会はたんに森村アートにキャッチアップしてきたばかりか、それを超えようとしていると指摘する。
「森村さんのアートが、一つの身体の中にある複数の自己を表現してきたとすれば、現代の文化現象は、複数の空間でそれぞれの(複数の)身体が存在し、そのことで自分と他者とのつながりを構築していることに特徴があるだろう。『自己の複数性』ではなく、『身体の複数性』そして身体の複数性を通じた『他者とのつながり』なのだ。何者かになり変わることは、自己を解体するよりむしろ、自己と他者を結びつけることになる。文化社会学の視点からは、現代アートが牽引(けんいん)してきた時代が、近年急激に速度を増してアートに追いつき、追い越したようにも見える」
たしかに、何者かになりきろうとする情熱は、バーチャルな手段を得ることによって、その版図を拡大し、複数の身体性さえ獲得したかのように思えるし、その複数の身体性が他の似たような複数の身体性とコミュニティをかたちづくることはありえるかもしれない。
だが、だからといって、森村アートがそのうちに含まれる「現代アート」がその後衛として後を追ってきた時代そのものによって、追いつかれ、追い越されていると考えるのはいかにも早計である。
 森村泰昌《ワタシの迷宮劇場 M053》(2015年)© Yasumasa Morimura
森村泰昌《ワタシの迷宮劇場 M053》(2015年)© Yasumasa Morimura
アートとして自立する要因は個性?時代様式?
なぜか? それはじつに簡単で、森村アートを始めとする現代アートは、アートだからである。つまり、アートはそれがどんなものであれ、アートとして自立する要因をかならずそのうちに含む。この自立要因があるからこそ、アートはアートとして時代から自立できるのであり、その時代が過ぎ去ったとしてもそれとともに消えてゆくことはないのだ。自立要因があるものがアートとして残り、ないものはエフェメラとして消えてゆくのである。
では、アートをアートとして「残らせる」自立要因とはなんだろう?
アーティストの個性だろうか?
もちろん、それもある。しかし、個性だけでアートが創れるのだったら、世の中はアートだらけになってしまうはずだ。そして、それらが全部「残ってしまった」なら、これはこれで大変なことになる。
しからば、個性ではなく一つの時代様式だろうか?
 森村泰昌《ワタシの迷宮劇場 M187》(1997年頃)© Yasumasa Morimura
森村泰昌《ワタシの迷宮劇場 M187》(1997年頃)© Yasumasa Morimura
これは一見すると突飛(とっぴ)な見方のように思えるかもしれないが決して突飛ではない。なぜなら、どんなに時代を超越しているように見えるアート作品だろうと、決して時代様式を超越することはできないからだ。それは、理性や感覚によって感知できるようなものではなく、後代の人だけが可視化できる集団的な無意識のようなものだから、アーティスト個人はそれを絶対に免れることはできない宿命にあるのだ。
そして、この意味でなら、「現代アートが牽引してきた時代が、近年急激に速度を増してアートに追いつき、追い越したようにも見える」という谷本氏の指摘は当たっている。森村泰昌にも免れることはできない現代アートの時代様式はあり、その時代様式は、2020年代の時代様式によって追いつかれ、追い越されている。これは確かなのだ。
しかし、そのことは森村アートが2020年代時代様式によって追いつかれ、追い越されているということを意味しない。なぜなら、森村アートはアートとして自立しているから、それが属する現代アートの時代様式が更新されようと、2020年代の時代様式に追いつかれ、追い越されることはありえないからである。
 森村泰昌《ワタシの迷宮劇場 M132》(2009年頃)© Yasumasa Morimura
森村泰昌《ワタシの迷宮劇場 M132》(2009年頃)© Yasumasa Morimura
アートの本質は引用のアレンジメント
それならば、いったい、森村アートがアートとして自立することを支えているものはなんなのだろう?
これは思っているよりもはるかに解くことが難しい問題である。
だが、ヒントはある。パスカルの『パンセ』の別の断章を引用しよう。
「あいつは新しいことは何一つ言っていない、などと非難しないでほしいと思う。というのも、わたしの場合、新しいのは内容の配置の仕方だからだ。(中略)同じように、わたしとしては、あいつは昔から使われている言葉を使っていると言ってくれるほうがうれしいと思う。同じ言葉でも異なった並べ方をすると別種の思想が生まれるのと同様に、同じ思想であっても、それが異なった並べ方をされると、別の論旨がかたちづくられるものだからだ」
この断章を読んだ現代アーティストで深く頷(うなず)かない者は皆無のはずである。この断章ほど現代アートの本質をついたものはない。すなわち、内容のすべては引用ないしは引用の断片であり、それ自体はいささかもアートを保証しない。アートは引用の仕方ないしは、何を引用してくるかというその思いつきにしか存在しないということがここでは述べられているのだ。
しかし、よく考えると、パスカルは現代アートの本質を予言したわけではない。パスカルはただパスカルが生きて属していた時代の芸術・文化様式、つまり古典主義の本質について語っているだけなのである。なぜなら、古典主義というのは、表現されるべきものはすべてギリシャ・ローマの先人たちが表現し尽くしてしまったのだから、自分たちができることはその引用のアレンジメントしかないという自覚から出発しているからである。
しかし、アートの本質はアレンジメントにしかないという点では一致していたとしても、古典主義と現代アートはやはり異なるものをもっている。
では、その異なるものとはなにか?
 森村泰昌《ワタシの迷宮劇場 M072》(1994年)© Yasumasa Morimura
森村泰昌《ワタシの迷宮劇場 M072》(1994年)© Yasumasa Morimura
写真的引用の現代アート、模写的引用の古典主義
それは、ニコラ・プッサン※とアンディー・ウォーホルを並べてみればよくわかるはずだ。ウォーホルの引用、それは写真的引用だ。プッサンの引用、それは模写的引用だ。現代アートと古典主義の違いはここにある。
では写真的引用と模写的引用の違いはどこにあるのか?
写真的引用は、かならずオリジナルに行き着くことができる。ウォーホルのキャンベル・スープは、たとえキャンベル・スープを写した写真がもとにあるとしてもその写真はキャンベル・スープをオリジナルとしている。
これに対して、模写的引用というものは、その構造においてオリジナルには決して到達しえないようになっている。
模写というのは考えてみれば実に不思議なものである。模写者は現実を写し取るのではなく、現実を写し取ったことになっている芸術作品(絵画その他)を写し取るのである。しかし、現実を写し取ったことになっているその芸術作品もまた、それに先行する芸術作品を模写しているのだ。であるからして、模写は、フランス語でいうミザナビーム(合わせ鏡的な中心紋の技法)のように無限遡行(そこう)するしかない。しかし、無限遡行しても、写し取られたはずのオリジナルな現実に到達することは原理的にありえない。なぜなら、真に手本とすべきギリシャ・ローマの古典作品は発見されていないことが多いし、また、発見されたとしても写し取られたオリジナルな現実は絶対に発見しえないからである。
というわけで、模写者は先行する模写者のアレンジメントのテクニックを模写しているにすぎないのであり、けっしてオリジナルを模写しているのではないということになる。
※ニコラ・プッサン(1594-1665)はフランスの古典主義の画家
 森村泰昌《ワタシの迷宮劇場 M073》(2013年)© Yasumasa Morimura
森村泰昌《ワタシの迷宮劇場 M073》(2013年)© Yasumasa Morimura
写真なのに模写的引用の森村アート
話が広がりすぎてしまった。
森村泰昌に戻ろう。
森村泰昌のアートは現代アートであるがゆえに、その引用の仕方は写真的引用のように見える。事実、森村アートは写真である。
だが、よく考えてみると、森村アートの引用の仕方は写真的引用ではない。それはむしろ模写的引用である。
だが、なぜ、森村アートは写真的引用ではなく、模写的引用といえるのか?
先行する芸術作品(絵画、写真)のアレンジメントのテクニックを模写しているのであって、オリジナルを模写しているのではないからである。
そう、森村アートとは、絵筆や絵の具ではなく、メイクや衣装というアイテムを用いた先行の芸術作品(絵画や写真)のアレンジメントのテクニックの「模写」にほかならないのである。また、今回の展示でも明らかなように、ポラロイドによる数限りない微調整は、複写そのものである。
オリジナルに到達できないミザナビームの感覚
だから、森村アートが模写の対象たる先行作品に漸近線的に近づけたとしても、その先行作品もまた、さらなる先行作品の模写であるから、オリジナルには永遠に到達できない。
そして、このオリジナルには永遠に到達できないというミザナビームの感覚が森村アートの本質の一つである。
森村アートを見たときにだれもが感じる一種の目眩(めまい)のような感覚は、この模写的引用のミザナビームからきている。
だが、森村アートをアートとして自立させている要因はこの模写のミザナビームだけかというと、じつはそうではない。
もしミザナビームだけだったら、それはルネ・マグリットのような作品にはなるが森村アートとはなりえない。
 森村泰昌《ワタシの迷宮劇場 M081》(2008年)© Yasumasa Morimura
森村泰昌《ワタシの迷宮劇場 M081》(2008年)© Yasumasa Morimura
森村アートを自立させる森村自身の「顔」
では、森村アートをアートとして自立させているのは何なのだろう。それは、森村自身の「顔」なのである。そう、いくら入念にメイクを施し、衣装をそっくりにつくって模写を完璧にしても、顔だけは先行作品に描かれた(写された顔)ではない。森村自身の顔なのである。森村自身の顔が、永遠に掴(つか)まえられないミザナビームの深遠の彼方から突如立ち現れてくる。これが森村アートの本質なのである。
森村アートの完璧に近い模写はただただ、ミザナビームの深遠に沈んだまま永遠に捉えられないオリジナルに代わって、森村の顔という「偽のオリジナル」を現出させるためにのみ奉仕している。
そう、すべての問題は顔にあるのであって、森村アートにおいては、無限の模写の末に現れてくる顔こそが、「ワタシ」が「ワタシ」であることを保証すると同時に、アートとして自立する要因となっているのである。
森村アートにおける徹底的模写という行為と、鏡に写った(あるいはポラロイドに撮られた)森村自身の顔。しかも、この森村自身の顔にこそ森村が探し求める「ワタシ」は付属しているのである。「ワタシ」を付属させた森村の顔がある限り、どんなに時代様式が変わっても、森村アートは決して時代に乗り越えられることはないのである。
 「なりきり」のための衣装なども展示されている。森村泰昌《衣装の隠れ家》2022年 🄫 Yasumasa Morimura 撮影:三吉史高
「なりきり」のための衣装なども展示されている。森村泰昌《衣装の隠れ家》2022年 🄫 Yasumasa Morimura 撮影:三吉史高

フランス文学者。元明治大学教授。専門は19世紀フランス文学。1949年横浜市生まれ。1973年東京大学仏文科卒業。1978年同大学大学院人文科学研究科博士課程単位習得満期退学。元明治大学国際日本学部教授。1991年『馬車が買いたい!』(白水社)でサントリー学芸賞、2000年『職業別パリ風俗』で読売文学賞評論・伝記賞。膨大な古書コレクションを持つ古書マニア。東京都港区に書斎スタジオ「NOEMA images STUDIO」を開設。書評アーカイブサイト「ALL REVIEWS」主宰。『渋沢栄一 上下』(文藝春秋)、『渋沢栄一「青淵論叢」 道徳経済合一説』(講談社)、『渋沢栄一: 天命を楽しんで事を成す』(平凡社)など渋沢栄一に関連する著作も多い。近著に『日本が生んだ偉大なる経営イノベーター 小林一三』(中央公論新社)、『フランス史』(講談社)『失われたパリの復元-バルザックの時代の街を歩く-』(新潮社)など。著書一覧はこちら。
最新刊は『稀書探訪』(平凡社)。同書に収められた稀覯(きこう)本コレクションの数々は現在、東京・日比谷図書文化館で、特別展「鹿島茂コレクション2『稀書探訪』の旅」として7月17日まで展示中。
(顔写真は鈴木愛子氏撮影)

展覧会名:京都市京セラ美術館開館1周年記念展「森村泰昌:ワタシの迷宮劇場」
会場:京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ
会期:2022 年 3 月 12 日(土)~6 月 5 日(日)
開館時間:10:00~18:00(最終入場は 17:30)
休館日:月曜日(祝日の場合は開館)
料金:一般:2,000(1,800)円、大学・専門学校生:1,600 (1,400)円、高校生:1,200(1,000)円、 小中学生:800(600)円、未就学児無料
※( )内は前売・20 名以上の団体料金。
※e-tix からの購入で各当日料金から 100 円引き。
※京都市内に在住・通学の小中学生は無料。
※障害者手帳等をご提示の方は本人及び介護者 1 名無料。確認できるものをご持参ください。
前売券:美術館ウェブサイトで販売中