それぞれ異なる学問領域を専門とする研究者や批評家、著述家が、各々の立脚点から同じ美術展を鑑賞、批評するクロスレビュー。今回は、東京・竹橋の東京国立近代美術館で、10月2日まで開催中の「ゲルハルト・リヒター展」を取り上げる。東ドイツに生まれ、子ども時代にナチス下で第二次大戦を経験し、今年90歳を迎えた現代アート界の巨匠リヒター。彼の画業60年を約120点の作品で概観できる本展を、筑波大教授でアートにも造詣(ぞうけい)が深い精神科医の斎藤環氏はどう読み解いたか。
ビルケナウ——アウシュビッツの「換喩」として——
@東京国立近代美術館 斎藤環(精神科医)
リヒターは、マルコ・ブラウによるインタビューで次のように述べている。「私の絵画《ビルケナウ》が批判を浴びたときにも、同じことを考えました。その批判である人がこう書いていました。『リヒターは、関心を引こうとしてそのタイトルをつけたのであって、絵はまったくそれと関係がない』。これはぜんぜん違います。タイトルをつけるということは正当なことです。作品を見る人に理解のための方向性、つまりひとつのきっかけを与えるためなのですから。作品だってそのように作られているのです。主題が既にもう絵画の性質を決めているのであって、作品のタイトルはその結果として生じるのですからね」
あるいは、絵画についてはこう述べる。
「絵画は完全に自由になりました。知識や才能、クオリティーを識別する基準からも解放されています。私たちは思うがままになんでもカンバスの上にのせることができるのです。それが芸術。自分たちが作り出すコンテクスト(編集部注:文脈)においては芸術なのです」(いずれもゲルハルト・リヒター、マルコ・ブラウ「音楽を聴くと、イメージが浮かぶ」『ユリイカ ゲルハルト・リヒター 生誕90年記念特集』54巻7号、2022年から)
これらの発言は「ビルケナウ」への注釈としては十分ではないかも知れないが、きわめて示唆的ではある。画家は本作において「コンテクスト」と「タイトル」が決定的な意義を持つことに、十分に自覚的だ。これはデュシャン以降、つまり「レディメイド」以降の作家の態度としては、まったく〈正統〉なものではないだろうか。
現代美術において「作品」は、すでにそれ自体が自立した美や価値を帯びることを要請されない。作品のタイトル、時代と社会、作家の名前と評価、そうした諸要素が相互に連携しあうことで、作品の意味や価値が決定づけられる。実は古典的な名作のほとんども、そのような価値体系と無縁ではないのだが、それでも作品が価値として自立し完結しているはずだという幻想ないし信仰には根強いものがある。しかし、この視点からどれほど「ビルケナウ」を凝視したとして、いかなる意味も見いだせないだろう。

ゲルハルト・リヒター《ビルケナウ(CR: 937-1)》 2014年 油彩、キャンバス 各260×200cm ゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)
“世界的重要作家”が“満を持して描く”“ホロコースト”という文脈
ここで、ごく簡単に「ビルケナウ」の成立過程を振り返っておこう。
本作は1944年8月に、アウシュビッツ=ビルケナウ強制収容所内で、「ゾンダーコマンド」と呼ばれるユダヤ人捕虜によって、内部告発の目的で隠し撮りされた4枚の写真をもとに描かれている。写真には、ゾンダーコマンドたちが野外焼却溝に並べられた死体を焼く様子や、林の中をガス室に向かって歩いていく女性たちの姿が映っている。リヒターは、ディディ゠ユベルマンがこの写真について論じた『イメージ、すべてに抗して』の書評を読んだことを一つのきっかけとして、本作の構想に至ったという。
作品が制作されたのは2014年。当時、既にリヒターの作家としての名声はゆるぎないものがあり、「ドイツ最高峰の画家」にして、世界的にも最重要の作家の一人とみなされていた。旧東ドイツのドレスデンに生まれ、西ドイツで美術教育を受け、フォト・ペインティングやグレイ・ペインティング、アブストラクト・ペインティングなど、多彩なスタイルの作品を制作してきた画家。その彼が満を持したかのように描くホロコースト。本作の鑑賞に際しては、以上のようなコンテクストをふまえておく必要がある。これを言い換えるなら、仮に無名時代のリヒターがいきなり本作を制作したとしても、批評界からは黙殺の憂き目にあっていた可能性が高い、と筆者は考える。作家の名声を光背にすることで、本作は初めてその真価を発揮する。繰り返すが、これはデュシャン以降、ウォーホール以降の現代美術にあっては、きわめて〈正統〉な価値観である。

ゲルハルト・リヒター《ビルケナウ(CR: 937-2)》2014年 油彩、キャンバス 各260×200cm ゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)
“油絵と、同サイズのコピーの配置”も作品の価値
それではあらためて問おう。「ビルケナウ」とは何なのか。
清水穣によれば、リヒターは過去に何度かアウシュビッツを主題とした絵画を制作しようと目論(もくろ)んで挫折した経緯があるという(清水穣「ビルケナウの鏡」ユリイカ前掲号)。一度目はアウシュビッツが「悲惨のポルノ」として消費されることを皮肉った作品で、まさにアウシュビッツの映像とポルノグラフィーの組み合わせを試みようとした。しかしこの作品は、中途で制作が放棄されている。1989年のベルリンの壁崩壊後にも作品制作が試みられるが、やはり頓挫している。「ビルケナウ」こそは文字通り三度目の正直として制作され、作家はようやく肩の荷を下ろす。リヒターは「この作品は、私が最終的に片付けねばならない負い目でした」と述べている(ゲルハルト・リヒター、ディーター・シュヴァルツ「対談」『ゲルハルト・リヒター』青幻舎、2022年)。
リヒターは「ビルケナウ」の制作過程を撮影し記録しているが、それによれば彼は、まず4枚の記録写真をカンバスに投影し、グリザイユ(グレースケールで陰影を描き、あとから色を乗せていく技法)で描き写した。さらにその上に、赤、緑、黒、白の絵の具の層を塗り重ね、もとのグリザイユを完全に塗りつぶした。本作でもリヒターは、他のアブストラクト・ペインティングと同様に、スキージ(大きなへら)を駆使している。スキージは絵の具を押し広げると同時に、絵の具を削り取る。その痕跡はコントロールが難しい分、絵画に偶然的要素を与えると考えられ、リヒターは好んでスキージを用いている。絵の具を塗り終わったらそれで完成、ではない。リヒターは4枚の油絵と同サイズのデジタルコピーを作製し、絵とコピーを向かい合わせて、正対するように配置する。言うまでもないが、この制作プロセスもまた、「ビルケナウ」の価値に含まれている。

「ビルケナウ」が展示された部屋。油絵4点(右手)とデジタルプリント4点(左手)が正対して配置され、その間に大きな鏡がある 写真提供:ゲルハルト・リヒター展 © Gerhard Richter 2022 (07062022)撮影:山本倫子
リヒターが試みたアウシュビッツの「換喩化」
それにしてもリヒターは、「ビルケナウ」で何を試みたのだろうか。
筆者の考えはこうだ。彼は「ビルケナウ」によって、アウシュビッツの換喩(かんゆ)化を試みたのだ。ならば、換喩化とは何か。以下に説明しよう。
言語学者のローマン・ヤコブソンは比喩表現を「隠喩」「換喩」「提喩」に分類した。本題とは直接関係がない「提喩」については省略するが、用例で示すなら、「鳩」で「平和」を、「ライオン」で「王」を示すような修辞表現が隠喩、「帆」で「帆船」を、「王冠」で「王」を示すのが換喩、である。隠喩では、「ライオン」全体が「王」全体を示している。なんらかの類似性(百獣の王=王国の頂点)や象徴性にもとづいて、全体で全体を示す比喩が「隠喩」である。一方、「帆」という部分で「帆船」全体を示すのが換喩である。「青ひげ」や「赤頭巾」のように、身体の一部や付属物で人物を示すのも換喩表現である。
絵画は基本的に、隠喩と象徴表現に親和性が高い。古典的な絵画は象徴表現を理解していないと意味が取れないとすら言われる。近代でもルドン、モロー、クリムトらの「象徴主義」はよく知られているし、さらに下って「ゲルニカ」をはじめとするピカソの諸作品などにも象徴性は顕著に見て取れる。私たちが絵画を見て「これはどういう意味?」と問うのは、絵画の象徴性を問うているのである。
しかし現代美術は、そうした象徴性や寓意(ぐうい)、意味や物語と決別することを一つの使命としていた。内容よりも形式を重視した抽象表現主義が一つの典型であるが、リヒター自身もその影響下にあったことはよく知られている。
スキルと名声を総動員した文脈の創造
「ビルケナウ」は表面的にはアブストラクト・ペインティングの手法が採用されており、その意味では抽象表現主義に近い印象を与える。決定的に異なるのは、その絵にホロコーストを象徴する「ビルケナウ」のタイトルが採用されている点だ。さらに言えば、その絵の具が何層も塗り重ねられた樹皮(ユベルマン)の下には、大量殺戮(さつりく)を証言する写真の模写が存在するということ。繰り返すが、本作においてはこうした「コンテクスト」がきわめて重要なのである。
本作の表層だけを眺めて、ホロコーストの主題を読み取ることは難しい。もちろん抽象画としての強度はすさまじく、画家リヒターの熟練の技巧は存分に発揮されている。そう、ポロックのドリップ・ペインティングが、「偶然」などより作家の「ドリッピングの技巧」によって成立していたように。しかしそれでも、この画面単体では、本作の価値は完結しない。むしろ本作は、制作のプロセスとコンテクスト、さらに言えば事後的な批評やナラティブの集積によって補完されることで、はじめてその真価を発揮するのである。
その意味で、本作は「ホロコースト」を象徴するような「全体」ではない。プロセスとコンテクストによってホロコーストに接続している「部分」でしかない。その意味でリヒターは、本作を「換喩」として成立させることに腐心していたとすら思われる。自身のスキルと名声とを総動員して、「リヒターのビルケナウ」が、ただちにホロコーストを意味するような文脈を創り上げるということ。

ゲルハルト・リヒター《ビルケナウ(CR: 937-3)》2014年 油彩、キャンバス 各260×200cm ゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)
過剰な象徴化による「反復」という副作用
戦争や惨劇は、それ自体が隠喩化、象徴化のモメント(編集部注:契機)をはらんでいる。東日本大震災後に生まれたおびただしいアート、映画、小説、詩などを想起してみよう。それ自体は創造性の自然な発露でもあり、文化のレジリエンス(同:回復力)という点からも価値があった。
問題があるとすれば、過剰な象徴化がしばしば現実から乖離(かいり)してしまうという点だ。「9.11」が「イラク侵攻」という象徴的誤作動をひきおこし、象徴化された「フクシマ」が、過激な反原発論者による風評被害を喚起してしまったように。さらに言えば、特権的な象徴化は、予防よりも反復を呼び込んでしまう懸念がある。トラウマが反復強迫として別の外傷を呼び込んでしまうように。それは悲劇全体を代理表象する〈かのような〉別の全体性、すなわち象徴がもたらす副作用なのである。
ホロコーストは表象不可能である。そう繰り返し述べられてきた。しかしそれでも、われわれはホロコーストの象徴化をどこかで希求してはいなかったか。いまなお制作され続けるホロコーストを巡る映画、小説、アートにおいて、そうした欲望の痕跡を見ずに済ますことは難しい。しかし繰り返すが、象徴化には副作用がある。「恐れつつも反復を引き寄せる」という副作用が。
東日本大震災が換喩化された事例として、私はACジャパンによる公共広告「あいさつの魔法。」を例に挙げたことがある(斎藤環「巻頭言」『現代思想2011年9月臨時増刊号 総特集=緊急復刊 imago 東日本大震災と〈こころ〉のゆくえ、2011年)。子供たちに挨拶(あいさつ)の大切さを啓蒙(けいもう)するための広告は、震災と何のつながりもない。しかし、発災直後に企業CMが自粛された結果、繰り返し放映されたあの広告は、繰り返し接したという事実によって「震災の換喩」として記憶されたのである。まったく同じプロセスによって、「著名な画家リヒターがホロコーストをテーマに制作した」という事実さえあれば、「ビルケナウ」はホロコーストの換喩たりうるのである。

ゲルハルト・リヒター《ビルケナウ(CR: 937-4)》2014年 油彩、キャンバス 各260×200cm ゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)
「換喩化」によって象徴化の有害性を解毒
リヒターの周到さは、本作のデジタルコピーを正対させることで作品を完成させたことにおいても発揮されている。作品の唯一性、オリジナル性にもまた、「象徴化」の契機がひそんでいることに、リヒターは自覚的だったのだろう。この身ぶりにおいても、リヒターが——その言葉を用いるかどうかとは別に——「換喩化」を企図していたことが示唆されている。
象徴化の有害性に「無意味」で対抗する運動には限界があった。しかしリヒターは、無意味ではなく「換喩化」というベクトルを導入した。彼の画業を振り返るならば、例えば写真を描き写し修正を加えた「フォト・ペインティング」にしても、写真の「部分化」という意味で換喩化のレッスンだったのではないだろうか。ただしそれは、意図を持った換喩化ではない。「作家の意図」もまた、別の全体性を呼び込んでしまう可能性があるからだ。リヒターの換喩化はどこまでも「偶然性」にひらかれている。換喩は偶然の作用のもと、別の換喩に連結し、オープンエンドの換喩的連鎖をもたらすだろう。象徴はかくして解毒されるが、換喩がどのような「現実的効果」を発揮するかは今後の課題となるだろう。
最後にリヒターの教訓をひとつ引用して擱筆(かくひつ)する。
「偶然を整えなくてはなりません。そうして初めて何かが生み出されるのです」(前掲の、ディーター・シュヴァルツとの対談から)

精神科医、筑波大学教授。1961年、岩手県生まれ。90年、筑波大学医学専門学群環境生態学卒業。医学博士。爽風会佐々木病院精神科診療部長(87年から勤務)を経て、2013年から筑波大学医学医療系社会精神保健学教授。また、社団法人・青少年健康センター会長として「実践的ひきこもり講座」「ひきこもり家族会」を主宰している。専門は思春期・青年期の精神病理、精神療法、および病跡学。2010年度に『関係の化学としての文学』(新潮社)で日本病跡学会賞受賞。2013年、『世界が土曜の夜の夢なら ヤンキーと精神分析』(角川書店)で第11回角川財団学芸賞受賞。著書に『文脈病』(青土社)、『社会的ひきこもり』(PHP研究所)、『ひきこもり文化論』(紀伊國屋書店)、『生き延びるためのラカン』(ちくま文庫)、『ひきこもりはなぜ「治る」のか?』(中央法規出版)、『ひきこもりのライフプラン』(畠中雅子との共著、岩波書店)、『オープンダイアローグとは何か』(医学書院)、『アーティストは境界線上で踊る』(

展覧会名:ゲルハルト・リヒター展
会場:東京国立近代美術館(東京都千代田区北の丸公園3-1)
会期:2022年6月7日(火)~10月2日(日)
開館時間:10:00~17:00(金・土曜は10:00~20:00) ※入館は閉館30分前まで
※9月25日(日)~10月1日(土)は10:00~20:00で開館します。
休館日:月曜日(ただし9月19日、26日は開館)、9月27日(火)
料金:一般:2,200円、大学生:1,200円、高校生:700円
※いずれも消費税込。
※中学生以下、障害者手帳を提示した人とその付添者(1名)は無料。
※本展の観覧料で、同時開催の所蔵作品展「MOMATコレクション」も、入館当日に限り観覧可能。
問い合わせ:050-5541-8600(ハローダイヤル)
公式サイト:https://richter.exhibit.jp/
巡回情報:2022年10月15日(土)~2023年1月29日(日) 豊田市美術館に巡回


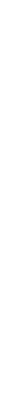
 ゲルハルト・リヒター《エラ(CR: 903-1)》 2007年 作家蔵 油彩、キャンバス 40×31cm © Gerhard Richter 2022 (07062022)
ゲルハルト・リヒター《エラ(CR: 903-1)》 2007年 作家蔵 油彩、キャンバス 40×31cm © Gerhard Richter 2022 (07062022)









