それぞれ異なる学問領域を専門とする研究者や批評家、著述家が、各々の立脚点から同じ美術展を鑑賞、批評するクロスレビュー。今回は、東京・竹橋の東京国立近代美術館で、10月2日まで開催中の「ゲルハルト・リヒター展」を取り上げる。東ドイツに生まれ、子ども時代にナチス下で第二次大戦を経験し、今年90歳を迎えた現代アート界の巨匠リヒター。彼の画業60年を概観できる約120点の作品を、戦争と戦後処理について思索し続けてきた作家、赤坂真理氏はどう見たか。
ともにカルト国家だった国の人間として〜リヒター展の消耗とやすらぎについて~
@東京国立近代美術館 赤坂真理(作家)評
広義の戦争の産物、時代や地域や国家や政治に翻弄(ほんろう)されることの産物。
そのようにわたしはゲルハルト・リヒターのアートを見た。そしてこれは今も続く孤独な戦後処理なのだろうと。
ある大きな戦争の後の余波のことを、国家はいつまでもいちいちは語らない。それが政治や経済その他の条件を今でも決定づけるものであっても。節目に語ることはあっても。共同体や世界にとって大事な演説がなされたとしても――ヴァイツゼッカー演説のような――、日々日常は、語らなくなる。しかしある戦争の影響は、個人の中にずっと続き、その落とした影の下で社会的にも個人的にも生きて次世代を育て、それが染みた世代がまた無意識に同じ作法をするのである。だから、戦争の影響というのは、半永久的だ。

ゲルハルト・リヒター《ビルケナウ(CR: 937-4)》 2014年 油彩、キャンバス 各260×200cm ゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)
個人の中で日々消化せずにおれない戦争の記憶や歴史
人は、自分一人の心の傷でさえ、繰り返し現れ、時に生活を侵食するまでであることを知っている。ましてそれに世界大戦という大量破壊と大量殺戮(さつりく)が絡んでいたなら、その記憶は、体験者から消え去ることはないだろう。幸せな時、楽しい時にさえ現れ、不意に、冷たい異物を呑(の)み込んでいたことを思い出すように、感じるだろう。不意に記憶がよみがえり、冷や水をかけられすべての楽しみが色褪(あ)せてしまうような体験をしたことがある人も多いだろう。そしてそれは周囲に沁(し)みていく。周りにいる者は、なぜかと知らず、その冷たい石のようなものを、自分もいつの間にか内化する。
戦争に、いかにしても反対しなければならない理由があるとしたら、これだけだと、わたしには思える。人間を壊し、人生コースを永遠に変えてしまい、その悲しみ怒りは無自覚にも世代継承されていくからだ。政治、経済、宗教、他のどんな戦争反対の論拠にも、すべてのまことしやかな反証がある。あるいは、それこそが、戦争の理由なのである。
そうして表立って語られることの少なくなった戦後処理が、一人のアーティストの中に、営々と行われていたことをわたしは感じ、重いめまいに近い感銘を受けた。記憶や歴史を昇華するでもない、しかし日々消化せずにはいられない、そのことのエネルギー、そのものを体験する感じで圧倒される。
これは、アートにだけできることかもしれない。物語テキストは、物語に引きずられすぎる。物語こそは、危険な側面があり、それがナチズムという異様な高揚につながったのかもしれないから。第二次世界大戦後ドイツで、たとえば劇作家のブレヒトが物語の構築を警戒して新しい演劇を模索したのは、こういうことだったろう。
* * *

ゲルハルト・リヒター 《2016 年6月8日(8)》 2016年 油彩、写真 16.7×12.6cm ゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)
最初にリヒターの作品を図版集で見た時、最初に目を引かれたのは、スナップ写真に絵の具を置いたものだった。その「置き方」、その「絵の具物質」のことを、何と言ったらよかったろう。異素材コラージュともなんとも言えない印象があり、忘れられなくなった。引かれたというよりそれがわたしの心に「入った」。入ってどかせなくなった。
写真を模写することに取り憑(つ)かれているリヒターとしては、写真そのものの上に絵の具を置くことは、めずらしかったのではないか。絵の具はここで、何かを描く媒質というよりは「物質そのもの」として、写真世界に在った。また、わたしの目が吸い寄せられたのは、ことさらにそういう写真だった。絵の具は何かを描くのではなく、あくまで異物として、空間に流し込んで固めたように、置かれていた。それはかつて流動体であり今は固体であり、かつて動いていたし今でも動きそうでいて、固まってそこに在る、「何か」。(作品群の中には、絵の具を引っ掻〈か〉くなどのリヒター的絵画的要素があるものもある)。
日常に流し込まれて固まった「それ」、それはあまりに異物なため、解釈が追いつかず、異物としてそのまま在り続け、あまりに普通に在り続けるためあたかも無いように日常を暮らせさえしそうなものなのである。

ゲルハルト・リヒター《1998年2月14日》 1998年 油彩、写真 10.0×14.8cm ゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)
ドイツという国は、第二次世界大戦後、そういう街の計画をしたのではないか、と思ってみる。街の真ん中に戦争メモリアルの建物があり、それは基本的には、ドイツを指導したヒトラーとナチスがユダヤ人にどれだけ酷(ひど)いことをしたかという記録である。「忘れない」ということがあまりにただのお題目と化している我が国日本からしてみると、「忘れない」のは素晴らしいことにも見える。だが、それもまた巨大なストレスなのではないか。まるで腫瘍(しゅよう)のように写真の上に在る絵の具物質のように。そして現実はもっと入り組んでいる。リヒター一族の楽しそうな写真の中に、「憎むべき敵に加担した側」と「敵に人間性を奪われた側」が一緒に笑っているように。
「忘れない」ことでEUの盟主となったドイツの戦後戦略
しかし、忘れてはいけないのだ。「それ」が繰り返してはいけない惨禍であり邪悪さだからというのと同じくらい、それを忘れないことで現代ドイツが保ち、ヨーロッパの覇権国になれているのだから。ドイツがEUの盟主となれたのは、ナチスの罪を限りなく断罪することが、キリスト教世界全体の贖罪(しょくざい)感につながるからだとわたしは思っている。ドイツが今日受ける尊敬と、繁栄とは、そのストラテジー(戦略)が実ったものだと思っている。もちろん、ヒューマニズムでもある、そして物語的ステラテジーだと思う。両者はいつだって、そんなに分けられるものだったのか。分けられないからこそ、心は、自分の平衡を保つ独自の方法を必要とするのではないか。
個人が記憶を忘れられないというのと、そのことが「具現化」されて万人の眼前にあるというのは、また別のことだろうと思う。もちろん、記憶というのはその持ち主とともに消滅するから、思い出すよすががあるのはよいことだとも思う。が、無視さえできそうなほどの日常の風景として「それ」がいつもあるのは、一体、そこに生きる人にとってどういうリアリティだろう?と思ってみる。

ゲルハルト・リヒター 《ストリップ(CR: 930-3)》 2013~2016年 デジタルプリント、アルディボンド、アクリル(ディアセック) 200×1000cm ゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)
魂を救う方法としての反復
神経症。という言葉が浮かぶ。
リヒターのアートは神経症的だ。コンセプチュアルと呼ぶ人もいるだろうが、コンセプチュアルアーティストにありがちな、方法論を速いサイクルで変えていく(方法論に飽きていく)ということがリヒターにはない。コンセプチュアルにやるというよりは、やむにやまれぬ生理衝動のように、生理的必要のように、反復をしているように、わたしには感じられる。方法論の反復もあるし、同じ作品内での数限りないほどの反復もある。まるで、意味がなくなるまで反復しようというように。コンセプトとしてやるのであれば、同じ手法をそんなに繰り返せるものではないと思う。ところが執拗(しつよう)なまでに繰り返すのは、それが彼の心を、魂を、救う、自分でもわからない衝動的な方法だったからなのではないか。
傷ついた人が、ある同じ行為を反復して傷を変容させることがあるようにわたしは思う。自分にもそういうことがあったし、周りでもそういう話をよく聞く。左手のスケッチばかりするとか、同じ場所の同じ夕方の写真を毎日撮るとか。そんなこととよく似た感じがする。だからこそ、有無を言わさず迫ってくる力がある。
そう、傷は、変容することが、あるだけではないか。なくなることはない。そして、どんなに変容しようと、痕跡そのもののように、物質的な何かが、残る。ある図版を折りたたんでコピーを繰り返すアート。イメージは比較的早い段階で鏡像の繰り返しも止める。そしてただの色の縞(しま)になってゆく。すべての意味は無くなったかのようだが、「それ」そのものが残る。残り続ける。
* * *

ゲルハルト・リヒター《ビルケナウ(CR: 937-1)》 2014年 油彩、キャンバス 各260×200cm ゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)
「写真のそっくりな模写」という手法の意味
近年の話題作である「ビルケナウ」。作家が40年かかってやっと制作し発表できたという作品。
ビルケナウ。白樺の谷という美しい地名。アウシュビッツとして知られるところ。
その犠牲になった人が歯磨きチューブに入れてレジスタンスに託したという写真が、元になっている。そこでは強制収容され死に至らしめられたユダヤ人の死体が燃やされている。盗み撮りのアングルで、それが撮られている。リヒターはそれを拡大し、模写し、その上に、塗り込めのような傷のようなペインティングを重ねてゆく。この作家がずっと用いてきた方法の集積の産物とも言える作品だが、これを見た時初めて、わたしは、彼が「写真のそっくりな模写」という不思議なことをやってきた意味が、わかった気がした。
写真のそっくりな模写というのは、一見倒錯的にも無駄にも見える。だが、そっくりに模写された写真ほど、写真から遠く離れられるものはないのではないか。

ゲルハルト・リヒター《モーターボート(第1ヴァージョン)(CR: 79a)》 1965年 油彩、キャンバス 169.5×169.5cm ゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)
模写によって遠くなる感情やメッセージ性
精巧な模写の過程というのは、アンディ・ウォーホールがアートにした陳腐なお絵描きキット――振られたナンバーに対応した色を置けば絵になる絵――のようだ。どんな悲惨なことあるいは残虐なことが写った写真でも、基本的には感情の籠(こも)らない、グレースケールや色の集積にできる。模写というものは、実物に近くなればなるほど、そういう作業になっていく。
写真の写実的描写は、写真そっくりでいて、写真から最も遠いものである。写真の模写は、写真のエモーションやメッセージ性と最も遠いものである。だからこそ、それは、なされる。なされなければならないのだと思う。他ならぬ、自分のために。
それは物語とは違うやり方でナラティヴ※的であり、連続パフォーマンスアートのようでもある。
※ナラティヴ ナラティヴとは物語の意味。文化における物語で、「ストーリー(粗筋)」とは異なり、神話やイデオロギー、また言語に限らないあらゆる領域まで含む。国民や民族、性別などの属性に深く関わるとされる。

ゲルハルト・リヒター《ビルケナウ(CR: 937-3)》 2014年 油彩、キャンバス 各260×200cm ゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)
それは元画像とは、似ても似つかぬものにする過程である。その絵は、ビルケナウの真実が「想起するもの」「心象」と言ってもいいが、その図像を写真像に「重ねていく」。写真像は(その模写像も含めて)「固有」である。これに対して、“それを食い破ってくる心の表象”、かきむしるようなその表象というのは、「どれもどこか似通る」。似通りながら、一回性のものである。その一回性は、ナラティヴとしてしか、あるいはパフォーマンスアートのようなものとしてしか、担保できない。行為自体がアートであることを、アートそのものは、保持しきれない。アートそのものの前に立つことは、その「なみなみならぬもの」を感じることでしかない。「並々ならぬことがあった」と感じることでしかない。
ここで思う、物語から遠く離れようとする営為もまた、物語によって担保されているのかもしれない、と。制作過程自体の、物語分解・解体という物語を考えなかったら、わたしたちは、何かただならぬものを感じてさえ、この作家のことをこれほどに考え続けるか、と。

ゲルハルト・リヒター《4900の色彩(CR: 901)》 2007年 ラッカー、アルディボンド、196枚のパネル 680×680cm パネル各48.5×48.5cm ゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)
カラーチャートに囲まれて得る不思議な安らぎ
わたしは歩き続け、最もポップな絵柄に見える、カラーチャートの部屋に行く。制作時期としてはビルケナウ以前のその作品に囲まれ、そこで不思議な安らぎを得る。もし、ある図像を極大まで拡大し、その極小部に入ってゆく。すると、そこには、ただ赤があるだけだ。ただ青があるだけだ。ただの赤、ただの青の只(ただ)中で、わたしは安らぐ。こんな「癒し」がアートにありうるのだ、とわたしは打たれる。
しかしやはり、何かが安らぎの内から現れる。まるで、内側から滲(にじ)んでくる血のようなもの。血と、血が出るのを許す傷のようなもの。リヒターの特徴的な作風の一つには、大きなヘラを使って、漆喰(しっくい)で壁を塗るようなものがある。時に塗りこめたところに引っ掻き傷を作る。その白に、ところどころにのぞく赤が、忘れがたい印象としてわたしに残る。塗りこめられずに滲んでくる血があるように。
滲んでくるもの。それは、さらに古い物語のようにわたしには思える。
すべてを起動させた物語。

ゲルハルト・リヒター 《アブストラクト・ペインティング(CR: 778-4)》 1992年 油彩、アルミニウム 100×100cm 作家蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)
共同体の裏切り者を裏切り続ける物語
ちょうど西暦の年数と同じだけの昔に、この地球のある地域の出来事を受けた物語。この物語がつくられなかったとしたら、ユダヤ人迫害もあったかわからない物語。その物語のために迫害は起き、その物語に則って贖罪が今も進行形でなされる、物語。――イエスの磔刑(たっけい)。
……この物語の精算は、気が遠くなるほどのものであったとしても、基本方針自体ははっきりしている。ユダを弾劾(だんがい)し続けること。決して許さないこと。共同体の裏切り者と定めし者を、切り続けること。切るものを決め、それをどこまでも切り続ける。いわば、裏切り者を裏切り続けること。それが、かつて選挙で選んだ人物だったとしても。
この方針は、全体的な繁栄には寄与するのだが、救えないものがある。そこまで明快に割り切れないものは救えない。もしかしたら、ナチスに協力したおじさんを好きだったかも知れない。世界的ベストセラー『朗読者』は、少年時代に恋をした年上の女性が、実はナチスの戦争犯罪に関係していたと知る話である。
誰が悪か。共同体の裏切り者は誰なのか。物語は、本当に言われる通りなのか、それも本当はわからない。あるいは近現代の殺戮は古い殺戮の拡大版、または縮小版なのか。
現代の宗教画に流れるリヒターの血
そう直観する時、リヒターの赤が、まるで磔刑の後の十字架の木目に血を描き込んだ、降架図などを描いた画家の筆づかいに思えてくる。そうかわたしは現代の宗教画を見ていたのか。この重力、意味が解体されても生じる求心力。そうだったのか。
流れる血は、リヒター自身の血なのだと、わたしは思う。

ゲルハルト・リヒター《ビルケナウ(CR: 937-2)》 2014年 油彩、キャンバス 各260×200cm ゲルハルト・リヒター財団蔵 © Gerhard Richter 2022 (07062022)

作家、アーティスト。東京生まれ。アート誌「SALE2(セールセカンド)」の編集長を任されたのをきっかけに、編集と文筆に携わる。1992年「起爆者」で小説家に。小説作品に、映画化された『ヴァイブレータ』『ミューズ』など。2012年『東京プリズン』発表。天皇の戦争責任を米国で問われる少女を通して「日本の戦後」を描いた同作で、戦後論ブームの先駆けとなる。批評と物語の中間的作品に『愛と暴力の戦後とその後』『愛と性と存在のはなし』など。2017年頃から叙事詩と巫覡(ふげき)的パフォーマンス「音楽詩劇」を、21年から心の傷の変容に関する瞑想(めいそう)やアートのワークショップ講師などもしている。22年9月現在の最新の著述は「あなたを駆動する物語について」(現代ビジネス、講談社)。個人と共同体を動かす危険なフィクションについて洞察している。

展覧会名:ゲルハルト・リヒター展
会場:東京国立近代美術館(東京都千代田区北の丸公園3-1)
会期:2022年6月7日(火)~10月2日(日)
開館時間:10:00~17:00(金・土曜は10:00~20:00) ※入館は閉館30分前まで
※9月25日(日)~10月1日(土)は10:00~20:
休館日:月曜日(ただし9月19日、26日は開館)、9月27日(火)
料金:一般:2,200円、大学生:1,200円、高校生:700円
※いずれも消費税込。
※中学生以下、障害者手帳を提示した人とその付添者(1名)は無料。
※本展の観覧料で、同時開催の所蔵作品展「MOMATコレクション」も、入館当日に限り観覧可能。
問い合わせ:050-5541-8600(ハローダイヤル)
公式サイト:https://richter.exhibit.jp/
巡回情報:2022年10月15日(土)~2023年1月29日(日) 豊田市美術館に巡回


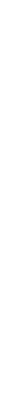
 ゲルハルト・リヒター《エラ(CR: 903-1)》 2007年 作家蔵 油彩、キャンバス 40×31cm © Gerhard Richter 2022 (07062022)
ゲルハルト・リヒター《エラ(CR: 903-1)》 2007年 作家蔵 油彩、キャンバス 40×31cm © Gerhard Richter 2022 (07062022)









