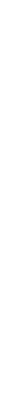文:羽田圭介
取材で四国へ行った際、徳島県鳴門市にある大塚国際美術館へ足を運んだ。延床面積2万9412㎡、ぜんぶ見て回ったら4km歩くことになる展示スペースには、世界26ヶ国の古代壁画から現代絵画まで、名作の陶板複製画が展示されているとのことだった。
期待半分、「でもぜんぶ複製画なんだよな」という少し冷めたような思い半分で展示スペースに入ってすぐ、ヨーロッパの教会内部かのような光景に驚かされた。システィーナ礼拝堂全体を模したアーチのついた空間には、ミケランジェロの『最後の審判』が天井や壁中に再現されている。天井高もとんでもなく高い。
スクロヴェーニ礼拝堂等、とにかく広い空間をそのまま再現しているものがごろごろあり、幾枚もの大きな画も原寸で再現していることもあり、とにかく見応えがあった。近くで見ると陶板の継ぎ目は見えるのだが、鮮やかな色味により、どんな画であるのか、サイズ感も含めかなりわかりやすい。
バロック、ルネサンス、近代、現代という系統分けの中には、レンブラントやダ・ヴィンチ、ムンク、ミレーなどといった有名どころも含まれており、複製画だからこそ可能な豪華夢の共演展示だ。
中でも一際人々の注目を集めていたのが、フェルメールの『真珠の耳飾りの少女』だった。「青いターバンの少女」が描かれた、美術に興味のない人でも見覚えのある絵であろう。作品と一緒のツーショット写真を撮ってもらっている女性がたくさんいて、近くで見るための順番待ちにはけっこう時間がかかりそうだった。
ただ僕はこの時点で、東京都美術館で開催中の「フェルメールと17世紀オランダ絵画展」へ行こうとはしていた。だから、東京に戻って本物が見られるんだし、わざわざここで複製画のために順番待ちをしなくてもいいやと、3メートルくらい離れたところからさっと見ただけで、順路に沿い上階まで進み、最後はバスキア等の現代美術の複製を見て美術館をあとにしたのだった。
その数日後、上野へ足を運んだ。平日の正午、桜が満開だからか人々も多い。東京都美術館へ訪れるのは10年ぶりくらいだった。音声ガイドプログラムがあったので、600円払いヘッドフォンと端末を受け取る。
ゆっくりと進む人の列に並びながら肖像画等、オランダの古典絵画を見てゆくと、さすがに陶板複製画とは違う、原画の色彩の深さにひきこまれた。所々で音声ガイド用の番号が記されており、指定された番号を端末に入力し解説を聞く。ただ、音声で解説されながら絵を見ると集中しにくく、そもそも大事なことは壁に掛けられた文章での解説でも知れるため、途中から音声ガイドをあまり使わなくなった。なにより、音楽で感想を方向づけられる感じが邪魔だった。やはり僕は、美術作品を鑑賞するに際し、自分がどう感じたかを大切にしたがる傾向にあるようだ。
展示終了日まで予約枠が完売したほどの混雑具合であるため、すべての絵を間近で見ようとすると順番待ちの列のスピードでしか進めず、えらい時間がかかる。ただ中高年女性が多い客層の中、上背のある男の僕は恵まれており、列の後ろに立っても絵をじゅうぶんに鑑賞できたため、全体の3割くらいはそうやって見て回った。
人が集まりすぎてそれが通用せず、自分も最前列で見てみたい作品があった。フェルメールの《窓辺で手紙を読む女》だ。2021年に終わったばかりの修復作業により、上塗りされていた白壁部分からキューピッドの絵が完璧な形で復元された、という映像を見せられた上での原画なので、期待も膨らむ。
列が進むというより、絵に対し放射状に集まった人たちが、最前列で絵を見終えたら離脱してゆく、という形で人の動きができていた。僕も時間をかけ正面から二列目まで進んだ。だが僕の前にいる総白髪のお婆さんが、一分以上経ってもどかない。
さすがに目玉の作品なので誰もが最前列で見たがっており、お婆さんがどかない限り、放射状の層の新陳代謝が進まない。でもお婆さんはどかない。僕含め、近くにいた数人もお婆さんに対し苛立っているような空気が漂いだし、何人かは諦めて離脱していった。
お婆さんは三分くらい経ってもどかない。そこまでくると僕の心境も変化してきていた。まず、二列目であっても、その距離で原画をじっくり堪能したという理由がある。他の理由としては、最前列を独占しているのが、お婆さんだからだ。
前日の午前、母方の祖母が施設で亡くなった。97歳だった。《窓辺で手紙を読む女》の前からどかないお婆さんはせいぜい80歳前後だろうが、それでも、人生で残された時間は短い。飛行機の長旅でドレスデン国立古典絵画館へ行くのは難しいだろうし、今度いつフェルメールの作品が日本で見られるのかもわからない。人生最後の《窓辺で手紙を読む女》鑑賞になるかもしれないと考えたら、見る時間が長くなっても仕方ないだろう。ましてや、絵に対する感受性が一際強い人であった場合、なおさらだ。
文章での解説や、たまに聴く音声ガイドで何回も反復され、気になったことがある。当時のオランダで、富を得た人たちが、文化的な教養の証として絵を所有していたという解説だ。金をもった人が、次に教養の証を欲しがる。わかりやすい構図だ。本連載をやっておいてこう書くのもなんだが、美術作品を買うというのは、金さえあれば誰にでもできる。他でいうと文学作品を読み通すのは時間もかかるし、読解力がなければ先に進めない。絵は、とりあえず一目で全体を見られる。もちろん、込められたメッセージを読み解くにはそれなりの教養や文脈の理解も必要だが、それらがなくとも、あるかのような対外的アピールはできる。僕の中で、絵という美術作品を軸にして、絵を生み出す画家たちへの尊敬の念と、教養の証を金で買う人たちに対する思いが、離れていった感じがした。買う人がいないと作る人の生活が成り立たないというのはわかるが、古典作品の場合、生前は貧乏暮らしをしていた画家も多い。
最後まで見終え、ミュージアムショップへ来てから気づいた。大塚国際美術館で陶板複製を遠目に見ただけの、フェルメール『真珠の耳飾りの少女』の原画を、結局見なかった。あれは今回、展示されていなかった。調べると、オランダのマウリッツハイス美術館に行かないと見られないらしい。幸いにも自分にはまだ、異国へ絵を見に行ったりする時間の余裕がある。見ておくべきものは死ぬまでにちゃんと見ておくべきなのだろう。亡くなって間もなかった祖母の静かな姿が、脳裏に浮かぶ。本人にそのつもりはないだろうが、その死からも、孫である自分は勝手に学ばせてもらった。

はだ・けいすけ/1985年東京都生まれ。明治大学商学部卒。17歳の時に「黒冷水」で文藝賞を受賞し小説家デビュー。2015年「スクラップ・アンド・ビルド」で芥川賞受賞。近著に『Phantom』(文藝春秋)、『滅私』(新潮社)、『三十代の初体験』(主婦と生活社)がある。