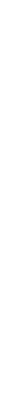文:羽田圭介
駅とかNHKとか、たまたま足を運んだ空間で目にしたとき以外、岡本太郎作品に触れたことがなかった。上野の東京都美術館で開催されている「展覧会 岡本太郎」へ足を運んだ。
入ってすぐ、『若い夢』という人間の子供ほどの大きさのオブジェに目をひかれる。色味や質感としては石や鉄のような無機質さを漂わせつつも、丸くくり貫かれた二つの大きな穴と、下側にある三日月形のくり貫きにより、頬杖をついた笑い顔の子供のように見え、かわいらしさが直球で伝わってくる。
絵画に関しては、『にらめっこ』のような作品でも顕著だが、赤青黄色緑白黒の色使いに目玉、という共通点のある作品が多かった。
これまでの僕の乏しいアート鑑賞歴においては、自分のほうから作品の良さを探しにいくような静けさが普通であったが、初めてちゃんと見る岡本太郎作品は、極彩色の色使いと目玉の眼力によって、生物としての本能にしたがい目を向けさせられるような、騒々しさがある。どんな作品もどこか顔に見える要素があれば、多くの人にもとっつきやすいだろう。
すっかり岡本太郎作品を満喫したつもりで上階へ行くと、空気が変わった。
1930年代を主としたパリ時代の作品は、世界のアートの潮流の只中にいるとでもいうような、ベーシックさがあった。そして招集された戦争中に描いた、『師団長の肖像』という作品には衝撃を受けた。下で散々見てきた岡本太郎らしさが一切ない、軍人を描いた肖像画なのだ。説明文に記載されていた、〈司令部に呼び出され、命令として描いたもの〉という文言が、今も深く心に刻みついている。
戦後すぐに描かれた『憂愁』という絵画は、宇宙のような亜空間に浮かぶ大きな茶色い岩に何本もの白旗、それらを照らしだす炎と影という、暗さの中に熱っぽい混沌を感じさせる作品で、後に続く作品群の原点に感じられた。本展覧会で見た中で、最も好きな作品だ。作家の個性がありつつも適度に抑制のきいた作品が、自分は好きなのかもしれない。
『明日の神話』は、目玉や極彩色等他の絵と似たようなテイストではあるのだが、横に長すぎて一覧できないため、そこには時間が流れる。絵の左のほうを見てから、歩いて右を見にいっているうちにも左側の視覚記憶は段々と薄らいでゆき、また左を確認しに戻ろうとする中で、上や下の明暗の違いにも気づいたりと、受け手の中でずっと変異し続ける面白い作品だ。
展示の順路の後半で、モニターに映像と音声が流されていた。マクセルのビデオテープの古いCMで、画面の中で目力のある岡本太郎が「芸術は、爆発だっ」と言っていた。僕はそれまで、「芸術は爆発だ」という文言を、なにかの誌面に活字で印刷されているのを読んだり、誰かが口にしたのを又聞きしたことしかなかった。本人が言っているのをアナログの映像と音声で見聞きしてしまうと、その生っぽさから、伝説的存在という雰囲気は削がれた。
そこで、一つの疑問が浮かぶ。アート作品という、文脈作りも大事になってくる世界において神秘性を帯びたければ、テレビCMで作家自身の生っぽさを披露するのは危険かもしれないと、太郎本人も考えたはずだ。それでもなお、CMに出たということは、日本のお茶の間にもっとアートを広げたかったという理由以外、考えられない。公共の場所向けの作品も多く作ってきたということも、その証左であるように思える。
やがて僕は、とあることに気づいた。いつも古典や現代アート等、どの展示を見に行っても、僕がじっくりと見ているそばを、多くの客たちはかなり早いペースで流し見し、会場から出て行くのがほとんどだ。ただ今回の岡本太郎展においては、平日の昼間であるにもかかわらず多くの来場客がおり、学生くらいの若い人から老人まで、一つ一つの作品を長い時間かけ見ている人たちがたくさんいた。物販コーナーもたいへんな賑わいで、皆色々買っていた。
正直にいうと、岡本太郎作品の良さはよくわからなかった。
勿論、ある程度の良さはわかる。『憂愁』や『明日の神話』なんかでそれはじゅうぶん感じた。ただ、単純ともいえる色使いや、目玉や顔といった理解しやすいモチーフの力もあり、それをエネルギーのようなものとして受けとりはするが、それは、わかったというより、作家による誘導に素直に従っているだけのような気もした。岡本太郎作品好きの人たちが発したり、評したりする文章等で、「生命力」「エネルギー」「ぶつかりあい」といった言葉によく出くわすが、その正体は、誘導、だろう。
海外のアートの最前線で活躍しつつ、それを日本の大衆へ橋渡す役を担った功績は偉大だ。岡本太郎にとってそれは、慈善事業のようなものでもなかっただろう。表現者である限り、自分の作品に対する人気を得たいと思うのは当たり前だ。かといって、自分の作品しか知らない人たちに好きになってもらっても、作り手の自尊心は満たされない。他多くのアート作品も知っている目の肥えた人たちに、自分の作品を好きになってほしいとなると、まずは日本の大衆にアートの教育を施すところから始めるほかなかっただろう。
他の作家たちのアート作品には興味を示さないが岡本太郎作品だけは熱心に見るというような、大晦日の紅白歌合戦や正月の初詣のような触れ方で、岡本太郎作品だけが崇拝される現状は、岡本太郎本人が望んでいた状態ではない気がする。
国内の多くの人々が、岡本太郎以外の作品も好きになり、これほどまでの岡本太郎人気が相対的に薄まって見えるくらいにならない限り、岡本太郎の思いは果たされない。だからせめて、太郞よりも好きな作家を多く見つけたいというような態度でもって、もっと色々なアート作品へ目を向け続けるのが、いいんでしょうね。
今回訪れた展覧会:「展覧会 岡本太郎」
岡本太郎作品のほぼ全てを所蔵する川崎市岡本太郎美術館と岡本太郎記念館の全面協力のもと、最初期から晩年までの代表作や重要作を網羅する。大阪中之島美術館からスタートし、現在、東京都美術館(上野)で開催中。会期は12月28日まで。その後、2023年1月14日〜3月14日、愛知県美術館へ巡回予定。詳細は公式サイトへ。

はだ・けいすけ/1985年東京都生まれ。明治大学商学部卒。17歳の時に「黒冷水」で文藝賞を受賞し小説家デビュー。2015年「スクラップ・アンド・ビルド」で芥川賞受賞。近著に『Phantom』(文藝春秋)、『滅私』(新潮社)、『三十代の初体験』(主婦と生活社)がある。