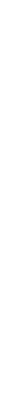文:羽田圭介
毎年、年賀状を10枚ほど書いている。それくらいしか書かないため、年賀状用のソフトやデータをパソコンに入れてはいない。そしてだいたい年末年始にコンビニで慌てて年賀ハガキ10枚セットを買おうとするため、微妙な絵柄や白紙のものしか残っていない。いつも白紙の年賀状ハガキを買うのだが、手書きで挨拶の文を書いても、かなり余白が残る。
なのでたいてい、新年の干支の絵を描く。2022年は、手元にあった毛筆タイプの筆ペンで、寅を描いた。寅は干支に出てくる他の動物たちの中では目と鼻が人間に近いため難しくなく、一枚あたり4分程度で描いている間、楽しかった。そして描いた寅を、人々からわりと褒めてもらえた。
すると嬉しいもので、もっと絵を描きたくなってくる。僕は小学校1~2年生の頃、絵画教室に通っていた。小学校3年生のとき、写生大会で埼玉県の金賞に選ばれた。4年生のときも、なにかの賞の佳作に選ばれた。以後、特に絵に没頭したり、褒められた時期もないのだが、絵の具やクレヨン、パステルでなにかを描くことに抵抗はない。
久々に絵画をやりたいな、と思ったものの家には一切の道具もなく、絵画道具をちゃんと揃えようとしたら家が散らかりそうだ。6年前に買った12.9インチのiPad Proがあったため、それにAppleペンシルを買い足して描こうと思い、家電量販店に行った。すると、最新のiPad ProとAppleペンシルの、紙に描いているような滑らかさに感動し、iPad Proごとアップルストアで買い直した。
製品が届くまでの間、デジタル絵画について調べているうちに、NFTなるもののことが気になっていった。なんでも、暗号通貨と同じブロックチェーン技術を用いたものらしい。
自分も、iPad Proでデジタル絵を描き、NFTを販売してみてもいいのではないか? とても面白そうだ。
ちゃんと知りたくなり、『NFTの教科書』(朝日新聞出版社)という本を読んだ。従来的なアート作品だと、日本の法律においては、転売により次々と高値がついていっても、アーティストには最初に売った金額以上の金は一銭も入ってこない。それが、NFTだと取引ごとにアーティストにも数割入ってくるようにできる。偽物をつかまされる可能性も排除できるし、いいことづくめではないか…と思う反面、法整備が追いついていない現状も知る。
その後もインターネット上や他の資料でも調べたりする限り、物理的な作品は存在せず、デジタルデータの所有権や閲覧権を売買しているだけというのが、気になった。それを市場の全員が理解しているわけでもないらしく、今後しばらくは、トラブルが生まれるかもしれない。NFTにまつわる解釈は、今のところ、人によって違うようだった。
届いたiPad proにProcreateという有料のイラスト制作アプリまでインストールしたのにもかかわらず、全然絵を描かないまま、数ヶ月が経過した。Procreateだとなんでもできてしまうぶん、なにから手をつければいいのかがわからなかった。
まずは、デジタルではなくアナログの道具を用い、絵を描くという行為のリハビリをしたほうがいいのではないか。勘を取り戻してから、デジタル絵画に移行しよう。
アクリル絵の具と筆2本、パレット代わりの四角い琺瑯容器、A4サイズの画用紙を買った。思えば、子供の頃の絵画教室や学校の授業では、支給されたり親が買ってくれたりした道具を使っていたから、自腹で絵画道具を買ったのは人生初かもしれない。それと、乾きやすいが鮮やかな発色のアクリル絵の具をちゃんと使うのも初めてだった。
まずは、うさぎのぬいぐるみをテーブルの上に置き、そのまま描いてみる。年賀状に描いた寅より、はるかに難しい。というのも、自然界にあるものと違い、人工的なものは表面の起伏が少なく、丸っこい頭部を立体的に描こうとすると、陰影のつけ方で表現するしかない。ものすごく久しぶりの絵の具を使った絵画に、いつしか没頭していった。音楽もかけない環境下で、小説以外の創作行為に没頭できるのはたいへん心地よかった。心地よさでいったら、小説を書いているときより上だ。2時間ほどで、ニンジンを持ったうさぎのぬいぐるみの絵は完成した。
後日、2作品目として公園の風景画を描いた。人工物であるうさぎのぬいぐるみと比べ、直線が一切ない自然界は構造が複雑で、僕は輪郭について考えさせられた。果たして輪郭というものは、存在するのか。絵を描くときにしか存在せず、人間が目で風景を見ているときに、輪郭なんてものはないのではないか。そうであるのなら、奥にある木と手前にある木を、どう描き分けるべきなのか。光と、光を受けての発色の違いが重要なのだろう––––。等々、観察しては筆が止まり、悩むプロセスが、面白い。子供の頃はそんなこと全然考えもしなかったのだが、久しぶりに描いている自分は、なぜこんなにも考えながら描くことができているのか。
おそらく、小説を書いてきたからだろう。小説の執筆と絵画には、似ているところがあると気づいた。小説は、ただ想像すればいいというものではなく、自分が想像したことを精確に描写するところにこそ、真価や個性が発揮される。だから、ものすごく奇想天外なフィクションや、ほぼエッセイかのような静かな日常を描いた小説でも、うまく書けているものは等しく魅力的なのだ。
絵を描くことに関しても、自分がどう筆を動かすかと同等以上に、自分にはどういうふうにそれが見えているかという、観察眼が大事だ。
4時間弱で書き上げた公園の絵は、それなりの出来にはなった。書き終えてすぐ、池の水面にちゃんと光の反射を描き加えればよかった等反省するも、キリがないのでそれ以上は手を加えず、次回に活かすことにする。
2枚の絵とも、なんとなく自宅のリビングに飾っている。そろそろ新しい絵を描こう……と最近も考えているのだが、ふと気づいた。デジタルの絵を描こうとしていない。そしてNFTは、どこへいってしまったのか……。
よって、NFTのことは未だ、よくわかっていない。NFTを「わかる」と言えるようになるには、アート作品を作り、出品してみるしかないのではないかと思っている。ただ自分の場合、NFT小説を書いたほうがいいのだろうが。

はだ・けいすけ/1985年東京都生まれ。明治大学商学部卒。17歳の時に「黒冷水」で文藝賞を受賞し小説家デビュー。2015年「スクラップ・アンド・ビルド」で芥川賞受賞。近著に『Phantom』(文藝春秋)、『滅私』(新潮社)、『三十代の初体験』(主婦と生活社)がある。