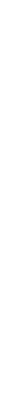文:羽田圭介
「国立新美術館開館15周年記念 李禹煥」へは、開館15周年記念の展示なのだから、ぜひとも行かなければならないと思っていた。
日曜の午後、地下鉄千代田線乃木坂駅で下車し、直結している国立新美術館へ歩く。それにしても、国立新美術館はつい最近開館したばかりというイメージだったのだが、僕が大学四年生だった2007年の開館からもう15年も経っていたことに驚いた。
李禹煥(リ・ウファン)については、雑誌なんかでたまに紹介されるアーチ状に曲がった巨大なステンレスの『関係項–アーチ』以外、なにも知らないで来た。入口でパンフレットとは別に、マンガの「李禹煥鑑賞ガイド」を手には取ったものの、すぐに畳んでポケットへしまい、無料の音声ガイドも無視し順路を進み始める。アート作品に関し、どれくらい自分の解釈を大事にすべきかは模索中であるものの、前回の「ライアン・ガンダー われらの時代のサイン」を経てより一層、自力で理解しようとする姿勢が大事なのではないかという思いが強まっていた。
蛍光シールを拡大させたような作品があった。なんだこれは、と思いながらしばらく見続けていると、太陽を直視したあと目をつぶったときに映る、網膜の中の夕焼けのように見えてきた。頭で理解するアートというよりは、視覚的錯覚に兆した心身の揺らぎを素直に感じるもの、としてとらえればいいのかもしれない。
角材が数本寄り添い立てられているだけの作品は、さすがにホームセンターの木材売り場じゃないんだからこれをアートと言われても、と思ったが、近づいてよく見ると、ホームセンターでは売られていないほどの太い角材で、ありそうでない、という遅れてくる変な視覚情報が印象に残った。
『点より』というシリーズ作品は、絵の具を染みこませた布かなにかを画布の上で直線状におしてゆき、段々とかすれてくると、また同じことの反復が規則正しくなされている。無数にあるそれらは一方向へと泳いでいる精子の群れのようでもある。デジタルで描かれそうな幾何学的な絵だが、それらは手作業で描かれており、慎重な作業であっただろうな、という緊張感に満ちた時間の経過の跡が見てとれるのであった。
段々かすれてくる線の反復である『線より』は、『点より』と似たような描き方であるように見受けられるが、見て受ける印象は異なり、子供の頃に夕方のテレビ再放送で見た『ガンバの大冒険』の、敵イタチ軍団のようなシルエットと荒々しさを秘めているものもあった。 余白だらけの『対話』は立体的でカラフルな絵で、まるで写真みたいだが、近づいてみると規則的でシンプルな筆運びの形跡が見てとれる。2000年前後の荒いCGみたいで、なんでこれをやったのだろうと考えながら見ていると、写真とCGと手描きの境界が曖昧になってきて、一つの対象物を見ているのにそれが脳内で三重に見えた。
作品そのものと、壁に貼られたタイトルの札だけをたよりに、今回も鑑賞を終えた。『関係項』や『対話』など、哲学をふまえたようなタイトルが多かったから、それを手がかりになんとか自分なりの理解、解釈ができたような気もするが、じゃあタイトルすらなかったらどれほど理解できたのだろうかとも思った。パンフレットとマンガの鑑賞ガイドを読みたい欲望にかられたものの、読んで言葉で理解してしまったら、自分がというよりもアートが言葉に負ける気がした。小説家である自分は言葉で表現する人間なのに、言葉は邪道だというような思考回路になっており、作家がつけたタイトルですら邪魔に思うほどだった。李禹煥の、視覚的な錯覚にはたらきかける作品群が、短時間でそうさせてきたのだろうか。
そして鑑賞してからちょうど一週間後の現在、この原稿を書きながら、パンフレットとマンガ「李禹煥鑑賞ガイド」を初めて読んだ。特に「李禹煥鑑賞ガイド」の出来が良く、李禹煥という作家がどういった育ちでなにに影響を受けてきただとか、作風の変遷等がわかり、たいへん理解の深まるものであった。
じゃあ、美術館で鑑賞中に、その場でも読めばよかったのではないか?
そんな思いも少しはわいてくるものの、わりと明確に、それは違うと判断できた。自分なりの手探りの解釈で過ごした一週間があったからこそ、パンフレットや鑑賞ガイドの“正しい”説明にふれても、作品を鑑賞したときに覚えた感触が心身へと強固に刻まれたままなのだと思う。アート作品に対する自分なりの接し方が定まった気がした。
国立新美術館の開館15周年を記念して、国際的にも大きな注目を集めてきた「もの派」を代表する美術家、李禹煥(リ・ウファン、1936年生まれ)の大規模な回顧展。会期は11月7日まで。詳細は公式サイトへ。

はだ・けいすけ/1985年東京都生まれ。明治大学商学部卒。17歳の時に「黒冷水」で文藝賞を受賞し小説家デビュー。2015年「スクラップ・アンド・ビルド」で芥川賞受賞。近著に『Phantom』(文藝春秋)、『滅私』(新潮社)、『三十代の初体験』(主婦と生活社)がある。