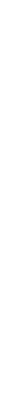文:羽田圭介
前回、NFTのことが未だよくわかっていないという結びで終えた。その後も継続的に調べる中で、teamLab(チームラボ)が発表した「Matter is Void」という作品のことを知った。NFT所有者が自由に書き換えられる文字の作品は面白いな、と感じた後、そもそもteamLabの常設展示作品すらちゃんと見ていないことに気づいた。夏の平日、豊洲にある「チームラボプラネッツTOKYO DMM」へ向かった。
首に冷感タオルを巻いて行ってもまるで無意味な熱さの中、豊洲駅から歩き巨大な箱形施設にQRコードチケットで入る。靴を脱がされ、出入口近くのロッカーへリュックや靴、靴下等をしまい、暗い道を歩き始める。水が流れる坂道に出くわすまでもすぐで、なんでも助走なしでいきなり始まるという感を受けた。
それにしても、クーラーの利いた涼しい空間で、足を冷やされて気持ちが良い。これが外の気温のままだったら、ちゃんと楽しめていないと思う。最適な気温の広い空間で、見せ場以外は光量が制限され暗いという、コントロールされた快適さの中では、身体の主体性が
薄まったり、反対に濃くなったりするのだった。
たとえば、前半にある「やわらかいブラックホール」は、暗闇の中、卵のパックを裏返したような並びのクッションの山々へ裸足で踏み入り、なんとかして反対側へと渡るエリアだ。
「タルコフスキーの『ストーカー』とまんま同じ空間だ」
そう口にしつつ、踏み入れた足がズボッと山と山との間に沈み、もう一歩を踏み出すのにも身体の勢いを要するのが楽しい。二十代くらいの若い客、しかも女性客が圧倒的に多い中、脚力に自信のある僕はそれを見せつけるかのように、色々な方向へと駆け回り、出口まで行き着く。警戒されるような振る舞いだったかもしれないが、それくらい、空間へ関与する自分の身体の主体性が濃くなり、色々と試してみたくなってしまったのだ。
すると僕に続くように、「やわらかいブラックホール」の中から女性二人のはしゃぐ声が聞こえ、Tシャツ姿の若い女性が駆けてきた挙げ句出口近くのクッションに仰向けでダイブしていた。女性が反動までつかい思いっきり身体を動かし、なにかに自分の体重をぜんぶ任せてしまう光景が珍しく、興奮とまではいかないが妙にいいものを見た気がした。
圧巻だったのが、四方八方を鏡で覆われた空間内で、天井からぶら下がった無数のLEDライトの発光点がコンピューター制御で不断に変化し続ける立体物をつくりあげる「The Infinite Crystal Universe」だ。鏡の迷路空間は『燃えよドラゴン』でブルース・リーが敵と戦っていた鏡部屋のようなかすかな緊張感があったし、その場に立っているだけで光の線がこちらに向かってきて宇宙空間をワープしているような錯覚にも陥る演出には、非日常世界への没入感があった。音楽もあわさり、人工物だけで成り立ったそこには、有機的なものが一切なくとも温かみがあった。
一転、ガーデンエリアにある「Floating Flower Garden:花と我と同根、庭と我と一体」では、これまた鏡に覆われた空間内で、上から吊された花々がコンピューター制御で上下していた。
こんなところに一人でじっとしていたらSF映画内の夢のシーンみたいに感じるのだろうが、実際にはスマートフォンで自撮りをしていたり、身体をくねらせるポージングをし男に写真を撮らせたりしている若い女性たちがそこらじゅうにいる。だいたいみんな、座ったり寝そべったりしていた。ふとその状況に対し僕は冷静になり、直立不動でただ周りを見ていると、安易な感想だろうが、集まった客たちの存在感も含めての作品なのかもしれないと感じた。
いくら過剰に綺麗な空間で自分にとって満足のゆく自分の写真が撮れても、それを自分が望むような人たちにちゃんとは見てもらえないまま、やがて有機物としての死を迎える。けれどもその現実は残酷というわけでもなく、花のはかなさを目の当たりにしている人たちは、自分たち人間のはかなさも心の奥底ではとっくに知っていて、受け入れながら楽しんでいるのだろう。
一時間半弱で施設を後にすると、歌人・小説家である加藤千恵さんの家に向かった。久々に会いたいと連絡したのは、上記施設内からであった。涼しい空間で夏バテから回復したからこそ、友人と会おうと思えた。突然の連絡にもかかわらず数人で訪問すると、カトチエがフード注文・配達アプリで中華料理を頼んでくれた。皆で中華料理を食べながら話に花を咲かせた後、僕は所用があったので早めに帰った。
実のところ、世にとっくに普及しきっているフード注文・配達アプリのサービスを利用したのは僕にとってそれが初めてで(自分で注文したわけではないからまだ利用したとはいえないのかもしれないが)、テクノロジーが進化するとできることは増えるのだなと思った。アート作品も、これからもっと、色々なやりようがあるのだろう。

はだ・けいすけ/1985年東京都生まれ。明治大学商学部卒。17歳の時に「黒冷水」で文藝賞を受賞し小説家デビュー。2015年「スクラップ・アンド・ビルド」で芥川賞受賞。近著に『Phantom』(文藝春秋)、『滅私』(新潮社)、『三十代の初体験』(主婦と生活社)がある。