アートは社会変革の触媒として有効なのか?──クィアアーティストたちが1994年に語ったこと【後編】
プライド月間のきっかけとなった「ストーンウォールの反乱」から25年後の1994年、12人のクィアアーティストがArt in America誌に、事件がアート界に与えた影響について語ってくれた。この特集から8人を抜粋して紹介する企画の前編に続き、後編ではデボラ・キャス、ケーリー・S・レイボヴィッツ、ヒュー・スティアーズ、ドナルド・モフェットら4人のインタビューを再掲する(モフェットは書面で回答)。

1.「もしアンディ・ウォーホルがレズビアンだったら? と考えるとワクワクする」──デボラ・カス

私にとって人生初の衝撃的なアート体験は、8歳くらいの時にメトロポリタン美術館で見たピカソの《ガートルード・スタインの肖像》だった。それは、私にとって初めての衝撃的な性的体験でもあった。それを見た瞬間、私は彼女の姿に自分を重ねたのだ(後にバーブラ・ストライサンドのことを知って、彼女に夢中になった時と同じだった)。この肖像画とそこに描かれている人物には、私を魅了してやまない何かがあった。その後、メトロポリタン美術館やニューヨーク近代美術館(MoMA)でピカソの作品をたくさん見て、分かったことがある。ピカソは、ああいう女性、あんな風な容姿と存在感を持つ女性、要するに物体ではない女性をほかには描いていなかったのだ! あの絵でピカソが描いたのは人であり、その「人らしさ」に私は圧倒された。その理由が、ガートルード・スタインが芸術家だったからなのか、ユダヤ人女性だったからなのか、レズビアンだったからなのかは分からない。ただ、8歳の私はこうしたことを無意識のうちに感知したのだと確信している。
その後、私はカーネギーメロン大学で美術を学んだ。1975年にニューヨークに戻ったとき、女性であること、そして画家であることは大した問題ではないように思えた。1975年から77年にかけては、スーザン・ローゼンバーグ、エリザベス・マレー、パット・スティア、ジョーン・センメル、ルイーズ・フィッシュマンなど、何人もの女性アーティストが初個展を開いていたし、当時は第2波フェミニズムの絶頂期でもあった。大学を出たばかりの23歳の私にとって、そうした状況はとても心強いものだった。
美大生時代の私は、完全に自分を男性として見ていた。ニューヨークに来てレズビアンであることをカミングアウトし始めた頃の私に啓示を与えたのが、さっき名前を挙げた女性アーティストたちの作品だ。それに、女性として女性を愛すると認識したことで、それまでは考えたこともなかった方法でアートに反映された自分の姿を見たいと思うようになった。たとえば、エリザベス・マレーの作品を見るのは、アドリエンヌ・リッチの詩を読むのとまったく同じ体験に思えた。彼女はフォーマリズム(形式主義)のベースを持つ作家でありながら、そこに個人的な要素を加えることでフォーマリズムを再構築している。当時はこんな風には言い表せなかったけれど、マレーの絵を見たとき、これは私のことを表現していると思った。それはとてもエキサイティングな体験だった。
初めて見た瞬間から大好きになったもう1人のアーティストは、アンディ・ウォーホルだ。彼にインスパイアされて作ったシルクスクリーン版画には、ガートルード・スタインの肖像やバーブラ・ストライサンドの肖像がある。《My Elvis》というタイトルのシルクスクリーン作品は、映画『愛のイエントル』(*2)のバーブラを描いている。
*2 バーブラ・ストライサンドが監督・脚本・主演を務めた1983年のミュージカル映画。学問が男性だけのものだった時代、ストライサンドが扮する主人公イエントルは男装してユダヤ教の神学校に入る。
私がアンディに惹かれるのは、彼が最初のクィアアーティストだったからだ。ここで言うクィアは、今私たちが政治的な意味で言うクィアのこと。同時代の同性愛者たちが、その事実を符丁化したり、隠したり、ほのめかしていたのに対し、アンディは50年代にクィアの男性であることがどういうことであるかをはっきりと絵の中で表現した。彼は初のメジャーなクィアボーイアーティストだった。女物の靴のイラストを描いていた頃から、彼はクィアの脳内を絵にしていたのだと思う。
レズビアンとしてそういう作品を見ると、ワクワクしてくる。もしアンディがレズビアンだったら、どんな感じだろうと考えてしまう。なぜなら、私が思うに、彼の作品は彼がゲイであることによって定義されているからだ。クィアであることが、彼の作品を彼の作品たらしめている。もし彼が女性だったら、ユダヤ人女性だったらどんなだろう、と考える。私と同じ年齢のユダヤ人の女性だったら? 彼は誰に夢中になるだろう? 彼が60年代に制作した鼻の整形手術の作品《Before and After》は、ユダヤ人の女の子としてロングアイランドで育った私にとって衝撃的だった。私のいたコミュニティと、アンディのコミュニティとでは、あの作品の受け取り方は全く異なるものだが、その違いに私はとても興味がある。私は、アンディがなぜバーブラを描かなかったのか、長いことその理由を考えていた。彼があの作品を作っていたとき、彼女はすでに大スターだったのに。
バーブラを描かなかったのは、(ユダヤ人である)彼女がアウトサイダーで、ある意味アンディと同類だったからなのかもしれない。彼女は民族的な意味でのアウトサイダーで、アンディはクィアであるという意味でのアウトサイダーだったが、文化的には彼らは同じ位置付けにあった。彼は自分を映し出してくれるものには興味がなく、ハリウッドが定義するような完璧なアメリカの男らしさ、完璧なアメリカの美しさを表現したかった。つまり、ゲイで、移民の子で、パッとしない容姿の自分が手に入れることができない、キラキラした魅力を描きたかったのだ。
私がバーブラに惹かれたのは、民族的な理由もある。彼女が出てきたとき、私の両親のような人たちは、「ユダヤ人らしすぎる」と言って彼女を嫌っていた。なぜあの娘は鼻を直さないのか、(すぐにユダヤ人だと分かる)名前を変えないのかと言って。でも、思春期にバーブラ・ストライサンドに出会ったとき、やっと自己投影できるスターが出てきたとゾクゾクした。当時13、14歳くらいだった私と同じ年頃の、多くのゲイの男の子も彼女に対して似たような気持ちを抱いたと思う。パワフルで、才能があって、ありのままの自分をさらけ出し、周りと違っていることに共感を覚えた。彼女は私にとって、アンディが理想としていたエルビスだった。この延長線上にあるのが、ガートルードの肖像だ。文化を外側から見る視点は重要だと思う。たとえば、ガートルードは、英語で書くためにはフランスに住まなければならないと言っていた。そしてアンディがアメリカ文化を正確に映し出すためには、おそらくゲイの白人男性でなければならなかった。文化の外に立ちながら、さまざまな方法でそれを試してみることは、ドラァグにも似て、いかにも同性愛者的な戦略だと思う。
私たちはこのような力強いロールモデルを必要としている。ゲイやレズビアン、女性、黒人など、権力を持たない人々にとっては厳しい世の中だからだ。たとえば、あなたがレズビアンである場合、それはつまり、あなたが個人として大切な何かを理解したということを意味する。ところが、いざそうなると、たちまちあなたのことを見たくない、聞きたくないという文化に直面することになる。あなた自身がようやく受け入れた「自分」を否定されてしまうのだ。残念ながら、それはアートコミュニティにも当てはまる。アートコミュニティがレズビアンを深く嫌悪していることは、この世界の権力構造を見れば一目瞭然だと思う。力のあるディーラー、コレクター、アーティストは、ゲイであろうとストレートであろうと、みんな男性だ。これについては、私が愛するすべてのゲイたちに引かれてしまう危険を冒してでも言っておきたい。レズビアンがゲイと同じくらい、女性が男性と同じくらい、黒人が白人と同じくらい稼ぐようにならないと、状況は変わらない。それは単純に数の問題だ。
昔に比べて状況が変化しているとは思えない。なにせ、フェミニズムという進化し続けるイデオロギーから生まれた30年分のアートを美術館が取り上げたのが、「Bad Girls」展(*3)ただ1つだけというありさまなのだ。しかも、同展はフェミニズムの歴史的文脈を軽視している。とはいえ、男性が仕切っているあらゆる美術館から無視されてきたこの重要な運動の、全ての側面を見せなければならないという重荷をこの展覧会が背負っていたことも無視できない。
*3 1994年にニューヨークのニューミュージアムで開催された展覧会。これに続いて「Bad Girls West」という姉妹展がカリフォルニア大学ロサンゼルス校のワイト・アート・ギャラリーで開催された。
フェミニズムから影響を受けたアートについて、歴史的視座に立つ大規模な展覧会を企画しないのは、女性アーティストの声をかき消すための分かりやすい方法だ。しかし、もっと目立たない方法もある。その1つが市場の形成だ。80年代を振り返ると、どのキュレーターたちも同じことをしていた。ストレートな白人男性アーティストを何人か集めて、(たとえば)「ネオ・エクスプレッショニズム」や「ネオ・ジオ」と名付け、手を変え品を変えて1シーズンに10回ほど似たような展覧会を開催し、それを3シーズン続ける。そうやって市場が作られていくが、彼ら以外のアーティストの作品は見向きもされなくなる。
あるいは、ストレートの白人男性の中堅アーティストの回顧展を開催し、展覧会カタログのために何本ものエッセイの執筆を依頼する。いくつかのエッセイでは「70年代のフェミニストアーティスト」というフレーズが使われるが、どれ1つとして、有名になった当の男性アーティストに影響を与えた女性たちの名前を挙げはしない。そうやって女性を黙らせ、キャリアを消し、歴史上存在したものをなかったことにする。将来は、名もない「ゲイやレズビアンのアーティスト」について言及されることがあるかもしれない。「90年代に活躍した、多様な文化的背景を持つアーティストたち」とか、「あのホイットニー・ビエンナーレ」というフレーズで歴史が書き換えられていくかもしれない。20年もアート界で同じようなことが繰り返されるのを見ていると、なかったことにするカラクリが分かってくる。
では、どうすればいいのか。アート界すら変えられないのだから、アートが社会変革の触媒として有効だとは思えない。アートは私にとって、たまたま情熱を傾けられるものにすぎない。時にはそう思えない瞬間もあるが、そんな時でも、かつて誰かの作品を見てそれが可能だと思った経験があるから続けているのだ。最終的に私が1番大事にしているのは、自分と関係のあるさまざまなコミュニティに対する責任だ。このインタビューに応じるのは、マーケティング戦術としては賢い選択だとは言い難い。でも、若いレズビアンのアーティストがこれを読んで、ほかにもレズビアンがいるんだと知ってくれるかもしれないから引き受けた。
この話は、ゲイやレズビアンのアートは存在するのか、という質問につながる。それは、25年前から女性たちに向けられてきた「女性のアート」はあるのか、という問いと同じだ。もちろんあるに決まっている。「男性のアート」があるのと同じように。ゲットー化は問題か? 大問題だと思う。だから、白人のストレート男性が自分たちの安全なゲットーからようやく抜け出そうと決めたのは、とても良いことだと思う。彼らはあまりにも長い間、ゲットー化されてきたし、私たちは何千年もの間、このゲットーを外側から眺めてきた。その囲いの中は、世界で最も地価が高い一等地だ。彼らは外界に出てきて、私たちと一緒に競争するべきだ。怖がっている場合ではない。地獄で会おうぜ、ベイビー!
2. 「ゲイが題材のアートで同性愛嫌悪をなくせるなんて楽観的過ぎる」──ケーリー・S・レイボヴィッツ/キャンディアス
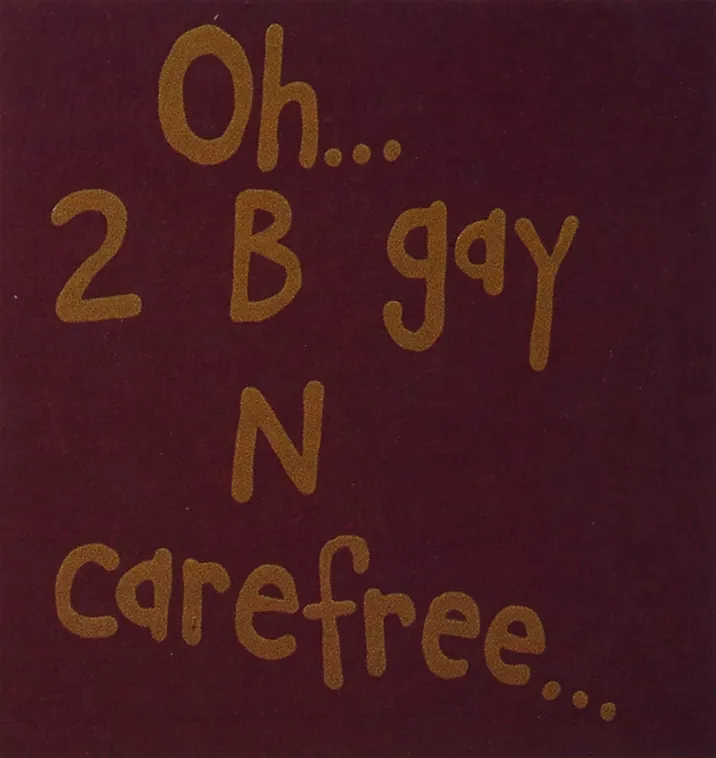
あなたが来るから掃除をしようとしたけれど、すぐ気が散ってしまって。ほら、ここに、こんなものがあった。去年の秋に日本で開いた展覧会のカタログ。向こうでは思ったより英語が通じなかったけれど、みんな私が何も知らない人みたいに手取り足取りしてくれたので、とてもよかった。そういうのは嫌いじゃないから。本当に1分たりとも放っておかれることはなかった。1987年に友人から「Candyass(臆病者、恥ずかしがり屋)」という言葉のゴム印をもらって以来、それでドローイングに印をつけるようになって、そのうち、それを自分の名前に加えるようになった。ユダヤ人の会計士とラッパーのユニットみたいだなと思ったから。日本語には「ass」(ケツ)という言葉がないので、カタログには「キャンディのお尻」と書かれている。
ほかに、こんなものもある。これは私が13歳の時に描いた、典型的なゲイボーイアート。当時の私にとって憧れの世界を描いた架空の郊外の街並みで、古き良きアメリカって感じ。まるでグランマ・モーゼスか、その同性愛者のひ孫が描いたみたい。ほら、一軒一軒違うでしょ? こっぱずかしいのは自分でも分かってる。
小学1年生の時から、「フランク・ロイド・ライトのような有名な建築家になりたい」という作文を書いていた。シェリル叔母さんが彼についての本をくれたから。私がライトに一番近づけたのは、この2つのサイドテーブル。安い家具のオークションで見つけて、あまりにブサイクだったからつい買ってしまった。その後、裏側に彼の名前が記されているのを見つけた。でも実は、私にとっての3大ヒーローは、ピーター・ソール、アンディ・ウォーホル、ロバート・ヴェンチューリ。エミリオ・プッチも大好きだけれど、ヒーローじゃない。でも今使っている財布はプッチのもの。人からはおしゃれだと思われてないかもしれないけれど、自分ではそうだと思っている。
プラット・インスティテュートで建築を学んでいたけれど、その学部が嫌いで絵画に専攻替えして、さらにインテリアデザイン学部に移った。でも、これも大嫌いだった。自分のやりたいようにしたくて、いつも先生たちと喧嘩していた。それで、1983年にFIT(Fashion Institute of Technology:ニューヨーク州立大学の1つ)に行くことにした。インテリア・デザイナーになるのには、そっちの方が適していると思ったから。プラットが力を入れていたのは、レストランの内装って感じだったかな。FITの先生たちは、私のやることを頭ごなしに否定しなかったし、有名なデザイナーが講評に来ることもあった。私は何年も前から雑誌で彼らの作品を見ていて(10歳の頃からアーキテクチュラル・ダイジェスト誌を購読していた)、何人かのデザイナーからインターンとして働かないかと誘われた。行ってみたら、彼らは本当にひどい人たちで、こんな生活は絶対イヤだと思ったけれど。
実は中西部に行くことにロマンを感じていたので、アイオワ、インディアナ、カンザスの学校を見学して、カンザスの学校が一番気に入らなかったからそこを選んだ。当時の私はそういう感じで物事を決めていたから。行ってみたら楽しくて、美術史学科は居心地がよかったし、美術学部の図書館での仕事も見つかった。うまくいっていたけれど、卒業制作展には参加させてもらえなかった。教授たちは私の作品が気に入らず、「こんな作品で卒業できると下級生たちに思われたら困る」と言われた。だから私は、教室を会場にして自分で展覧会を開くことにした。テレビドラマ「パートリッジ・ファミリー」の音楽をBGMにして、ポルノ雑誌のコラージュや、「ウィッシュ、フィッシュ、ディッシュ、リリアン・ギッシュ」とかそういうことを厚紙に書いた詩画も展示した。図書館の司書たちはみんな見にきてくれたし、作品を買っていく人もいた。どの作品も10ドルか20ドルくらい。お気に入りの作品には、「マイケル・ジャクソンより君を愛してる」と書かれていた。それにどれほど深い意味があるのか、さっぱり分からなかったけれど。
当時、私はスターン兄弟(ダグとマイクの双子の写真家・現代アート作家)の作品が好きだったので、ボストンに引っ越した。そこで新しいムーブメントが生まれていると思ったから。でも行ってみたら、そんなことはなかったし、その頃にはスターン兄弟もそこに住んでいなかったと思う。結局何年かボストンで暮らして、展覧会をやることはないだろうと諦めかけていたら、ある人がボストン現代美術館(ICA)で毎年「ボストン・ナウ」という地元アーティストの公募展をやっていると教えてくれた。私は、自分の負け犬っぷりを世界に知らしめてやろうと、ICAに完全にイカれた手紙を送りつけた。そうしたら、入選して展覧会に参加できてしまった。そこからすべてがトントン拍子に進んで、今に至るというわけ。
「ゲイのアーティスト」と呼ばれることに、抵抗感は一切ない。私の作品は私自身についてのもので、私はゲイだから。数年前、「Go Fags(がんばれ!オカマ)」と「Homo State(ホモ・ステート)」と書かれたペナントを作った。ハーシュホーン博物館と彫刻の庭でのグループ展に参加したときは、アンチの論客がテレビで騒ぐような強烈な絵ではなく、「ゲイアート」という言葉を入れた作品を展示した。ストーンウォールの記念日のためには、ピンク、白、青のヤムルカ(ユダヤ人男性が被る小さな帽子のようなもの)を作ろうと思ってる。学生時代、私が見聞きしたことのあるアーティストたちは、みんなすごいインテリばかりだった。私には理論武装なんて無理だから、自分なりにやるしかないと思った。それで、自伝的な作品を作りはじめた。
レッテル貼りに文句を言う人たちにはイラっとする。世の中はそういうものだと思うから。すべてのものにレッテルが貼られるし、もし貼られていないなら、それはまだ誰もそれについて話題にしていないから。街でエイズ撲滅運動の赤いリボンをつけている人の何が問題なんだろう? ACT UP(エイズ撲滅を目指す国際的な草の根運動)のメンバーからしたら物足りないかもしれないけれど、多くの人にとっては大きな一歩だし。私が自分の家でこういう作品を作るのは簡単だけど、それを家に飾ってくれる人たちにとっては大変なこと。ガスや水道の修理の人なんかに見られたりすると気を使うから。
私の作品の一部には、確かにある種のゲイらしさがあると思う。たとえそれが8歳児みたいなセンスで、定義するのが難しいものだとしても。ひょっとすると、いかにもゲイっぽいと言えるのかもしれない。たとえば、14番街で買ったペアの磁器人形にペイントした歴史的なレズビアンのシリーズなんかもそう。私は子どもの頃、こういうものが大好きだった。磁器で出来た小鳥や花の置物を見ると、つい買ってしまう。それと、マルティプル(*4)も大好き。自分の展覧会の会場で、見にきてくれた人から「あなたの作品を壁一面に飾っていて、まるでキャンディアスの祭壇みたいになっている」と言われると嬉しくなる。マルティプルにすると手軽にたくさん買えるし、高価な一点もので保存に苦労するよりいいんじゃないかな。私はたくさんの作品を無料で配ったり、安く売ったりしている。アートの民主化のためだと言いたいところだけれど、私自身買い物が大好きだからだと思う。どの作品も、エディションを作りすぎてしまう。「これは人気が出そうだ」と思うと、足りなくなるのが心配になって。欲しいと思っている人に、「在庫切れです」と言うのが辛いから。
*4 量産されたアート作品。1点ものではないため安価に購入することができる
私にとってフェミニズムは、自然な考え方。そのマイルドなバージョンに浸って育ってきたから。母は若くて、私とは21歳しか歳が離れていない。子どもの頃はいつも母の味方だった。ビリー・ジーン・キングがボビー・リッグスと対戦(*5)したのは、私が小学校3年生の時だったと思うけれど、もちろんビリー・ジーン・キングを応援していた。ただ、フェミニズムに問題を感じたことが1度だけある。カンザス州のローレンスで、分離主義者のレズビアンのグループが、男だからという理由で私を悪人扱いした。その時は、罪悪感を覚えると同時に腹が立った。見るからにホモっぽい私は生まれてこの方ずっと、いつ殴りかかられるか戦々恐々としている。だから、女性になって道端に泣き崩れられたらどんなにいいかと思う。そうしたら、「オカマ野郎、自力でなんとかすればいい」と見放されるかわりに、誰かが助け起こしに来てくれるから。
*5 1973年にテキサスで行われたテニスの男女対抗試合。世界中の話題を集めたこの試合でキングが圧勝したことで女子テニスが興行として注目され始め、賞金などの男女格差の是正に繋がっていった。
政治的なゲイのアートが登場する以前のアート界がどんな感じだったのか、私は直接知らない。前の世代に比べたら私は苦労していないと思う。展覧会を開けるのは、アート界が私の作品を受け入れてくれるからだし。とはいえ、どんなに皆が大丈夫だと言ってくれても、この状況がずっと続くわけじゃないことは知っている。美術雑誌の大昔のバックナンバーをめくっていると、載っているのは聞いたことがない作家ばかりだと気づかされる。少し不安だけれど、あまり気にしてない。たぶん、もうちょっとすると私は落ち目になるかもしれない。でも、ほかに何をすればいいのか分からない。一方で、流行は繰り返すものだし、私もそれに期待している。まだ売れてない作品はいっぱいある。80年代後半から90年代前半にかけて作った作品が1200点ほどあるので、20年後くらいにリバイバルが来たら、いつでも売れるよう準備を整えておく。この部屋にある物を地下室に移動させたとき、ルームメイトたちに手伝ってもらったんだけれど、いつまで経っても作業が終わらなくて。1人が「燃やしたら?」と言ってきたから、私は「これは私の老後資金!」とやり返した。
ゲイを題材にしたアートで同性愛嫌悪の風潮を変えられるなんて楽観的過ぎると思うし、どんな理由であれ、自分のアートを重要視するのは絶対にイヤだ。深刻で偉そうなアートは大嫌い。たぶん、コメディタッチの作品を作り続けているのはそれが理由だと思う。あるいは、そういうやり方でしか物事に対処できないのかもしれない。とにかく、それが私の得意分野。文章を面白おかしく編集するのは得意だし。私はできる限り、自分の展覧会の会場にいるようにしている。そうすれば、作品を真面目くさったアートのレベルから引き降ろせるから。アーティストが会場にいれば──特に私みたいなのがいれば──多くの人が「あ、分かりやすい」とか、「バカっぽい」とか、「これ好き」と思ってくれるはずで、変に崇拝したりしないと思うから。
3. 「弱いことがパワフルな表現になり得るし、変化を促す方法になり得る」──ヒュー・スティアーズ

私は自分の絵を、個人的な意識の寓意、あるいはその象徴だと考えている。もちろん、美術史からの引用も多く含まれている。《Man & IV》という作品は、「Hospital Man」というシリーズの一部で、ヨーロッパ絵画の定番である権力者の肖像を参照したものだ。腰に手を当てたポーズは、ヴァン・ダイクやベラスケスが描いた人物像を彷彿とさせる。王権を象徴する笏(しゃく)の代わりに点滴のスタンドを脇に添えて、ベッドは非常に帝国的な感じだ。こうしたモチーフは、ある種の主題を示唆しておきながら、それを混乱させる。病院の白いガウンは、赤ちゃん人形が着ているドレスか洗礼衣のようで、うっすらと天使のような雰囲気が漂っているように見えるかもしれない。
最近仕上げた別の絵では、病院のベッドに横たわる2人の裸の男たちを描いた。1人は胸にカテーテルを入れられていて、管が体に入っていく場所にもう1人がキスをしている。このヒックマンカテーテルは、中心静脈に挿入するゴム製のチューブで、エイズによる失明を防ぐための投薬に使われる。失明に関しては私自身も心配しているが、この装置は身体にとっては侵略とも言える奇妙な異物だ。一度埋め込んだらずっと入れておかないといけないし、それがもとで感染症に罹って死んでしまう人もたくさんいる。だけど、この絵自体は、病気をエロティックに捉えている。エイズというのは、非常に独特で複雑で計り知れない現象だ。セックスや自分自身に対する認識、欲望と結びついているものだからだ。私は、絵の中でこれらすべてを表現しようとしている。
私は昔からずっと具象的な作品を描いてきた。なぜなのかは分からない。おそらく、私の社会的な背景や、昔から絵を描くのが得意だったことが関係しているんだろう。高校時代に、その能力を伸ばしてくれる良い先生に出会えたことも大きかった。1989年にミッドタウン・ペイソン・ギャラリーで展覧会を開いた時、ギャラリーは私のことをポール・カドムスのようなリアリズムの画家の系譜の中に位置付けていた。だが、私自身はそうは思っていなかった。私は自分のやっていることを、写真やコンセプチュアル・アートと同列の、現代アートの文脈の中で捉えていた。そういう作品については美術史の授業で学んでいて、イェール大学在学中もたくさん見ていた。それはともかく、1991年になる頃には、ギャラリーにとって私の作品は売りにくいものになってきていた。女装をモチーフにすることが多くなってからは特に。最初のうちは、そういう絵も受け入れてくれていた。どこか控えめで、申し訳なさそうに描いていたからだと思う。でも次第に、「ヒールを履いて何が悪い」という感じで、悪びれずに真っ向からそれを表現するようになった。それで、所属ギャラリーをリチャード・アンダーソンに変えたんだ。
私の作品には最初から「ゲイ」の要素があった。だが、こういう概念自体は問題だし、議論が必要だと思う。自分は「ゲイカルチャー」の中では、完全に余所者のように感じる。その一方で、私が描くものは、自分の経験や、周りで起きていることに対する反応から生まれたものだ。高校時代はずっとゲイであることを隠していたが、男性ヌードを描いたり、マレーネ・ディートリッヒがシルクハットをかぶってタバコを燻らすアイゼンスタットの写真に影響された絵を描いたりしていた。それから、フランス語の授業で読んでいたラシーヌの『フェードル』(*6)に着想を得た小さな絵も描いた。これ以上の「禁断の愛」があるだろうか?
*6 ギリシャ神話を題材にした戯曲。主人公のフェードルは義理の息子に恋をしてしまう。その息子は、父を裏切った人物の娘に恋をしている。
最近になってようやく、同性愛者たちの声が表に出てくるようになってきた。そして、堂々と才能を伸ばしたり、互いに影響し合ったりできるようになってきた。その過程で明らかになってきた重要なことは、ゲイという文脈の中でも、ストレートの文脈と同じように多種多様なあり方が存在するということだ。ゲイの表現は1種類ではなないし、「ゲイアート」はマーケティング用のレッテルだ。それを回避できるかどうかは難しい部分もあるが、そのことを議論し、私たちをひとくくりにすることの愚かさを暴くことは大事だと思う。
マイノリティの作品に対する批評のあり方の問題点を認識することも重要だ。批評家から絶賛されているので見にいくと、実際はひどい代物だったりする。これは作家をバカにしていると思う。なぜ、すべての人を同じ基準で評価しないのか? 品質の問題は重要だ。私だってそういう風に下駄を履かせてもらいたくない。私は、ひたすらアートに心血を注いで、それを認めさせることが自分の仕事だと思っている。たまたまゲイだからという理由で、変にひいきされたくない。
それから、アートが真実を暴くとか、潜在意識をあらわにするといった考え方はしないようにしている。そうではなく、新しい絵を描くごとに、新たな真実や意識が生み出されていると考えている。基本的にアーティストというのは、しっかりと自分の仕事をしていれば、自分よりも先に進むことができる。この病院の絵のシリーズは、私が自分のセクシュアリティや病気を受け入れるのを助けてくれた。それを描く過程で、作品が私の人生に影響を及ぼしていると感じる。
私は怒りを糧に制作をするのは得意じゃないが、少し前に、ものすごく高いヒールの靴を履いた黒人男性の大きな絵を描いた。それを見て、ハイヒールは象徴だと気づいたんだ。ヒールが高くなればなるほど主張が強くなって、怒りを入れる容器としての特徴が強くなる。それは挑戦的な姿勢、攻撃的なまでのセクシュアリティを表している。それと同時に、足をすくませ、動きを縛る、不自然なものでもある。私はその全てを受け入れようとしている。自分の中にあるそういう要素を全部受け入れようと。男らしさと結びつけられている通常のパワーとは対照的に、弱さ・傷つきやすさもパワーの源となり得る。弱いことがパワフルな表現になり得ること、変化を促す方法になり得ることについて、もっと話し合うべきじゃないだろうか。
1991年の1月に入院して、その時から病院を描くようになった。今はそのテーマをどんどん広げているところで、直近の2つの展覧会で発表した作品にも登場した浴室のモチーフもその一部だ。それは私の病気と結びついている。浴室は、文化と本能のぶつかり合いを表すものでもある。私たちはそこで糞や小便をし、気持ち悪くなった時には吐いて、そして体を洗う。いろんな記号を身につける前、私たちはそこで裸になっている。それから、浴室でもう1つすごいと思うのは、そこには排泄物を入れるために人間が作ったいろいろな彫刻があるということだ。
病気はとても重要なテーマだ。誰もが病気を恐れている。特にアメリカでは異常なまでに清潔を保つことにこだわり、死の可能性にビクビクしている。ほんの100年前までは風邪をひいて死んでいたのに。これらの作品はすべて、私がエイズを発症し、それに対処しなければならないことから生まれている。どうすれば、それを受け入れ納得できるようになるのか。あるいは、どうすればそれと共存しながら制作を続け、そこから先に進めるのか。絶望の中で毎日をどう生きればいいのか。
もう1つ付け加えるとすると、私の作品の多くは、狩りを成功させるために洞窟に狩りの絵を描くという原始的な発想と通じるものがある。それは呪術みたいなものだ。私自身も、私の絵の中の人たちのように行動したいし、優しくしてもらいたい。描くことで、それが現実になるのを期待している。男性がもう1人の男性を抱いている絵は、そういう優しさ、ずっと私を気にかけてくれ、そばにいてくれる人がいたら、という願いが込められたおまじないなんだ。それは希望的観測であり、同じ状況にいてトラウマを抱えた人たちの指標のようなものでもある。彼らはそれを見て、「ほかにも同じ経験をした人がいる」と感じることができる。《イーゼンハイムの祭壇画》(マティアス・グリューネヴァルト作)には、ひどい皮膚病に苦しんでいる人物が描かれているが、この絵は恐ろしい皮膚病を患う人々が治療を受けていた修道院のために描かれたものらしい。私の絵を見た人の中には、それを生々しすぎると感じる人もいる。でも、一方ではこう言ってくれる人もいるんだ。「よく描いてくれた。私たちの生活の一部を絵の中で見ることができて嬉しい」と。
4. 「本当の問いは社会変革のプロセスにアートが参加できるかどうか」──ドナルド・モフェット
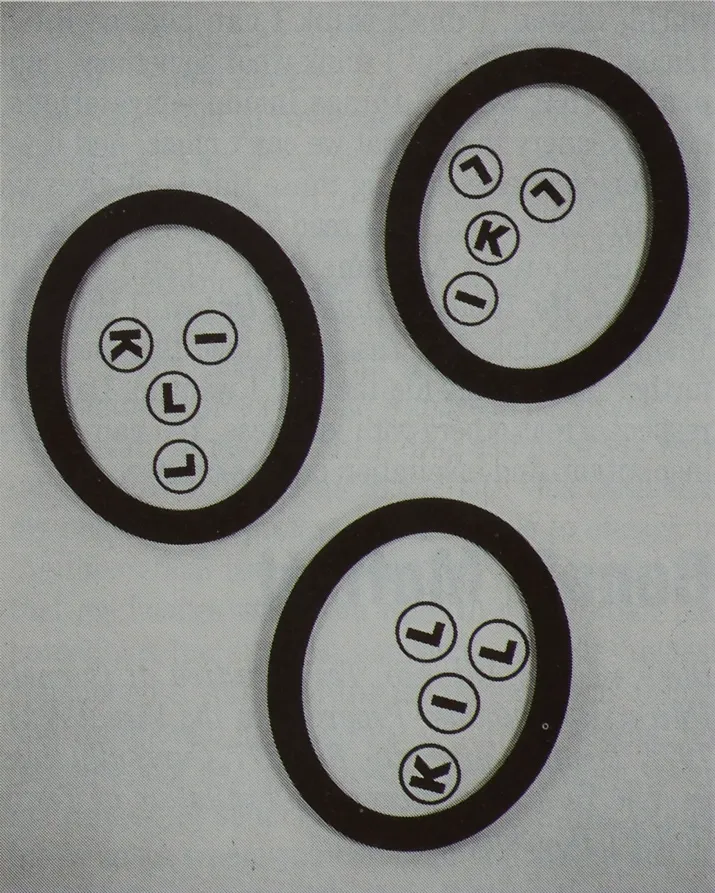
親愛なるホランド・コッター様
あなたの質問に対する答えは、ジョイスの『ユリシーズ』の最後の一節のように、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエスだ。全てイエスとセックス。答えは分かっていたが、あなたの手紙を受け取ってからというもの、あまりよく眠れなかった。正直言って、この特集は私を不安にさせる。スキャッター・アート(モノを床に散乱させた現代アート作品)の特集で取り上げられるよりはマシかもしれないが。
それはともかく、「フェミニズムはあなたのアートにどの程度影響を与えましたか?」という質問に関しては、この領域で最も厳しく、最も尊敬する3人の師匠の名前を挙げることで説明に代えさせてほしい。それは、バーバラ・ジョーダン(アフリカ系アメリカ人の女性政治家)、バーバラ・クルーガー、メディア(ギリシャ神話に登場する王女)だ。
「アートは社会を変えられると思いますか?」という質問に対する回答は、ヨーロッパの歴史を見ると、もちろん「イエス」。でも今は? 難しいだろう。アートは、映画やテレビの狂騒と華やかさ(そして明らかに社会を変えられる力)の影で、ますます不安げに縮こまっているように感じられる。オペラが社会を変えることができるのかと問うようなもので、答えはノーだ。今はもう変えられない。
しかし、オペラがこの役割をほとんど放棄しているのに対し、大部分のアートはまだそうではない。つまり、私からすれば、本当の問いは社会変革のプロセスにアートが参加できるかどうか(あるいは参加させてもらえるかどうか)だ。アートとそれを世に広めようとする業界は、あなたが言うところの「より大きなコミュニティ」、つまり世界と「つながるための通路」を再構築できるだろうか? それができると期待したい。この業界はなんだか息苦しいから。
「リスクとリターン」についての質問だが、深刻なリスクというのは、すべてのアーティストが常に直面しているものだ。ただ、コンテンツの飽和によってそれが少々増幅されている。アート界の衰弱し痩せた経済的土壌の上で、私が果たして生きていけるのかどうか疑問だ。だが、ほんのわずかなリターンとして、蔓延する異性愛的価値観という図体のデカいまぬけを愚弄できることの純粋な喜びについて記しておきたい。危険な不安と思い込みに駆られた、この独りよがりののろま。我々のように怒りというモップと消毒薬を持ったごく少数の者たちを除いて、ほとんど全員を窒息させるネバネバした分泌物のような存在を。
「エイズの流行は、あなたのアートにどの程度影響を与えていますか?」という問いについては、エイズによる大惨事は、今も引き続きアーティストとしての私の野心に冷や水を浴びせ、脅かし続けている。愛、セックス、暴力、死という、残酷な円環が(毎日)私の目の前で繰り広げられ、そして、それが私の作品となる穴に栄養を供給している。最後に「ストーンウォールの反乱については?」全面的に支持する。
真心を込めて、ドナルド・モフェット
(翻訳:野澤朋代)
from ARTnews


