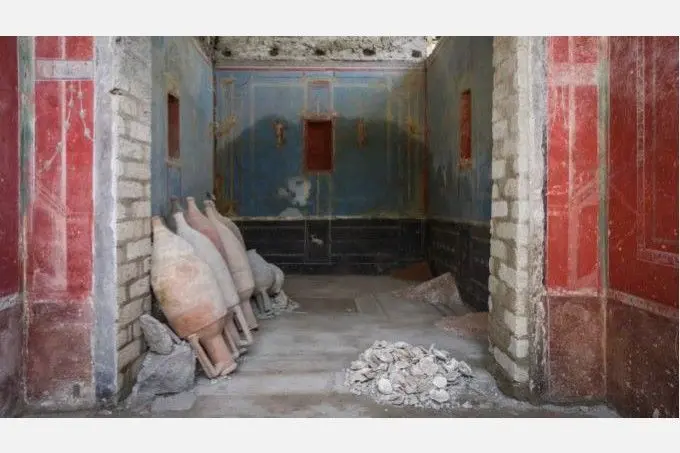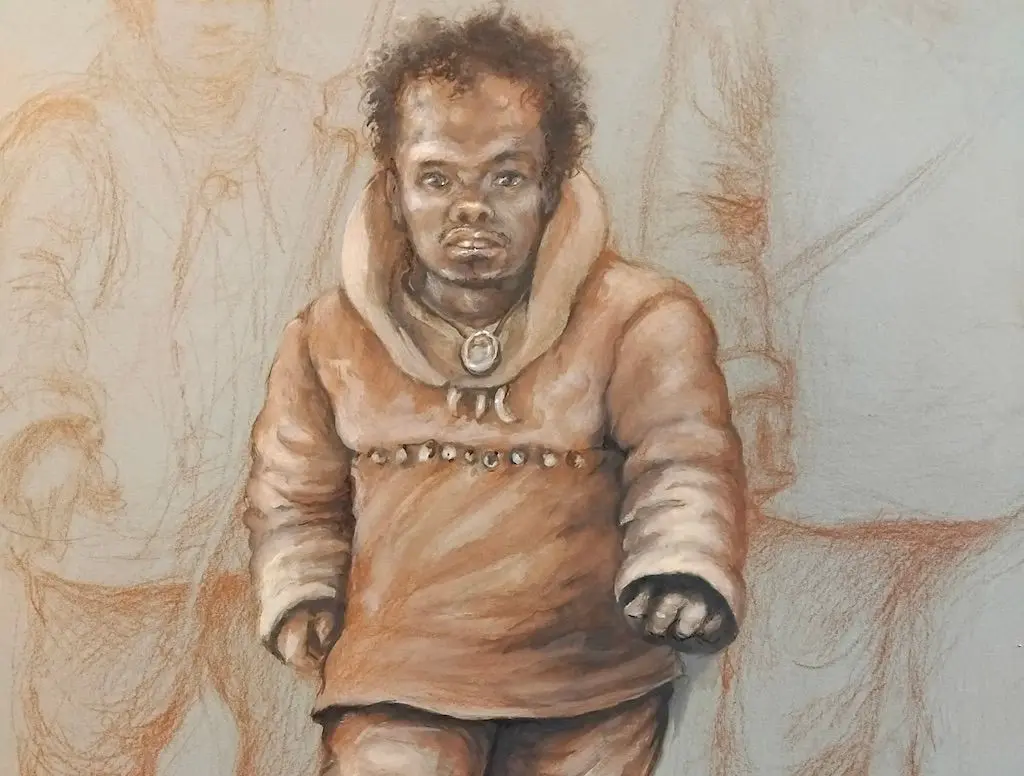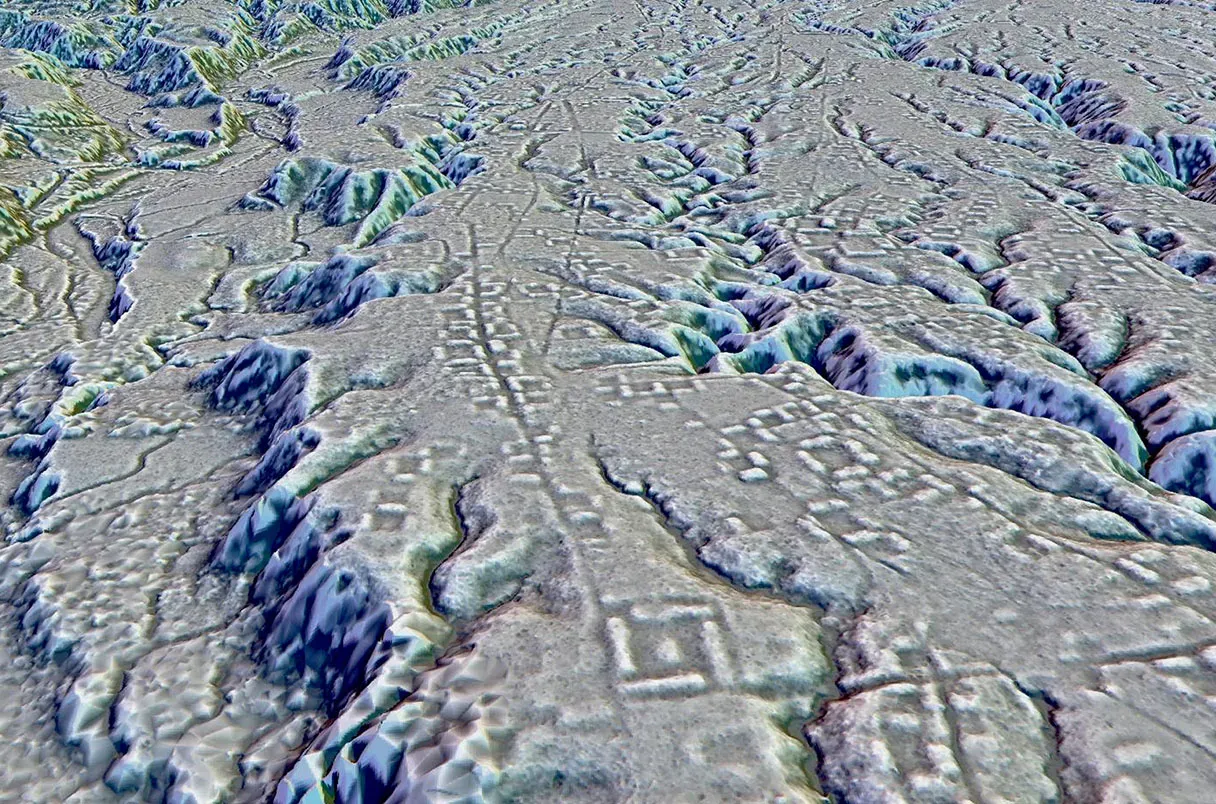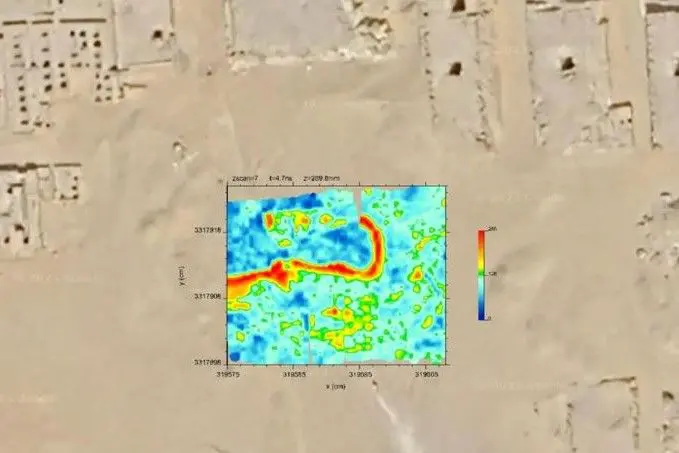1500年前の銀貨が交易史を書き換える! 最新研究でベトナム・バングラデシュ間の技術の交流が判明
シンガポール国立大学の研究者らが東南アジア各地で発見された4世紀以降の銀貨「ライジングサン/シュリヴァツァ」を調査した結果、バングラデシュとベトナムで作られたものが同じ鋳型である可能性が高いことが判明。これにより、当時すでに東南アジアには2000キロメートル以上に渡る交易圏が築かれていたことが分かった。

シンガポール国立大学の研究者らが、東南アジア各地で見つかった4世紀以降の銀貨245点を調査したところ、バングラデシュとベトナムで作られたものが同じ鋳型である可能性が高いことが判明した。研究成果は8月12日に学術誌「Antiquity」で発表された。
調査対象となったのは、ミャンマー、カンボジア、ベトナム、タイから出土した銀貨「ライジングサン/シュリヴァツァ」。表と裏にそれぞれ太陽の昇る図柄と、ヒンドゥー教のシンボルであるシュリヴァツァが刻印されていることからその名が付けられている。研究者たちが「ライジングサン/シュリヴァツァ」の図案や重量、製造技術を綿密に調査した結果、バングラデシュとベトナムのものが同じ鋳型から打たれたと考えられる類似性を発見した。
中国の記録には、すでに2世紀ごろからペルシアと中国間の各地域には交易ネットワークが張られていたと記されている。今回の調査結果はそれを裏付けるものであり、地域間で鋳造技術が文化を越えて共有され、ある時点でこの2つのグループが2000キロメートル以上の距離を超えて直接交易を行っていたことを示している。
古代世界において貨幣は大きな重要性を持っていた。共通の図案を使用することは政治的に同盟関係であることを示す一方、他と類似しない図案や独特な材料加工は関係の分裂や意思疎通の断絶を示唆することがある。それを受けて、研究の共著者でプロジェクトの主任研究者であるマリア・デ・イオリオはサイエンティフィック・ニュース・トゥデイの取材に対して、「私たちの鋳型を巡る研究は、東南アジア本土における通貨ベースの経済の拡大と収縮を地図に示すのに役立ちます。それは同時に主要港湾、交易拠点、そして政治権力の変化を明らかにするものでもあります」と語り、今後の調査に期待を寄せた。
今回の発見について、筆頭著者のアンドリュー・ハリスは、「これは広範囲にわたる長距離流通の説得力のある証拠を提供しています。東南アジアを孤立した王国の集合体としてではなく、動的で結ばれた地域として考えることを我々に迫るものです」と同メディアに話している。
多くの古代東南アジア銀貨は略奪、不法取引、破壊の危険にさらされており、ミャンマーで続く内戦のような政治的不安定は、考古学的遺跡をさらに脆弱にしている。これを踏まえてハリスは、「これらの研究は偽造品の特定、不法取引の抑制、そして遺物が個人コレクションに消えたり溶かされたりすることからの保護にも役立つ」と強調した。(翻訳:編集部)
from ARTnews