アートとジェンダー──芸術作品に映る差別・継承・女性蔑視問題を読み解く【アートで祝う国際女性デー】
フェミニズム研究者で東京大学総合文化研究科教授の清水晶子と、美術・文化研究者で金沢美術工芸大学で教鞭を執る山本浩貴が、フェミニズム・アーティストの具体的な作品を取り上げながら、マイノリティによる芸術実践の歴史をひも解く。アートが示唆する多様性の受容と、その可能性とは?

山本:皆さん、こんにちは。今回はフェミニズム研究者の清水晶子さんをゲストにお招きして、「アートとジェンダー」というテーマでお話をさせていただきたいと思っています。清水さん、よろしくお願いします。
清水:こんにちは、清水晶子です。大学で教員をしており、専門はフェミニズム理論・クィア理論です。わかりやすく言うと、私たちが自分の身体、体というものをどうやって感じているのか、感じ方が私たちの身体の外にあるはずの社会とか文化とどう関わっているのか等を研究しています。一言でいうと、性と身体をめぐる文化の政治を分析する、といったところでしょうか。今日はよろしくお願いいたします。
山本:よろしくお願いします。最初にミーティングをさせていただいたときに、清水さんが「自分はフェミニズムを代表する自分の意見は持ち合わせていない」とおっしゃっていた事が印象に残っているんですけど、そのあたりを最初にご説明いただけますか?
清水:「フェミニズムを代表しない」というのは、フェミニストなら誰でも言うんじゃないかと思います。フェミニズムってすごく広い。もちろん、女性の生存の可能性を狭めるというフェミニズムは基本的にはないはず。あるいは、権利を抑制するとか、差別を推進しようというフェミニズムも基本的にはないはずなんですけど、そこだけが一緒で、あとは本当に立場が皆さん違うんですよね。なので、「私はフェミニズムを代表して、こうやって言います」って、難しい表現になってしまうんです。
「クィア」とは?
山本:ありがとうございます。先ほどの自己紹介でも出てきましたが、「クィア」という用語も、簡単にご説明いただけますか?
清水:クィアという言葉も使われ方がすごく変わってくるので、「これです」というのは、とても難しいです。この用語が、文化あるいは学問の主流の場で使われるようになったのは、1990年前後で、もともと非常に強い侮蔑語だった、というイメージを引きずっていました。

1980年代を通じて、欧米諸国ではエイズの大流行があって、男性同性愛者や、トランスセクシャルのコミュニティが非常に大きな打撃を受けました。病気で打撃を受けるのと同時に、社会的なホモフォビア(同性愛嫌悪)も、ものすごく激化して、政治がそういった人たちを完全に見捨てる体制をとっていくんですよね。
それに対抗して、強い運動が出てきます。エイズ・アクティビズム、それから、それをベースにしたクィア・アクティビズムと言われるものです。この運動の中心思想は「主流の文化に迎合することを拒絶する」というものでした。
それから、クィアの運動というのは、そもそもあった記号イメージというのを、どういうふうにリアプロプリエーション(再盗用・再流用)していくのか、ということがとても重要で、つまり、そもそもクィアという非常に侮蔑語だった、強い侮蔑語だった言葉を、自分たちの言葉として使うことによって、言葉の音は変えないんだけれども、意味合いを完全に変えてしまおう、という狙いもあるんですね。
山本:そうするとクィアといったときに、たとえば「ホモセクシュアルな人たちのムーブメント」というようなイメージが先行しがちなんだけど、それだけではなく、メインストリームからある種存在しないものとされているというか、その存在自体をきちんと認識されなかったり、認められていない人たちが、対抗的な仕方で自分たちの存在を世の中に表現していく、みたいな捉え方でしょうか。
清水:そうですね。そういう側面があると思います。ちょっと難しくて、「同性愛の運動ではない」というと多分違うんですが、そこは常に両面を持っているというか、「同性愛者の運動だよね?」と言われたら、「同性愛者だけの運動ではない」と言いつつ、じゃあ「同性愛者の運動じゃないよね?」と言われたら、「いや、同性愛者の運動だ」と言うような、そういうところがクィアムーブメントにはあるんですね。
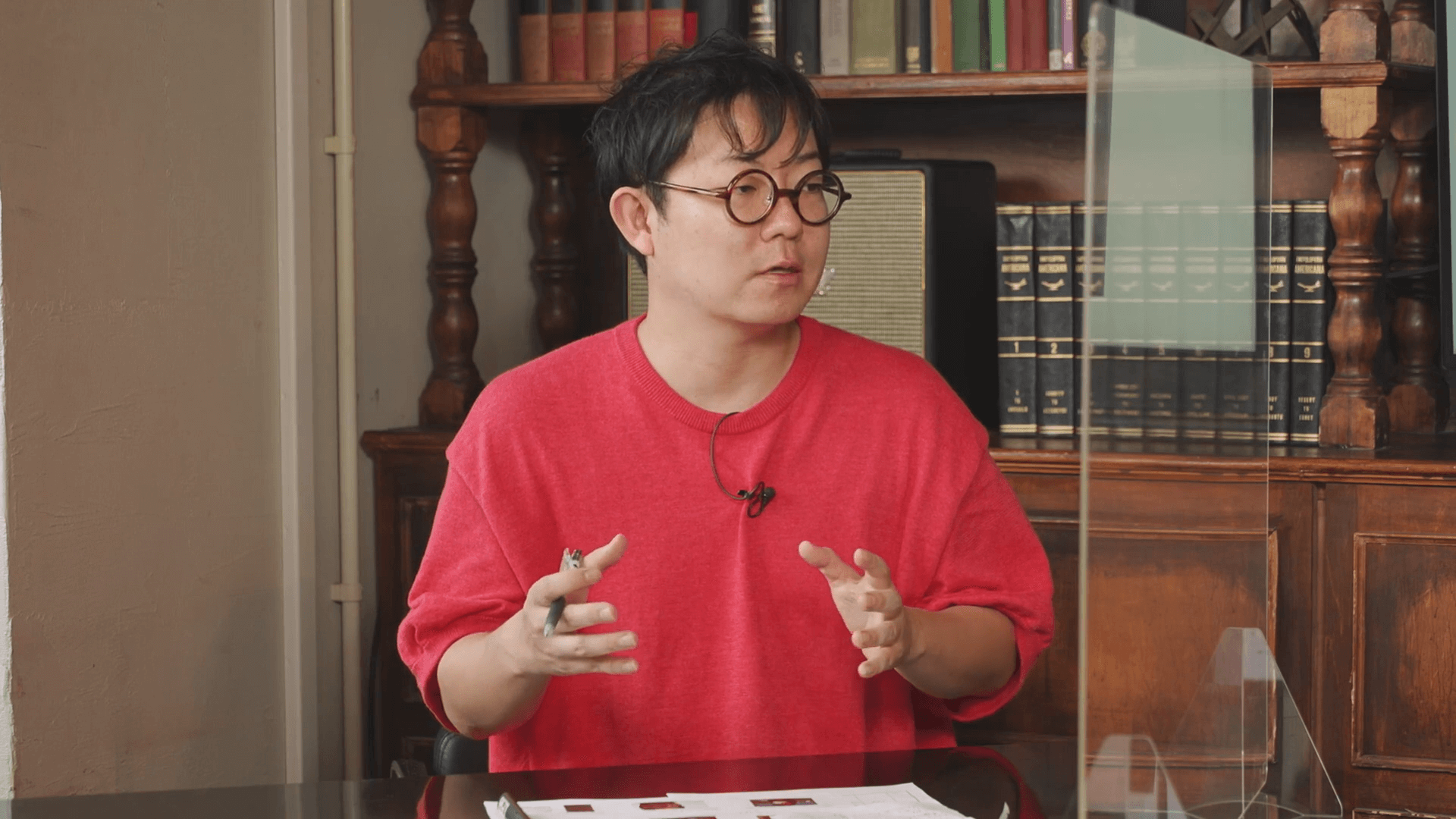
森村泰昌とシンディ・シャーマン
山本:ありがとうございます。それでは、いくつか作品に入っていきたいなと思います。清水さんは、博士論文のテーマが、森村泰昌さんとシンディ・シャーマンの作品研究なんですよね。
清水:はい、テーマ自体は可視性と自己表象の政治なのですが、お二人の作品を論じながら考えていくチャプターがあります。
博士論文研究をやったときに興味があったのは、私たちが「自分たちの身体を知る」というのはどういうことなのかという話だったんですね。そのときに、私の身体というのは私とズレがある。私は私の身体として生きているんだけれども、「私が、どういう人間か」という事と「私が、他の人からどういう人間かと判断されているか」というのは、結構違うんですね。
そうすると、私の身体を相手にどう受け止め「させる」ことができるだろうか、という問題が否応なく出てくる。実際に、フェミニズムの中では、女性性と仮面、あるいは演技性という問題が、ずっと議論されてきています。
つまり、女性性というのは、私の中から出てきているのか、そうではなくて、私が要求される社会的な要請によって私がそれを演じているのか、そもそもそのふたつに違いはあるのか、という事が、70年代から80年代を通して激しく議論されたんです。私は、そういう議論がおもしろくて好きだったんです。
リュス・イリガライというフランスの哲学者がミミクリー(擬態)という概念を使って女性性について考えています。これは、基本的に、女性は女性を演じないと、社会の中で生きていくことができない、だから、女性を演じるんだけれども、その演じている女性は私ではないし、本当は女性でもない。けれども演じないわけにはいかないので、むしろその女性性を演じきることによって「私はこんなに上手に演じていますが、これは演技なんですよね」という態度を獲得する、そうやって要求された演技としての女性性との間に距離をとる。
いろいろ細かく議論があるんですけど、この「ジェンダーの演技」というテーマに私はすごく興味があって、そこで森村さんとシンディ・シャーマンに行き着いたんです。
個人的には森村さんの作品を観ると、元気が出る。なんでかというと、森村さんはジェンダーというより人種も入っていますが、要するに、非西洋人の作家というのが、どういうふうに受け取られるのかということを念頭に置いたうえで、たとえばゴッホになって見せるっていう、まさにリュス・イリガライの提唱したようなことを実践するわけですよね。
そのときに、もちろんゴッホじゃないんだけど、森村さん自身が日本人の男性であるということが納得されているので、もちろんこれはゴッホじゃない。その事によって、ある種の批判だったり、西洋中心主義に対しての森村からの批判というのが見えてくるという、そこに新しい可能性が出てくる。それで、すごく元気になるんですね。
シンディ・シャーマンの作品は、森村さんの作品と対照的だと感じていて、彼女の場合は白人の女性ですよね。「白人の女性としてあるべき姿」を演じる。そのときにシャーマンとシャーマンが演じているイメージとの間に、もちろん同じじゃないんだけど、イメージがシャーマンの方に寄ってくるところがあって、森村さんの場合はある種安全な距離というのがイメージと自分の間にあるんだけど、シャーマンの場合はイメージと自分の間に、自分の安全性を確保するための距離が保てなくなっていく部分があるように思います。
シンディ・シャーマン

清水:実際に、たとえば1980年代の《untitled》はきれいに進んで行くんですけど、だんだんシャーマンの作品って、体が溶けていって目だけが残っていたりとか、吐瀉物だけが映っていたりとかってするようになっていって、イメージとの距離の置き方の困難、その距離が置けないということが、自分自身を破壊していくという事をとてもよく表している、というふうに考えました。
山本:その距離というのは、シャーマン自身が白人女性であり、白人女性のイメージを演じている。一方で、森村さんは、日本人であり西洋の人ではないという事を理解した上で、そのイメージを体現しているから、そこにはある程度安全な距離があるということですね。
「ジェンダーの演技」に潜む課題
山本:「ジェンダーの演技」に関して連想されるのが、スピバックも言っていた「戦略的本質」という概念です。僕が博士過程で勉強していたころの指導教官が、ソニア・ボイスという黒人女性作家なんですが、ソニアと話していたときに、彼女も80年代に黒人女性のある種のステレオタイプみたいなものを「ドローイング作品の中に、自分の写真を入れる」という手法で演じていました。
その一方で、ある種のジレンマを引き起こす部分ですが、受け手側に狙い通りに受け取られず、むしろそのステレオタイプを強化してしまうというか、場合によっては現状追認的な表現にもなってしまう時があります。
たとえば、シャーマンの場合は、その場にいることが、白人女性だからというのもあり、多少承認されている。その場にいることが承認されていない人ほど、とにかくその場にいるために使えるイメージを使うしかないという部分があって、しかし、それを使ってしまうと、今おっしゃったように、ステレオタイプに飲み込まれてしまうというか、イメージが自分を飲み込んでしまうという問題があるので、答えはないのですけど、そこはやはり、いろんなジェンダー表現を追及していくときの、大きな問題のひとつだろうと思っています。
山城知佳子が表現する継承「取り込みの暴力」
山本:次は、山城知佳子さんをご紹介します。取り上げるのは、《あなたの声は私の喉を通った》という作品です。この作品、山城さん自身のバックボーンである沖縄のことが語られています。清水さんは、山城さんの作品にご関心があるというお話をされていましたが、どういう視点で見てらっしゃるんですか。
清水:山城さんはこの作品と、《肉屋の女》という作品がありますが、それがとても好きで。記憶を継承するとか、引き継ぐとかっていうことを、山城さんはわりとよくテーマになさっていますね。
山本:そうですね。この《あなたの声は私の喉を通った》という作品も、映像内で山城さんと重なる、沖縄戦のサバイバーであるご老人の方々が、沖縄の戦争体験を語っていて、それを山城さんの身体を通して語っていくみたいな形式です。
清水:そうですね。声は向こうの声で、山城さんがリップシンクしていくということなんですが、山城さんの作品って、継承がスムーズにいかない感覚というのがあって、それこそタイトル通り「あなたの声は私の喉を通った」というふうには、スルっと通らない。この作品中の山城さんは、ずっと苦しそうなんです。
もちろん、語りの内容がとても辛いという側面はあるのですが、それ以上のものを感じさせる一面もあるというふうに思っていて、たとえば「なにかを継承する」という行為は、他者を自分の中に1回取り込んで、その上で、それを自分の問題として発信していく、という側面があるわけですよね。
それはとても重要で、私たちはそれをしなくちゃいけないんだけれども、でも同時に、「私が取り込んで継承しようとしている他者は、私に取り込まれることを承認してくれるのだろうか」というような、「取り込みの暴力」が確実に存在します。山城さんは、それを強烈に表現なさる方だと思っています。
やなぎみわ──50年後の自分から見える「女性の継承」
山本:次に、やなぎみわさん。有名なのが、《マイ・グランドマザーズ》のシリーズですよね。これは、主に若い女性の人に頼んで、50年後の自分を想像してもらう作品。プロセスとしては、「本当に50年後の自分は、そのようになるのか」、「どういう根拠でそう思うのか」などといったことを、やなぎさん本人と対話をしていく。

山本:そのプロセスも含めて、1年かかる時もある様ですが、そこにテキストと、その人の50年後の姿というのが映される、という作品です。これもさっきの山城さんと似たようなテーマが表現されていると思いますが、清水さんはどのように感じますか?
清水:まさに継承で、特にこのやなぎさんの《マイ・グランドマザーズ》に関しては、明らかに女性の継承の話で、本当にとてもビッグテーマのひとつなんです。
ただ、やなぎみわさんの《マイ・グランドマザーズ》のシリーズがとてもおもしろいなと思うのは、単線的な時間軸というのが、かなり意図的に避けられているという点なんです。
継承の時間軸で一般的なのは、上の世代から下の世代へ、血のつながったおばあさんからお母さんに来て、お母さんから子どもへ、というような時間軸ですよね。50年後の自分が自分のおばあさんになっているということは、そもそもその時点で、タイトルの「マイ・グランドマザーズ」じゃなくて、自分自身でしょ?と思ってしまいます。だけど、タイトルによれば、それは「自分のおばあさん」であると。
本当は自分のおばあさんというのは、時間軸的には自分より前にいる人なんですけど、それが自分の未来にいる、という設定自体がちょっと変わってるなと思います。
それから、この作品の中で、おばあさんになった人たちが、自分の後継者を自分で選んでいくというモチーフが、繰り返し出てくるんですね。「自動的に子どもができて、子どもにさらに孫ができたので、自分に孫娘がいます」ではなくて、自分の跡を継ぐというか「自分の孫娘にあたる人たちを、自分がどう選んでいくのか」みたいなことがテーマとしてあるように感じるんですよね。
特に、やなぎさんがひとりで全部決めているわけではなくて、候補として名乗りを上げた方とお話をなさる中で、そういうテーマが繰り返し出てくるということが、とても興味深いですね。
山本:かなりいろんなパターンがありますが、たとえば占い師をやっていて、子どもたちがどんどん来るんだけど、自分の後継者でピンとくる人がなかなか来ない……という話が出てきたり、必ずしも血縁関係みたいなのに縛られない継承の形というか、その人を待ち続けている自身の50年後の姿が出てくるわけですよね。
この後に、やなぎさんは、《グランドドーターズ》という作品を作るんですけど、それは逆におばあさんが自分がすごい小さなときに聞いた、自分のおばあさんから聞いたお話みたいなものを語っていくのがだんだん子どもの声になっていくみたいな。そういう形で、やなぎさんは意図的に単線的な時間軸を錯乱させているのかなと思いますね。
「なぜ偉大な女性アーティストはいなかったのか」
山本:別のトークテーマに入っていきたいと思います。僕の専門領域のひとつが「ソーシャリー・エンゲージド・アート」(アートの社会的実践)という概念で、日本でも現代アートの文脈で、よく議論がされています。
まず、カリィ・コンテというアメリカのキュレーターが執筆した「ソーシャル・プラクティスへの大きなうねり──1970年代の米国におけるフェミニスト・アート」(*1)という論文を紹介したいと思います。
*1 カリィ・コンテ「ソーシャル・プラクティスへの大きなうねり──1970年代の米国におけるフェミニスト・アート」『ソーシャリー・エンゲイジド・アートの系譜・理論・実践 芸術の社会的転回をめぐって』アート&ソサイエティ研究センター SEA研究会、2018年。
この論文の中で「1960年代から1970年代の第2波フェミニズム運動が、ソーシャル・プラクティスに及ぼした重大かつ決定的な衝撃については滅多に取り上げられることはないし、またフェミニスト・アーティストたちが、この社会的展開のパイオニアだったことはあまり認識されていない」といったことが語られています。
ほかにも、「なぜ偉大な女性アーティストはいなかったのか」という、古典ともなっているようなリンダ・ノックリンによる論文があります。その中では、美術史の中で男性中心主義というのが優勢だったことによって、社会的な事情から女性が芸術家になりにくかった、という事情はもちろんだけど、その現状を追認する形で、美術史家や研究者たちも、女性芸術家を認識していなかった、といったことが書かれています。
同じように、現在のソーシャルプラクティスの議論においても、フェミニズムの運動に影響を受けた作家たちの活動が、方法論的にもいろんな影響を現代のソーシャルプラクティスの担い手に及ぼしているんだけど、それが見過ごされている、というような問題提起があります。
カリィ・コンテは、この中で特に70年代のアメリカに焦点を絞って作品を見ているんですが、この第2波フェミニズム運動の時代を、清水さんはどういうふうに理解していらっしゃいますか?
清水:波の話は厳密な定義が難しいところですが、「第2波フェミニズム」と言われているのは、実態的には60年代70年代、研究者によっては80年代ぐらいまで、というのが一般的ですね。この第2波では、問題意識の大きな変化があったというふうに言われています。
いわゆる「第1波フェミニズム」は、まず「男性と同じ権利を獲得する」という大きな目標(女性に同等の権利がないという問題)があったんですよね。具体的には、参政権の問題がありましたし、それから財産権、相続権などの獲得など、いかに「女性が公的な領域に進出するか」が第1波の大きな目的だったんですね。
第2波というのは、もちろん第1波が完全に達成して第2波になるわけじゃないんですけど、第2波はその問題を引き継ぎながら、同時に公的な領域に進出するだけではなくて、そもそも公的な領域と私的な領域というのをどう分けてきたかという、その部分に切り込もうとするのが第2波と言われているんですね。
第2波で争点となる「私的な領域」というのは、たとえば人間関係の問題だったり、家庭の話だったり、ということです。
いわゆる「個人的なことは政治的なこと」というスローガンはよく知られていますが、これがなぜ第2波にとって大事かというと「私的領域の部分は、あくまで個人的な問題であって、社会的、あるいは政治的なイシューとして考える必要がない。それは権力の問題ではなくて、個人の問題なんだ」という論理に対して、「私がどういう家庭生活を送るのか」あるいは「職場でどういう身の振る舞い方を要求されるのか」などの個別的問題がじつは社会問題や政治問題につながっていて、その全部に、女性の社会的な地位や立場というものが、深く関わっていると、第2波では強く主張されたからなんですね。
ミエレル・レーダーマン・ユケレスの「メンテナンス・アート宣言」
山本:なるほど。ざっくりまとめると、プライベートという領域の中に押し込められて、今まで争点化されてこなかった論点を、第2波では問題視していく、という感覚ですね。その影響が見られるアーティストに、ミエレル・レーダーマン・ユケレスという人がいます。

山本:ユケレスは70年代の頭に「メンテナンス・アート宣言」という短い宣言文を書いたんですよね。そこでは「女性の家庭内での労働は、至極プライベートな領域に押し込まれており、女性がアーティストとして結婚をしたり出産をしたら、そこに閉じ込められてしまい、アーティストとしての活動ができない。だから、自分は、女性が家事労働として背負わされているメンテナンス活動を、むしろ自分のアート作品として提出していく」という宣言を出して、パブリックパフォーマンスとして、普段自分が家事労働としてやっていることを、ギャラリーや美術館で作品として展示していくんですね。
その後も、第2波フェミニズムの考え方に影響を受けた作品を制作していて、たとえば、《タッチ・サニテーション・パフォーマンス》という作品を発表しています。これは、実際にニューヨークの清掃作業員たちと、1年間を通して朝の点呼から活動を共にし、ニューヨーク中のすべての清掃作業員の人たちと握手をして回るというパフォーマンス作品です。
清水:握手するんですか?
山本:握手するんですよね。今でいうエッセンシャル・ワーカーのような人たちが対象で、彼らもある種「メンテナンス」といえる労働をしており、必要だけれども、非常に不可視化され、周縁化され、場合によっては下に見られている。そういった人たちがニューヨークという場所にとって必要であるということを承認していく、その行為としてすべての人と握手して、その写真というのを飾っていく、という作品になります。
美術界におけるハラスメント
山本:最後のテーマが、美術界におけるハラスメントです。これらは、セクシャルハラスメントだったり、パワーハラスメントだったり、あるいは複合的な形で起こっていると思いますが、それらが当事者からの異議申し立てにより、公になるパターンが増えていると思います。しかし、まだまだ公になっていないハラスメントも、たくさんあるでしょう。
自分もその立ち上げに際して賛同のメッセージを寄せるなど、個人的にも応援している「表現の現場調査団」という活動が2021年から立ち上がっていて、ジェンダーによって表現の現場にどういったことが起きているか、どういうハラスメントを受けたのか、ということについて、その被害を受けた人たちに最大限配慮する形で具体的に調査を行っています。
そのうえで、WEBサイトを通した情報提供や、他の分野との連携、啓発運動をしています。表現の現場の中では弱い立場にあるフリーランスの人たちを、ハラスメントから守るための具体的な法改正というのを要求していく運動も起こっています。
これも、一足飛びでの問題解決はできないと思うんですけど、表現の現場の中で起きやすいハラスメントの問題を改善していくために、なにができるのか、どういうことが大事なのか、という観点で清水さんのご意見を伺いたいなと。
清水:本当に難しいと思うのが、「どうにかしなくてはいけない」というのはみんなわかっているんだけど、ものすごく効果的な方法がひとつ見つかるかというと、恐らくどこでも見つかっていない、ということだと思うんですよね。
でも、今おっしゃったみたいに、まず実態をちゃんと把握するっていうのはとても大事で、それをどこまでできるかという段階で、すでにいろんなブロックというか、実態を把握させないような力がすごく働くので、その中でどうやって実態を把握していくのか、ということが、とても重要だと思います。
もうひとつは、ハラスメントは社会的な力関係を背景にしているものなので、そこを変えなくてはいけない。それはその現場だけで、学校なら学校とか、表現の現場なら表現の現場だけでできる話ではもちろんない。でも、そこが変わらないと、最終的にハラスメントがなくならないと思うんですね。
イギリスで大学のセクシャルハラスメントが問題化したときに、いくつかの試みが教員や学生団体の共同活動の中で発生していったのですが、その中のひとつに、「お互いの経験をシェアする」という試みがあるんですね。
経験をシェアして、そのまますぐに、この人が悪いといって告発できるかというと、そうはできない場合が多い。告発のためのシェアというよりも「私はこういうことをされて、こういう経験をして、これは不当だと思う、これは正しくないと思う、これは暴力的だと思う」という感覚のシェアが重要なんですね。ハラスメントの被害者は、そうした感覚が当事者にそもそも信じてもらえない、自分が間違っているのではないか、という状況に陥りやすい。ハラスメントを可能にする環境というのは、そういう状況のときですね。
弁護士に相談して、法律的にどうなのか確かめることも重要ですが、その前に「あなたのその話を、私たちはちゃんと聞くよ」という、そういった場所を作ろう、という試みなんですよね。それは、地道な活動ですが、とても重要です。
どうしても自分の感覚を信じられない、自分が本当におかしいのか、自分が考えすぎなのか、過剰反応なのか、ということで、だいたいみんなが悩みます。
そのときに、経験をシェアできる場があると、「これだけ多くの人が同じような経験をしていて、みんながちょっと変だと思っているということは、やっぱり変なんじゃないか」と思えるようになる。ハラスメントの加害者や社会が耳を傾けない世の中なのだとしたら、私たちがお互いの声を聞こうという動きは、より一層重要なんじゃないかと思います。
オンライン上のMeToo運動(*2)は、それに近い効果も持ったと思いますが、本来は個別の名前で出して、全体に公開するという形じゃなくて、もうちょっと安全に言える、聞いてもらえるという場所を作る、ということが大事だと思います。
*2 MeToo運動については、2006年のタラナ・バークによるものと、2017年の女優のアリッサ・ミラノによるものとがあるが、ここでは2017年のムーブメントを指す。
実際は、各女性団体などによって、そのような試みはされていると思いますが、そこにアクセスできない人も、やはり存在します。そこをどうしていくのか、というところが今後重要になっていくと思っています。
山本:ハラスメントの渦中にいる人が、異議を申し立てるというところまで、1人で持っていくというのはすごい難しい。聞いてくれる人がいることで、ある種自分も少し客観視ができたり、シェアをすることで、それはハラスメントなんじゃないかという形で認識ができたり、そういった声を拾っていく場所が、これまではあまりなかった。
オンラインで言える人だけじゃなくて、もっと傷つきやすい人にも支援が必要ですね。たとえば、もうちょっとクローズドな場で、安全性を確保して、安心をさせた上でちゃんと話を聞く場所を作るとか、そういった取り組みが、アートの中でも、実行されていかなきゃいけないのかなと。もちろんアートだけの問題ではないですけれど。
「カナリアがさえずりを止めるとき」展
山本:最後に、「カナリアがさえずりを止めるとき」という展覧会を紹介したいと思います。
カート・ヴォネガットの有名な「炭鉱のカナリア論(*3)」では、アーティストは、炭鉱におけるカナリアのように、社会で起こっていることを敏感に察知して、それを一般の人に伝える役割があるとしています。それも、ステレオタイプなアーティストの像かもしれませんが、アート界でこういうハラスメントが起きてしまうと、そういったこともできなくなってしまう。つまり、ある種社会のカナリアとしての役割というのを、アーティストが果たせなくなってしまう、あるいは、その説得力がなくなってしまう状況が起きるんじゃないか、という問題提起で開催された展覧会になります。
*3 アメリカの作家、カート・ヴォネガットが1969年にアメリカ物理学会で講演した際に言及したとされる論説。19世紀後半のイギリスでは、多くの鉱山労働者を死に至らしめた有毒ガスを検知するために、人間よりも先に有毒ガスの影響が出やすいカナリアを「ガス検出器」として活用していた。ヴォネガットは、これをアーティストと社会の構図に援用し、芸術の社会における役割の1つが、社会の危機感知だと語った。
この展覧会のように、これからもハラスメントの問題に対して、議論が必要だと思っています。ハラスメントがアート業界でも起こってしまう現実は、根の深いところで、アートの可能性をつぶしてしまっているのではないか、自分たちの領域の中でやるべきではないのではないか、という問題提起で、今回の対談を締めたいと思います。



